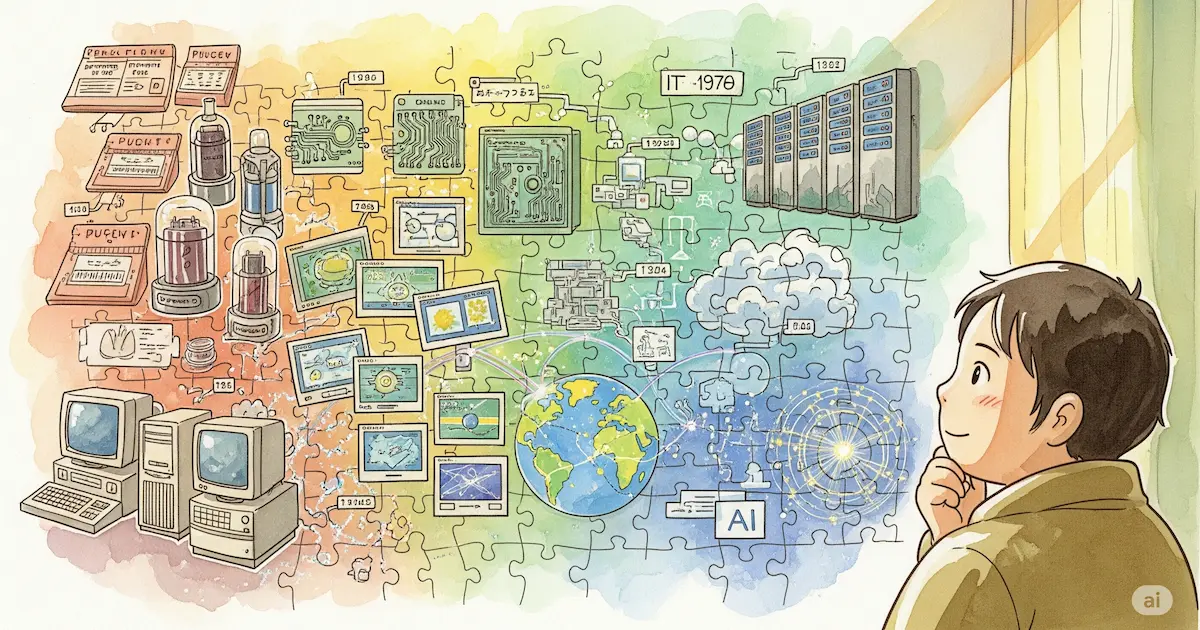🍀概要
この資料は、過去のITストラテジスト(旧 システムアナリスト、上級アドミニストレータ含む)試験問題(論述形式)をテキスト化した「ITストラテジストの歴史書」です。Web上では見つけにくい、貴重で有益な示唆を含む、過去の問題文を、調査してテキスト化しました。 過去の課題から、現代そして未来に求められる理想像を紐解き、あなたの知識と視点を深めます。分析や考察に役立つよう、すぐにコピペして利用できる形式となっています。
🧾問題・設問
出典:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験 平成21年~令和7年(2009~2025年) 午後2(🔗取り扱いガイドライン)
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成6年~平成20年(1994~2008年) 午後2
出典:情報処理推進機構 上級アドミニストレータ試験 平成8年~平成20年(1996~2008年) 午後2
📘ダウンロード
こちらから、掲載した問題文を全て含む、MS Word、PDFファイルをダウンロードできます。
※情報処理推進機構のガイドラインをご確認の上、ご利用ください。(🔗取り扱いガイドライン)
🪄アーカイブ全文
| 略称 | 試験区分 |
|---|---|
| ST | ITストラテジスト試験 |
| AN | システムアナリスト試験 |
| SD | 上級アドミニストレータ試験 |
📗R07:2025
【ST-R07-1-PM2-Q1】基幹システムの刷新方針の策定について
これまで,販売や生産などの基幹業務を担っている基幹システムは,導入時点の業務に適合した業務システムとIT基盤を長期にわたって維持,改修してきた結果,システム構造が複雑化していたり,最新技術が適用できない旧式のITであったりすることが多かった。
このような状況では,担当するIT要員のスキルが継承できなかったり,必要なIT要員が確保できなかったりするリスクが存在することがある。また,企業が進める業務の変革に迅速に対応できなかったり,IT運用・保守費用がかさみ新たなサービスへのIT投資が捻出できなかったりなど,競合他社に劣後することもある。
ITストラテジストは,これらの経営上の課題を解決するために,基幹システムの刷新方針を策定することがある。その際には,まず,次のような事項を検討し,基幹システムを刷新することの必要性や経営上の有効性を明らかにすることが重要である。
・現行システムの改修ではなく,新しいシステム構造やITへ刷新する必要性は何か。
・新しいシステム構造やITへ刷新することによる,経営上の有効性は何か。
そして,刷新によって実現される業務プロセス,業務や組織の必要な見直し方法,優先度を考慮した段階的な移行,刷新の効果と費用などを検討し,基幹システムの刷新方針を策定する。
さらに,策定した基幹システムの刷新方針について,事業部門との交渉や調整を行い,事業部門からの協力や支持を得た上で,経営層に説明し,承認を求める。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった基幹システムの刷新方針の策定の背景にある,事業概要と事業特性,基幹システムの概要と課題を,400字以上800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた基幹システムについて,あなたはどのような刷新方針を策定したか,刷新することの必要性や経営上の有効性を明らかにして,あなたが特に重要と考えて工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた基幹システムの刷新方針について,あなたは事業部門とどのような交渉や調整を行い,経営層にどのような説明をしたか,経営層の評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R07-1-PM2-Q2】DXの企画策定について
昨今,企業は,経営課題の解決において,製品・サービス,業務プロセス,組織, 企業文化・風土などの変革が必要である場合,変革の実現に当たり,デジタルトランスフォーメーション (DX) を推進することがある。例えば,熟練者不足の解消が経営課題で,その解決において DX を推進する場合,既存データを活用した業務の最適化, 業務の標準化・自動化,潜在化している熟練者のノウハウのナレッジ化などの変革を進めることで,経験の浅い人でも熟練者に近い業務が遂行できたり,ナレッジを組み合わせた新製品・新サービスの開発が実現できたりする。また,熟練者にナレッジを更に高度化する指導者の役割を担わせたり,未経験人材の採用が可能になったりして, 企業文化や働く人の意識を変えていくこともできる。
このようなDXの推進に当たり,ITストラテジストは,例えば次のようなことを明確にし,DXの企画を策定することが重要である。
・デジタル技術とデータ活用が変革の実現にどのように貢献できるか。
・事業部門や管理部門などとどのように役割を分担し,DXを推進するか。
・デジタル技術の導入とデータ活用に関わる投資金額は幾らか。
また,DXの推進に当たり,変革を阻害する様々な要因が想定される。例えば,改修や新技術の導入が困難なレガシーシステム,外部組織との複雑な連携プロセス,変革を積極的に受け入れない組織や人などが挙げられる。ITストラテジストは,このような変革を阻害する要因を想定して経営層や事業部門と協議し,経営層や事業部門の意思を取り入れた対応策をDXの企画に反映させることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった DX の企画策定において,解決すべき経営課題,必要となった変革は何か,事業背景,事業特性とともに400字以上800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた変革の実現に当たり,あなたはどのようなDXの企画を策定したか。あなたが特に重要と考え,工夫したことを明確にして,800字以上 1,600 字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた DX の企画策定において,あなたは変革を阻害する要因としてどのようなことを想定し,どのような対応策を DX の企画に反映させたか。対応策に取り入れた経営層や事業部門の意思を明確にして,600字以上 1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R06:2024
【ST-R06-1-PM2-Q1】DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に向けた新たな情報技術の採用について
企業は,情報技術を使った新サービスの開発や既存事業の改革などの施策を企画し,DXを実現する。その施策の中で,従来の情報技術では実現できなかったことを実現するために,企業にとって利用実績の乏しい,AIやIoTなどの新たな情報技術の採用を検討することがある。
ITストラテジストは,新たな情報技術の採用に関する検討の中で,その情報技術によって施策を実施できるかどうかについて,机上確認と技術検証を行う。例えば,業務要件への適合性,業界における規制への対応,性能・拡張性・セキュリティなどの非機能要件への適合性,情報技術の利用における継続性などについて机上確認し,その後,試験的な導入やシミュレーションなどを通じて,技術検証を行う。
机上確認と技術検証を通して,事業への適用におけるその情報技術の特性を理解した上で,リスクとその対策を具体化する。例えば,AI倫理などのコンプライアンスに関するリスク,計画していた予算や体制などの経営リソースに影響を及ぼすリスクなどを確認し,それらへの対策とともに経営層に説明し,承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったDXの実現に向けた新たな情報技術の採用について,DXの狙い,施策の内容,検討対象となった新たな情報技術とその必要性を,事業特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた新たな情報技術について,施策の実施に向けて,あなたはどのような机上確認と技術検証を行ったか,その結果や工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報技術を採用するに当たって,机上確認と技術検証を通して,あなたはどのようなリスクとその対策を具体化し,経営層にどのように説明したか,経営層からの指摘,指摘を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R06-1-PM2-Q2】新しいビジネスモデルの策定について
今日,ITストラテジストは,事業部門とともに事業戦略に基づき,新しいビジネスモデルを策定することが求められている。新しいビジネスモデルの策定では,顧客,提供価値とそれを具現化する製品やサービス,収益の獲得方法を定義する必要がある。
ITストラテジストは,新しいビジネスモデルを策定する際には,ITで次のようなことを新たに実現できないか検討することが重要である。
・ITで新たな顧客接点や魅力的な顧客体験(CX)を実現できないか。
・ITで製品やサービスの新しい価値を提供できないか。
・ITで低コストなオペレーションを実現し,収益に貢献できないか。
例えば,新たな収益源を検討していた和服メーカーでは,建設会社や介護施設などの新規顧客の獲得を目指し,作業者や高齢者の健康を見守る,利用料金定額制の新しいビジネスモデルを企画した。このビジネスモデルでは,IoTとクラウドサービスを活用し,銀などの導電繊維を織り込んだ衣服を着るだけで,体温や心拍数を収集して,熱中症などを監視する新しい価値を提供している。
新しいビジネスモデルが事業化される際には,事業環境の変化によって,顧客数や業務量,アクセス数やデータ量などのITの要件が,当初の要件とかい離することがある。ITストラテジストは,このようなかい離を想定して,拡張や縮退のできるITの採用,地域や顧客層を限定した段階的な立ち上げなどを検討し,ITの投資費用とともに,事業部門へ提案する。そして事業部門からの評価を受け,提案の改善を行う。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった新しいビジネスモデルの策定について,背景にある事業概要と事業戦略を,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業戦略に基づき,あなたはどのような新しいビジネスモデルを策定したか,顧客,提供価値とそれを具現化する製品やサービス,収益の獲得方法,ITで新たに実現したことを,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた新しいビジネスモデルが事業化される際の,あなたが想定した,当初の要件とのかい離は何か,提案した内容と事業部門の評価,事業部門の評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R05:2023
【ST-R05-1-PM2-Q1】ITシステムに関わる改修要望の分析と対応方針の立案について
昨今のITシステムは,ビジネスの変化の速さを背景に,構築後もITシステムの利用部門から,サービスや業務の改善のための,様々な改修要望が挙がってくる。
そのような改修要望は,利用部門の視点だけで検討した部分的な内容にとどまっている可能性がある。利用部門から相談を受けたITストラテジストは,改修要望に対する利用部門の問題認識や,現状の業務プロセス,ITシステムの機能,ITシステムの利用状況などの情報を収集し,客観的に現状の分析を行う。その際,経営に貢献し続けるITシステムの実現に向け,次のような全社視点での多面的な分析を行った上で,改修要望が挙がってきた問題の真因を特定することが重要である。
・利用部門が認識している,問題に関連する制約事項や前提条件を,個別最適ではなく,全社最適の視点で見直す必要がないか。
・他の事業部門のサービスや業務に関連する,同様の問題や改修要望がないか。
・バリューチェーンの上流や下流における業務プロセスやITシステムに,この改修要望に関連する問題がないか。
・ITシステムの利用者,ITシステムの運用者,顧客,取引先などのステークホルダに,この改修要望に関連する問題や他の改修要望はないか。
さらに,特定した問題の真因の解消に寄与する,解決手段,スケジュール,実行体制,投資効果などについて利用部門や関係部門と協議し,対応方針として立案する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITシステムの改修要望の分析において,事業概要,分析の対象となる業務とITシステム,利用部門からの改修要望,利用部門の問題認識について,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた改修要望に対して,あなたはどのような情報を収集し,どのように分析し,どのような問題の真因を特定したか。工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた問題の真因について,あなたは利用部門や関係部門とともに,どのように協議し,どのような対応方針を立案したか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R05-1-PM2-Q2】個別システム化計画におけるシステムリスク対応方針の立案について
顧客の生活や企業の事業活動の基盤として利用され,継続して安定したサービスの提供を求められるシステムの個別システム化計画では,システムリスク対応方針の立案が重要である。システムリスク対応方針の立案とは,企業の情報システム戦略やセキュリティポリシーなどに基づき,故障によるシステム停止,人為的ミスやサイバー攻撃による情報漏えいなどのインシデントに備える施策の検討である。
ITストラテジストは,個別システム化計画におけるシステムリスク対応方針の立案に当たっては,事業や顧客,提供するサービスの特性を十分に考慮し,社外の事例も参考にした上で,インシデントが社会や自社の経営に与えるインパクトを想定する。
次に,想定したインパクトに応じて,予防策と発生時対策から成るシステムリスク対応方針を関連部門とともに立案する。予防策とは,インシデントの発生を最小限に抑える施策で,許容される停止時間に応じた冗長性確保,情報漏えいを防止する認証・認可の厳格化などがある。また発生時対策とは,インシデント発生後のインパクトを最小限に抑える施策で,迅速な情報共有のための顧客と社内への緊急連絡システムの構築,迅速な復旧を実現するための定期的なリカバリ訓練の実施などがある。
これらの検討を基にITストラテジストは,施策の準備,実行及び維持や,組織の体制強化などに要する費用を明らかにするとともに,システムリスク対応方針の効果を検討し,事業部門と経営層に提案して承認を得ることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった個別システム化計画におけるシステムリスク対応方針の立案において,対象としたサービスと個別システムの概要を,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた個別システムにおいて,あなたはどのようなシステムリスク対応方針を立案したか。想定したインシデントとインパクトを明らかにし,立案に当たり工夫した点とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステムリスク対応方針について,あなたは事業部門と経営層にどのような提案を行い,承認を得たか。事業部門と経営層から指摘を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R05-1-PM2-Q3】組込みシステム・IoT製品の社会環境の急変に勝ち抜くための革新的な製品戦略について
近年,新型コロナウイルス感染症拡大による新しい生活様式,行動変容,さらには少子化による労働力低下の問題など,社会環境が急変している。そのような環境下で競合他社との競争に勝ち抜くためには,変動する市場のニーズに適合し,加えて社会に新たな価値を提供する革新的な製品を投入する製品戦略が重要である。
革新的な組込みシステム・IoT製品の例として,コンビニエンスストアの冷蔵室内の過酷な作業をロボットとAIによって無人化する“飲料自動補充システム”,海上の生け簀に代わり,IoTを活用し,陸上で省力化した“海老養殖システム”などがある。
革新的な製品戦略には,プロダクトイノベーションの考え方があり,そのアプローチには“技術主導型”,“ニーズ主導型”,“類似品型”,“商品コンセプト型”がある。これらのアプローチによって製品を企画する際には,テレワークなど,行動が制限された環境でも,市場・競合他社の動向調査,最新の技術情報の収集は必要である。さらに,製品企画に対してステークホルダから承諾を得るために,プレゼンテーションなどによる提案も重要である。
組込みシステムのITストラテジストは,製品企画を立案するに当たり,市場・競合他社の動向調査結果及び収集した最新の技術情報などを基に,市場のニーズに適合する製品であるかを吟味する必要がある。また,製品化の過程においても早期の製品化などに鑑みて課題を抽出し,解決策を策定しておくことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステム・IoT製品の概要と企画の経緯,プロダクトイノベーションでのアプローチした型とその理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたアプローチした型において,どのように市場・競合他社の動向調査,最新の技術情報の収集を実施して検討したか,ステークホルダへは,どのように提案し,承諾されたか,製品化の過程でどのような課題を抽出し,その解決策を策定したか,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた調査結果,収集した情報は,どのように寄与したか,また,ステークホルダへの提案の評価,製品化の過程で抽出した課題の解決策に対する妥当性の評価について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R04:2022
【ST-R04-1-PM2-Q1】ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について
近年,顧客が商品やサービスに興味をもってから,購入や利用までの一連の体験を通じて得る満足度を向上させることが,企業が差別化を図るために重要になっている。そのため,ITを活用して,顧客との接点を増やしたり,関係性を高めたりすることで,顧客に新たな価値を感じてもらえる新商品や新サービスを提供することがある。
ある保険会社では,顧客の声を収集,分析したところ,多くの商品で年齢ごとに保険料が一律であることに不満が多かった。また,契約と保険金の支払以外で顧客との接点が少なかった。そのため,健康に気を使えば保険料を割り引く,健康増進型の保険商品を企画した。具体的には,スマートデバイスで契約期間中の顧客との接点を増やし,顧客の同意のもと健康診断や歩行などの健康データを収集する。そして収集した健康データを活用して,翌年以降の保険料を割り引く仕組みを提供した。さらに,健康的な食事などへのアドバイスや,スポーツジムの利用の割引を提供した。それによって,顧客に新たな価値を感じてもらえる新商品を実現した。
ITストラテジストは,ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画を行う際,次のような事項を検討することが重要である。
・どのような顧客に対して,接点を増やしたり,関係性を高めたりするか。
・顧客との接点で,どのような新たな価値を提供するか。
・新商品や新サービスを実現するためにどのようなデータを扱うか。
その上で,顧客満足度を向上させる新商品や新サービスについて,顧客満足度を測る指標や投資効果とともに,経営層に提案する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画において,事業概要,顧客満足度を向上させることが必要となった背景を,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた顧客満足度を向上させるために,ITを活用してどのような新商品や新サービスを企画したか。顧客との接点や関係性,新たな価値,扱うデータを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について,経営層に何を提案し,どのように評価されたか。経営層の評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R04-1-PM2-Q2】基幹システムの再構築における開発の優先順位付けについて
長期にわたって改善を繰り返してきた基幹システムは,複数のサブシステムが複雑に連携し合い,保守性が低下し,事業環境の変化に追随できなくなっていることが多い。このような基幹システムの再構築には,多くの費用,期間が必要であり,一度に全てのサブシステムを再構築することはリソース制約とともにリスクも大きい。一方,経営層からは業務効率の大幅な向上や,投資効果を早期に享受することが求められるようになってきている。
ITストラテジストは,基幹システムの再構築を計画する際,全体システム化計画との整合性に留意しつつ,それぞれのサブシステムを,どのような順序で,どのくらいの費用と期間を掛けて再構築するかの優先順位を検討する。優先順位を検討する際,次のようなことを考慮することが重要である。
・経営層からの要請,業務や現行システムが抱える問題,制度変更への対応など,対象となるサブシステムが解決すべき課題の重要性及び緊急性は何か。
・どのような順序で,どのくらいの費用と期間を掛けて再構築すると,投資効果を早期に享受し,改修規模を極小化できるか。
・現行の機能の再利用,IT部門のリソース制約,技術上の難易度などを考慮した上で,どのような順序で取り組むことで,再構築リスクを軽減できるか。
ITストラテジストは,検討した優先順位について,定性・定量の両面における投資効果とともに経営層に説明し,承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった基幹システムの再構築の計画策定について,企業の事業概要,背景となった事業環境の変化,基幹システムの概要を,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた基幹システムについて,あなたはそれぞれのサブシステムを,どのような優先順位で再構築することとしたか。特に重要と考えて考慮したこととその内容,あなたが工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた優先順位について,経営層にどのような説明を行い,どのような評価を受けたか。経営層の評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R04-1-PM2-Q3】経営環境の急激な変化に伴う組込みシステム事業の成長戦略の意思決定について
昨今の組込みシステム,IoT製品の業界は,デジタルトランスフォーメーション(DX)推進などによる多様な分野への急激な市場拡大,また新型コロナウイルス感染症拡大による社会情勢の変化などによって経営環境が急変し,今後の業績,事業の成長の見通しが不透明となっている。
経営環境を取り巻くそのような状況下において,事業の成長を目的とした意思決定のためには,成長戦略の継続的な見直しが必要である。成長戦略を見直す手法として,成長戦略を新規・既存製品と新規・既存市場の組合せで四つに分類し,製品市場マトリクスとして検討する考え方がある。具体的には,①新製品開発戦略(新規製品を既存市場へ投入),②新市場開拓戦略(既存製品を新規市場へ投入),③多角化戦略(新規製品を新規市場へ投入),④市場浸透戦略(比較的経営環境の変動が小さい既存市場での既存製品維持)である。例えば既存製品の売上減少,市場の縮小・消失などが見込まれる場合では,新市場開拓戦略と多角化戦略が考えられる。多角化戦略の例として,事務機器メーカのアルコール自動噴霧器の市場への投入,防災機器メーカのAI自動顔認証体温測定装置の市場への投入などがある。
組込みシステムのITストラテジストは,既存製品,既存市場又は新規市場を分析し,経営環境の変化に対応する事業の成長を見据えた成長戦略を立案するなどの意思決定を行うことが重要である。その際に,立案した目標と結果がかい離するなどの経営リスクをあらかじめ分析し,その分析結果に対応するための経営リスクマネジメントも重要である。さらに,新規製品投入の場合には,早期に開発するために必要な保有技術・新規開発技術を鑑みた検討が必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステムの製品の概要,経営環境の変化,及びそれに応じた,製品市場マトリクスにおける成長戦略の内容を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた成長戦略における市場の特徴,成長戦略を立案した根拠及び意思決定に至った過程,また,どのような経営リスクを想定し,どのような経営リスクマネジメントを実施したか,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた成長戦略を立案した根拠及び意思決定に至った過程を基に,現時点における成長戦略の評価,意思決定の評価,経営リスクマネジメントへの評価を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R03:2021
【ST-R03-1-PM2-Q1】デジタルトランスフォーメーションを実現するための新サービスの企画について
企業は,データとディジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むことが重要になってきている。
流通業のグループ会社である倉庫会社では,物流保管サービスのプラットフォーマに変革するというDXを実現するための新サービスを企画した。具体的には,ICタグを使って商品1個単位に入出庫や保管を管理できるように物流保管システムを改修し,グループ外の一般企業にも,オープンAPIを用いた物流保管サービスを提供した。これによって,洋服一点ごとの管理ができる倉庫を探していた衣料品レンタル会社などを新規顧客として獲得している。
工場設備の監視制御システムなどを提供している測量機器メーカでは,サービス業にも事業を拡大するというDXを実現するための新サービスを企画した。具体的には,赤外線カメラなどを搭載したドローンを活用し,ドローンで撮影した大量の画像データをAIで解析することによって,高所や広範囲なインフラ設備を監視する年間契約制のサービスを提供した。これによって,インフラ点検を安全かつ効率的に行いたい道路運営会社や電力会社を新規顧客として獲得している。
ITストラテジストは,DXを実現するための新サービスを企画する際には,ターゲットの顧客を明確にし,その顧客のニーズを基に新サービスを検討する必要がある。
さらに,DXを実現するための新サービスを具体化する際には,収益モデル,業務プロセス,新サービスの市場への普及方法,リスク対応策,協業先などを検討し,投資効果と合わせて経営層に提案することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったDXを実現するための新サービスの企画について,背景にある事業環境,事業特性,DXの取組の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたDXを実現するために,あなたはどのような新サービスを企画したか,ターゲットとした顧客とそのニーズ,活用したデータとディジタル技術とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたDXを実現するための新サービスを具体化する際には,あなたは経営層にどのような提案を行い,どのような評価を受けたか。評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R03-1-PM2-Q2】個別システム化構想におけるステークホルダの意見調整について
事業目標の達成に向けて,事業戦略に掲げられている変革を実現するために,ITストラテジストは,事業部門,IT部門,本社部門,IT子会社などのステークホルダとともに,個別システム化構想を策定する。
ITストラテジストは,あるべき業務及びシステム,投資効果,開発スケジュールなどについての試案を検討し,各ステークホルダと試案について協議して,個別システム化構想案を取りまとめる。しかし,各ステークホルダの立場の違いから,個別システム化構想案の内容に対して意見の相違が発生することがある。各ステークホルダから協力を得て,事業戦略と整合性の取れた個別システム化構想として完成させるためには,ITストラテジストが構想案に対して反対意見や疑義をもつステークホルダへの説得を行った上で,意見の調整を行い,構想案に反映して内容を確定することが重要である。例えば,次のような調整をすることがある。
・実現する業務やシステム化機能の優先順位に関する事業部門からの反対意見に対しては,業務負担軽減のための施策や,サービスレベルの見直しを提案する。
・人的リソース不足に懸念を示すIT子会社に対しては,開発スケジュールを事業部門,IT部門とともに見直して,IT子会社の負荷調整を図る。
・投資効果や費用リスクを懸念する本社部門に対しては,段階的な導入による効果創出の早期化や,SaaS活用などによる初期投資コストの抑制案を提案する。
さらに,ITストラテジストは,内容を確定した個別システム化構想について,事業目標達成への寄与のために,事業戦略への影響,投資効果などを経営層に説明し,承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった個別システム化構想の策定において,背景となった事業目標,事業戦略に掲げられている変革の概要,関係するステークホルダについて,業務特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたステークホルダについて,個別システム化構想案に対してどのような意見の相違があり,あなたはどのように意見を調整したか。個別システム化構想案の概要と意見の調整で工夫したこととともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた意見の調整結果を反映した個別システム化構想について,経営層からどのような評価を受けたか。評価を受けてあなたが改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R03-1-PM2-Q3】異業種メーカとの協業による組込みシステムの製品企画戦略について
近年,異業種メーカとの協業による組込みシステムの製品が様々な市場に進出している。新分野における新製品の開発及び既存製品の機能の見直しを検討し,IoT,AIを導入した異業種メーカと協業することで,新たな価値を創造した製品戦略を策定することができ,未開拓の新市場などへの参入が可能になる。
既存製品の市場におけるライフサイクルのステージが成熟期・衰退期の時期であっても,異業種メーカと協業することによって,既存製品を新たなニーズに対応した価値のある製品として新市場に投入する戦略が考えられる。また,新市場の調査結果を基に企画した製品について,自社の保有技術だけでは製品化,販路の開拓などの実現が難しい場合でも,異業種メーカとの協業によって実現できることもある。
例えば,ディジタルサイネージメーカでは,防災機器メーカ,自動販売機専門メーカとの協業によって“高機能型IoT自動販売機”を製品化することが挙げられる。
協業する企業は,投入する製品を補完する部分及び新市場を分析し,技術的な適性,実績,企業系列などを吟味し,社内方針に従って選定される必要がある。
組込みシステムのITストラテジストは,企画した製品に関して協業する各企業と協議した上で,課題の抽出,課題に対する解決策,適用範囲などを取りまとめることが求められている。その過程の中で,協業する企業の分担範囲をトレードオフしながら切り分け,最適な製品を企画することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが異業種メーカとの協業で企画・検討をした組込みシステムの製品の概要,企画・検討に至った経緯を,新市場の特徴とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品において,異業種メーカとの協業を検討した理由,協業する各企業の分担範囲及びそのトレードオフ,各企業から挙がった課題及びその解決策として考えられる内容を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた異業種メーカとの協業について判断したことの妥当性,分担を考えた内容の妥当性,課題に対する解決策についての評価を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R01:2019
【ST-R01-1-PM2-Q1】ディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決について
今日,ディジタル技術を活用した業務プロセスによって多くの事業課題の解決が可能となった。ITストラテジストは,ディジタル技術を活用して効率化できたり,品質の向上が図られたりする業務を特定し,業務プロセスにディジタル技術を活用することによって,事業課題の解決を実現することが重要である。このような例としては次のようなものがある。
病院において,看護師が看護に専念できる時間をより多く確保するという事業課題に対し,看護に直接関わらない業務を特定し,その中で記録業務プロセスに音声認識装置とAIの活用を図った。これによって看護師は迅速に記録業務を行うことが可能となり,看護に専念する時間が増え,事業課題を解決した。
組立加工業において,経験の浅い作業者でも熟練作業者と同等の作業水準を達成するという事業課題に対し,熟練作業者が行っていた組立業務プロセスにAR機器とIoTの活用を図った。これによって熟練作業者と同等の作業水準が達成され,事業課題を解決した。
ディジタル技術を活用した業務プロセスの実現性の担保に当たっては,ディジタル技術の機能,性能,信頼性などを検討することが必要であり,先行事例の調査や実証実験が重要である。ITストラテジストは,ディジタル技術を活用した業務プロセスが,事業課題の解決にどのように貢献するかについて,投資効果を含めて事業部門に説明する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決において,解決しようとした事業課題及びその背景について,事業概要,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業課題の解決に当たり,あなたはどのようなディジタル技術を活用し,どのような業務プロセスを実現したか,その際に実現性を担保するためにどのような検討をしたか,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたディジタル技術を活用した業務プロセスが,事業課題の解決に貢献することについて,あなたが事業部門に説明した内容は何か。また,事業部門から指摘されて改善した内容は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R01-1-PM2-Q2】ITを活用したビジネスモデル策定の支援について
規制緩和や異業種の参入,技術の進展などによって業界を超えた企業間の競争が激しくなる中,新規顧客の獲得,競争優位性の確保,新たな収益源の創出などが企業の経営課題となっている。
昨今,企業は,こうした経営課題を解決するために,スマートフォンやIoT,クラウドサービスなどのITを活用したビジネスモデルを策定し,それを実現している。
ビジネスモデルの策定では,顧客は誰か,顧客にどのような価値を提案するか,事業の収益や利益をどのように確保するかなどを検討することが必須である。ITストラテジストは,ITをどのように活用してビジネスモデルを実現するかという観点で,事業部門の検討を支援することが求められる。
例えば,カーシェアリング事業では,自動車の貸出しを希望する顧客に対し,スマートフォンで空車を探して利用の予約ができる,利便性の高いサービスを提供している。また,自動車に搭載したIoT機器で貸出し・返却を無人化することで運営コストを最小化し,利益を確保している。
電子決済サービス事業では,手軽に支払をしたい顧客に対し,スマートフォンでQRコードなどを提示するだけで決済できるサービスを提供している。加盟店からの決済手数料に加えて,購買データの販売料で収益を確保している。
策定したビジネスモデルを立ち上げるためには,初期利用者の獲得,サービス基盤の迅速な整備,実行体制の構築などの施策が重要である。ITストラテジストは事業部門とともに,策定したビジネスモデルと施策を経営層に説明し,承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に携わったITを活用したビジネスモデルについて,経営課題,ビジネスモデル策定の背景を,現行事業の特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた経営課題の解決のために,どのようなビジネスモデルを策定したかについて,顧客,価値提案,収益や利益確保の方法,活用したITを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたビジネスモデルを立ち上げる上で,あなたが重要と考えた施策は何か。また,ビジネスモデルとその施策について経営層から指摘されて改善した内容は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-R01-1-PM2-Q3】組込みシステムの製品企画における調達戦略について
組込みシステムの製品において,近年のAI,IoTなどの進展に伴い,他社製品との連携,複合化,新要素技術の導入など,高度化,複雑化した要求が増えている。
組込みシステムのITストラテジストは,製品を企画する際にシステムアーキテクトなどに協力を求め,必要な技術を洗い出す必要がある。洗い出した結果を基に,現在の自社保有技術と経営戦略との両面から中長期的な展望を視野に入れ,自社開発と外注化などによるアウトソーシングを含めた外部調達との棲み分けを分析し,調達方針を検討しなければならない。
調達戦略では,既存製品の購買費,内製,外製を鑑みた新規開発費などのコスト削減を検討する。自社保有技術があっても陳腐化によって,競合他社と比較して弱みとなることが考えられる場合は,強みとするために,新技術を用いた製品を自社開発以外に調達することも検討する必要がある。また,ネットワークを利用した製品においてセキュリティに関するスキルが自社にない場合は,外部の専門家を要請するケースもある。これらの調達先の選定は,例えば,これまでの自社との関係・実績,強みとなる技術評価,長期的な供給の安定性,見積提示価格,品質管理体制などの項目から関連部門と吟味して方針を決定することが重要である。
組込みシステムのITストラテジストは,製品を企画する際に必要な技術を洗い出し,中長期的な視点で自社開発と外部調達との棲み分けを決定し,外部調達については,外部へ情報を開示するリスクにも配慮しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが企画した組込みシステムの製品の概要,製品企画の背景,調達戦略の特徴を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品の自社保有技術の内容,調達先の選定に関する方針内容,専門家の要請に関する検討内容,外部調達に伴うリスク及びそのリスクに対応するために配慮した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた調達先の選定の方針の妥当性,外部調達に伴うリスクに対して配慮した内容の評価,外部調達による副次効果,及び将来の展望について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H30:2018
【ST-H30-1-PM2-Q1】事業目標の達成を目指すIT戦略の策定について
ITストラテジストは,事業目標の達成を目指してIT戦略を策定する。IT戦略の策定に当たっては,実現すべきビジネスモデル又はビジネスプロセスに向けて,有効なIT,IT導入プロセス,推進体制などを検討し,事業への貢献を明らかにする。
IT戦略の策定に関する取組みの例としては,次のようなことが挙げられる。
・顧客満足度の向上による市場シェアの拡大を事業目標にして,AI,IoT,ビッグデータなどを活用した顧客個別サービスを提供する場合,システムソリューション,試験導入,データ解析に優れた人材の育成などを検討する。
・グローバルマーケットでの売上げの大幅な増大を事業目標にして,生産・販売・物流の業務プロセスの革新によるグローバルサプライチェーンを実現する場合,グローバルIT基盤の整備,業務システムの刷新や新規導入,グローバル対応のための運用体制作りなどを検討する。
ITストラテジストは,経営層に対して,策定したIT戦略が事業目標の達成に貢献することを説明し,理解を得なければならない。また,策定したIT戦略を実行して事業目標を達成するために,ヒト・モノ・カネの経営資源の最適な配分を進言したり,現状の組織・業務手順などの見直しを進言したりすることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったIT戦略の策定において,事業概要,事業目標,実現すべきビジネスモデル又はビジネスプロセスについて,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業目標の達成を目指して,あなたはどのようなIT戦略を策定したか。有効なIT,IT導入プロセス,推進体制,事業目標達成への貢献内容などについて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT戦略の実現のために,あなたは経営層にどのようなことを進言し,どのような評価を受けたか。評価を受けて考慮したこととともに600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H30-1-PM2-Q2】新しい情報技術や情報機器と業務システムを連携させた新サービスの企画について
近年,ITストラテジストは,事業戦略を実現するために,オープンAPIやタブレット端末などの新しい情報技術や情報機器(以下,新技術という)と業務システムを連携させ,顧客満足度や生産性などを向上させた新サービスを企画することがある。
銀行業では,“フィンテックを活用して顧客満足度と収益の向上を図る”という事業戦略を実現するために,フィンテック企業が提供するスマートフォン向けアプリケーションソフトウェア,オープンAPIと銀行のシステムを連携させたビジネスモデルを検討し,顧客がいつでも入出金の確認や送金ができる新サービスを企画した。
航空業では,“高品質かつ効率的な整備作業によって,安全かつ安定した運航を実現する”という事業戦略を実現するために,タブレット端末と整備管理システムを連携させた整備作業のビジネスプロセスを検討し,整備士が作業場所で,整備計画や図面の確認,点検箇所の撮影と作業報告などができる新サービスを企画した。
ITストラテジストは,新技術と業務システムを連携させた新サービスを企画する際には,事業戦略を実現するために,ビジネスモデル又はビジネスプロセスを検討し,どのような利用者にどのような便益を提供するのかを定義する。そして,投資効果を算出した上で,新サービスを企画する。
さらに,新サービスの導入では,新サービスの有効性,信頼性,安全性などを検証する必要があり,試験的な導入,機能や範囲を限定した段階的な導入などの対応策も立案した上で,経営層に提案し,承認を得ることが必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった新技術と業務システムを連携させた新サービスの企画において,企画の背景にある,事業概要,事業特性,事業戦略,新技術を採用した必要性について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業戦略を実現するために,新技術と業務システムを連携させて,どのような新サービスを企画し,どのような利用者に提供することを検討したか。検討したビジネスモデル又はビジネスプロセス,利用者の便益,投資効果を明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた新サービスにおいて,新サービスの導入でどのようなことを検証するためにどのような対応策を立案し,経営層に提案したか。対応策の評価と評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H30-1-PM2-Q3】組込みシステムの製品企画戦略における市場分析について
組込みシステムの市場は,IoT,AIなどの新技術の影響で,新製品の投入が活発化している。新製品を企画する際には,同業他社の動向などを調査して優位性を確保し,更に新技術の潮流を把握する必要がある。その上で市場の分析手法を用いて,市場に投入する新製品の売上高,利益率,販売数などを試算し,その結果を勘案して戦略を立案する。
市場の分析手法として,市場成長率を縦軸に,市場占有率を横軸にとり,全体を4象限に分割し,当該企画製品がどの象限に該当するかを分析する手法がある。市場占有率は,新製品と類似の製品を投入している先行メーカを参考にしながら試算し,目的の象限に合致するように戦略を立案する。例えば,市場成長率が高く,市場占有率が低い場合は,拡大戦略を立案する。具体的には,販売促進・販売代理店強化・積極的な展示会への出展などで訴求力を高め,更に利用者の要求情報などを基に新たな機能を追加する。これに対し,市場占有率の拡大が見込めない場合は,参入を取り止めたり,調査した市場から別の市場へと切り替えたりする戦略もある。
別の手法として,市場の魅力などを縦軸に,当該企画製品の優位性などを横軸にとり,全体を9象限に分割する手法もある。特徴として,前述の手法と比較したとき,自社に合った指標を選択できる利点がある。その一方で,内部データを多く使用するので同業他社との比較が難しい,主観的な分析となるなどの懸念もある。
組込みシステムの新製品を企画する際に,ITストラテジストに求められるのは,投入する市場の売上規模,市場成長率,市場占有率などを調査・分析し,その分析結果から製品投入の戦略を立案することである。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが企画した組込みシステムの新製品の概要・特徴及び企画に至った経緯について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた新製品の投入を考えた市場について,どのように調査したか。分析手法の選定理由,分析方法,分析内容及び立案した戦略について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた市場の調査方法,分析内容は妥当であったか。戦略の評価及び市場参入の評価とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H29:2017
【ST-H29-1-PM2-Q1】IT導入の企画における投資効果の検討について
企業が経営戦略の実現を目指して,IT導入の企画において投資効果を検討する場合,コスト削減,効率化だけでなく,ビジネスの発展,ビジネスの継続性などにも着目する必要がある。IT導入の企画では,IT導入によって実現されるビジネスモデル・業務プロセスを目指すべき姿として描き,IT導入による社会,経営への貢献内容を重視して,例えば,次のように投資効果を検討する。
・IoT,ビッグデータ,AIなどの最新のITの活用による業務革新を経営戦略とし,売上げ,サービスの向上などを目的とするIT導入の企画の場合,効果を評価するKPIとその目標値を明らかにし,投資効果を検討する。
・商品・サービスの長期にわたる安全かつ持続的な供給を経営戦略とし,ITの性能・信頼性の向上,情報セキュリティの強化などを目的とするIT導入の企画の場合,システム停止,システム障害による社会,経営へのインパクトを推定し,効果を評価するKPIとその目標値を明らかにし,投資効果を検討する。
ITストラテジストは,IT導入の企画として,IT導入によって実現されるビジネスモデル・業務プロセス,IT導入の対象領域・機能・性能などと投資効果を明確にしなければならない。また,期待する投資効果を得るために,組織・業務の見直し,新しいルール作り,推進体制作り,粘り強い普及・定着活動の推進なども必要であり,IT導入の企画の中でそれらを事業部門に提案し,共同で検討することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった経営戦略の実現を目指したIT導入の企画において,事業概要,経営戦略,IT導入の目的について,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた目的の実現に向けて,あなたはどのようなIT導入の企画をしたか。また,ビジネスの発展,ビジネスの継続性などに着目した投資効果の検討として,あなたが重要と考え,工夫したことは何か。効果を評価するKPIとその目標値を明らかにして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT導入の企画において,期待する投資効果を得るために,あなたは事業部門にどのようなことを提案し,それに対する評価はどうであったか。評価を受けて改善したこととともに600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H29-1-PM2-Q2】情報システムの目標達成の評価について
情報システムを活用し,経営戦略の実現や業務上の問題解決などをする際,情報システム導入の目的を定めた上で,例えば,インターネットからの受注件数や顧客への納期遵守率などの指標とその目標値を具体的に設定することが大切である。そして,稼働後に,設定した目標値に対する達成状況を繰返し評価する必要がある。その際は,次のようなことが重要である。
・客観性を担保するために,業務処理の時間を実際に測定したり,情報システムの受注データ件数を調べたりするなど,定量情報を収集する。
・関係者に目標値の達成状況に関するヒアリングを行う際は,特定の個人,部門に偏った意見収集にならないように考慮する。
・設定した目標値に対する達成状況を,業務面,システム面それぞれの実現度合いを対象に評価する。
評価の結果,設定した目標値と達成状況に差異が見られた場合,差異が発生している原因の分析を行った上で,業務面,システム面の課題を抽出する。経営層,利用部門,情報システム部門に評価の結果と課題を説明する際は,今後の経営環境の変化及び情報システム導入の目的に照らし合わせ,課題を解決することによる目標達成への貢献の見込み,課題解決の緊急度を整理した上で,課題対応の優先度もあわせて説明することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの目標達成の評価において,情報システム導入の目的及び概要,設定した指標とその目標値について,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた目標値について,あなたはその達成状況をどのように評価し,その結果はどのようなものであったか。また,抽出した業務面,システム面の課題はどのようなものであったか。重要と考え,工夫した点とともに800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた評価の結果及び抽出した業務面,システム面の課題に対し,あなたはどのように経営層に説明したか。それに対する意見はどのようなものであったか。意見を受けて改善したこととともに600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H29-1-PM2-Q3】組込みシステムにおける事業環境条件の多様性を考慮した製品企画戦略について
組込みシステム製品の事業環境は,昨今のIoTソリューションの急成長などに支えられた新市場開拓,新分野進出などによって活性化し,市場が拡大している。それとともに,異業種からの新規参入が増加し,他社との競争が激化している。また,組込みシステム製品へのAIなどの先端技術の導入も進むなど,事業環境条件は多様に変動している。
そのような状況において,他社との競争に勝ち抜くために,組込みシステムのITストラテジストは,製品を企画する際にまず,事業環境条件の多様性を的確に分析し,その分析結果を基に製品企画戦略を策定することが重要である。
事業環境条件を,自社内の環境資源である内部環境と社外に存在する外部環境に大別する。内部環境については,競合他社と比較して自社の強み・弱みの要素を挙げ,分析する。外部環境については,機会・脅威の要素を挙げ,分析する。それらの分析結果の各要素を検討・調整して,最適な戦略の策定を行う。その検討例を次に示す。
・自社の保有技術,知的財産などによる強みを生かした方策の検討
・保有していない技術などの弱みを強みに変える方策の検討
・市場の需要拡大などの機会に強みを生かす方策の検討
・弱みと,競合他社の低価格化,新規参入などの脅威とが重なる場合の対策の検討
・セキュリティ面,将来の市場の縮小化などの脅威に伴う対策の検討
製品企画を検討する際には,事業環境条件の多様性を考慮しながら適切な分析手法を用い,その分析結果を基に製品企画戦略を策定することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステム製品の企画の概要,製品の特徴及び事業環境条件の多様性について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品企画の際に分析した内部環境・外部環境の各要素を挙げ,それぞれどのように分析したか。また,各要素に対して,どのような方策又は対策を検討したか。その検討内容を基に,どのような観点で製品企画戦略を策定したか。分析・検討・策定した内容を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた内部環境・外部環境の分析結果,それらの分析結果に基づいた方策又は対策の妥当性,及び策定した製品企画戦略の評価について,策定した結果を含め,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H28:2016
【ST-H28-1-PM2-Q1】ビッグデータを活用した革新的な新サービスの提案について
近年,今まではコンピュータで処理しにくかった膨大な情報であるビッグデータを活用し,革新的な新サービスを実現することによって,事業を優位に展開することが可能となってきた。
例えば,センサと通信技術の向上によって収集できるようになったビッグデータを活用し,生産管理や物流管理を高度化する新サービスが実現されている。具体的には,製造分野では,生産設備の稼働情報と製品の品質情報との相関関係を分析し,生産設備の最適設定・予防保守などの新サービスを展開している。
また,文章や画像,音声などの非構造化データの認識技術や処理方式の確立によって,大量の文献や,消費者がSNS上で発信する情報,監視カメラ情報などのビッグデータを解析し,新サービスに活用し始めている。具体的には,医療分野では,多数の患者の電子カルテ,医療画像情報,投薬情報などを統計的に分析し,副作用が少ない処方箋の作成という新サービスを行っている。
ITストラテジストは,事業を優位に展開するために,ビッグデータを活用した革新的な新サービスの提案を行うことが求められることがある。その際に,次のような事項について検討することが重要である。
・革新的な新サービスは,どのような顧客に,どのような状況で,どのような効果や効能を実現するのか。
・革新的な新サービスは,ビッグデータを活用することによって,どのように実現され,今までのサービスとどのように違うのか。
さらに,ビッグデータを活用した革新的な新サービスを,マネジメント層に提案して承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,ビッグデータを活用した革新的な新サービスの提案の背景にある事業環境,事業概要について,事業特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業を優位に展開するためのビッグデータを活用した革新的な新サービスは何か。顧客や状況,効果や効能,実現方法,今までのサービスとの違いを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた,ビッグデータを活用した革新的な新サービスを,マネジメント層にどのように提案し,どのように評価されたか。改善の余地があると考えている事項を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H28-1-PM2-Q2】IT導入の企画における業務分析について
事業全体の業務の効率向上・スピードアップ,新規事業による売上拡大などの事業目標の達成に向けて,ITストラテジストが事業部門とともに業務分析を行い,真の問題を発見してその原因を究明し,問題の解決策としてIT導入を企画することが増えている。特に,経営の要求に適時適切に応えられないIT,標準化されていないITなどが業務のボトルネックになっていたり,モバイルコンピューティング,IoTなどの新しいITの活用によって業務改革,新規事業が実現できたりする場合,ITストラテジストへの期待は大きい。
業務分析では,事業目標を理解し,まず,業務内容,業務プロセス,IT活用などの現状を調査して問題を発見する。次に,個々の問題を関連付けたり,顕在化していない問題を探ったり,経営の視点で業務全体をふかんしたりして真の問題を発見し,その原因を究明する。この過程では,例えば次のようなことが重要である。
・業務フロー,業務機能関連図などを作成して業務を可視化する。
・MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive),バリューチェーン分析などの手法を利用して全体を網羅する。
・ベンチマーク,他社の成功事例などと客観的に比較検討する。
問題の解決策の策定では,ITストラテジストはIT導入を企画し,適用するITの機能,性能を明確にすることが必要である。その上で,投資規模,ITの導入範囲などを検討し,事業部門に対してIT導入の投資効果を説明する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,事業目標の達成に向けたIT導入の企画における業務分析について,事業目標の概要,業務分析が必要になった背景を事業特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務分析において,どのような手段,工夫で真の問題を発見し,その原因を究明したか。また,問題の解決策としてどのような機能,性能のIT導入を企画したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT導入について,その投資効果をどのように事業部門に説明したか。また,今後,改善すべきことは何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H28-1-PM2-Q3】IoTに対応する組込みシステムの製品企画戦略について
既存の組込みシステムは,特定の領域・環境などを前提としたスタンドアロン型が主流であった。しかし,近年はインターネットの普及に伴い,監視・制御などにInternet of Things(IoT)の活用が進むことによって,組込みシステムの利用が拡大してきている。このような潮流の中で,組込みシステムのITストラテジストには,IoTに対応する組込みシステムの製品企画が求められている。
既存システムを基にして,IoTを活用したシステムを企画する際には,IoTへの対応によって外部との情報のやり取りが可能となるので,情報の利活用によるサービス,データ解析などによる新たな価値の創造などについて調査する。その調査結果を基に分析した後,関連部署と協議して,既存システムの中からIoTを活用すべきシステムを選択し,製品企画を立案する。
一方,新分野,新市場への参入を目指して,IoTを実現する統合システムを企画する際には,情報を利活用したソリューションに携わっている,エンタープライズ系のITストラテジストとの連携が考えられる。その際に必要なのは,組込みシステムの特徴が生かされた製品企画か否かを双方で十分に検討すること,技術的な内容を共有すること,及び役割分担を明確にすることである。さらに,要件によっては,新たな機能を追加して柔軟に対応しながら参入しやすい製品企画を立案する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,IoTに対応する組込みシステムの製品企画の概要と企画に至った経緯,及び既存システムの市場,新分野,新市場のそれぞれの内容と特徴を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品企画において,既存システムを基にして,IoTの活用によるシステムを企画した場合は,どのような観点・手順で選択し,新たな価値を付加したか。また,IoTを実現する統合システムを企画した場合は,組込み系・エンタープライズ系の双方で検討すべき役割分担・立案の内容,及び配慮すべきと考えた事柄とその理由は何か。そのいずれかについて800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた既存システムの選択,又は統合システムの企画に対してどのように評価したか。また,そのシステムは,今後どのように改善又は,発展させるべきか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H27:2015
【ST-H27-1-PM2-Q1】ITを活用したグローバルな事業について
近年,国内の少子高齢化と市場の成熟などによって,日本企業は国内の顧客だけでなく,海外の顧客も視野に入れ,グローバルに事業を拡大する必要に迫られている。また,既に海外で事業を展開している日本企業も,為替変動,新興国の市場拡大などに伴って,グローバルで見た最適なビジネスプロセスを模索し,事業戦略を策定した上で,改革を行っている。グローバルな事業戦略には,例えば次のようなものがある。
・金融機関の法人事業では,国内向けの金融サービス事業から,海外も含めた金融サービス事業へ,顧客を拡大する。
・アパレル企業では,これまで新興国で生産してグローバルに輸出していたSCMに,地産地消などの考え方を参考にして,生産国でも販売する。
ITストラテジストは,ITを活用したグローバルな事業を実現する際に,事業戦略を踏まえ,改革すべき業務機能を見極め,その業務機能を実行する業務組織を定義した上で,業務フローなどを描き,新しい業務の全体像を定義する。また,それを支えるITの要件と主要な機能を整理した新システムの全体イメージを作成する。その際には,次のような観点で検討することが重要である。
・グローバルで一元的に行う業務と,各国で個別に行う業務の切り分け
・多通貨,多言語,日本と異なる法規制・商習慣,時差など
さらに,新しい業務の全体像と新システムの全体イメージを経営者に説明して,承認を得る必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,ITを活用したグローバルな事業の概要と特性,事業戦略について,800字以内で具体的に述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業戦略を踏まえ,改革すべき業務機能,定義した業務組織と新しい業務の全体像,及び新システムの全体イメージについて,特に重要と考えて検討した内容とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた新しい業務の全体像と新システムの全体イメージを,経営者にどのように説明し,経営者にどのように評価されたか。更に改善の余地があると考えている事項を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H27-1-PM2-Q2】緊急性が高いシステム化要求に対応するための優先順位・スケジュールの策定について
企業は,厳しい競争に勝ち抜くために,新しいチャネルの開拓,市場に対応した組織編成,短いサイクルでの新製品・新サービスの開発などに取り組んでおり,情報システムの全体システム化計画で対象とした業務,組織,製品・サービスなどは変化し続けている。一方で,モバイルコンピューティング,クラウドコンピューティングなどの新しいITの活用が広がり,それらが今までにない付加価値を生んだり,コスト削減を実現したりして,事業に貢献する事例が増加している。これらを背景に,情報システムの導入・改修に関して緊急性が高いシステム化要求が,事業部門から継続的に挙げられている。
緊急性が高いシステム化要求への対応に当たっては,まず,要求が事業戦略に適合することを確認し,システム化範囲を定め,要求をどのように実現すべきかを明確にする。次に,緊急性が高いシステム化要求への対応を,全体システム化計画の中でどのように位置付けるかを検討し,優先順位・スケジュールを策定する。その際,例えば次のような観点での検討が重要である。
・情報システム基盤の整備,アプリケーションシステムの統合,業務の見直しなどによって全体の投資削減又は相乗効果が期待できる場合,これらの実施を含めて検討する。
・計画中又は進行中の個々の情報システムの導入・改修への影響が最小限にとどまるように検討する。
ITストラテジストは,緊急性が高いシステム化要求への対応に当たり,事業部門に対して,策定した優先順位・スケジュールによって,情報システムの導入・改修が全体システム化計画において最も効率的・効果的に進められることを説明し,承認を得なければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが事業部門から受けた情報システムの導入・改修に関する緊急性が高いシステム化要求は何か。要求の背景,事業の特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた要求への対応に当たり,どのような観点で検討し,どのような優先順位・スケジュールを策定したか。特に重要と考えたことを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた優先順位・スケジュールを事業部門にどのように説明し,その説明した内容に対して事業部門からどのような評価を受けたか。その評価を受けてあなたが改善したこと,又は今後,改善すべきことは何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H27-1-PM2-Q3】多様な顧客要求に応えられる組込みシステムの製品企画について
組込みシステム製品(以下,製品という)には,多様な顧客要求に応えることが求められ,要求自体もますます複雑化する傾向にある。その一方で,競合他社との価格競争力に加えて,品質向上,高信頼性,短納期化なども必要とされる。組込みシステムのITストラテジストには,そのような潮流に柔軟に対応し,受注に結び付けられる製品を企画することが求められている。そのためには,まず,市場調査,技術動向調査などを実施し,多様な顧客要求及び製品化に伴う課題について検討する。次に,その結果を基に,課題に対する施策の提案を関連部署に依頼する。その後,提案された施策について,関連部署と協議し,製品企画を立案する。その際,初期投資予算,自社の強み,保有技術,体制,リリース時期,施策の優先順位などを考慮する必要がある。例えば,システムアーキテクト,エンベデッドシステムスペシャリストなどに対して,開発の効率向上などの施策の提案を依頼した場合,提案される施策としては,次のような項目が想定される。
・共通部の洗い出しによるプラットフォームの採用などの標準化の提案
・市場調査,技術動向調査を基にしたオプションの用意,機能のカスタマイズの提案
・モジュール,ライブラリなどの資産の再利用による設計効率向上の提案
組込みシステムのITストラテジストは,提案された施策の妥当性を精査し,関連部署と協議しながら製品企画を立案し,施策の効果を製品リリース後に評価することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,多様な顧客要求に応えられる製品企画の概要について,製品企画に至った経緯,市場調査,技術動向調査などの結果を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品企画において検討した,多様な顧客要求と製品化に伴う課題の内容,それに対する関連部署から提案された施策の内容,及び関連部署と協議して立案した製品企画の内容と立案が決定に至った根拠を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた,関連部署から提案された施策の内容の妥当性,立案内容の評価,及び製品リリース後の施策の効果とその評価を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H26:2014
【ST-H26-1-PM2-Q1】ITを活用した業務改革について
近年は,ITの進展によって,事業課題に対してITを積極的に活用し,新たな事業・サービスを展開することが可能になっている。このような中,ITストラテジストは,事業部門と協力して,ITを活用した業務改革を実施することによって,事業・サービスの優位性確保,新規顧客の獲得などの事業課題に対応することが求められている。
ITを活用した業務改革には,例えば,次のようなものがある。
・外勤業務サービスの差別化のために,営業員,サービス員にタブレット端末などのスマートデバイスを配備し,業務進捗状況の迅速な確認,顧客別情報の適時適切な提供などの業務改革を行い,顧客対応時間の増加,顧客サービスの強化を推進する。
・店舗の売上げ拡大のために,内部のPOS情報,外部のSNS・ブログの情報を活用した顧客の購買傾向の分析と的確な品ぞろえ,対象を絞り込んだ顧客への情報発信などの業務改革を行い,販売機会の創出,顧客の囲い込みを推進する。
・物流サービスの優位性確保のために,配送車両にGPS端末と各種センサを配備し,位置確認,道路情報に基づく配送経路の柔軟な変更,顧客への的確な情報提供などの業務改革を行い,顧客満足度の向上,物流サービスの品質向上を推進する。
ITストラテジストは,ITを活用した業務改革を実施する際,事業課題に関連する業務の現状と将来見通し,複数の改革案と各案の効果の比較,活用するITの費用などを検討し,定量的な費用対効果の根拠を示して経営者に説明することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,ITを活用した業務改革について,業務改革の背景にある事業課題を,事業の概要,特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業課題に対応するために,実施した業務改革とそのときに活用したIT,及び費用対効果の定量的な根拠とそのときに検討した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務改革の実施結果は,経営者にどのように評価されたか。更に改善する余地があると考えている事項を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H26-1-PM2-Q2】情報システム基盤構成方針の策定の一環として行うクラウドコンピューティング導入方針の策定について
昨今,急激に変化している事業環境において,企業が競争に勝ち抜くためには,変化に俊敏かつ柔軟に対応できる情報システムが求められている。その一方で,情報システムは肥大化・複雑化しており,開発コスト・運用コストの削減が求められている。このような課題に取り組むために,短期間の導入,初期導入コストの削減,処理量の変動に対する柔軟性などを期待して,情報システム基盤構成方針の策定の一環としてクラウドコンピューティング導入方針を策定する企業が増えている。
クラウドコンピューティング導入方針の策定に当たっては,全体システム化計画との整合性に留意し,例えば次のような検討をすることが重要である。
・クラウドコンピューティングの情報システム基盤とそれ以外の情報システム基盤が混在する場合,基盤間の整合性,事業展開への対応の俊敏性,柔軟性に問題はないか。
・クラウドコンピューティングを長期間利用したり,自社運用型情報システムと連携したりする場合,TCOは想定の範囲内か。
・サービスを外部に委託する場合,利用部門の要望を達成できるサービスレベル,情報セキュリティ対策などを提供できるサービスプロバイダが存在するか。
このような検討を踏まえ,ITストラテジストは,クラウドコンピューティング導入方針を明確にする。また,クラウドコンピューティング導入方針の有効性,期待効果などを経営者に説明し,経営者から承認を得なければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,情報システム基盤構成方針の策定の一環として行うクラウドコンピューティング導入方針の策定について,情報システムの課題とクラウドコンピューティング導入の背景を,事業環境,事業特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた課題への取組みとして,どのようなクラウドコンピューティング導入方針を策定したか。特に重要と考えて検討したことを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた導入方針について,経営者にどのように説明し,承認を得たか。経営者の評価,更に改善する余地があると考えている事項を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H26-1-PM2-Q3】組込みシステムの非機能要件について
組込みシステムのITストラテジストには,組込みシステムの企画を推進するために,要求事項を取りまとめる能力が求められる。その際に,機能要件だけを重視すると,企画した製品に想定外の問題が発生し,解決のために新たなコストが必要となるなど,経営そのものに大きな影響を与える場合がある。さらに,機能要件以外に性能,品質などの非機能要件を明確にすることは,製品戦略的にも他社との差別化及び優位性の確保につながるので重要である。
組込みシステムの主な非機能要件を次に示す。
・システムの信頼性・可用性・保全性・安全性
・システムの性能及びスループット・速度などの時間効率性
・情報の機密性を含めたセキュリティ
・操作・習得の容易さなどに関する使用性
・発熱,騒音,CO2排出量,消費エネルギーなどの環境リスクの緩和性
・製品の長期安定供給の保証
組込みシステムのITストラテジストは,システムアーキテクト,エンベデッドシステムスペシャリスト,マーケティング部門,調達部門などに非機能要件の洗い出しを依頼する。その際に,洗い出した非機能要件を達成するために必要な,知的財産権,コストなども報告を受ける。次に各担当・各部門から提示された非機能要件は,内容を分析・評価し,その評価結果から製品戦略にどのように適用すべきかを検討する。非機能要件は,製品戦略的にも他社との差別化,自社の強みに寄与することになる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが非機能要件の分析を重要と考えた組込みシステムの概要と,その背景・技術的な特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた組込みシステムにおける非機能要件の洗い出しに当たり,どのような観点で担当・部門を決定し依頼したか。各担当・各部門から報告された内容,分析・評価結果とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた非機能要件の評価結果及び製品戦略に適用したことの妥当性を,リリース後の売上実績,市場の反響などを含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H25:2013
【ST-H25-1-PM2-Q1】経営戦略実現に向けた戦略的なデータ活用について
事業者間の競争が激しくなる中,新規顧客の獲得,顧客満足度の向上などの経営戦略を実現するために有効な施策を立案し,実施することが重要になっている。事業に関連する社内外の様々なデータに着目して事業の現状を的確に把握したり,多方面から分析を行って変化の兆しをいち早く察知したりして,施策の立案に結び付けることができる,戦略的なデータ活用が注目されている。
例えば,戦略的なデータ活用による施策の立案としては,次のような事例がある。
・インターネット上の様々なWebサイトの情報を分析して一般消費者の潜在的なニーズ,他社の動向などを察知し,商品の企画,販売拡大などの施策を立案する。
・POS,電子マネー,ネット販売などの顧客の購買履歴データを分析し,商品の品ぞろえの見直し,顧客への新たな提案などの施策を立案する。
・設備,機器の稼働実績データを分析し,故障の予兆を察知して予防保全の提案を行ったり,運用改善の提案を行ったりする新たなサービスの提供などの施策を立案する。
ITストラテジストは,戦略的なデータ活用による施策の立案について経営者,事業責任者に説明するために,経営戦略上の有効性,運営体制,人材育成上の課題,他社の成功要因などの事項を検討しておくことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった経営戦略実現に向けた戦略的なデータ活用について,対象となった事業の概要と特性,及び戦略的なデータ活用を行うことになった背景を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた戦略的なデータ活用について,活用したデータと分析方法を明らかにするとともに,分析結果を踏まえて立案し,実施した施策を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた施策について,経営者,事業責任者に説明するために,どのような事項を重要と考えて検討したか。また,立案し,実施した施策に対する経営者,事業責任者からの評価について,改善すべき点を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H25-1-PM2-Q2】新たな収益源の獲得又は売上拡大を実現するビジネスモデルの立案について
インターネットなど情報通信技術の普及・発展によって,新たな収益源の獲得又は売上拡大を実現するビジネスモデルの構築が可能になってきた。
企業は,提供する商品・サービス,顧客との接点及び新規事業機会の創出に情報通信技術を適用することによって,新たな収益源の獲得又は売上拡大を実現することができる。例えば,次に挙げるような新しい概念の商品・サービス,顧客及びマーケットを対象としたビジネスモデルを立案することができる。
・商品を販売する事業ではなく,情報通信機能と組み合わせることによって,商品を使ったサービスの利用環境を提供するビジネスモデル
・インターネットを利用したシステムを導入することによって,個々の顧客に対して,商品・サービスを直接提供するビジネスモデル
・GPSや無線LAN通信技術を適用することによって顧客の行動,所在などの情報をタイムリに収集して,新たな商品・サービスの提供機会を創出するビジネスモデル
ITストラテジストに求められるのは,このようなビジネスモデルの立案において,ビジネスプロセスが技術的に実現可能であること,顧客・仕入先などの関係者から受け入れられること,投資対効果を確保できることなどの確認・検証を行い,その結果を経営者に提案することである。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが立案に携わった,新たな収益源の獲得又は売上拡大を実現するビジネスモデルについて,経営上の課題,目標及び立案することになった背景を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた経営上の課題,目標に向けて,どのようなビジネスモデルを立案したか。対象とした商品・サービス,顧客及びマーケットを明確にして,適用した情報通信技術を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたビジネスモデルの立案において,どのようなことの確認・検証を行い,その結果についてどのように経営者に提案したか。提案に対する経営者からの評価を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H25-1-PM2-Q3】組込みシステムの製品戦略におけるプロモーションの支援について
組込みシステムのITストラテジストは,市場動向と自社技術を踏まえて製品開発戦略を策定する役割を担う。また,製品の販売に関して,プロモーション部門及び営業部門(以下,営業部門という)を,的確に支援することが求められる。
企業にとって自信がある製品を開発しても,ターゲットとする利用者にまず製品が認知されなければ購入につながらない。その対応として最も重要なことは,高い訴求効果を得ることである。ITストラテジストは,営業部門に対して,開発計画時の市場調査の分析結果などを提示し,支援する必要がある。また,開発担当者を通じて,自社技術の要点,知的財産権などによって競合メーカとの差別化を図れる強みについて,利用者に対する営業部門の説明を支援することも重要である。さらに,営業部門から製品のサンプルなどの要求があった場合は,開発部門に対して提供時期などの計画の立案と実行を指示する必要がある。
次に重要なことは,プロモーション開始時期の決定である。ITストラテジストは,適切なプロモーション開始時期を見極めるために,販売開始時期を踏まえて営業部門などとプロモーション開始時期を協議し,検討する必要がある。プロモーション開始後は,営業部門から市場の反響や売上実績などの報告を受け,効果を評価し,その結果によって製品戦略を見直す必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステムの製品概要を,市場の特徴及び強みとなる自社技術を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品に関するプロモーションにおいて,営業部門及び開発部門に,どのような支援,指示を行ったか。また,それぞれの部門は,どのように行動したか。さらに,プロモーション開始時期の決定に当たって,どのような内容を協議し,検討したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた支援,指示内容及びプロモーション開始時期について,プロモーション開始後の市場の反響,売上実績などから評価した結果を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H24:2012
【ST-H24-1-PM2-Q1】ITを活用した事業戦略の策定について
企業は市場における競争力を高めるために,競合他社との差別化を図った製品・サービスの提供,コストリーダシップの実現,ニッチ市場への参入・拡大などの競争戦略を立案する。立案した競争戦略に基づき,ITストラテジストは,業種ごとの事業特性を踏まえて,ITを活用した事業戦略を策定し,経営トップ,事業責任者に対して提案する。競争戦略を実現するための事業戦略の例を示す。
・他社との差別化を図るために,店舗の販売責任者に,店内での売行き,顧客の動きをリアルタイムに提供して,サービス品質を向上させる。
・ローコストオペレーションのために,拠点間,企業間で情報を共有して連携し,バリューチェーンの再構築を行う。
・ニッチ市場での地位を確立するために,インターネット,モバイル機器などを活用した新しいサービスを提供する。
事業戦略の策定においては,その合理性,実現可能性などの観点から様々な検討を行う必要があり,ITストラテジストには,例えば,次のような分析が求められる。
・先進のITを活用した事例の詳細な調査・分析
・大幅な業務効率向上や他社との差別化が,ITの活用によって可能な業務プロセスの明確化と課題分析
・活用するITの機能・性能・信頼性などについての要求レベルの分析
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITを活用した事業戦略の策定において,前提となった競争戦略について,事業特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた競争戦略に基づき,どのような検討を行い,どのような事業戦略を策定したか。活用したITを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた事業戦略を経営トップ,事業責任者に対してどのように提案し,どう評価されたか。更に改善する余地があると考えている事項を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H24-1-PM2-Q2】事業継続計画の策定について
東日本大震災をはじめ,国内外で発生した災害・事故では,事業継続計画の重要性を再認識させられた。また,既に事業継続計画を策定していても,災害・事故の直接・間接の影響を受けて,計画の見直しを余儀なくされた企業・組織も多い。
ITストラテジストは,全体システム化計画の策定の中で,事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態などを的確に捉え,事業部門と共同で事業継続計画を策定しなければならない。事業継続計画には,基本方針,想定リスク,事業継続対象の範囲,目標復旧期間,実行体制などの項目が盛り込まれる。事業継続計画の策定においては,例えば,次のような点に着目して検討する必要がある。
・情報システムのハードウェア,ソフトウェア,データ,ネットワーク,ファシリティなどの管理実態を把握した上で,そこに存在する問題点を明確にする。
・明確化された問題点に対応するための事前対策を整理し,初期コストと運用費用を見積もり,対策のための投資の是非について,事業部門と協議する。必要に応じて,情報システムに関する基本的な考え方,構成の変更など,抜本的な対策についても検討する。
・事業部門,情報システム部門だけでなく,人事,総務などの間接部門を含めた全社的な人的リソース・スキルを把握し,災害・事故発生時の事後対策実行体制を確立するためのアクションプランを作成する。
事業継続計画の策定では,計画の実効性を高めることも重要である。そのために,情報システムの変更などに伴う計画内容の定期的な見直し,関連外部機関との相互支援体制の準備,計画に基づく教育・訓練の実施などについても,あらかじめ検討しておく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった事業継続計画の策定において捉えた,事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態について,どのような点に着目して事業継続計画を検討し,策定したか。策定した事業継続計画の概要とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた事業継続計画の実効性を高めるために,工夫した点は何か。更に改善する余地があると考えている項目を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H24-1-PM2-Q3】技術動向の分析に基づいた組込みシステムの企画について
組込みシステムのITストラテジストには,新たな組込みシステムの企画・開発計画,又は既存の組込みシステムの高機能化・多機能化のための企画・開発計画を策定し,推進することが求められている。付加価値及び競争力をもった組込みシステムの企画・開発をするためには,関連する技術動向の分析が重要であり,組込みシステムのITストラテジストには,的確で高い分析能力が求められる。
組込みシステムに関連する技術は,通信,情報,アーキテクチャ,ユーザインタフェース,ストレージ,半導体,計測,制御,プラットフォームなど多岐にわたっている。これらの技術動向の分析によって,開発対象の組込みシステムの付加価値及び競争力を高められる有用な技術を見極め,導入の適否を判断する。このとき,市場参入時期,開発スケジュール,開発コスト,検証容易性,保守容易性,製品の安全性,知的財産,国際標準,法令などについても考慮する必要がある。
例えば,無線通信と制御LSIの技術動向の分析結果から,開発が困難と考えていた省電力かつ低価格な組込みシステムの実現が可能になる場合もある。また,半年後に制定される見込みの国際標準にいち早く対応して開発すれば,市場競争力を高められる可能性もある。さらに,自社にない技術を外部から導入することによって,開発費を低減でき,開発期間短縮も期待できる。ただし,外部から技術を導入するときは,知的財産など,考慮すべき点が多い。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが技術動向の分析に基づいて企画した組込みシステムの性能,機能などの概要と,企画の背景及び目的について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた組込みシステムの企画に際して,どのような技術動向の分析を行ったか。また,分析の結果によって,付加価値及び競争力を高めるために取捨選択した技術は何か,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた技術動向の分析及び技術の取捨選択は,適切であったか。また,市場からはどのように評価されたか。更に改善する余地があると考えている事項も含め,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H23:2011
【ST-H23-1-PM2-Q1】情報通信技術を活用した非定型業務の改革について
事業方針・戦略を策定したり,次期の新製品・サービスの機能・性能を決定したりする非定型業務では,直面している問題の解決手順,共通の判断基準が定められていないことが多い。
非定型業務を改革するに当たっては,まず,例えば,次のような改革目標を設定する必要がある。
・業務処理の生産性を劇的に向上させる。
・問題解決の飛躍的なスピードアップを図る。
そして,顧客の視点から業務仕分けをすることによって,担当者が有用な業務に専念できるようにする。また,組織内外から問題解決に関して知見のある人材を探し出したり,問題解決に向けた協働作業を行えるようにしたり,情報の収集・共有・分析を行って問題解決を図れるようにしたりすることが重要である。
非定型業務の改革目標を達成するためには,情報通信技術の活用を検討し,必要なツールなどの導入を図ることが重要である。情報通信技術を活用したものには,スマートフォン,タブレット型PC,Wiki,SNS,Web会議システム,BI,ビジネスアナリティクス,検索エンジンなどがある。
また,改革目標を達成するためには,次のような工夫も重要である。
・組織の役割や構成を見直したり,コミュニティを活用したりする。
・これまでのワークスタイルを見直す。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが改革に携わった非定型業務について,事業の概要,業務の内容・特性,及び改革が必要となった背景を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた非定型業務において,どのような改革目標を設定し,どのような改革をしたか,活用した情報通信技術とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた改革目標を達成するために,あなたが特に重要と考え,工夫した点は何か。また,それらを実施した上で,更に改善できると考えた事項は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H23-1-PM2-Q2】事業の急激な変化に対応するためのシステム選定方針の策定について
企業は昨今,新規顧客を開拓するための新サービスの早期立上げ,競合他社に対する優位性を確保するための販売チャネルの急拡大や新製品の短期投入などへの対応に直面している。このような急激な変化に対し,開発期間の短縮,投資額の制限,開発要員の限定などの強い制約条件の下で,システムを更改したり,新規に構築したりする場合がある。
この場合,ITストラテジストは,まず,システムで実現しなければならない機能・性能・運用などの要件を整理する。次に,強い制約条件を考慮して,新業務プロセス,アプリケーションシステム,IT基盤などについて,例えば,次のようなシステム選定方針を策定する。
・既存のIT基盤で稼働しているソフトウェアパッケージ,アプリケーションシステムを利用し,新業務プロセスを既存の業務プロセスに合わせる。
・最適なクラウドコンピューティングサービスを選択し,利用する。
・新業務プロセス,アプリケーションシステム,IT基盤などをアウトソーシングする。
強い制約条件の下でシステムを稼働させ,業務が行えなければならないので,システム選定方針の策定に当たっては,次のことが重要である。
・新システムで対応できない業務プロセスの実現方法の確立
・新システムを使いこなすためのチェンジマネジメントの計画
・クラウドコンピューティングサービス,アウトソーシングサービスなどの詳細な調査・比較
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
事業の急激な変化に対応するためのシステム選定方針の策定に当たって,事業の急激な変化とあなたが考慮した強い制約条件は何か,事業の特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた強い制約条件を考慮した上で,あなたが策定したシステム選定方針及び策定した理由を,システムで実現すべき要件とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステム選定方針の策定に当たって,あなたが特に重要と考えて計画したこと,調査・比較をしたことは何か。また,それらを実施した上で,更に改善できると考えた事項は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H23-1-PM2-Q3】組込みシステムの企画・開発計画におけるリスク管理について
組込みシステムの企画・開発計画の策定及び開発計画の推進などのプロセスには,様々なリスクが存在する。これらのリスク管理について,組込みシステムのITストラテジストには,十分な知識,並びに,リスク分析結果の評価能力及び対応策決定能力が求められる。
企画・開発計画の策定において実施すべきリスク管理の対象は,市場動向,販売開始時期,価格設定,知的財産,標準規格,製品の安全性などである。
リスク管理では,次に示すようにリスク分析,リスク評価を行う。
(1)リスク分析では,まず,プロセスの成否に関わる要素に対して,直接的,間接的に影響を及ぼすリスク源を抽出する。次に,リスク源の発生頻度と影響度を求める。リスク分析で重要なのは,想定されるリスクとそのリスク源を全て洗い出すことである。
(2)リスク評価では,リスク分析の結果に基づいて,経営へのインパクトなどを評価し,どのリスク源に対して対応策を実施するのか,優先順位を含めて決定する。対応策には,リスク源の発生頻度や影響度の低減,リスクが現実化した場合の損失の移転・軽減などがある。対応策は,コストと有効性を評価して決定することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステムの企画・開発計画の策定において,市場動向を踏まえた企画の背景及び目的,並びに,その企画・開発計画の策定におけるリスク管理の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたリスク管理で,対応の優先順位が高いと決定したリスク源を順に三つ挙げ,それぞれの発生頻度,影響度及び対応策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対応策の有効性について,どのように評価したか。対応策を実施した各部門など他者からの評価も含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H22:2010
【ST-H22-1-PM2-Q1】事業環境の変化を考慮した個別システム化構想の策定について
個別システム化構想を策定する際には,事業環境の調査・分析の結果を基に,全体システム化計画と整合性をとりながら,システム化の目的,範囲,開発体制,導入時期,システム方式などの概略を決める。
昨今は,事業環境の変化が激しいことから,ITストラテジストは,事業部門との密接な情報交換を行いながら,例えば,次のような点について検討して事業環境の将来動向を把握し,個別システム化構想に反映させる必要がある。
・事業の外部環境(法規制の動向,他社の事業戦略や商品開発力の状況,顧客や利用者の評価など)の現状と今後の見通し
・事業の内部環境(財務状況,サービス体制,商品開発体制,システム状況など)の現状と今後の見通し
これらの検討結果から,既存システムの延命の是非,新システムの開発・導入の時期,システムの規模に応じた最適なシステム方式などを判断し,個別システム化構想を策定する。
なお,事業環境の変化に柔軟に対応できるシステムを構築するための工夫として,ソフトウェアパッケージを活用した迅速な導入と定着,SOAの適用,SaaSなどの外部サービスの利用なども重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった個別システム化構想の策定について,その概要を,事業の特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた個別システム化構想の策定に際して,事業環境の将来動向を把握するために検討した内容と,認識した事業環境の状況を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた事業環境の状況を踏まえて,変化に柔軟に対応できるシステムにするために,どのような個別システム化構想としたか。また,どのような点を重要と考え,工夫したか,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H22-1-PM2-Q2】情報システムの追加開発における業務の見直しについて
既存の情報システムが事業の変化に伴う業務の変更に適応できず,業務遂行に問題が発生すると想定される場合,情報システムの全面再構築ではなく,一部を改修したり,新たな機能を追加したりする追加開発を実施することがある。このような場合,追加開発に先立って業務の見直しを行うことで,情報システムの肥大化・複雑化を抑えることができるとともに業務の効率が向上したり,利用者の利便性が向上したり,情報システム運用の効率が向上したりする。
ITストラテジストは既存の情報システムの制約を考慮しながら,業務と情報システムの問題点を分析し,次のような観点から業務の見直しを進めることが重要である。
・業務ルールや業務分担の変更
・過剰業務,重複業務,低付加価値業務などの廃止・削減
・情報技術の一層の活用による業務の効率向上
情報システムの追加開発における業務の見直しでは,利用者・利用部門が従来の業務・情報システムに執着し,業務の見直しに消極的なことも多い。この点に配慮してITストラテジストは,業務の見直しを進めるに当たって,利用者・利用部門の意識改革を進める必要がある。具体的には,現行業務を十分に理解し,全体最適化・コスト最小化の視点から,業務と情報システムの問題点を指摘してその解決策を提示したり,利用者の利便性向上や情報システム運用の効率向上に関して説明したりして,理解・協力を得ることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの追加開発の背景と概要について,業務の特性とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの追加開発に当たり,あなたはどのような観点で業務の見直しを行い,その結果,何がどのように向上したか。あなたが考慮した既存の情報システムの制約とともに,800字以上1,600字以内で述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務の見直しに当たって,利用者や利用部門の理解・協力を得るために,あなたが特に重要と考えて工夫した点を,600字以上1,200字以内で述べよ。
【ST-H22-1-PM2-Q3】既存製品の性能向上,機能追加を目的とした組込みシステムの製品企画について
自社の組込みシステムの既存製品に対して,市場での競争力を強化するために,性能向上や,機能追加を図ることがある。例えば,省エネルギー化,小型化,大型化,長寿命化,高速化などによって,他社よりも優れた製品を提供できれば,市場で訴求力を発揮できる。
性能向上,機能追加の内容は,製品の特性,背景などによって異なる。製品企画の立案に際しては,どの場合も,性能・機能に対する社会の要請及びユーザニーズを見極める必要があり,次のような項目について考慮することが重要である。
・実現すべき性能・機能とコストとの関係
・実現すべき性能・機能と自社保有技術との関係
・製品のライフサイクル,販売開始時期,販売価格などの戦略
・関連技術の動向及び知的財産
・拡張性及び柔軟性
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった“性能向上,機能追加を目的とした組込みシステムの製品企画”の背景と概要について,既存製品の性能・機能,特徴とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた製品企画を立案する際に調査し,検討した項目及びその内容を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた内容に基づいて立案した製品企画では,どのような性能向上,機能追加を盛り込んだか。また,立案した製品企画を実現するために,どのような点について配慮したか。立案した製品企画に対する現在のあなたの評価及び他者の評価を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H21:2009
【ST-H21-1-PM2-Q1】事業施策に対応した個別情報システム化構想の立案について
企業では,事業戦略に基づいて,より具体的な事業施策を策定する。ITストラテジストは,事業施策の背景や目的を十分に理解した上で,情報システムが果たすべき役割を見極め,個別情報システム化構想を立案しなければならない。個別情報システム化構想の立案に当たっては,事業施策に対する情報システムの有効性を示しながら,例えば次のような仕組みを検討する必要がある。
・通信販売の強化策への対応では,事業の拡大スピードに対応できるシステム方式や販売物流の仕組み
・製造拠点の海外展開策への対応では,グローバルな生産協調や現地事情を考慮したシステム運用の仕組み
・顧客の維持・拡大策への対応では,営業情報の有効活用,素早い伝達や新たな営業機会創出の仕組み
これらの検討結果を基に,個別情報システム化構想の投資効果を更に高めるために,既存システムの改修か新規開発か,ソフトウェアパッケージの利用か個別開発か,情報システムの自社保有か外部サービス利用かなど,情報システムの構築方法について様々な検討や工夫を加えることも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった個別情報システム化構想の立案対象となった事業施策の概要と,情報システムが果たすべき役割を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業施策に対応した個別情報システム化構想を立案する際に検討した仕組みの内容と,その結果を基にして立案した個別情報システム化構想の概要を,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた個別情報システム化構想の立案において,投資効果を高めるために,情報システムの構築方法についてどのように検討し,工夫したか,また,その結果をどのように評価しているか,600字以上1,200字以内で述べよ。
【ST-H21-1-PM2-Q2】情報システム活用の促進策の立案について
業務の効率向上や意思決定の迅速化などを目的に情報システムの導入を計画し,システム要件どおりに導入したが,活用が進まず,導入の目的を達成できない場合がある。活用が進まない原因として,例えば次のようなことが考えられる。
・情報システムの機能を十分に活用するためのノウハウの共有が不十分で,利用者は一部の機能しか使っていない。
・利用部門の管理者のリーダシップが足りないので,利用者に情報システムの利用を徹底できない。
・正確なデータがタイムリに入力されないので,必要とする情報が必要なときに入手できない。
このような例では,活用を進めるための直接的な対策として,情報システム活用のノウハウに関するトレーニング,管理者の意識改革,データ入力チェックリストの制定などが挙げられる。
しかし,直接的な対策だけでは,活用が進まないことがある。多くの場合,幾つかの原因があって,それらの間に関連があったり,隠れた原因があったりする。したがって,ITストラテジストは活用が進まない真の原因を分析し,有効な対策を検討する必要がある。その上で,実行手順・対象範囲・期間・体制などを明確にした情報システム活用の促進策を立案しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが活用の促進策を立案した情報システムの概要と導入の目的について,事業や業務の特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムが活用されない真の原因について,あなたの分析の結果を,分析の観点を含めて800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた分析の結果,あなたは情報システムの導入の目的を達成するために,どのような促進策を立案したか,工夫した点とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【ST-H21-1-PM2-Q3】開発工程の遅延に対処するための組込み製品の企画の変更について
新しい機能をもつ組込み製品の企画に際しては,ターゲット市場の動向,競合他社の動向,社会的制約,自社の営業力,実現可能性といった様々な情報を分析し,市場で最も有利な時期に販売を開始できるようにすることが重要である。ところが,開発工程の遅延によって,意図した時期に販売を開始できなくなることがある。
例えば,新機能の一部の実装に手間取り,開発要員を追加投入しても予定していた販売開始時期までにすべての機能を実装できなくなることがある。このようなとき,“販売開始時期を遅らせる”,“一部,機能制限のある製品を先に販売開始し,すべての機能を実装した製品の販売を少し延期する”など,組込み製品の企画を変更しなければならないことがある。
開発工程の遅延に対処するために,組込み製品の企画を変更する場合,次のような点について分析や検討を行って,変更案をまとめる必要がある。
・追加の開発投資が発生したときの採算性
・販売開始が遅れたときの,競合他社に対する優位性への影響
・企画変更後のスケジュールと実現可能性
・先に販売開始するとしたときの,一部,機能制限のある製品と,販売時期をずらしてすべての機能を実装した製品とにおける,機能差と価格差との間のバランス
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった組込み製品の企画のうち,開発工程の遅延に対処するために,企画の変更によって販売を実現させた製品について,その製品の概要を,機能や特徴,製品戦略なども含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた組込み製品の企画の変更において,要因となった開発工程の遅延の内容と遅延が発生した理由は何か。また,その対処のためにあなたはどのような点について分析し,検討したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた分析・検討の結果,あなたはどのような変更案を作成したか。また,その後の販売開始に至るまでの状況の変化や,採用されなかった変更案との比較なども含めて,採用した変更案をどのように評価しているか。600字以上1,200字以内で述べよ。
📗H20:2008
【AN-H20-1-PM2-Q1】情報技術を活用した労働生産性向上のための新たな業務モデルの定義について
我が国は,欧米先進国と比較して,労働生産性(一定の労働コストに対する生産高の比率。以下,生産性という)が低いと指摘されている。しかし,日本企業の中にも,情報技術を使って高い生産性を実現している企業が出てきている。
システムアナリストには,生産性向上のために,情報技術を活用した新たな業務モデルの定義を行うことが期待される。生産性向上のためには,まず,業務を見直した上で,次のように,コスト削減と収益向上のための競争優位性の強化の両面をにらんで,新たな業務モデルの定義を行う。
・コスト削減を優先すべき業務については,情報技術を活用したセルフサービスの導入,自動処理,シェアードサービスの導入,オフショアの利用など
・競争優位性の強化を優先すべき業務については,情報技術を活用した意思決定の支援,経験や知見の組織的な共有など
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,生産性向上のための情報技術を活用した新たな業務モデルの定義について,その概要を,必要となった背景,直面していた課題を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた新たな業務モデルについて,どのように業務を見直し,定義したか。特に重要と考え,工夫したことを中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた新たな業務モデルの定義に対して,経営者からの評価に基づいて,今後に残された課題と取組方針を簡潔に述べよ。
【AN-H20-1-PM2-Q2】情報システム導入の際の業務革新を支援するチェンジマネジメントについて
近年,情報技術を活用したシェアードサービスや,ビジネスプロセスアウトソーシングなどによってサービス向上やコストダウンを図る企業が増えている。このような場合,情報システムの導入と同時に,業務プロセスや,社内や社外との役割分担を見直す業務革新が必要である。
業務革新の推進においては,関係者間での意見の相違や利害の対立が生じることも多い。システムアナリストは,情報システムの構築を支援することと併せて,情報システムの利用部門が主体となって実施する業務革新を支援する。具体的には,導入する情報システムの定着を図り,業務プロセスや役割分担の変更を促し,それらの状況を管理する,チェンジマネジメントを行う。
チェンジマネジメントは,次のような観点から実施することが重要である。
・システム導入に伴う利害,及び利害関係者の明確化
・利害関係者とのコミュニケーションと業務革新への動機付け
・業務革新の目的やゴール,業務プロセス,役割分担の共有
・意識改革や業務プロセスの変更状況のモニタリング
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,情報システム導入の際の業務革新について,その概要を経営目標などの背景とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務革新を支援するチェンジマネジメントをどのように実施したか。チェンジマネジメントが必要になった理由,重要と考えた点,工夫点などとともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたチェンジマネジメントについて,あなたはどのように評価しているか。今後,改善したい点とともに簡潔に述べよ。
【AN-H20-1-PM2-Q3】システム化全体計画の策定について
システム化全体計画の策定に当たっては,まず,社内各部門から出される個別システム化案件ごとに,システム化の目的,範囲,費用対効果などを検討した上で,経営戦略との整合性を考慮して,実施すべき案件を絞り込む。
次に,個別システム化案件の,システム化の範囲や方法,開発体制,開発スケジュールを全体的にとらえてシステム化全体計画を調整する。効率が良く,効果的なシステム化全体計画にするために,次のような観点で検討することが重要である。
・個別システム化案件の優先順位や開発スケジュールを調整することによって,開発体制,移行と安定稼働,システム導入効果の実現,利用技術などにまつわる実施上のリスクを低減できないか。
・個別システム化案件の間で,機能の共通化やシステム間連携の標準化の可能性を検討することによって,効率の良い開発・導入ができないか。
・ソフトウェアパッケージ,外部サービスなどを利用した,新たな発想によるシステム化の方法を採用できないか。
・オフショア開発など,費用を削減するための開発体制を構築できないか。
システムアナリストは,これらについて検討し,関連部門と調整した上で,システム化全体計画を策定しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に携わったシステム化全体計画の概要を,システム化の実現方法,全体の体制やスケジュールを含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム化全体計画の策定に際して,すべての個別システム化案件を全体的にとらえて,効率が良く,効果的なシステム化全体計画にするために,どのような観点から検討して計画を作成したか。特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステム化全体計画の作成について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【SD-H20-1-PM2-Q1】提供サービスの競争力強化を図るためのIT活用について
企業や組織が,競争力のあるサービスを提供するためには,サービス自体の高度化や差別化を図るとともに,IT活用についての徹底した検討が欠かせない。各種の予約や照会,会員向けの情報提供,製品のサポート受付や情報提供など,様々なサービスにITが活用され,競争力強化に寄与している。例えば,インターネット上での金融機関のサービスや宅配便のきめ細かな荷物照会サービスは,高度なIT活用に支えられている。
こうしたサービスでは,PCや携帯電話でのネットサービスなど多様な手段を提供して,顧客にITを直接利用させることが多くなってきている。競争力強化のためには,次のようなサービス関連情報の収集・分析が重要になる。
① 自社のサービス及び競合するサービスの現状と課題
② 自社のサービス及び競合するサービスでのIT活用状況
③ サービスやIT活用に対する顧客のニーズ
顧客にとって魅力あるサービスを提供できるように,これらの分析結果を基に,IT活用方針を定め,実現する内容・手段・技術に独自の工夫を取り入れる。さらに,サービス提供時間の拡大,利用の簡便さ,レスポンスの速さ,エラー時の対応の容易さなど,顧客視点からの改善も加えて,競争力強化を図る。
上級システムアドミニストレータには,IT活用による工夫や改善が顧客に高く評価され,企業や組織にとって大きな成果となるように,適宜,評価を確認し,改善に取り組んでいくことが期待されている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,サービスの競争力強化を図るための取組みについて,そのサービス及びIT活用の概要を,あなたの立場とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたIT活用において,競争力強化のために,どのような情報の収集・分析を行ったか。また,分析結果を基に,どのような工夫や改善を行って,IT活用による競争力強化を実現させたか。具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた取組みの結果をどのように評価しているか。評価で判明した課題や更なる競争力強化のための取組みについて,簡潔に述べよ。
【SD-H20-1-PM2-Q2】顧客層を拡大するためのデータ活用について
企業が業績の拡大を目指すには,顧客層を拡大することが重要である。様々なデータを活用して,顧客や市場の動向を的確に把握し,新製品の開発や店舗での品揃えの充実などの施策を実施することが求められる。
例えば,大規模小売店では,社内に蓄積されている売上データを商品別,年代別,性別又は地域別に分析することで,商品の売上傾向や顧客の購買傾向を把握することができる。競合店の折り込みチラシの調査や現地調査を実施したり,市場調査レポートなどの外部データを活用したりして,市場の動向や顧客の購買動向をつかむこともできる。これらの分析結果や調査結果を基に,競合店と比較して,自店の強み・弱みを把握し,店舗での品揃えの充実や価格戦略などの施策を実施することは,顧客層を拡大するための重要な手段となる。また,競合店の動向を注視しながら,販売促進のキャンペーンを実施することも,有効な施策となる。さらに,これらの施策を実施するだけでなく,刻々と変化しているマーケットの動きや顧客の嗜好などをタイムリーに把握し,一度実施した施策に改良を加えたり,違った観点からの新しい施策を追加したりすることも必要である。
上級システムアドミニストレータには,社内外のデータを活用して,顧客層を拡大するための施策を実施するとともに,実施した施策の効果を継続的に検証し,次の施策に反映させる役割が求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが顧客層を拡大するために実施した施策の概要について,あなたの立場とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた施策の立案に際して活用したデータと,その分析結果を述べよ。また,分析結果を施策にどのように役立てたか。そのねらいも含めて具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた施策の実施結果をどのように評価し,次の施策にどのように反映させようと考えているか。簡潔に述べよ。
【SD-H20-1-PM2-Q3】内部統制の取組みにおけるIT業務処理統制について
企業においては,直面する様々なリスクに対応するために,内部統制の重要性が増している。内部統制の一部であるIT統制は,IT全般統制と個別の業務システムにかかるIT業務処理統制とに分けられる。利用部門が深くかかわる後者は,業務システムにおいて,承認された業務がすべて正確に処理,記録されることを確保するために業務プロセスに組み込まれたITにかかる内部統制である。
IT業務処理統制としては,取引データの信頼性(完全性,正確性,正当性)の確保やエラー処理への対応,マスタファイルの正確な更新などが挙げられる。例えば,販売システムでは,すべての売上が漏れなく,正確な内容,金額で計上され,請求書の発行や入金管理に問題がないかどうかの確認が必要になる。そのためには,取引デー夕に誤りや不正が生じるリスクに対しては,それぞれの業務は権限をもつ人が社内ルールどおりに処理しているか,データ入力者以外が入力結果をチェックしているか,システムによって処理件数などを照合しているかなど,具体的な統制方法を決める必要がある。さらに,サンプリングチェックや定期的な確認・照合など,統制評価の手続も明確にしておくことが求められる。
上級システムアドミニストレータには,業務プロセス上のリスクを明らかにし,リスクに対応するために適切なIT業務処理統制と統制評価の手続が取られるよう取り組むことが期待されている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたがかかわったIT業務処理統制の取組み体制と担当した業務システムの概要について,あなたの役割も含めて800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたIT業務処理統制の検討において,担当した業務システムの業務プロセス上で重大なリスクと判断した事項は何か。複数の事項を挙げ,それぞれに対する統制方法について,工夫した点を含めて,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた各事項の統制方法について,どのように評価しているか。統制評価の手続も含めて,簡潔に述べよ。
📗H19:2007
【AN-H19-1-PM2-Q1】システム化全体計画におけるシステムアーキテクチャについて
個別に開発された情報システムは,ハードウェア,OS,DBMS,アプリケーション構造などの基本方針としてのシステムアーキテクチャが総合的に検討されていないので,全体の整合性に欠けることが多い。また,新規システムと既存システムとの連携にコストや時間が掛かる,運用や保守のために複数の体制が必要になる,セキュリティ対策が煩雑になる,新技術への適応が難しい,などの問題を抱えていることも多い。このような問題を解決するために,プラットフォームの統一,Web化,セキュリティ管理方針の制定,SOA(Service Oriented Architecture)への移行などのシステムアーキテクチャを検討する必要がある。
システムアーキテクチャを検討する際には,例えば,次のような観点から総合的に現状と対比することが重要である。
・開発・運用・保守の経済性や効率性
・制度改正などの事業環境変化への適応性
・技術者の確保・育成の容易性
・利用している技術の将来性
システムアナリストは,システムアーキテクチャの検討後,システムの全体像,既存システムの移行方針,今後開発するシステムへの適用方針,予算などを検討し,システム化全体計画に反映させる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが検討に携わったシステムアーキテクチャの現状と問題点,及びシステム化全体計画の概要を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム化全体計画における基本方針としてのシステムアーキテクチャはどのようなものであったか。また,どのような観点から,総合的に現状と対比したか,あなたが重要と考えた点とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステムアーキテクチャについて,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【AN-H19-1-PM2-Q2】リスクに対応する統制方針に基づいた情報システム構想の策定について
昨今,有害物質が食品に混入するなど,品質面や安全面で事故を起こした場合に,発見が遅れたり,対応が不適切であったりすると大きな経営責任問題になることがある。このような事態に陥らないように,企業は,対応すべきリスクの特定,リスク発生の予防策,発生した場合の対応策などを明確にした統制方針(以下,リスク統制方針という)を定める。このリスク統制方針を実現するために,情報技術を導入して対応を図ることが多くなっている。例えば,次のようなものである。
・食品の安全確保のために,RFIDを活用してトレーサビリティを強化する。
・医療過誤防止などの業務品質向上のために,カルテなどにバーコードを付けて業務ミスをなくす。
・迅速かつ的確なクレーム対応のために,コールトラッキングシステムや音声認識システムを活用して統合コールセンタを構築する。
リスク統制方針に基づいた情報システム構想の策定においては,導入する情報技術やシステム化範囲によって投資額が大きく左右される。システムアナリストは,リスク統制方針に基づいて業務プロセスを設計し,その業務プロセスを実現する情報技術活用の方針を策定する。その上でシステム化範囲を決め,情報システム構想を策定する必要がある。
その際,品質面や安全面のリスクが発生した場合の影響度や損害予想額,情報技術活用への投資額,運用体制などの実現可能性を検討することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,リスク統制方針に基づいた情報システム構想の策定について,想定されたリスクとリスク統制方針の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたリスク統制方針に基づいて,あなたはどのような情報システム構想を策定したか。あなたが情報システム構想において重要と考え,検討した点とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システム構想の策定について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【AN-H19-1-PM2-Q3】経営意思決定を支援するための情報システム構想の策定について
多くの組織で,関係者が様々な経験や情報を共有し,合理的な意思決定を行うために,経営意思決定を支援するための情報システムが導入されている。しかし,現実には,情報システムの本来の導入目的・役割を果たしているとはいえない状況がある。ERPなどの基幹系情報システムに蓄積されている情報だけを経営者に提供するという情報システムも多い。
このような現状から,意思決定に有効な情報を社内外から収集し,経営者に提供する情報システム構想の策定が求められている。経営者が合理的な意思決定を行えるようにするためには,次に挙げるように,重要な意思決定は何か,その意思決定に当たって本当に必要としている情報は何か,その情報をどこから収集し,どのように経営者に提供するかという観点で,情報システム構想を策定する必要がある。
・新商品や新サービスの企画にかかわる意思決定のケースでは,競合他社の動向,市場や顧客の意見などの情報が重要である。業界団体などからの他社の販売情報,インターネット上の書込み情報,新聞掲載情報などを収集し,経営者に提供する。
・製品やサービスの品質にかかわる意思決定のケースでは,設計上や製造上の不具合に対応するために,技術的な解析結果や社内外の対応実績の情報などを組織で共有する。
・企業の社会的責任を果たすための意思決定のケースでは,顧客の生の声が重要である。顧客からのクレーム情報などを経営者に直接提供する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが構想の策定に携わった経営意思決定を支援するための情報システムについて,必要になった背景及びシステムの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムが支援する意思決定,提供する情報,情報源及び提供方法について,あなたはどのように検討し,構想を策定したか。経営者が合理的な意思決定を行えるように,工夫した点とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システム構想について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【SD-H19-1-PM2-Q1】経営環境の変化に対応した情報システムの見直しについて
営業対象先の拡大や顧客ニーズの多様化などによって,企業の経営環境が,目まぐるしく変化している。そうした変化に対応して業務効率を維持し,向上させていくためには,業務プロセスの見直しが重要である。また,業務プロセスの変更に併せて,情報システムについても見直しをしないと,効率よく運用できない場合が多い。
例えば,顧客サービス部門で,多様化し,高度化する顧客のニーズに的確に対応するために,従来から保有していた顧客名,住所,電話番号などの顧客情報に加え,顧客の嗜好,取引状況,家族構成などのきめ細かな情報を保有し,活用する必要がある。そのために,顧客情報の収集方法や活用方法に様々な工夫が求められるので,情報システムに新たな機能が必要になる。また,法人向け営業が主であった営業部門が,新たに個人向け営業を展開する場合は,現行業務プロセスに,個人向けの業務プロセスを追加する必要がある。さらに,個人向けサービスの向上を図るために,サービス部門の機能拡充も必要になり,関連する情報システムの対応も求められる。
新業務プロセスに必要な機能が,既存の情報システムで実現できない場合には,情報システム部門と連携し,新たな情報システムの検討が必要となる。
上級システムアドミニストレータは,新業務プロセスの機能要件を明確にし,利用部門の立場から情報システムの見直しに参画する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
経営環境の変化に対応し,業務プロセスと情報システムを見直した事例の概要を,あなたの役割を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,新業務プロセスに必要な機能を既存の情報システムで実現できるかどうかをどのように分析し,対策を講じたか。具体的に述べよ。また,機能要件を情報システムで実現する過程で明らかになった問題点とその解決策について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イでとった解決策をどのように評価しているか。着手できなかった課題や新たに明らかになった課題とともに述べよ。
【SD-H19-1-PM2-Q2】コスト低減のためのデータ活用について
海外市場における競争激化など,企業における価格競争力の重要性が増している。コスト低減のためには,コストの現状を分析し,改善策を立案し,実行につなげていくことが必要である。現状の分析では,データを収集して,様々な切り口で分析し,コスト構造を明らかにすることが重要である。
例えば,製造業においては,原材料の仕入れ,製造,在庫管理,品質管理,出荷作業などの各工程の直接費だけでなく,製造機器の維持管理費用などの間接費も含めた製造原価を把握し,どのコストに注目すべきか,適切な手法で分析する必要がある。売上データと製造原価を製品別,工程別の切り口で分析することによって,具体的なコスト低減策の立案が可能となる。例えば,利益率の低い製品については,その原因となっている工程のプロセス改善によって,製造原価を低減することができる。
同様に,飲食店などのサービス業においても,仕入れ,在庫管理,調理,配膳,片付け,会計などの各部署の要員の稼働率を把握するとともに,店舗の賃借料や水道光熱費などの維持管理費用を把握し,分析する必要がある。売上データと要員の稼働率などを,曜日別,時間帯別の切り口で分析することによって,具体的なコスト低減策の立案が可能となる。例えば,要員の稼働率が低い部署については,要員配置の無駄をなくし,人件費を削減することができる。
売上データとコストに関するデータを,製品,サービスだけでなく,顧客別,店舗別などの切り口で分析し,収益拡大につながる具体的な改善策を立案し,実行できるようにすることは,上級システムアドミニストレータの重要な役割である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたがコスト低減策の立案のためにデータ活用した事例の概要を,業務の背景とあなたの役割を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,コスト低減策を立案し,実行できるようにするために,どのようなデータを収集し,どのような切り口で分析したか。コスト低減策の内容とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イの分析結果に基づいて実行したコスト低減策に対する評価と今後の課題について,簡潔に述べよ。
【SD-H19-1-PM2-Q3】トラブル対策に関する情報システム構築段階からの取組みについて
情報システムの本番稼働後に,予期せぬ様々なトラブルに見舞われるケースは少なくない。例えば,受発注や生産,物流などの業務の中枢を担っている情報システムでトラブルが発生すると,多数の顧客や取引先に影響を及ぼし,対応を誤ると大きな被害を生じ,企業として非常に深刻なダメージを受けるおそれもある。
情報システムがトラブルなく,安定して稼働していることは,利用部門にとって必須の要件である。そのために,想定されるトラブルのケースを,システム構築段階から漏れなく洗い出して予防策を組み込むことや,発生した場合の対処を検討しておくことが,利用部門に要求される。利用部門が主体的にかかわる事項としては,検収テストの徹底,分かりやすい利用マニュアルの作成,利用者教育の徹底,トラブルケース別の緊急体制や情報システム停止中の代替策の検討などが挙げられる。
万が一,トラブルが発生した場合,利用部門は業務への影響を最小限に抑えるために,情報システム部門と協働して,トラブルの状況を速やかに把握し,適切に対処する必要がある。情報システムの復旧見通しがはっきりしない場合には,影響が予想される顧客や取引先などに対し,いつ,何を,どのような方法で伝えるか,また,復旧までの間,業務をどのように行っていくかなど,迅速かつ的確な判断と代替策の実施が求められる。こうした場合に備えて,業務やデータ,顧客別の処理の優先度などを考慮して,本番稼働までにあらかじめどのように対処するかを検討し,対処策を具体的に決定しておくことが望ましい。
上級システムアドミニストレータは,利用部門を代表して,こうした課題に対して主体的に取り組んでいく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが利用部門の立場でトラブル対策に取り組んだ情報システムの概要を,あなたの立場と役割を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの構築段階で,利用部門としてトラブル予防のために取り組んだ内容と工夫を具体的に述べよ。また,トラブル発生時に,利用部門では,状況に応じてどのように対処することにしたか。緊急体制や代替策などについて,具体的に述べよ。
■設問ウ
本番稼働状況を踏まえ,設問イで述べたトラブル対策に対する評価と,改善を図った事項や課題について,簡潔に述べよ。
📗H18:2006
【AN-H18-1-PM2-Q1】情報システム投資の中長期計画の策定について
企業では,情報システム投資の中長期計画の中で,数年間の情報システム投資の優先順位を明らかにする。システムアナリストは,経営戦略を踏まえて,投資すべき分野や配分を検討した上で,各部門から出された情報システム化案件を選別し,経営戦略上不可欠な案件を加味して情報システム投資の中長期計画を策定する。その際,例えば,次のような観点から案件を評価することが重要である。
・業務効率向上,在庫削減,納期短縮など,情報システム投資を必要としている経営課題の重要度
・法的制度及び社会的制度の変更,セキュリティ対策など,経営環境の変化に対応する情報システム投資の緊急度
・情報活用,基盤整備,研究開発など,情報システム投資の戦略性
システムアナリストは,情報システム化案件の重要度,緊急度,戦略性,投資額と期待効果などを総合的に評価して,中長期計画を策定しなければならない。その際,定性的な項目についても客観的な評価ができるように工夫をすることで,経営戦略を踏まえた投資額の妥当性や優先順位の根拠を示すことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に携わった情報システム投資の中長期計画の概要を,背景にある経営戦略とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた計画の策定に当たり,経営戦略を踏まえて,情報システム化案件をどのような観点で総合的に評価し,投資額や優先順位をどのように決定したか。あなたが特に重要と考え,工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた計画の策定に当たって工夫した点について,あなたはどのように評価しているか。また,今後改善したい点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【AN-H18-1-PM2-Q2】競争力強化のための情報システム化案の作成について
昨今,競争力強化のためにITを活用して,ビジネススピードの向上,新たな顧客サービスの提供,業務コストの大幅な削減などへの取組が行われるようになっている。
システムアナリストは,競争力強化のために,次のような情報システム化案を作成する必要がある。
・顧客の待ち時間を大幅に短縮するために,複数部門にまたがって数週間かかっている契約プロセスを,データを一元管理するシステムによって契約窓口で即時に完了できる契約プロセスに変更する。
・顧客サービスの向上及び営業の業務効率向上のために,営業担当者が見積書を作成して顧客に提出するプロセスを,インターネットを利用して顧客が条件を入力すると,売値を即時に算出できるプロセスに変更する。
・売れ残りや品切れを減らすために,人の経験と勘による発注プロセスを,POSシステムを有効に活用して適正量を発注するプロセスに変更する。
システムアナリストは,このような情報システム化案の作成に当たって,ITを活用した業務プロセスを再設計する必要がある。業務プロセスの再設計においては,顧客から見た価値を高めるという視点で必要業務を抽出して付加価値を生まない業務を見直すこと,複雑な判断や専門的な作業の一部をITに置き換え業務を高度化すること,などの工夫が重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが作成に携わった競争力強化のための情報システム化案について,背景となった事業の競争状況及び事業の課題を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業について,どのような競争力強化のための情報システム化案を作成したか。その作成に当たり,ITを活用した業務プロセスの再設計において,あなたが特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システム化案の作成について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【AN-H18-1-PM2-Q3】業務統合におけるシステム化計画の策定について
近年,部門ごとに実施されていた受注業務の集中,グループ企業全体での共同購買,人事や経理のシェアードサービスなどの業務統合が増えている。
このような業務統合において,経営層や企画部門などからは,業務効率向上の目標として,業務処理日数,サービス開始時期などが提示される。システムアナリストは,それらの業務統合の目標達成に向けてシステム化計画を策定する。
業務統合におけるシステム化計画の策定では,統合後の新たな業務プロセスとシステムの全体像,新規開発や部分改修などのシステム開発方針,既存システムとの連携方針,マスタスケジュール,体制などを明確にする必要がある。
システム化計画の策定に当たって,システムアナリストは,次のような点に考慮することが重要である。
・できる限り例外が発生しない,標準の業務プロセスを設計すること
・既存システムの改修の規模を算定し,新規開発の場合の規模と比較した上で,システム開発方針を策定すること
・既存システムなど多くのシステムとの連携が必要な場合には,システム連携基盤の導入によって開発期間を短縮し,開発コストを抑えること
・システム開発やシステム移行だけでなく,ユーザ教育や業務移行などの手順と体制を明確にし,マスタスケジュールを立案すること
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に携わった業務統合におけるシステム化計画について,背景となった業務統合の概要及び目標を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの業務統合において,あなたはどのようなシステム化計画を策定したか。あなたが業務統合の目標を達成するために,特に重要と考え,工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステム化計画について,あなたはどのように評価しているか。また,今後改善したい点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SD-H18-1-PM2-Q1】経営的視点からの情報システムの選択について
新たな事業展開や,既存事業の変革又は大幅な拡大などに際して,関連する情報システムの整備は必須である。整備を進める際には,独自開発やソフトウェアパッケージ導入による自社システムの構築が適当か,ASPやアウトソーシングなどの外部専門サービスの利用が適当か,それらの組合せが適当かなど,利用部門としても慎重な判断が求められる。この判断は,経営的視点から,対象となる情報システムをどのように位置付けるか,機能面や性能面,運用面での必須要件は何か,稼働時期やコストをどう考えるかによっても異なる。
外部専門サービスは,給与計算関係業務では長年にわたって多くの実績があり,近年はほかの業務でもメニューが充実してきている。インターネットショップは,外部専門サービスで手軽に構築できる。CRM,SFA,業種ごとのメニューなども増加している。事業の先々の見通しが不透明な場合でも早期に必要な環境を用意し,その後の状況を見て柔軟に対応するために,こうしたサービスを利用するケースがある。一方で,将来にわたる競争力や自社でのノウハウ蓄積のために,時間やコストがかかっても自社システムの構築を選択するケースもある。また,自社システムの構築と外部専門サービスの利用の組合せ範囲を見直したり,組合せ方式からいずれかに切り替えたりすることもある。
利用部門は情報システム部門とも十分に協議を重ねた上で,経営的視点から対象事業の目的や特性にふさわしい情報システムを選択することが求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
新たな事業展開や事業の変革,拡大などを支援する情報システムの企画検討の際,自社システムの構築と外部専門サービスの利用との比較・検討をしたケースにおいて,対象とした業務と情報システムの概要,あなたの役割について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの比較・検討において,経営的視点による選定基準を挙げ,自社システムの構築と外部専門サービスの利用のそれぞれについて基準の項目をどう評価し,選定したか。また,その際,利用部門として,特に検討を要した事項について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アでの経験を踏まえ,今後同様なケースで情報システムを選択する場合,手順,方法及び判断において改善すべき事項を簡潔に述べよ。
【SD-H18-1-PM2-Q2】ソフトウェアパッケージ利用における業務プロセスやルールの見直しについて
経営上の判断や全体最適の視点からソフトウェアパッケージ(以下,パッケージという)の利用を決めるケースも多いが,利用部門にとっては自社開発以上の困難に直面することがある。
パッケージの利用を想定して準備を進める場合においても,まず現状を分析し,解決すべき問題点や達成すべき目標を明確にし,あるべき業務プロセスを検討しなければならない。その上で,パッケージが備える機能,業種・業務特性との適合性,自社の要件との整合性などについて,どのような差異があるかを明らかにしていくことになる。
パッケージのカスタマイズは極力抑制し,回避することが望ましいが,競争力の源泉となる自社特有の処理や取引先との関係などに絞り込んで,最小限のカスタマイズや追加開発も行われる。しかし,こうした対応によっても,システムに期待される要件のすべてを充足することは難しい。多くの場合,パッケージの機能や対象業務範囲の制約から,それまでに検討してきた業務プロセスや処理ルールを見直したり,代替策や運用面で工夫したりすることになる。
利用部門はこうした事態を受け入れ,当初想定したあるべき姿との間で生じる差異に対し,新たな発想で再度業務を見直し,ビジネス上の目的実現に向けて取り組むことになる。上級システムアドミニストレータは,利用者に大きな負担がかかったり,重大な問題が起きたりしないように,関係者と協働していく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
パッケージを利用して実現した業務プロセスの概要について,パッケージ利用の経緯とあなたの役割を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたパッケージ利用に当たり,それまでに検討してきたあるべき姿との間でどのような差異が生じ,どのような問題に直面したか。差異が生じた際,問題解決のために実施した業務プロセスや処理ルールの見直しの内容,代替策や運用面での工夫について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イでの対応について,システム稼働後の業務状況を踏まえ,あなたはどう評価しているか。また,今後改善すべき課題と対応方針について,簡潔に述べよ。
【SD-H18-1-PM2-Q3】業務改善におけるデータ活用について
企業は,継続的に業務を改善し,業務のスピードアップを図るなど,業務運営の効率向上を目指している。そのためには,様々なデータを活用し,現状を分析した上で,業務改善策を立案して実施することが必要である。
例えば,営業担当者が効率よく営業活動を行うためには,販売促進ツールの準備,見積書の作成,契約書類の作成,納品の手配,請求書の発行,売掛金の回収などの営業事務の効率向上を図る必要がある。営業事務の効率向上を阻害している問題点を洗い出し,業務上の課題を設定するために,実績データから作業工数を集計することや各作業に費やすコストのデータを算出することなどが求められる。各データを分析することによって問題点を把握し,課題を設定し,改善策を立案して実施することで業務のスピードアップを図り,業務の効率向上を推進することができる。
上級システムアドミニストレータには,現状の業務を分析するために必要なデータを収集し,そのデータを分析することで現状の問題点を把握することが求められる。その上で,取り組むべき課題を設定して業務の改善策を推進し,業務全体の効率向上を実現する役割を担っている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが業務改善のためにデータを活用した事例について,あなたの立場・役割を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの事例について,当初設定した改善目標の概要及び現状の問題点を把握するために収集したデータとその分析結果を具体的に述べよ。さらに,実施した改善策とその効果を具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務の改善について,今後,改善効果を継続的に測定して業務改善に結び付けるためには,どのような仕組みを組み込めば効果的か。あなたの考えを簡潔に述べよ。
📗H17:2005
【AN-H17-1-PM2-Q1】情報システム部門の役割の変化に対応した人材の確保・育成計画について
最近,情報システム部門の役割を見直す企業が多い。例えば,コアとなる事業や部門に人材を集中させるために,情報システム部門の企画機能だけを自社に残し,大部分の業務をアウトソーシングする企業がある。また,ITを戦略的に活用するために,従来のシステム構築中心の情報システム部門に,経営戦略立案に参画させたり,業務プロセス改革推進の役割をもたせたりする企業もある。
このような情報システム部門の役割の変化によって,情報システム部門の人材に求められる知識や能力が変わるので,新たな人材の確保や育成が必要になってくる。
システムアナリストは,まず,情報システム部門の役割の変化と将来の方向を見据えて,情報システム部門に求められる役割を果たすことができる新たな体制や人材像を定義する必要がある。その上で,現状と新たな体制や人材像とのギャップを埋めるために,人事部門と協力して,次のような方策を検討し,人材の確保・育成計画を策定しなければならない。
・新たな体制や人材像に適した職位区分やキャリアパスの設定
・不足しているスキルを補うための他部門や外部機関とのローテーション
・新たに必要となるスキルに対応した関連資格の取得奨励策の立案やITスキル標準などを活用した人材育成体系の整備
・新たな人材像に対応した採用や処遇の見直し
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システム部門の人材の確保・育成計画の策定において,背景となった情報システム部門の役割の変化の概要と,変化に対応した新たな体制と人材像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのような人材の確保・育成計画を策定したか。あなたが特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた人材の確保・育成計画の結果について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【AN-H17-1-PM2-Q2】IT基盤の整備計画について
近年,企業ではオープン系システムが導入の手軽さから多数採用されてきた。これらのシステムは,それぞれに異なるプラットフォームや開発環境で構築されることが多く,開発や運用のコストが高くなったり,障害発生やセキュリティのリスクが増大したりする傾向がある。また,既存システムとの連携が複雑になり,新しいシステムを導入するときに,時間とコストがかかるようになってきた。これらを避けるには,プラットフォームやネットワークの整理,システム間の連携方式の標準化,開発や運用の標準化,セキュリティ対策などのIT基盤の整備を行うことが重要となる。
IT基盤の整備には,開発や運用のコストの低減,障害発生やセキュリティのリスクの低減などのねらいがあり,同時に,ビジネスの変化に対応できる柔軟性や拡張性の確保にも配慮する必要がある。したがって,IT基盤の現状の問題点を分析するだけではなく,ビジネス戦略を理解した上で,IT基盤のあるべき姿を考えることが重要である。システムアナリストは,次のような点に考慮して,IT基盤の整備計画を作成しなければならない。
・ITの技術動向,信頼性,可用性
・ビジネス戦略を踏まえたアプリケーションやデータとIT基盤との適合性
・IT基盤の移行計画とビジネス戦略との整合性
・IT基盤技術者の育成やIT基盤の運用体制の確立
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったIT基盤の整備計画について,そのねらいと計画が必要になった背景,実現を目指したIT基盤の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのようなIT基盤の整備計画を作成したか。また,計画の作成に当たって,ビジネスの変化に対応できる柔軟性や拡張性に配慮し,ねらいどおりの効果を得るために,あなたが特に重要と考え,工夫した点は何か。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT基盤の整備計画について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【AN-H17-1-PM2-Q3】中期経営計画の変更に対応した情報システム計画の見直しについて
多くの企業で,経営戦略に基づいた中期経営計画と情報システム計画が策定され,実行されている。
昨今,経営環境の激変を背景に,中期経営計画の変更が度々行われ,計画中又は開発中の情報システム化案件の内容も大幅に変更されるなど,情報システム計画は大きな影響を受けている。しかし,情報システム計画は,基盤整備やアプリケーション開発などに一定の期間と投資を必要とするので,変更できないこともある。また,変更した場合には,投資計画を大幅に見直さなければならない。
そこで,システムアナリストは,中期経営計画の変更に対応して,関連部署と調整し,投資効果などを再検討して情報システム計画の見直しを行う必要がある。その際,次のような点を考慮して見直し案を作成し,経営者の判断を仰がなければならない。
・情報システム計画において,中長期的な経営上の効果を考慮して,変更すべきでない内容には,継続して投資する。
・経営の根幹にかかわる中期経営計画の変更に対しては,計画中又は開発中の情報システム化案件の内容を抜本的に見直す。
・計画中及び開発中の情報システム化案件の状況を総合的に分析し,情報システム化投資のロスを最小限にするよう調整する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システム計画の見直しについて,背景となった中期経営計画の変更内容と情報システム計画への影響を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたは中期経営計画の変更に対して,どのような情報システム計画の見直し案を作成したか。あなたが特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システム計画の見直しについて,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
【SD-H17-1-PM2-Q1】情報システムの活用による間接業務の効率向上について
経営効率向上の一環として,間接業務の効率向上策を推進している企業が多い。間接業務の効率向上のためには,業務プロセス全体を効率の観点から見直し,間接部門で集中処理している事務作業の一部を,データの発生場所である現場部門へ移管するなど,部門間の適正な役割分担を図る必要がある。
間接業務の見直しに当たっては,まず業務プロセス全体を見直し,無駄な業務や重複業務などを整理した上で,集中させた方が効率の良い業務と,分散させた方が効率の良い業務を明確にする必要がある。各部門がその特性に応じて業務上の役割を適正に分担し,情報システムを活用した最適な業務プロセスを構築することによって,間接業務全体の効率を向上させることができる。その結果,間接部門では,事務作業の軽減や効率向上だけでなく,現場サポート業務及びデータの集計や分析などの経営サポート業務の強化が可能になる。
上級システムアドミニストレータは,現場部門及び間接部門の適正な役割分担を図り,情報システムを活用することで,一連の業務がスムーズに流れるように,関係する各部門と連携を取りながら,間接業務全体の効率を向上させる役割を担う。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,業務プロセス全体の見直しを行った間接業務の効率向上策の概要を,部門間の役割分担の見直し及び情報システムの活用を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例について,施策実現の過程であなたが最も重視したことを,重複業務の整理,集中・分散すべき業務と部門間の役割分担,及び情報システム活用の観点を含め,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた事例について,あなたは間接業務の効率向上策の成果をどのように評価しているか。今後の課題とともに述べよ。
【SD-H17-1-PM2-Q2】情報の社外流出事故の防止について
近年,情報の社外流出問題は,企業における大きなリスクの一つといわれるようになった。企業には,顧客や取引先の情報,新商品や研究開発の機密情報,及び従業員の個人情報など,社外への流出事故を防止すべき情報が多い。セキュリティを高めることは,企業防衛に役立つだけではなく,顧客の信頼や従業員の安心を得ることにもつながる。
情報の社外流出問題に対しては,次のような観点を考慮することが重要である。
・データベース保護を含む,セキュリティ確保のための情報システム機能
・業務の従事者の監督や規律・モラルの保持,アクセス権限の付与など,内部管理
・外部委託時の秘密保持契約,データの取扱いなど,委託先の管理・監督
上級システムアドミニストレータは,セキュリティポリシの設定に積極的に関与するとともに,そのポリシに基づいて部門の業務プロセスを具体的に見直す必要がある。アクセスログの取得・保管やデータベースの暗号化などといったセキュリティ確保のため,情報システムの改善や再構築が必要なこともある。業務の従事者の監督や相互けん制,機器やデータの持出しに伴う事故対策など,運用面のルールを見直し,教育・研修を通じて管理体制を定着させることが必要である。これらの対策に当たっては,情報の社外流出リスクの大きさ,業務の運用効率への影響を考慮した様々な工夫が望まれる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが経験した業務の中で,情報の社外流出事故の防止のためにとった対策の概要を,業務の内容,対象情報の内容,及び情報システム上の対策を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの対策を実施するに当たって,セキュリティを高めるためにどのような工夫を行い,その効果はどうであったか。内部管理や委託先の管理・監督の観点から,セキュリティポリシの設定と関連させて具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アの対策に関し,今後に残された課題と,その課題に対する取組について,あなたの考えを簡潔に述べよ。
【SD-H17-1-PM2-Q3】外部データの効果的な活用について
企業は様々なデータを蓄積し,業務分析や計画立案などの企画業務に活用している。企画業務にデータを活用する場合,内部データだけでは不十分なことが多いので,外部データで補完する作業が必要になってくる。外部データについては,データの特性などをよく理解した上で,活用する必要がある。
例えば,金融商品の中・長期の販売計画を立案する場合,商品別販売実績などの内部データを使って,過去数年間の販売実績を分析し,販売量の経年変化や販売動向などを把握する必要がある。併せて,同時期の他社類似商品の販売状況を外部データベースなどから入手し,需要動向を把握した上で,販売計画を立案することも重要である。しかし,外部から入手したデータは,必要な項目がなかったり,項目名は同じでも含まれている内容が違っていたりする場合があるので,外部データはその特性を十分に吟味して活用することが必要である。さらに,商品を取り巻く環境や消費者動向を把握するために,独自に調査したり,外部調査機関に依頼したりして,不足するデータを収集することも求められる。
上級システムアドミニストレータは,内部データだけでなく,外部データについてもデータの特性を十分に把握し,企画業務に効果的に活用する役割を担っている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが企画業務に,内部データと外部データを活用した事例の概要を,そのねらいとあなたの役割を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの事例について,外部データを活用する際に,データの特性上,どのような問題点があり,それをどのように解決したか。また,外部データの活用の成果を,あなたはどのように評価しているか。具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アの事例を踏まえて,今後,企画業務での外部データの効果的な活用を推進するために,あなたはどのような施策が必要と考えるか。施策の意図も含めて,簡潔に述べよ。
📗H16:2004
【AN-H16-1-PM2-Q1】業績評価指標を総合的に取り扱うシステムの立案について
近年,多くの企業では,統合基幹業務システムをはじめとする様々なシステムが整備され,企業活動に関するデータが統合的に収集,管理できるようになってきた。
しかし,厳しさを増す企業間競争に打ち勝つためには,更に,企業活動に関するデータから,様々な活動目標の達成度を分かりやすい形で経営にフィードバックし,迅速で的確な経営判断に役立つシステムを実現する必要がある。具体的には,組織や管理レベルごとの活動目標に関するKPI(Key Performance Indicator)などの業績評価指標を設定し,達成度の把握に必要なデータを収集し,加工・編集するシステムが考えられる。業績評価指標としては,事業単位別・顧客別の売上高や利益率,生産リードタイムや納期遵守率,製品の不良率や顧客からのクレーム数などがある。このような業績評価指標を総合的に取り扱うシステムを立案する場合,システムアナリストは,業績評価指標の使用目的や用途を理解し,必要となるデータやその特性を確認した上で,タイミング良く提供するために,次のような工夫を行わなければならない。
・豊富なデータソースからデータを収集,連携するための仕組み
・必要なデータが既存のシステムにない場合の代替案や新たなデータ収集の仕組み
・データの収集を早めるためのデータ発生・入力部門との調整や業務処理の変更
・データの加工を速めるための二次データベースの構築
・必要な人に,分かりやすい形でタイミング良く提供する仕組み
・システムが経営環境の変化に追従し,効果的に利用される仕組み
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが立案に携わった,業績評価指標を総合的に取り扱うシステムについて,設定された業績評価指標とデータ収集・加工・提供の仕組みを中心に,システムの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの立案に当たって,あなたはどのような点を考慮したか。また,あなたが特に重要と考え工夫した点は何か。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステムの立案について,あなたはどのように評価しているか。また,今後改善すべき点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【AN-H16-1-PM2-Q2】国内外でビジネスを展開する企業における情報システムの統制について
国内外でビジネスを展開する企業では,中長期の海外進出計画に合わせて情報システム構築計画を作成する。その際,統制指針を作成せずに,国ごとに計画を作成して情報システムを構築すると,日本本社とは異なるシステム構築や運用保守が行われ,国をまたがった業務の連携に不具合が生ずる場合がある。このような事態を避けるために,業務システムやIT基盤,運用保守などについて,情報システムの統制指針を作成することが重要になる。統制指針の例として,次のようなものがある。
・調達,生産,販売,会計など業務ごとのソフトウェアパッケージの適用指針
・情報セキュリティ基準やハードウェア,ソフトウェアの選定指針
・自社で保持すべき運用保守機能についての指針,及び地域ごとのデータセンタやアウトソーシングの活用指針
情報システムの統制指針の作成に当たって,システムアナリストは,企業グループ全体として標準化すべき業務プロセス,それに伴って必要になる業務システム機能やデータ資源などを明確にしなければならない。その際,国ごとの情報システム要員,スキル水準,業務システム,IT基盤の整備状況,ITリテラシなどの実情を調査・分析し,統制指針の緊急度や優先度を定める必要がある。また,統制指針を定着させるために,業務や情報システムごとに段階的な統制方法を盛り込むなどの工夫をしなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが統制指針の作成に携わった,国内外でビジネスを展開する企業の情報システムについて,統制指針が必要になった背景と,対象になった業務や情報システムの全体像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムについて,あなたはどのような統制指針を作成したか。また,統制指針の作成に当たって,あなたが特に重要と考え工夫した点は何か。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた統制指針について,あなたはどのように評価しているか。また,今後改善したい点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【AN-H16-1-PM2-Q3】部門間にまたがる業務プロセスの“あるべき姿”に基づいた改革の立案について
部門間にまたがる業務プロセスの“あるべき姿”を設計し,現状の業務プロセスとのギャップを明確にし,業務プロセスの改革を実施することがある。このようなアプローチによって,業務プロセスの抜本的な見直しが可能になり,問題が顕在化している一部分の業務プロセスの見直しやボトムアップのアプローチで業務プロセスを改善する以上の効果が期待できる。
業務プロセスの“あるべき姿”は,一般に,他社の先進事例や成功事例,ベストプラクティスなどを参考にして,新しい業務プロセスとして設計される。
改革の立案に当たって,システムアナリストは,新しい業務プロセスと現状の業務プロセスとのギャップを整理し,次のような点を重視して,ギャップの克服や解消のための対策を講じる必要がある。
・ギャップの原因になっている現行のビジネス慣習や組織などを調査・分析し,問題点の本質と対策のポイントをつかむ。
・新しい業務プロセスを実現するために,情報技術の最適な活用を検討する。
・経営者やマネジメント層と業務プロセスの改革のねらいやリスクを共有し,トップダウンで進めるべき事項を明確にし,その進め方を検討する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,部門間にまたがる業務プロセスの“あるべき姿”に基づいた改革について,改革に至った背景と改革の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた改革の立案に当たって,業務プロセスの“あるべき姿”と現状の業務プロセスとのギャップの克服や解消のために,あなたはどのような対策を講じたか。あなたが特に重要と考え工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策について,あなたはどのように評価しているか。簡潔に述べよ。
【SD-H16-1-PM2-Q1】システム化要件の定義における利用部門の役割について
近年,ビジネス環境の激しい変化を受けて,情報システムに対する利用者の要求もますます高度化し,多様化している。情報システムに求められる主要な要件としては,経営戦略や事業方針との整合性の確保が挙げられる。
例えば,情報システムに組み込むべき業務プロセスやデータのモデルは,経営戦略や事業方針を十分に確認し,費用対効果の検討や優先付けを行いながら,利用部門が定義する必要がある。同時に,現状の業務や情報システムについても問題の本質や要件の実態を把握し,情報システムの機能の利便性や操作性などを考慮する必要がある。また,一度定義したシステム化要件は,状況の変化によって追加や変更が発生することも多い。状況の変化への対応とともに,漏れのないシステム化要件の定義や潜在的な業務要件の抽出などは,業務を熟知している利用部門が主体となって行わなければならない重要な課題である。利用部門は,要件定義での討議に主体的に参画するとともに,効果的な定義を行うための手順や方法なども身に付けておく必要がある。
これまでのシステム化要件の定義では,情報システム部門や外部機関にその作業をゆだね,必ずしも十分とはいえないことが多かった。その結果,開発期間の延長や運用直後からのメンテナンスが発生し,開発費用の増加やシステムのライフサイクルの短縮が生じている。利用部門が,システム化要件の定義を中心に,システム開発プロジェクトにいかに主体的に参画していくかが,システム開発を成功に導く上でのポイントになっている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが利用部門としてかかわった業務要件の抽出やモデル化を伴うシステム化要件の定義作業の概要を,その作業における利用部門の役割と定義した要件の概要を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,経営戦略や事業方針と整合性のとれた業務要件の抽出やモデル化のために,あなたは,どのような手順や方法を用いたか。また,その作業で発生した主要な問題と対応策について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた事例において定義したシステム化要件の妥当性について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに述べよ。
【SD-H16-1-PM2-Q2】顧客情報の有効活用について
企業において,顧客情報の様々な有効活用が求められている。これまで,顧客と様々な接点をもちながら,各部門に散在していた顧客情報を有効に活用できれば,顧客満足度を高めることができ,優良顧客や企業の収益力の増大が期待できる。
具体的には,店舗や営業員,電話,電子メールなどの様々なチャネルから入ってくる顧客情報を1か所に集約し,有効活用しようというケースが増えている。例えば,コールセンタでは,顧客からの問合せに即答できるように,多くの質問と回答の中から典型的な対応例を検索・抽出できるようにしている。コールセンタで解決できない場合は,対応できる部門がコールセンタからの情報を迅速に引き継げるようにしている。また,複数の部門が顧客に対応する場合,一元化された顧客情報を使用し,各部門が情報を共有すれば,整合性のとれた顧客対応が可能になる。こうした対応を通じて,顧客満足度を高め,更に,収集された顧客の声を総合的に分析し,活用することで,新たな商品やサービスの企画に生かすこともできる。
上級システムアドミニストレータは,顧客戦略を理解した上で,関連部門の立場を調整しながら,顧客情報を集約し,有効活用することによって,顧客にとって価値のある情報やサービスを,一貫して提供できる仕組みを作ることができる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが構築に携わった顧客情報の集約と有効活用の事例について,顧客戦略や情報技術の活用も含めて,その概要とねらい,あなたの役割を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例について,どのような顧客情報を集約し,どのように有効活用したか。部門間の連携や情報技術の活用とも関連させて,具体的に述べよ。また,当初のねらいは実現したか,していなければその原因について述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた事例について,期待する成果を更に高めるために,あなたはどのような施策が有効と考えているか。今後の課題とともに述べよ。
【SD-H16-1-PM2-Q3】商品やサービスの開発のスピードアップについて
顧客ニーズの激しい移り変わりに伴い,商品やサービスのライフサイクルが短くなっており,顧客の支持が得られるものをいかに早く市場に出せるかが重要になっている。
商品やサービスの開発では,マーケティング部門や研究開発部門などの連携のもとで,次のような一連のプロセスを実施する。まず,顧客や市場から収集した情報の分析に基づいて,商品を企画し,試作を行う。次に,顧客による試作品の評価などによって,商品化の見通しがついたところで,商品製作やサービス提供の仕組み作りや改良,量産体制の準備を行い,販売戦略も立案する。
商品やサービスの開発のスピードアップは,社内外の知見や関連情報の迅速な収集・分析,適切な開発ツールの導入,部品の共通化,製作工程の標準化など,個別プロセス自体の変革や効率向上の結果として実現することも多い。また,個別プロセスの組替えや並行処理,一部のプロセスの他部門や外部への委託などによる,業務プロセス全体にわたる変革も有効である。商品やサービスの開発を支えるインフラストラクチャとして,顧客情報,商品情報,関連技術情報などの共有化や活用,開発業務のマネジメントに必要な仕組み作りも重要である。限られた時間と要員で,商品やサービスの開発のスピードアップを図るには,情報技術の活用が欠かせない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった商品やサービスの開発で,情報技術の活用によってスピードアップを図った事例について,対象となった商品やサービスと開発業務プロセスの概要を,あなたの立場を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務に関し,開発のスピードアップを図るために,あなたはどのような工夫をしたか。スピードアップの阻害要因がどこにあったか。また,阻害要因を解消できなかった場合はその原因を含めて,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた業務について,あなたはスピードアップによる業務上の成果をどのように評価しているか。また,今後,その成果を一層高めるためにはどのような施策が有効と考えているか。簡潔に述べよ。
📗H15:2003
【AN-H15-1-PM2-Q1】新規ビジネス立上げに必要な情報システム投資計画の策定について
新規ビジネスの立上げに際し,ビジネス特性に合致した効果的な情報システムを構築することが重要になっている。情報システム投資を伴う新規ビジネスの例として,次のようなものがある。
・新たな商品・サービスの開発と市場への投入
・他社製品も保守対象に加えたサービス事業の拡大
・最終顧客に対する直販ビジネスへの参入
新規ビジネスの立上げに当たっては,目標とする投資回収期間や利益率を満足するよう,システムアナリストも参加して,予想収益,初期投資,オペレーションコストなどを含むビジネスプランの検討が行われる。また,新規ビジネスを支援する情報システムには,立上げの早さと確実さ,ビジネス支援機能の充実度,ビジネス規模の急速な拡大への対応力などが求められる。
このような中,システムアナリストは,次のような観点からビジネスプランを満足する情報システム投資計画の策定を行うことが求められる。
・立上げの早さと確実さ,ビジネス支援機能の充実度,初期投資やオペレーションコストの制約などを同時に満足するパッケージや独自開発など最適な実現方法の組合せは何か。
・初期投資を抑え,収益拡大に沿って追加投資をしていくようなプランはないか。
・情報システム投資を十分行うことで,売上の増大やオペレーションコストの一層の削減が図れ,より良いビジネスプランとすることができないか。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システム投資案件について,投資計画策定の前提となった新規ビジネスと情報システム投資計画の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた新規ビジネスを十分支援し,かつビジネスプランを満足する情報システム投資計画を,あなたはどのような観点から策定したか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システム投資計画の策定結果について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H15-1-PM2-Q2】企業の枠を超えた業務プロセスの統合について
競争力を高めるために,多くの企業が業務プロセスを簡素でスピーディなものにする努力をしている。昨今の厳しい経営環境は,より一層の競争力強化を企業に迫っており,この方策として,最新のITを活用し,企業の枠を超えて業務プロセスを統合するケースが増えている。例としては,次のようなものがある。
・サプライヤやカスタマとの間で生産・在庫・販売に関する情報を互いに開示し,自社と取引先との調達・生産・販売の業務プロセスを統合し,強固なアライアンス関係の確立とリードタイムの短縮やコストの削減を図る。
・物流業者や3PL(サードパーティロジスティクス)業者との間で物流業務プロセスを統合し,顧客サービスの向上と物流コストの削減を図る。
・メーカ,代理店,販売店などそれぞれの企業の取引先との受発注の業務プロセスを統合し,取引のスピードアップと販売・調達コストの削減を図る。
このような業務プロセスの統合は,経営企画部門や事業部門とシステム部門との共同で進められることが多い。その際,システムアナリストは,次のような点に留意して,ITを有効活用した業務プロセスの統合を円滑に進める必要がある。
・対象業務の現状と将来の課題分析に基づく業務プロセス統合の可能性検討
・業務プロセス統合の目的と効果の明確化
・業務プロセス統合に伴う取引先や社内組織への影響把握と対応策検討
・業務プロセス統合に向けた取引先などとの調整
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった企業の枠を超えた業務プロセスの統合について,統合を進めることに至った背景と統合のねらい及び対象業務プロセスの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたは,ITを活用して,どのような業務プロセスの統合を立案したか,統合前と統合後の業務プロセスの比較を中心に具体的に述べよ。また,立案に際して,あなたが特に重要と考え工夫した点は何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務プロセスの統合について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H15-1-PM2-Q3】ビジネスの変革のためのITの活用について
近年,インターネットや統合型アプリケーションパッケージ,ブロードバンドネットワークなどITの急速な発展と普及,低価格化によって,ITを活用してビジネスを変革するケースが増えている。例としては,次のようなものがある。
・インターネットを活用した,ダイレクト販売による低価格での商品提供の実現と新しい顧客層に向けた販売チャネルの拡大
・CRMアプリケーションを活用した,販売とサービスのプロセス統合による顧客サービスの向上と優良顧客の囲い込み
・ブロードバンドネットワークを活用した,サプライヤとの共同開発による新製品の市場投入期間の短縮
ビジネスを変革するこのようなITの活用に当たっては,現行ビジネスの分析,先進事例の調査,実現したいビジネスについての業務要件とシステム機能要件の整理をした上で,システムの全体構想を描くことが重要である。システムの全体構想では,業務プロセスや業務アプリケーション及び情報システム基盤の構想立案を行う。その際,ITを有効に活用していくために,次のようなことを考慮する。
・ITの最新動向と自社への適合性
・関連システムとの連携方法
・現行業務からの移行方法又は現行業務との連携方法
システムアナリストは,システムの全体構想の中で,ITの活用がビジネスの変革にどのように貢献するのかを具体的に示さなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったビジネスの変革のためのITの活用について,その背景となった現行ビジネスの状況及びシステムの全体構想の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの全体構想の中で,ビジネスの変革にITの活用がどのように貢献するのか。また,ITを有効に活用していくために,あなたが特に重要と考え工夫した点は何か。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたビジネスを変革するためのITの活用について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【SD-H15-1-PM2-Q1】関連する業務プロセスの改善について
これまで部門における業務プロセスの改善は,部門全体の業務プロセスを構成する個々のプロセス単位に着手することが多かった。その結果,個々のプロセスは最適化しても,部門全体として最適化することができないケースがあった。
例えば,物流管理部門において,部門全体のコスト削減を目指して業務プロセスの改善に着手する場合,仕入処理では,発注や検品作業の効率を優先して発注サイクルを長くするような検討をすることがある。この結果,需要との整合性がとれにくくなり,仕入量の過不足が発生する。一方,在庫管理では,商品が適量に発注されることを前提に,商品の保管レイアウトや棚番管理などを改善する。しかし,実際には,適正な在庫量とはならず,一時的に余分なスペースの確保や棚番管理の見直しが必要になる。場合によっては,過剰在庫や品切れ対応などでコストも増加する。
部門全体を対象とした業務プロセスの改善では,個々のプロセスの順序や改善効果のプロセス間の影響度合いを全体的な視点で検討する必要がある。
特に,個々のプロセス間で,互いに利害が一致しないようなケースでは,プロセス相互の調整という改善ステップを踏みながら,部門全体としての改善効果を実現させるようなアプローチをとる必要がある。部門全体としての体制作りやITを活用した情報共有の仕組み作りも欠かせないものになる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった業務プロセスの改善について,全体の概要及び個々のプロセス間で利害の一致しない点を,改善作業におけるあなたの役割とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務プロセスの改善について,部門全体の改善効果を実現させるために,どのようなアプローチをとったか,その中で,利害が一致しないプロセスをどのように調整したか,具体的に述べよ。また,改善を進める上で発生した予期しない事態に対し,どのように対応したかを述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたアプローチを評価して,部門全体のプロセス改善を目標どおり実現できた場合は,成功に結びついたポイントを,できなかった場合は,今後,どのようにして実現しようとしているのか,あなたの考えを述べよ。
【SD-H15-1-PM2-Q2】原材料や部品の調達業務の改革について
原材料や部品の調達業務は,ITの進歩によって,大幅に変わりつつある。インターネットの普及に伴い,企業間における情報の共有と活用によって,計画的でタイムリーな調達を可能にし,リードタイムの短縮や在庫の削減を図るケースが増えてきた。
調達業務の改革に際しては,期待する成果を上げるため,取り扱う品目や業態に応じた仕組みを検討する必要がある。例えば,ネット調達によって調達コストの削減を図ったり,関係企業間の受発注データなどの交換によって調達業務の効率向上を図ったりする。また,調達業務を戦略的に再構築することによって,調達・生産・在庫の各領域にわたるコスト削減や業務の効率向上を図るなど,総合的な成果を期待する例もある。
上級システムアドミニストレータは,調達業務の改革を円滑に推進するために,関係者間の意志疎通を十分に図り,目的やねらいを明確にした仕組みを構築する必要がある。取引条件の設定,コードの統一,業務運用上の責任の切り分け,特に,電子商取引の場合は,決済上のトラブルや機密保持対策などを含め,ビジネス上のルールを設定することが必須である。関係者の意識変革を図り,思い切った発想で業務の仕組みの再構築を行って,業務の効率向上を図ることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった,原材料や部品の調達業務の改革について,その概要を,取組のねらい,ITの活用を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた調達業務の改革について,期待する成果を上げるために,業務の仕組みの構築に際し,どのようなビジネス上のルールを設定したかを述べよ。また,構築の過程で生じた問題と,それをどのように解決したかを述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた調達業務の改革について,期待する成果を一層高めるためには,どのような施策が有効だと考えるか,今後の課題と対比させて簡潔に述べよ。
【SD-H15-1-PM2-Q3】戦略実現のためのデータ活用について
ITの進歩によって,大量に蓄積された生データや画像などの多様なデータが迅速に扱えるようになってきた。また,利用できる外部の情報が豊富になり,各種の外部データが容易に活用できるようになった。部門の戦略や企業戦略の実現を支援するために,これらの各種データを有効に活用することが求められている。
例えば,コンビニエンスストアでは,各店舗から得られる膨大な売上データの分析結果や地域のイベント情報及び天候の情報などを,商品の品ぞろえ,更には新商品の開発に活用している。最近では,独自のカードを発行し,その顧客データを活用して各種サービスを実施したり,店舗を多機能化して,チケット予約や画像データを有効に使った各種の情報サービスを提供したりすることで,固定客の確保や顧客層の拡大に結びつけようとしている。
一方,商品を提供する側のメーカでは,新商品のヒット率や開発効率の向上,生産コスト削減などに各種データを活用している。販売実績データを多面的に分析したり,インターネット上で画像データを使って商品に対する顧客の反応を分析したりして,その結果を迅速に商品開発に結びつけている。また,コスト削減のために,事業分野別に分析した自社の経営情報と,海外現地情報や同業他社動向の調査情報など外部データを活用し,特定商品の生産拠点の海外移転という戦略を実現しているところも多い。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった業務で,部門の戦略や企業戦略の実現のために,大量のデータや多様なデータを活用した事例について,その戦略及びデータ活用の概要を,外部データの活用を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例について,データ活用のポイントを戦略実現の視点から具体的に述べよ。また,それによって実現した戦略上の成果について,評価及び問題点を含めて述べよ。
■設問ウ
現在より更に大量のデータや多様なデータがより迅速かつ容易に扱えるようになった場合,設問アで述べた戦略の実現方法や実現のスピードは,どのような影響を受けると考えるか,あなたの考えを述べよ。
📗H14:2002
【AN-H14-1-PM2-Q1】ビジネススピードの向上を目指すIT戦略の立案について
消費者のライフスタイルや価値観が多様化し,市場が急速に変化している。このようなビジネス環境の中で,経営判断や業務遂行の迅速化(以下,ビジネススピードの向上という)は,各企業にとって大きな経営課題の一つである。ビジネススピードの向上を目指し,IT戦略を立案する企業は多い。例としては,次のようなものがある。
・経営指標を随時,最新の状態で把握し,問題を素早く摘出することで,経営判断の迅速化を目指したERPシステムを構築する。
・供給者から消費者までを結ぶ,調達・製造・販売の一連の業務のつながりを円滑にし,迅速な商品提供を目指したSCMシステムを構築する。
・顧客からのレスポンスやクレームなどについて関係部署が情報を共有し,迅速な顧客対応を目指したCRMシステムを構築する。
ビジネススピードの向上を目指すIT戦略の立案に当たって,システムアナリストは,その有効性を評価するために,ベストプラクティスを研究したり,ITの自社への適合性を検討したり,技術動向を判断したりすることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが参画した,ビジネススピードの向上を目指すIT戦略立案の背景となった企業のビジネス環境と情報システムの置かれた状況の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた状況の下で,ビジネススピードの向上を目指して立案したIT戦略を述べよ。また,その中で,あなたが特に重要と考え工夫した点は何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT戦略について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H14-1-PM2-Q2】情報システムの全体構想の立案について
グローバルな競争に勝ち残るための事業の再構築,経営資源の最適配置のための企業統治の強化,ビジネスチャンス追求のための新しいビジネスモデルの構築など,多くの企業でビジネスの大きな変革が起こっている。このビジネスの変革に柔軟に対応できるシステム化計画が求められているが,個々のシステム化計画で個別に対応することは,全体的な観点では,効率の低下を招いたり,コスト増になったりすることが多い。したがって,ビジネスの変革の方向を的確にとらえ,中長期的かつ全体最適の視点から情報システムの企画・設計・開発・運用に関する全体構想を描き,この全体構想の下で,個々のシステム化計画を立案することが重要になる。
情報システムの全体構想では,例えば,次のようなシステム化の方針が明確にされなければならない。
・オフィスシステムやネットワークなどのシステム基盤の整備方針
・集中システムや分散システムなどのシステムアーキテクチャの方針
・パッケージソフトウェア利用や独自開発などの開発・導入方針
・ASP(Application Service Provider)などの外部リソースの活用方針
企業が直面する経営環境の変化の中で,システムアナリストは,システムをビジネスの変革に柔軟に適応させ,ITの革新的な変化を取り入れるための様々な工夫をシステム化方針に盛り込んで,情報システムの全体構想を立案しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが参画した情報システムの全体構想の立案時に,経営環境の変化とビジネスの変革をどのように認識したか,その概要を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたビジネスの変革の中で立案した情報システムの全体構想について,あなたが特に重要と考えたシステム化方針を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システムの全体構想について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H14-1-PM2-Q3】統合型業務パッケージの導入計画立案について
近年,業務改革や情報の統合などを目的として,ERPに代表される統合型業務パッケージを導入する企業が増えている。
統合型業務パッケージは全体最適の視点で導入するものであり,特定部門のシステム化ニーズにこたえたり,個別業務課題を解決したりするものではない。したがって,ニーズの異なる部門間の調整をスムーズに行ったり,適正な機能の追加・変更を行ったりするために,導入の基本方針を明確にすることが重要である。基本方針には,パッケージの提供するベストプラクティスの適用方針,既存の業務プロセスとのギャップに対する機能の追加・変更方針,プロジェクトの運営方針,段階的移行又は一斉移行などの移行方針などを盛り込む必要がある。基本方針を策定する場合,例えば,次のような観点が重要である。
・業務プロセスの抜本的な再構築を実現するベストプラクティスの適用方針であること
・仕様決定段階などで,個別業務ニーズへの対応に際して明確な判断のできる機能の追加・変更方針であること
・全体最適の視点から,トップダウンによって効果的かつ効率良く導入を推進できるプロジェクトの運営方針であること
・既存システムからの移行や,新業務プロセスへの移行の準備を考慮した移行方針であること
統合型業務パッケージの導入計画立案に当たって,システムアナリストは導入を成功させるために,基本方針を明確にしなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した統合型業務パッケージの導入計画について,導入の目的と導入計画の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた導入計画を立案するに当たって,あなたはどのような基本方針を策定したか,あなたが特に重要と考え工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた基本方針について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【SD-H14-1-PM2-Q1】成功事例を活用した業務プロセスの再構築について
経営環境の変化を受けて,企業の事業展開や部門における業務の在り方が見直され,それに伴う業務プロセスの再構築が行われている。
業務プロセスの再構築に際しては,顧客や経営視点に立脚した検討が求められ,部門の業務についても個別的な対応ではなく,関連するプロセス全体を対象にしなければならない。
再構築を迅速に推進するために,様々な成功事例をモデルとして活用しているケースがある。しかし,成功事例を活用する場合には,公開されている対象範囲や内容のレベルを確認するとともに,自企業の特性との相違にも十分に留意する必要がある。
例えば,活動基準をベースにした原価管理を導入して,製品やサービスの損益を的確にとらえ,業務改善につなげた成功事例を活用しても,コスト意識が低く,組織の壁があり,業務活動の標準化が進んでいない企業では,大きな効果は期待できない。通常,公開されている成功事例は,成功の背景となっている企業の組織風土や社員の変革意識など,企業の特性の説明が不十分な場合が多い。
また,事例を活用する場合でも,公開されている成功事例をそのまま鵜呑みにせず,どの部分が自企業にとって適合するかを十分に見極めることが,効果を上げるためのポイントとなる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが再構築に携わった業務プロセスの概要と,再構築の背景となった顧客や経営上の課題を,800字以内で述べよ。
■設問イ
活用した成功事例とその事例を選んだ理由,及び成功事例を自社の業務プロセスの再構築に確実に生かすために払った留意点について,自社の特性と関連させながら述べよ。
■設問ウ
業務プロセスの再構築の効果と今後の主要な課題を,成功事例を生かせた部分と生かせなかった部分に分けて述べよ。
【SD-H14-1-PM2-Q2】業務要件と整合のとれたアプリケーションソフトウェアの調達について
情報化の進展に伴い,情報システムを構築する段階で,利用部門がアプリケーションソフトウェアの開発を直接外部に依頼し,調達するケースが増加している。
業務要件と整合のとれたソフトウェアを調達するためには,社内の調達基準に基づいて,対象業務の要件やシステムの動作環境などを明確に提示する必要がある。
利用部門では,業務の特性を踏まえたシステム化要件を明確に定義し,提案元や提案されたソフトウェアを評価するための基準などを事前に整備することも求められる。
ソフトウェアの調達における準備から発注までの手順は,次のように行われる。
・経営方針に合致した業務要件を,上位レベルのプロセスモデルやデータモデルとして定義し,まとめる。
・ソフトウェアなどの評価基準や契約条件などを事前に設定し,外部へ提案依頼する。
・外部からの提案内容を,評価基準に基づいて比較検討し,調達先を決定する。
・調達に際しての詳細な条件を明確にして,調達先と契約の上,発注を行う。
しかし,現実の調達では,提案内容の明確な評価基準をもたないまま調達先を決定し,ソフトウェアの検収時点で業務要件との不整合が明らかになったりするなど,調達のためのマネジメント不備によるトラブルも数多くみられる。
このような事態を回避するためには,利用部門においても調達手順に従った的確なマネジメントが欠かせない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
情報化の対象になった業務と,調達したソフトウェアの概要を,利用部門において調達マネジメントにかかわったあなたの立場とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた調達に際して,業務要件などを,相手に分かりやすく提示するために,どのような点に留意したか。また,どのような点がうまくいかなかったか,その原因はどこにあると考えるか,対象業務の特性を踏まえて述べよ。
■設問ウ
外部からの提案内容に対して,どのような基準で評価を行ったか。また,評価基準の有用性をどのように考えたか,今後の課題とともに述べよ。
【SD-H14-1-PM2-Q3】情報システム導入後の評価と業務の改善について
ERPに代表されるような業務モデルを組み込んだソフトウェアパッケージの活用が進んでいる。導入した情報システムを十分に活用するためには,導入段階だけでなく,導入後も引き続き,その利用実態を適切に把握・評価し,情報システムを活用した業務の改善を続ける必要がある。
例えば,ERPを導入する場合,従来の業務プロセスに合わせてソフトウェアパッケージの機能の追加・変更を実施することが多い。しかし,過度な機能の追加・変更を実施すると,その後のバージョンアップなどに迅速に対応できず,必要な経営情報がタイムリーに得られなくなり,当初の目的を十分に達成しなくなった事例も見られる。また,ERPの場合は,業務モデルが組み込まれ,運用も容易という意識があり,導入後の保守・運用体制が不十分な場合が多い。業務環境の変化に伴う継続的な機能変更や要員教育などが十分に実施できず,事務作業の停滞や人員の増加に悩んでいる事例も見られる。ERPの導入に際しては,導入時点でのコストや導入期間の評価だけでなく,導入後の機能の追加・変更の影響や保守・運用体制などを継続的に評価し,対応していく必要がある。
上級システムアドミニストレータは,利用者側のリーダとして情報システムの導入にかかわるだけではない。導入後も,情報システムの利用状況を把握し,導入の目的の達成度合いを評価することによって,情報システムを活用した業務を継続的に改善する役割を担っている。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが導入に携わった業務モデルを組み込んだ情報システムの概要と導入の目的を,業務上の要請を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムについて,導入後の業務環境の変化に伴い,情報システムを活用した業務に,新たにどのような改善が必要になったか。問題となった業務環境の変化及び業務モデルの活用を考慮した解決策を,具体的に述べよ。
■設問ウ
業務モデルを組み込んだ情報システムの導入について,あなたはどのように評価しているか。実施した機能の追加・変更の範囲や導入後の保守・運用体制などと絡めて,あなたの考えを述べよ。
📗H13:2001
【AN-H13-1-PM2-Q1】情報戦略の策定について
激しい競争を勝ち抜くために,企業は戦略的なアライアンスの締結や新しいビジネスモデルの構築など,従来の枠組みにとらわれない革新的な経営戦略を打ち出している。今日,このような革新的な経営戦略の中心は情報戦略であり,IT活用の優劣がそのまま企業競争力の差として現れる。近年,サプライチェーンマネジメント,CRM(Customer Relationship Management),eビジネスなどの情報戦略を具体化する企業は多い。
情報戦略を推進して期待どおりの効果を上げるには,業務・組織改革を合わせて行うことが肝要であり,システムアナリストは情報戦略を推進する立場から,業務・組織改革についての指針を示す必要がある。
システムアナリストは情報戦略の策定に当たって,例えば次のような観点で計画を策定することが重要である。
・経営層の参加によって,全体的な推進力が確保でき,総合的に意思決定を下せる体制を作ること
・情報戦略を進める上で,業務・組織改革の対象部門に戦略の目的を理解させ,共有化を図ること
・情報戦略を段階的に進めなければならない場合,それに歩調を合わせて業務・組織改革を進めること
・情報戦略を推進する体制と業務・組織改革を推進する体制とが円滑に意思疎通でき,タイムリーに調整を行えること
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報戦略の背景となる経営戦略について,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたが策定に参画した情報戦略とそれに伴う業務・組織改革について,その概要を述べよ。また,情報戦略の策定の中で,情報戦略に合わせて業務・組織改革を進めるために,特に重要と考え工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報戦略と業務・組織改革について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H13-1-PM2-Q2】インターネットを活用した情報システムの計画策定について
近年,企業は売上の増大やコスト削減のために,顧客や他企業との新たな関係作りに着目し,インターネットを活用した電子店舗システムや資材調達システムなどを構築することが多くなっている。
このようなシステムでは,取引先が不特定で,かつ広範囲なことが多く,新たな商取引の流れや業務を構築するので,サービス要求レベル,システムの機能要件,システム化範囲,処理能力・利用者数などのシステム規模を,計画当初に予測することが困難である。また,情報システムが期待どおりの効果を発揮するためには,既存のチャネルや既存の業務プロセスの再検討も必要である。
したがって,インターネットを活用した情報システムの構築に当たっては,当初構築する範囲・規模を限定し,それを順次,拡大するやり方が考えられる。この場合,コンテンツの更新,カスタマーサポート,システムの運用・保守などの体制を新たに整備したり,物流・決済などの他システムとの連携を再構築したりする必要もある。
システムアナリストは,インターネットを活用した情報システムの計画策定に際しては,体制や他システムとの連携を考慮した上で,当初の範囲・規模を限定し,運用後に拡大できるような,段階的な実施案を考えることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが計画策定に参画した,顧客や他企業を含むインターネットを活用した情報システム構築の背景と概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの計画策定に際して,あなたはどのような観点から当初の範囲・規模を限定したか,その理由とともに述べよ。また,当初の情報システムを計画するに当たって,体制や他システムとの連携について,工夫した点は何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システムの計画について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H13-1-PM2-Q3】業務プロセスの再設計について
企業においては,調達・生産・物流・販売など一連の活動全体を対象とするサプライチェーンマネジメントシステムを構築し,競争力を高める動きが活発になっている。
このようなシステムでは,目的とするシステム化効果を実現するために,システム開発・導入に先立って,組織や企業の壁を越えた業務プロセスの再設計を行うことが不可欠である。
業務プロセスの再設計を組織や企業の壁を越えて行う場合には,ソフトウェアパッケージに組み込まれた標準業務プロセスを適用したり,多くのベンチマーキングによって明らかにされたベストプラクティスを参照したりすることで,再設計を迅速かつ効率良く行うことができる。この場合,システムアナリストは,次のような点を考慮しなければならない。
・業務プロセスの再設計について,顧客満足度の向上やシステム全体での最適効率の追求など,基本的観点が明確であるか。
・業務プロセスの統合や連携や廃止が考えられるか。その業務プロセスに対して参照できる標準業務プロセスやベストプラクティスがあるか。
・参照する標準業務プロセスやベストプラクティスは,自社の既存の業務プロセスと比べてどのような違いがあり,どこまで適用可能か。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが計画策定に参画し,業務プロセス再設計の対象となったシステムの概要と,業務プロセス再設計の基本的観点について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの開発・導入に際し,どのように業務プロセスを再設計し,標準業務プロセスやベストプラクティスをどう取り込んだか。また,その中で重要と考え,工夫した点は何か。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務プロセスの再設計について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【SD-H13-1-PM2-Q1】知識やノウハウを活用した業務の付加価値向上について
多くの企業では,業務の付加価値向上のために,社員が日常業務で体験した事例や長年培ってきた業務上のノウハウなどを,組織として活用する必要性が高まっている。
通常,目に見えない暗黙的な形で個人の中に留まっている知識やノウハウを活用するには,これを目に見える形に置き換えたり,より効果的な内容にするために関連する知識やノウハウと結合したりする。この処理を継続的に繰り返し行うことを,ナレッジマネジメントという。
具体的には,次のような手順をとる。商品販売やサービス業務では,顧客や取引先との折衝場面を通じて知識を獲得する(共同化)。獲得した知識は,実績データによる客観的な裏付けやスペシャリストのアドバイスを受けて,販売促進などの支援策として目に見える形に置き換える(表出化)。これらの支援策は,戦略会議などの場で関連する施策と連携され,重点施策として販売やサービス活動に反映される(連結化)。この結果,更に新たな知識やノウハウが蓄積されて業務の付加価値が向上していく(内面化)。このようなプロセスの繰返しは,知識やノウハウを創造し,増殖させるために欠かせないものである。
ナレッジマネジメントを実践させるためには,知識やノウハウの蓄積だけでなく,社員がそれを活用できる能力を備えていることも必要である。また,ナレッジマネジメントを定着させるためには,組織風土や個人の意識の変革も重要で,継続的な啓蒙活動,知識やノウハウの提供者への奨励なども欠かせない施策になる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったナレッジマネジメントの概要を,知識やノウハウの活用を必要とした背景やあなたの役割とともに,800字以内で述べよ。
■設問イ
ナレッジマネジメントの実践において,蓄積した知識やノウハウを活用しながら増殖させるために,どのように取り組んだか,情報技術の活用を含めて述べよ。また,そこで発生した問題と,それを解決するために創意工夫した点を述べよ。
■設問ウ
ナレッジマネジメントを定着させるために,組織風土や個人の意識の変革にどのように取り組んだかを述べよ。また,取組の結果に関するあなたの評価を,今後の課題とともに述べよ。
【SD-H13-1-PM2-Q2】業務改善のための情報化投資と効果について
企業が業務の改善を図るためには,情報システムを活用することが有効である。情報システムの構築には,多額の投資を要することが多く,投資に見合う効果を上げることができるかどうかを見通した上で,開発に踏み切ることが必要である。投資の決定に当たっては,業務の仕組みを検討し,情報システムを開発する費用のほか,これを定着させ,運用していくための費用も考慮する必要がある。
情報システム投資の効果には,定量的な効果と定性的な効果がある。定量的な効果は,作業効率の向上による人件費の削減,販売促進費や物流費の削減など,数値で算定することが容易である。製品やサービスに対する顧客満足度の向上,企画・管理力の強化,業務上の判断力強化などの定性的な効果についても,数値化を試みるなど客観的に評価できるよう最大限の工夫を行うことが重要である。二つの効果を総合的に評価し,情報システムの構築・運用にかかる費用と対比させ,期待効果実現に関するリスクも加味して,投資を決定する必要がある。
より大きな効果を実現するには,稼働後の継続的な改善努力が欠かせない。計画どおりに情報システムが利用され,新しい仕組みが定着しているか,期待どおりの効果を実現しているか見極めた上で,一層投資効果を高めるために必要な新たな施策を検討し,実行に移すことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった業務改善の概要を,そのねらい,情報システムの内容,構築・運用の各段階の費用を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務改善について,期待した効果に関して数値化した内容とその根拠を述べよ。また,定性的な効果に関して行った,評価に客観性をもたせるための工夫を述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた業務改善の実施後,効果をどのように把握し,計画と対比したかを述べよ。また,より効果を高めるため,どのような施策を実施したかを述べよ。
【SD-H13-1-PM2-Q3】情報技術活用による間接部門の経営スタッフ機能強化について
企業活動の様々な分野に情報技術が活用されるようになり,情報技術活用の効果は,単に事務処理の効率向上にとどまらず,企業の経営戦略の立案や業務企画などの分野にまで及んでいる。多くの企業が間接部門の見直しを行っているが,その背景には,間接部門に対して定型的な事務処理を中心とした業務だけでなく,経営スタッフとしての機能を一層強く発揮することを求めるようになったことが挙げられる。
例えば,人事部門では,給与計算などの定型的な業務に加え,組織変更などに臨機応変に対応するための適正なスキル・キャリア管理の実施や,キャリアパスに基づく研修体系の充実が求められている。社員情報データベースを充実させ,それを活用した最適な人員配置案作りや,多様な研修体系を実現するためにeラーニングを活用するなど,新しい仕組みの構築が求められるようになってきている。
経理部門では,決算処理や財務諸表の作成などの業務に加え,業績データを多元的に分析したり,シミュレーションを行ったりするなど,経理の専門家としての立場から経営を支援する機能が求められている。さらに,連結会計を円滑・迅速に進めるための関連会社の指導や,企業買収・合併の企画及び企業の海外進出時の経営支援までもが求められるようになってきている。
上級システムアドミニストレータは,情報技術を活用して定型業務の効率向上を図るとともに,経営支援に有効なデータベースの充実やデータ活用の新しい仕組みの構築に取り組む必要がある。これらの情報や仕組みをより高度に活用し,経営企画業務にスタッフとしてかかわれるように,スタッフ教育の充実など人材面での強化にも注力する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
情報技術活用による間接部門の経営スタッフ機能強化のため,あなたが携わった業務プロセス変革の概要を,経営上の要請を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務プロセス変革の過程で遭遇した業務上の問題と,それにどのように対処し解決したかを具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アの経営スタッフ強化に対応するために,あなたが提案した人材面での強化策と成果を具体的に述べよ。
📗H12:2000
【AN-H12-1-PM2-Q1】インターネットをビジネスに活用する情報戦略について
インターネットをビジネスに活用する情報戦略は,顧客満足度や利益率の向上などの経営目標を達成するための有力な手段として期待されている。このような情報戦略の例としては,次のようなものがある。
・在庫の削減や顧客の望むものの提供を可能にするBTO(Build To Order)方式による生産
・顧客層の拡大と販売コストの削減を目指す顧客へのダイレクトな販売
・情報システム化にかかわる社内のテーマ・資源・コストの管理統制の仕組み
・調達コストの削減やリードタイムの短縮を目指すダイレクトでオープンな調達
このような情報戦略の実現のためには,既存のビジネスプロセスでは対応できないことも多く,個々のプロセスの見直しや,新たなプロセスの設計も必要となる。これらの例としては,次のようなことが挙げられる。
・BTO方式の実現及び顧客へのダイレクトな販売のための,受注・与信・決済・物流プロセスなどの見直し
・ダイレクトでオープンな調達のための,見積り・発注・決済プロセスなどの見直しと認証プロセスの設計
インターネットとビジネスを取り巻く環境が急激に変化している中で,このような見直しは短期間で実施することが重要である。そのために,システムアナリストは企業全体のビジネスプロセスを見渡し,場合によっては社外で既に実施されているサービスの利用や社外への業務委託などを計画し,短期間でインターネットをビジネスに活用できるようにしなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画したインターネットをビジネスに活用する情報戦略について,その概要を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報戦略の短期間での実現に向けて,どのようなビジネスプロセスの見直しを行ったかを述べよ。その中で,あなたが特に重要と考え,工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたビジネスプロセスの見直しについて,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H12-1-PM2-Q2】情報を共有し活用するシステムの計画策定について
企業全体で情報を共有し活用することによって,業務を効率化したり,顧客満足度を向上させたり,売上げを伸ばしたりすることを目的にしたシステムの開発・導入が進んでいる。このようなシステムとして,グループウェアやイントラネットを利用したシステム,及びナレッジマネジメントを活用したシステムなどが挙げられる。
情報を共有し活用するシステムの計画に当たって,システムアナリストはシステム機能やITツールの利便性に着目するだけでなく,システムを日常業務の中に定着させるための方法について検討することが重要である。そのためには,情報を分析し体系化した上で,次のような点に着目する必要がある。
・生きた情報や価値ある情報を効率よく収集できること
・情報の鮮度を維持したり,錯そうした情報を整理したりすること
・必要な時に必要な人に必要な情報を提供できること
システムアナリストは,情報を共有し活用するシステムの計画策定に当たって,システム開発・導入の目的を明確にし,ねらいどおりの効果が発揮できるようにしなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報を共有し活用するシステムの計画について,その概要を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの開発・導入の目的を簡潔に述べよ。その目的を達成するために,システムを日常業務の中に定着させる方法について,計画策定の段階で,あなたが特に重要と考え工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方法を採用した結果について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H12-1-PM2-Q3】情報システムのパイロット開発・導入について
ERPのように企業全体に導入されるシステムや,サプライチェーンマネジメントのように企業内だけでなく関連企業にも導入されるシステムでは,多くの部門が関係するので,影響範囲が広がっている。また,新たな業務プロセスが導入されるなど,システム利用者への影響も大きくなっている。このようなシステムでは,システムの全機能・全部門を対象に一気に開発・導入を行うと,大きなリスクを伴うことが想定される。このような場合には,パイロット開発・導入によって,機能・性能・運用について次のような評価を行ってから,全面的な展開に進む方法がある。
・新しい業務プロセスを実際に運用する場合,部門を限定して適用し,機能が運用面で十分であるかどうかを検証する。
・新しい技術・手法を適用する場合,対象を限定して適用し,性能を確認する。
・社内外の多くの部門に関連するシステムを開発・導入する場合,協力の得やすいところから導入して,運用面での成功事例を作る。
パイロット開発・導入を効果的に実行・検証するためには,プロジェクトの編成,パイロット対象となる部門や機能の選定,既存システムとの連携方法,利用部門への教育などで様々な工夫を行う必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが計画策定に参画したパイロット開発・導入を採用した情報システムの概要について,関連する部門・組織の範囲や新たに導入・変更された業務プロセスを中心に,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムについて,機能・性能・運用の面からどのような問題点を想定し,パイロット開発・導入計画を策定したか。また,パイロット開発・導入計画を効果的に実行・検証するためにどのような方策をとったか,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方策の結果をどのように評価し,引き続く全面的な開発・導入にどのように反映させたか,簡潔に述べよ。
【SD-H12-1-PM2-Q1】中堅・中小企業における情報化の推進について
経営環境の変化や情報技術の進展によって,中堅・中小企業においても,情報化の推進は事業発展の重要課題となっている。
これまで,これらの企業の情報化は,経営者の意向に左右されたり,推進できる人材が確保できなかったりすることから,思うように進展しないという状況が多かった。
中堅・中小企業における情報化の特徴は,経営者が最も重要と考える経営課題に対象を絞ることで,情報化の企画に直結させやすいことである。情報化の企画段階では,経営者の思いを的確にくみ取り,経営戦略にベクトルを合わせた計画としてまとめる能力が必要になる。しかし,現実には,これらの能力をもつ情報化推進者は不足しがちで,システムの開発作業と併せて外部の力を借りなければならないことが多い。
システムの運用においては,個々の利用者の意識や能力の差が大きいことから,導入時の個別指導や,能力に応じた様々な運用支援策が必要になる。さらには,運用中のシステムについても,利用者が片寄ったり,業務要件の変化に対応できなくなったシステムを,手作業で補完して使用し続けたりするような事態を避けるための措置も欠かせない。
このような中堅・中小企業特有の課題を解決しながら情報化を進めるためには,推進者の確保と,スキルや時間などの不足を,外部の専門家の支援などによって,どのように補完するかということがポイントになる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
中堅・中小企業の情報化推進者としてあなたが対応した経営課題の概要とあなたの役割,及びシステム稼働までに携わった作業の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
情報化の企画段階において,どのように経営者層と方針のすり合わせを行い,情報化計画にまとめたか,スキルや時間などの不足を補うために利用した外部からの支援を含めて述べよ。また,そこで発生した主要な問題点と,その解決策を具体的に述べよ。
■設問ウ
導入したシステムを計画どおり活用するために,利用者に対して,どのような支援を行い,どのような効果を上げたか,あなたの企業における利用者の実態を踏まえて述べよ。
【SD-H12-1-PM2-Q2】ユーザ部門で実施する運用テストについて
情報システムを効果的に運用し,業務効率の向上を図るためには,システム導入時に,ユーザ自らが主体的に情報システムをテスト・検証しておくことが必要である。ユーザ部門で実施するテストでは,新しく構築した業務プロセスが効率的に運用できるかどうかを中心に検証する。
例えば,日常の仕事が新しい業務プロセスで効率的に運用できることを検証するためには,実際のデータを使って業務プロセスのテストを行うことが最も有効である。また,導入したシステムについてのテストだけでなく,他システムや他部門と連携してテストを実施することによって,総合的に業務プロセスを検証することも重要である。トラブル対応やリカバリ機能などをテストで確認し,検証しておくことも忘れてはならない。このようなテストの結果,業務運用上の問題点が発見された場合には,計画した業務効率向上の目標が達成できるように,システム機能や運用方法を変更したり,要員教育を追加・拡充したりするなど,適切に対処していく必要がある。
上級システムアドミニストレータは,導入しようとしている情報システムの運用テストに,部門のリーダの立場で積極的にかかわり,新しい業務プロセスが効率的に運用できることを検証し,適切な対処をする必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった部門の情報化の概要及び情報システム導入時に実施したテストの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたテストで発見した業務運用上の問題点を具体的に述べよ。また,それらの問題点について,システムの機能面や運用面でどのように対処し,解決したかを述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた,テストで発見した問題点への対処の経験から,限られた期間内にテストを効率的に行い,かつテスト結果の信頼性を保つために,ユーザ部門主体で実施するテストをどのように主導すべきだと考えているか。今後のテストで工夫していきたい点を簡潔に述べよ。
【SD-H12-1-PM2-Q3】基幹システムのデータの活用について
コンピュータとネットワークの利用技術が発展し,多種多様なデータを有効に活用することで,業務効率の向上を図ることができるようになってきた。立案・分析・管理などの業務で,基幹システムのデータを抽出して活用することは,データの正確性や入力作業の省力化などの面で有用な手段である。しかし,そのためには,様々な工夫が求められる場合が多い。
例えば,営業戦略立案で多様な分析を行う場合,基本となる売上や経費などのデータは基幹システムから抽出することが多いが,その際,分析に必要な項目や履歴データが保有されているかどうかを確認しなければならない。また,使用するデータを,基幹システムから効果的に抽出するタイミングを見極めることも必要である。ほかの手段で入手した新たなデータを追加したり,データを加工したりする仕組みの構築について検討することも必要になる。
上級システムアドミニストレータは,分析などに必要とされるデータが,基幹システムから入手できるのか,基幹システムから入手できないデータについては,どのような手段を考えるのかなどを検討する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
立案・分析・管理などの業務で,あなたが携わった基幹システムのデータを活用した業務及び情報システムの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの導入の目的と,その目的を実現するために,どのようなデータが必要と考えたかを具体的に述べよ。また,それらのデータのうち,基幹システムから入手したデータ及びそのデータを入手するために行った工夫について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた情報システムについて,基幹システムから入手できなかったデータをどのように補完したか,業務上の成果を含めて,具体的に述べよ。
📗H11:1999
【AN-H11-1-PM2-Q1】情報システム部門の役割の見直しについて
従来,情報システム部門は企業の中でユーザニーズに基づいて,情報システムの企画・開発・運用・保守などを行ってきた。しかし,近年,企業の経営戦略上の要請や多様化するユーザニーズ,情報技術の急激な進展に対応するため,情報システム部門の役割の見直しが必要になっている。
情報システム部門の役割の見直しには,情報システム部門を企画部門として位置づけたり,従来の任務の一部又は全部をアウトソーシングしたり,ユーザ部門に企画・開発・運用・保守の一部又は全部を任せたりすることなどが挙げられる。
一方,企業にとって情報戦略は経営戦略を支える要素として,また,情報システムは経営課題を解決する手段として,ますます重要になっている。したがって,情報システム部門の役割の見直し計画は,効率化や人的資源不足などの解決だけをねらうものであってはならない。情報システム部門の役割の見直しに当たっては,次のような点を考える必要がある。
・企業内で保持すべき機能
・情報戦略を立案する機能・役割の組織編成
・情報システム化にかかわる社内のテーマ・資源・コストの管理統制の仕組み
・情報システムの企画・開発・運用・保守が最も効率良く実行されるための組織編成と業務分担
・システムアナリストなどの高度情報化人材の育成方法
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報システム部門の役割の見直し計画について,その見直しが必要になった背景と情報システムを取り巻く環境を,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたが策定に参画した情報システム部門の役割の見直し計画の概要を述べよ。また,その見直し計画の中で,あなたが特に重要と考えた点は何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた見直し計画について,今後に残された課題とその取組方針を,あなたはどのように考えているか,簡潔に述べよ。
【AN-H11-1-PM2-Q2】ERPパッケージの導入計画の策定について
企業の基幹業務にERPパッケージを適用するケースが増えている。ERPパッケージの導入においては,洗練されたビジネスプロセスの取込みや,システム開発の期間短縮とコスト低減などが一般的に期待されている。
ERPパッケージの導入に当たっては,これまで企業内に定着していた既存のビジネスプロセスと,ERPパッケージが提供するビジネスプロセスとの間のギャップについて,どのように分析し解決するかが最も重要である。そのためには,ERPパッケージの内容と導入方法について検討し,本来のERPパッケージの良さを十分に引き出す必要がある。すなわち,単にギャップの所在に独自プログラムの追加で対処するよりも,むしろERPパッケージの提供するビジネスプロセスをできるだけ取り込み,独自プログラムの追加を最小にしなければならない。そのために次のようなことが行われる。
・ERPパッケージ導入の意義や導入する際に発生する諸問題を,あらかじめユーザに明確に説明し,十分認識させる。
・各業務に精通した専門家を加え,早期にできるだけ正確なギャップ把握を行う。
・一部の事業領域又は業務領域を選んでプロトタイピングを実施する。
システムアナリストは,ERPパッケージの導入に当たって,まずその目的を明確にした上で,経営トップの意向,ユーザニーズ,プロジェクト予算などを十分踏まえてギャップを解決し,当初の期待効果が出せるように導入計画を策定しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画したERPパッケージの導入計画について,導入の背景と目的,導入計画の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた導入計画において,既存のビジネスプロセスとERPパッケージのビジネスプロセスとのギャップをどのように分析し,導入の目的を踏まえてどのような解決策を立案したか,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたギャップの分析と解決の方法,及びその工夫について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H11-1-PM2-Q3】システム開発計画における新技術の導入検討について
近年,情報技術の進歩は著しく,システムアナリストは常に最新の技術動向を把握しておく必要がある。新技術の活用によって,コスト削減・効率化・性能向上などのシステム面の効果に加えて,新たなビジネス分野への進出や流通チャネルの拡大などのビジネス面の効果が期待できる。したがって,システム開発計画の策定では,新技術を活用したシステムの実現方法を検討することが重要になる。
しかしながら,個々の企業にとって新しい技術を導入する場合,導入の可否の判断に直接影響する次のようなリスクが存在する。
・今後の事実上の標準にならないおそれがある。
・性能や信頼性を保証する実績が少ない。
・新たなセキュリティ上の問題を生じるおそれがある。
新技術を選択し導入を決定するには,認識されたリスクを回避するための対策を立案することが前提になる。
このほか,新技術を円滑に導入して期待した効果を上げるためには,次のような点を考慮しなければならない。
・既存の技術に新技術を加えることによる運用負荷の増大への対策
・既存のソフトウェア資産・ハードウェア資産からの移行方法や接続性の確保
・技術者への新技術の教育や訓練の方法
・新たな保守体制の確保
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画したシステム開発計画について,システムの概要と選択した新技術の概要,及び新技術導入で期待した効果を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム開発計画の策定に当たって,あなたはどのようなリスクを認識したか。また,認識したリスクを回避するためにどのような対策を立案したか,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた新技術を円滑に導入して期待した効果を上げるために,あなたが工夫した点を述べよ。
【SD-H11-1-PM2-Q1】業務プロセスの再構築について
業務プロセスの再構築においては,個々の現状の業務プロセスにとらわれず,思い切った発想から仕組みを考えることが重要である。業務プロセスの本来の目的を十分認識し,これに必要な機能を満たす最適な仕組みを作るためには,自部門内の現状にとらわれず,関連他部門を含めた全社的視点と自部門の在り方の双方を意識することが重要である。業務プロセスの再構築では,従来の業務プロセスとの違いが大きいほど,周到な準備と関係者の意識改革が必要である。新しい業務の仕組みを定着させ,効果を上げるためには,企画段階から関係者に幅広く参画してもらうなどの施策も必要である。
従来できなかったような新しい業務プロセスを実現するためには,情報システムの活用が有効になる場合がある。例えば,購買業務の効率向上のために,ネットワークを通じて取引先と生産や在庫の情報を共有し,その情報に基づいて製造現場から原材料を直接発注するなど,納入指図から決済までの業務プロセスを短縮し簡素化を図るような方策が考えられる。この場合,あらかじめ取引先や関連部門と,業務手順やルールなどについて十分検討し,関係者に周知することが必要である。また,経費の承認申請やりん議など煩雑で冗長になりがちな業務の効率を向上させるためには,これらの手続を情報システムの活用によって一元化し,承認手続を含めて簡素化を図るべきである。そのためには,思い切った権限委譲を含め,権限と責任について検討することも必要になる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたは,どのような業務プロセスの再構築を情報システムの活用によって可能にしたか,その概要とねらいを800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた業務プロセスの再構築において,従来の業務プロセスをどのように変えたか,また変える際にどのような問題が生じ,これをどのように解決したか,情報システムの活用と関連させて具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた業務プロセスの再構築について,今後より一層の業務上の効果を上げるために,とるべき方策を簡潔に述べよ。
【SD-H11-1-PM2-Q2】部門情報システムにおけるデータ活用の高度化について
近年,ビジネス環境の変化は厳しく,各部門においては,短期間で情報システムを構築してデータを活用し,業務上の成果を上げることが期待されるようになっている。また,情報技術の急激な進展やユーザの情報リテラシの向上によって,単なる表計算ソフトウェアの活用にとどまらず,データベースの分析用ソフトウェアを活用した高度な顧客分析や販売分析など,ユーザ部門でも比較的複雑な情報システムを構築し,データ活用の高度化を図ることが可能になってきている。
各部門でこのような情報システムを稼働させ,データを十分に活用して業務上の成果を上げるためには,運用段階まで含めた十分な計画を策定して,慎重に取り組む必要がある。期間情報システムとの連携によって,必要なデータを適宜更新し,整合性のあるデータを提供できるようにすることも重要である。また,部門情報システムの有効活用には,業務的な利用促進に重点を置いた十分な教育や研修が必要になる。さらには,情報技術に詳しいユーザだけでなく,一般的なユーザが十分活用できるように,操作が容易なシステムを指向するとともに,導入後の技術的なサポートによって,ユーザの作業負担を少なくする工夫が求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが構築に携わったデータ活用を目的とした部門情報システムについて,その業務上の目的とシステムの概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた部門情報システムについて,データを有効活用し,業務上の成果を上げるためにどのような工夫を行ったか,データの活用内容と併せて具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた工夫について,あなたはどのように評価しているか。また,今後より一層のデータの有効活用を推進するために,解決すべき課題とその解決策を簡潔に述べよ。
【SD-H11-1-PM2-Q3】営業・マーケティング部門における情報技術の活用について
情報技術を活用して営業活動を支援したり,サービスや商品の魅力を高めたりして顧客層の拡大を図ることは,企業にとって有力な戦略である。しかし,技術ありきのシーズ指向に陥ることなく,あくまでも顧客の視点を考慮したビジネスの観点から企画を行うことが重要である。近年のように顧客のし好の変化が激しい環境下では,販売の状況や傾向を素早く把握し,その変化に迅速かつ適切に対応できることが重要である。例えば,インターネットによる直販チャネルやPOS情報を活用し,顧客の反応を見つつ,売れ筋商品中心の品ぞろえを行ったり,セット販売の組合せを変えたりして拡販を図るなど,柔軟な対応が可能になる。
情報システムやネットワークの活用は,業務処理の改善だけでなくマーケットの拡大にも役立つ。例えば,ネットワークを活用し,情報提供サービスなどを付加することによって商品やサービスの魅力を高め,新たな需要を創造することもできる。このような視点は,営業・マーケティングなどの部門で情報技術を活用する上で,今後一層重要になると考えられる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった営業・マーケティング部門における,情報技術を活用した業務施策の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた施策について,その効果を上げるため顧客の視点からどのような工夫や試みを行ったか,その結果及びその結果をもたらした原因を含めて具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた工夫や試みについて,あなたはどのように評価しているか。また,今後より一層の成果を得るために,どのように情報技術の活用を図るべきか,簡潔に述べよ。
📗H10:1998
【AN-H10-1-PM2-Q1】システム化範囲の策定について
システム化計画での重要な作業項目として,システム化範囲の策定がある。要求分析の段階では,ユーザから様々な開発要求が出される。これに対して,システムアナリストはシステム開発の費用対効果やリスクを見極め,システム化による効果が最大限に得られるよう,システム化範囲の策定を行わなければならない。
そのためには,ユーザのシステム開発要求について,次のような視点をもって検討することが重要である。
・業務手続・手順や組織の役割・責任分担の変更で改善できるところはどこか。
・業務改善との連携でシステム開発の効果が出るところはどこか。
・システム開発段階で技術面の問題が発生しないか。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画したシステム化計画の概要とユーザのシステム開発要求について,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたはシステム化範囲の策定に当たって,どのようなことを検討したか,検討した手順とともに述べよ。また,システム化の効果を最大限に高めるために,あなたが特に重要と考え,工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたシステム化範囲の策定について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H10-1-PM2-Q2】ネットワークシステムのリスクマネジメントについて
最近,顧客情報の流出や不正アクセスによるシステム破壊などの事件が発生しており,ネットワークシステムのリスクマネジメントの在り方が問い直されている。
コンピュータの利用は,ホスト中心から分散ネットワーク,更にインターネットと進展している。守るべき情報資産は様々に分散し,それらへのアクセスも様々な場所から行えるようになって,対策の在り方は根本から大きく変化してきている。対策を考える際には,ユーザなどのモラルに過度に依存するのではなく,リスクの客観的な認識の上で抑止や防止を行う必要がある。
リスクの発生確率と影響度は,情報システムのハードウェアとソフトウェア及びネットワークの構成やその機能によって異なってくる。したがって,まずネットワークシステムの全体を俯瞰(ふかん)し,リスクの発見・確認と評価を行う必要がある。そして,対策立案の際には費用対効果の分析だけではなく,経営的な判断も加味して総合的に判断することが重要になる。発生形態が極めて例外的であり,対策実施の負荷が大きな場合には,対策を行わないという判断もありうる。ただし,そのような場合においても,システムアナリストは,リスクの網羅的な洗い出しや定量化などを行い,客観的で適切な判断が行われるように配慮しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたがリスクマネジメントの対象としたネットワークシステムの概要と,その中でリスク分析を行った手順について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたリスク分析によって,どのようなリスクが発見・確認されたか。また,そのリスクをどのような考え方に基づいて評価し対策を立案したか,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策立案について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H10-1-PM2-Q3】システム開発におけるSIベンダの活用について
システムを自社要員だけで開発することは一般に困難な場合が多く,外部のベンダを活用するケースが多い。特に,最近のクライアントサーバシステムでのシステム開発では,マルチベンダの製品構成を取りまとめるSIベンダの事例も多くなっている。このような場合,SIベンダの技術力や取りまとめる能力によって開発の成否が決まることが多く,SIベンダ選定の重要性はますます高まっている。
選定に当たっては,まず,活用目的を明確にし,システム開発における委託側とSIベンダ側との役割分担を決定する必要がある。その上で各SIベンダに提案を依頼し,提案品質やコスト,過去の実績などを総合的に判断する必要がある。提案品質とは,提案の網羅性や具体性,新技術やアプリケーションについての技術力,要求項目に対する創意工夫などである。提案品質を的確に評価するためには,各SIベンダを同一基準で評価できるような提案依頼内容にしたり,技術力を客観的に把握できるような実演を依頼したりするなどの工夫が必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画したシステム開発計画の概要とSIベンダ活用の目的について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた活用目的を達成するため,あなたが決定したSIベンダとの役割分担について述べよ。また選定に当たって,どのような評価項目を重視し,どのような方法で評価したか。提案品質を評価するために工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
SIベンダの選定結果について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【SD-H10-1-PM2-Q1】部門の情報化推進におけるソフトウェアパッケージの活用について
コンピュータの急速な進歩,普及によってエンドユーザ自らがコンピューティング環境を活用し,業務効率の向上を図ることができるようになった。
部門の情報化を推進する場合,従来のように膨大な費用や時間を掛けて独自のシステムを開発することは,必ずしも得策ではない。目的に合ったシステムを,短時間に効率よく構築するために,信頼性の高いソフトウェアパッケージを導入し,それを効果的に活用している企業が多い。例えば,営業企画部門では,ホストコンピュータから必要データをパソコンにダウンロードし,表計算ソフトなどを使って,エンドユーザが素早く売上げなどを分析できるようになってきた。また,利用部門で活用できる予算管理や在庫管理などの業務パッケージが普及してきた。その結果,売上げ・利益の予実管理や適正在庫の維持管理などを,簡単にかつ低コストで実現し,業務効率を向上させることが可能になってきている。
上級システムアドミニストレータは,業務効率の向上を図るため,部門の情報化を推進する際に,独自のシステムの開発を企画するだけでなく,ソフトウェアパッケージを有効に活用するなど,最善の方法を選択することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたの所属する部門における,あなたの役割及び部門情報システムの概要を,システム導入の目的を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた部門情報システムの導入に際して,どのようにソフトウェアパッケージを活用したかについて述べよ。また,そのソフトウェアパッケージの選定経緯を述べ,活用の効果について,業務的な観点からの評価を述べよ。
■設問ウ
ソフトウェアパッケージの活用を含めた部門情報化の推進について,今後どのような計画を考えているか,その目的と効果を含めて述べよ。
【SD-H10-1-PM2-Q2】情報システムの活用に関するユーザ教育について
情報システムの活用には,ユーザの能力に応じた教育が不可欠である。ユーザ教育は従来,情報システム部門が主導してシステム操作などを中心に画一的に進められることが多かった。最近は,パソコン単体の利用だけでなく,共用データベースの活用,グループウェアの利用など,利用形態の多様化と複雑化が進み,業務への応用範囲が大幅に広がっている。これに伴い,情報システムの活用に関するユーザ教育は,業務改善に役立てるという視点が一層重要になってきた。
上級システムアドミニストレータには,情報システム部門などの支援を得ながら,次のような点に留意して,情報システムの活用に関するユーザ教育を計画し,実施することが望まれる。
・情報システム化の目的やねらいを明確にし,理解させる。
・業務改善への意欲と,そのために情報システムを積極的に活用する意識をもたせる。
・情報システムの活用に関して,費用対効果を意識させる。
・実務又は実際に即したテーマによって,業務改善のために情報システムを活用する方法を学ばせる。
このようにして,業務改善を目的に情報システムを活用する能力を一層高め,業務上の成果に結びつけていくことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが計画した情報システムの活用に関するユーザ教育の概要を,情報システムの利用形態及びユーザ教育のねらいを含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたユーザ教育を計画,実施する上で,あなたが特に重要と考えた点を挙げ,それらについてどのような工夫を行ったか,業務上の成果に関連付けて具体的に述べよ。
■設問ウ
あなたが所属する部門の業務上の成果を一層高めるため,情報システムの活用に関するユーザ教育の上で,今後推進したい施策とその効果について,あなたの考えを述べよ。
【SD-H10-1-PM2-Q3】部門情報システムにおけるセキュリティ管理について
情報システムの普及と高度化によって,コンピュータシステムに蓄えられるデータは,企業の経営を左右するほど重要なものになってきている。一方で,ネットワーク化の進展に伴い,データの流通が容易になり,共有化が推進されてきた。企業では,このような環境下で,機密度の高いデータを扱わなければならないという難しい課題に直面している。
多数のパソコンが社内に配置され,ネットワーク化されている環境では,セキュリティを情報システム部門で一元的に管理することは,大変難しくなってきている。情報システム部門では,ユーザIDの管理やウィルスチェックなどのシステム的なセキュリティ確保の方策を実施することが必要である。さらに,全社的な観点からネットワークへのアクセス基準,ソフトウェアやデータの利用基準などを整備することも重要である。一方,利用部門では,アクセス基準や利用基準を基に,日常の運用基準を整備し,部門内にセキュリティ対策の実施を徹底させることが必要である。また,ユーザのセキュリティに関する意識の高揚を図ることも重要である。
このように,情報システム部門と利用部門が相互に役割を分担して十分にセキュリティを確保した上で,データの共有や活用を推進することは,上級システムアドミニストレータの役割である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたの所属する部門におけるあなたの役割及び部門情報システムの概要を,部門で実施しているセキュリティ対策を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたの部門で実施しているセキュリティ対策を,全社のセキュリティ対策との役割分担の観点から述べよ。また,部門におけるセキュリティ対策の運用上の問題点は何か,それにどう対応したかについて述べよ。
■設問ウ
今後,更に部門の情報化が推進されることによって,セキュリティを確保する上で予想される問題点は何か,その対応策を含めて述べよ。
📗H09:1997
【AN-H09-1-PM2-Q1】情報戦略の策定について
現在,経営課題の一つとして,ビジネススピードの向上が強く求められている。情報システムの役割も,単純作業の肩代わりや業務プロセスの効率向上から,経営への貢献へと拡大しており,ビジネススピードの向上を実現するための情報戦略が求められている。この情報戦略の例には,次のものがある。
・現場で把握した顧客ニーズを迅速に営業活動に反映する。
・実績情報を,多様な視点から分析しやすい形に整備し,計画立案の中でタイムリに活用する。
・販売・物流・生産の情報を総合的に管理し,柔軟かつ迅速なトータルロジスティックスを実現する。
ただし,情報戦略を策定する際には,情報システムとそれを取り巻く状況についても十分考慮しなければならない。多くの場合,情報システム要員の数やスキルの不足,情報システム基盤の整備不足,情報リテラシ向上の遅れなど幾つかの課題があり,それを解決しなければ,望ましい情報戦略の実現はできない。
システムアナリストはこのような課題を見極め,どのように解決していくのかを現実的に検討し,情報戦略を策定する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
ビジネススピード向上のために,あなたはどのような情報戦略を策定したか。その概要と,背景となる事業環境及び経営戦略について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報戦略の策定段階で,どのような現状の課題が識別されたか。また,それに対してどのような対策を立てたか,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策について,あなたはどのように評価しているか,簡潔に述べよ。
【AN-H09-1-PM2-Q2】情報システムの中長期計画の策定について
昨今,企業を取り巻く環境やビジネス領域が大きく変化している。更に,新しい情報技術が急速な早さで普及し続けている。このような中で,情報システムの中長期計画の策定がますます重要になっている。
情報システムの中長期計画の内容として,例えば次のものがある。
・情報システム開発の優先順位づけ
・情報システム基盤の整備計画
・情報システムの開発・運用体制の整備計画
情報システムの中長期計画では,経営戦略や業務革新・制度改革・組織の再編などとの関連を明確にしておかなければならない。
システムアナリストにとって重要なことは,情報システムが経営課題の解決や経営活動に貢献できる点について検討を深め,経営トップから計画の承認を得ることである。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報システムの中長期計画について,計画の概要とそれが必要になった背景を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの中長期計画について,検討した手順を簡潔に述べよ。また,情報システムが経営課題の解決や経営活動に貢献できる点として,あなたが特に重要と考え,力点をおいて検討したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報システムの中長期計画について,まだ不足している点,問題点は何か。また,今後一層の強化・拡充を図っていくべきことは何か,あなたの考えを簡潔に述べよ。
【AN-H09-1-PM2-Q3】基幹業務におけるクライアントサーバシステムの導入計画について
近年,基幹業務においてもクライアントサーバシステム(CSS)を採用し,システムを開発するケースが増えている。
CSSを採用する理由として,中長期的に新技術・新製品がより多く期待できると考えている場合やトータルな開発コストの削減,開発期間の短縮を期待する場合などがある。CSS採用のメリットを享受するためには,採用の目的を明確にし,CSSの特徴を踏まえたシステムの計画,設計をすることが重要である。
一方,CSSを採用することによって,次のようなシステム開発・運用上のリスクや制約が生じる。
・マルチベンダになるケースが多く,その際,技術的な取りまとめや障害対策が難しい。
・ホストシステムと比較し,信頼性が劣ると考えられる製品も多い。
・CSSでは,大量帳票出力など実現することが難しい機能もある。
・分散システムとしての運用の検討が必要である。
基幹業務システムの開発に当たっては,CSS採用によって生じると考えられるシステム開発・運用上のリスクや制約について,計画段階からその対策を十分に検討する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
CSSを適用した基幹業務システムの機能概要及びCSSの採用によって,あなたが期待した効果を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた期待効果を達成するために,システム化計画段階で工夫した点を簡潔に述べよ。また,CSSを採用することによって発生すると考えたシステム開発・運用上のリスクや制約を幾つか挙げ,それらに対して計画段階で検討した対策について,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた計画段階での工夫及びリスクや制約に対する対策の効果を,それぞれどのように評価しているか。また,問題点について今後どのように改善すべきと考えているか,簡潔に述べよ。
【SD-H09-1-PM2-Q1】非定型業務の改善について
企業における業務は,手順や判断基準の定められた定型的な業務と,これらをあらかじめ定めることが困難な非定型的な業務に分かれる。販売管理業務を例にとれば,販売実績を収集し,一定の方法で分析して報告するのは定型的な業務であり,市場の変化や規模を見通し,これに基づいて販売戦略を立案するのは非定型的な業務といえる。経営環境が厳しく,しかもその変化が激しくなるにつれ,判断や創造性発揮などの面で,より質の高い仕事を行うことが要請され,非定型的な業務の改善が一段と注目されるようになってきている。
非定型的な業務の改善を支援する情報システムには,ユーザの判断や創造性の発揮を求められる仕事を行う際に有効な情報を,迅速に提供できる仕組みが重要である。的確な判断を速やかに下すためには,ユーザ自身が,必要なデータをデータベースから取り出し,分析や加工を行う必要がある。蓄積データを元に統計処理やシミュレーションを行うことによって,市場予測や事業化検討を行うことも可能になる。また,問題発見・分析を支援するツールを使うことで,顧客満足度の向上やアイディア創出に役立たせることもできる。このように,ユーザがそのもてる能力を最大限に発揮できるような仕組みを作り,活用を図ることによって,業務上の成果を上げていくことが望まれる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが実施した業務改善の概要について,非定型的な業務を中心に,その背景及びねらいを含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの施策に関し,非定型的な業務の改善の上で特に工夫を行った点について,情報システム活用の内容を含めて述べよ。
■設問ウ
非定型的な業務の改善の結果について,あなたはどのように評価しているか。また,今後の改善策として何をすればよいか,あなたの考えを述べよ。
【SD-H09-1-PM2-Q2】業務上のコミュニケーションにおける情報技術の活用について
近年の情報技術の進展は著しく,その活用範囲は急速に拡大している。コンピュータがコミュニケーションツールとしても利用されるようになってきた。
最近,企業で広く活用されている電子メールは,その代表例である。電子メールをうまく活用することによって,企業内コミュニケーションの確実性と効率を高め,業務上の成果を上げている企業も多い。全国各地の営業担当者に,他社製品との比較情報や新製品の情報などを,正確かつ迅速に伝達することによって,顧客サービスを向上させたり,販売機会を増やしたりすることに成功した例もある。
一方で,コミュニケーションツールは導入したものの,期待した効果が得られないケースもある。例えば,電子メールを全社に導入して,社内りん議のスピードアップをねらっても,担当者の責任範囲や承認ルールを見直さなければ,そのねらいの実現は難しい。
生産性の向上やリードタイムの短縮,売上げの増加など,経営上,業務上の目標達成のためには,単に新しいコミュニケーションツールを導入するだけではなく,業務そのものを見直し,必要に応じて組織を変革し,その上で情報技術を活用することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
業務上のコミュニケーションに関して,どのような点を問題と認識し,改善を試みたか。その概要をコミュニケーションツールの活用を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの改善に対して,業務上の成果や経営面での貢献はどうであったか,具体的な例を挙げて評価せよ。また,コミュニケーションツールの活用に関してどのような点が有効であったか,その理由も含めて述べよ。
■設問ウ
今後,コミュニケーションツールの活用範囲をどのように拡大,発展させようと考えているか。また,そのときにどのような点が障害となるか,あなたの考えを述べよ。
【SD-H09-1-PM2-Q3】システムの運用におけるユーザ部門の役割分担について
従来は,情報システム部門が中心となってシステムを構築・導入し,システムの運用も情報システム部門が一元的に実施してきた。近年,情報技術の急速な進歩によって,情報システムの活用範囲が広がり,多様化するにつれ,情報資源の管理や障害時の対応など,システムの運用面でユーザ部門の果たす役割が増えてきている。
各部門に情報システムを導入し,全社ネットワークを使って部門間で情報を交換する場合,全社ネットワークのパフォーマンス管理や障害対応については,情報システム部門が担当するが,ユーザ側のパソコンやプリンタの障害などへの初期対応は,ユーザ部門が担当するようになってきている。新しいアプリケーションを導入するときや,システムのバージョンアップを実施するときも,情報システム部門などの助言を得て,ユーザ側で作業を実施したり,問題に対処したりする場合がある。ただ,この役割分担も一様ではなく,システムの機能や規模,関係部門でのシステムの位置づけ,ユーザのシステム利用度合いなどに応じて,ユーザ部門の役割も変わってくる。
上級システムアドミニストレータは,関係する部門間で,システムの運用面での役割分担を調整することによって,情報システムを効果的に活用し,業務の効率向上に努める必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたの所属する部門での情報システムの概要と,あなたの情報システムへのかかわり方を,システム導入の目的を含めて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの情報システムを効果的に活用するために,あなたの部門では運用面でどのような役割を分担したか。また,その際に問題となった点と対応策及び結果について述べよ。
■設問ウ
今後,情報システムを活用して,より一層業務の効率を向上させるために,あなたの部門での運用面の役割分担で重視なければならない点は何か。現状の反省点と対応策について,あなたの考えを述べよ。
📗H08:1996
【AN-H08-1-PM2-Q1】適用業務システム開発における業務の見直し計画の立案について
顧客ニーズの多様化,ビジネススピードの向上,グローバルな競争の激化など,企業を取り巻く環境は急激に変化している。それに伴い,新たな業務が発生したり,業務ルールが変わったり,業務手続が複雑になったりしている。
このような中で適用業務システム開発を行う場合,業務手続の改善や標準化などの業務の見直しが一層重要になる。業務の見直しでは,見直し項目の洗い出しやそれらの因果関係の整理,改善の難易度や手段などの検討が行われる。これらを効率良く進めるために,システムアナリストはユーザ部門と協力して,具体的な業務の見直し手順を立案することが重要である。
業務の見直しによって,開発すべき適用業務システムの範囲や要件・機能が明確になるだけでなく,システム自体がシンプルになって,ユーザが使いやすいシステムや開発・運用・保守のしやすいシステムを実現することもできる。
適用業務システム開発の計画に当たり,システムアナリストは企業戦略や事業環境に着目し,業務の見直し計画を立案する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した適用業務システム開発計画の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた適用業務システム開発計画の立案に当たって,あなたが策定した業務の見直し計画の手順を簡潔に述べよ。また,その手順の中で,業務の見直しを効率良く進めるために,特に重要と考え,工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた業務の見直し計画が実施されると,システムの開発又は運用や保守にとってどのような効果があるか,あなたの考えを簡潔に述べよ。
【AN-H08-1-PM2-Q2】情報リテラシの向上について
近年の職場への急速なパソコンの普及・浸透によって,利用者自身による情報処理の機会が一層増加している。しかも,利用者が習熟しなければならないパソコンソフトの種類も利用方法も多岐にわたっている。
企業にとっても,パソコンの装備率と全社的な利用水準の向上は,業務のスピードアップやオフィスの生産性向上を図るうえで重要事項であり,組織的・中長期的に取り組まなければならない戦略的課題になっている。利用水準を高めるためには,情報リテラシの向上を図ることが極めて重要である。
このためには,利用者が使いやすいシステム環境を整備したうえで,次のような取組みが考えられる。
・全社的な利用技術向上のための教育制度の整備と専門スタッフや組織の設置
・利用者問合せ窓口としてのヘルプデスクの設置や,各職場へのシステムアドミニストレータの配置などの組織作り
・各種通達や決裁文書の電子化など,パソコン活用を前提にした業務ルールの見直し
・パソコン活用促進に向けた各職場への啓蒙活動
このようにシステムアナリストは,中長期的な視点で組織的な取組み課題を明確化し,計画的・継続的に全社的な情報リテラシの向上を図っていくことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
パソコンを職場へ展開した背景と現在の装備状況・利用状況について,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたが計画した情報リテラシ向上のねらいと具体的目標は何かを述べよ。また,利用者への教育や支援組織の整備,業務ルールの見直しなど,情報リテラシ向上のために,あなたが重要と考えて計画し,実施したことを具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた情報リテラシ向上のための施策の成果をどのように評価しているか,今後,改善すべきと考えている点も含めて簡潔に述べよ。
【AN-H08-1-PM2-Q3】適用業務システム開発でのソフトウェアパッケージの利用計画の立案について
最近,開発期間の短縮や開発・運用・保守の費用削減などを目的として,ソフトウェアパッケージ(以下,パッケージという)を利用した適用業務システム開発の事例が増えている。独自開発に比べてパッケージを利用する利点が明確になるのは,次のような条件を満たす場合である。
・パッケージの業務モデルやデータモデルが対象業務に適合している。
・カスタマイズが少ない。
・パッケージのプラットフォームや情報技術がその企業の情報システムの中長期計画に一致している。
しかしながら,ユーザ部門の業務やシステム開発要求を的確に把握しきれないと,予想外のカスタマイズが発生したり,ユーザにとって使いにくいシステムになったりすることがあり,パッケージを利用する利点が失われることもある。
一方,パッケージの業務モデルやデータモデルに合うように,ユーザの業務を見直すという考え方もある。業務の見直しは組織的に進めなければならないので,業務プロセスなどの変更に多くの工数がかかり,システム立上げまでにかなりの時間が必要になることもある。しかし,効果的に進んだ場合には,業務処理の質的向上やスピードアップなどの改善効果が期待できる。
適用業務システム開発でのパッケージの利用計画の立案に当たっては,システムアナリストは企業の事業環境,情報システムの中長期計画なども含めて総合的に考えなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した適用業務システム開発計画の概要を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた開発計画の中で,パッケージ利用の目的と利用に当たって設定した課題を簡潔に述べよ。また,その課題を解決するために,あなたはどのようなことを重要と考え,計画したか,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたパッケージの利用計画について,どのように評価しているか,あなたの考えを簡潔に述べよ。
【SD-H08-1-PM2-Q1】部門間の連携が必要なエンドユーザコンピューティング(EUC)の推進について
情報の共有化や有効活用を目指したEUCの推進では,部門を超えた情報の連携や,部門間での作業分担などの調整が必要になることが多い。この場合,他のユーザ部門や情報システム部門との協力なしにはEUCの推進は難しい。経営責任者の協力を得て,トップダウン的なアプローチをとったり,関連部門のキーパーソンの賛同を得て,早い段階から協力体制を整備したりすることが必要である。他のユーザ部門との間では,共有すべきデータのコードを統一したり,データの整合性を確保したりするための調整が必要になる。システム構築後のデータの保守・管理の手順や役割分担を取り決める際にも,関連部門との調整が重要になる。また,EUCを展開するうえで,技術的な問題の解決や全社システムとのインタフェースの設計などで,情報システム部門の協力も必要である。
上級システムアドミニストレータは,EUCの目的や必要性,経営目標との関連などを踏まえ,部門を超えた協力関係を構築する必要がある。また,自らリーダシップを発揮して,EUCを推進しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが導入するに至ったEUCのシステム概要を,その経緯と目的も含めて800字以内で述べよ。
■設問イ
そのシステムの導入に当たり,他部門とどのような調整を行い,協力関係を築いたか,具体的な調整内容及び行動について述べよ。また,協力関係を築くうえで,どのような困難があったか,その解決策も含めて述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた調整や協力の結果について,あなたはどのように評価しているか,今後の改善点も含めて述べよ。
【SD-H08-1-PM2-Q2】部門情報システム構築における外部の力の活用について
部門情報システムの構築では,情報システム部門の協力が十分には得られなかったり,部門内の要員や技術力が不足したりすることもあり,外部の力を活用することが必要な場合が多い。例えば,部門業務のあり方やシステム化計画の検討において,外部コンサルタントの斬新なアイディアや客観的な評価を得ることは効果的である。また,システムの開発や運用においても,単に要員不足を補うためだけではなく,外部の知見や技術力を生かす観点で外部の力を活用することが重要である。
部門情報システム構築において,外部の力を活用する際には留意すべきことが多い。まず,外部に期待する役割を明確にし,その役割を果たせるかどうかという視点で協力者を評価し,選定することが大切である。
また,仕事を効率良く進めるためには,協力者とのコミュニケーションが重要である。情報システム構築に必要な情報を十分に伝えなければならないが,現実には,伝えるべき内容の調査や整理が不十分なことが多い。コミュニケーションスキルの不足やシステム特有の専門用語が障害になる場合もある。内部と外部の役割分担を明確にして,情報システム部門とのかかわりや役割についても十分調整を行ったうえで,部門情報システムの構築を推進する必要がある。
上級システムアドミニストレータは,このような点に特に留意し,外部の力を活用した部門情報システムの構築において,リーダシップを発揮していくことが必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが取り組んだ部門情報システムの構築の概要と,外部の力を活用したねらいを800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アの部門情報システムの構築において,どのような視点で外部の協力者を評価し,選定したかについて述べよ。また,部門情報システムの構築を推進するうえで,協力者とのコミュニケーションについて,特に問題又は障害となった点を挙げ,それらをどのように克服したかを述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた外部の力の活用に際し,情報システム部門とのかかわりや役割に関する調整で留意した点について述べよ。
【SD-H08-1-PM2-Q3】データの効果的な活用について
上級システムアドミニストレータが推進する部門情報化のねらいの一つに,データの効果的な活用がある。
活用の対象となるデータは多種多様である。例えば,営業部門で使用されるデータには,氏名や住所などの顧客情報,日々の取引状況や営業活動の記録,自社製品の特徴や価格などがある。また,業界のトレンドや同業他社の業績なども重要なデータである。活用の仕方には,“売上速報”に代表される新鮮さ(スピード)に重点をおくレポート類がある。基幹システムから定期的に取り込んだ取引実績データを基に,過去数年間の取引実績推移をいろいろな切り口で集計し,分析する場合もある。また,営業活動記録や同業他社の業績のように,随時にデータを取り込んで活用する場合もある。データの戦略的な活用という観点からは,集約されたデータだけでなく,POSシステムのように生データを収集し,直接それを活用する仕組みも必要である。
上級システムアドミニストレータに求められるのは,情報化のねらいを十分に把握したうえで,情報システムを利用してデータを効果的に活用することである。その際に,データの形式,性質,量,他のデータとの関連などを考慮する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが担当している業務と,その業務で活用している主要なデータについて,データの形式,性質,量,他のデータとの関連などを含めて800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アのデータについて,情報システムを利用してどのようにデータを業務に活用したか,その目的と特徴的な活用方法を述べよ。また,情報システムの利用に際し,データを活用していくうえでの制約をどのように調整し,克服したかについて述べよ。
■設問ウ
あなたが今後活用したいと考えているデータについて,その形式や性質,量,他のデータとの関連などを述べ,どのような活用の仕方が考えられるか,業務改善のねらいとともに,あなたの考えを簡潔に述べよ。
📗H07:1995
【AN-H07-1-PM2-Q1】開発計画策定における合意形成について
情報システムの開発計画を立案し承認を得ることは,システムアナリストの重要な課題である。そのためには,計画の立案段階において関連部門長の参画を得て,計画への承認が得やすい体制にしておくことが必要である。また,関連部門にシステム化の必要性や効果を十分アピールし,理解を得ておくことが重要である。
関係者間での意見の相違や個別の利害の対立がある場合などには,全社的な視点に立って,できる限りそれを調整し,合意形成を図ることが必要である。このような場合,関連部門長やキーパーソンを集め,重要案件についての検討会を開催し,意見の調整を図ることや,意見の相違点を明確にして経営トップの判断や指示を仰ぐことなどが考えられる。
このように,システムアナリストは,開発計画についての合意形成のため,必要情報の提供や異なる意見の調整,計画骨子の効果的な説明などを実施する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが計画策定に参画したシステム開発の目的と概要及び開発計画立案体制について,800字以内で述べよ。
■設問イ
その計画立案時に,開発の必要性や新システムにおける実現機能,開発スケジュール,開発予算などについて,関係者間で調整すべき意見や利害の相違には,どのようなものがあったか述べよ。また,それらの点についてどのような方法で合意形成を図ったか,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問ア及びイで述べた計画立案体制や合意形成の方法について,あなたはどのように評価しているか,今後の改善点も含めて簡潔に述べよ。
【AN-H07-1-PM2-Q2】情報システム部門の役割について
従来情報システム部門は汎用コンピュータを中心としたセンタ集中型の情報システムの計画・開発・運用管理を中心に業務を行ってきた。最近経営環境の急激な変化や情報技術の革新,エンドユーザコンピューティングの浸透などによって,情報システム部門を取り巻く環境は大きく変化し,それに伴い情報システム部門の役割が変わってきている。
エンドユーザコンピューティングを積極的に推進している企業では,ユーザ部門に開発や運用管理の一部を任せるケースもかなりみられるようになった。また,ユーザ部門に対するサービスの提供を主体とした業務から,情報戦略の企画立案を主体とした業務へ,情報システム部門の役割を見直すところも多くなっている。
一方,ユーザの利用形態がますます多様化することで,情報システムは複雑化している。その結果,ハードウェアやソフトウェアの資源管理,システムの障害管理,セキュリティ管理,分散システムのメンテナンス作業などにおいて,ユーザ部門だけでは対処できない問題や部門ごとの個別対応では効率が悪い状況が発生している。そのため,企業の中で統制のとれた組織的な取組みの重要性も増している。
システムアナリストは,情報システムの中長期計画や情報システム開発計画の立案に当たって,企業・団体における情報システム部門を取り巻く環境の変化を踏まえ,情報システム部門の役割について十分に検討する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報システムの中長期計画又は情報システム開発計画の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた計画の策定に当たって,あなたは情報システム部門の役割についでどのような見直しを行い,その結果どのような役割を設定したか,設定に至った理由とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで設定した情報システム部門の役割について,今後の検討課題と目指すべき方向は何か,あなたの考えを簡潔に述べよ。
【AN-H07-1-PM2-Q3】情報システム基盤の整備計画の策定について
最近,クライアントサーバシステムやエンドユーザコンピューティングが普及し,WANやLANを利用したネットワークコンピューティングが進展している。その結果,情報システムの稼働環境や開発環境が多様化し,情報システム基盤の整備の必要性が高まっている。例えば,次のような内容が挙げられる。
・ネットワークの整備や高度通信網への対応
・データベースやミドルウェアの整備
・エンドユーザコンピューティングに対応するための新しい環境の整備
情報システム基盤を整備するねらいとしては,情報システム全体にわたる情報処理の効率化促進,適用業務システムの開発・運用コストの削減,エンドユーザの広範な情報活用ニーズへの対応などが挙げられる。更に現行の情報システムの改善にとどまらず情報システムの拡張や発展を支えるための基盤を整備して,情報システムやそれを取り巻く環境の変化に備えるという観点も重要である。
情報システム基盤の整備を計画するに当たって,システムアナリストはそのねらいを明確にし,ねらいどおりの効果が得られるようにすべきである。そのためには,利用する情報技術の適合性や信頼性を分析するとともに,情報システムの稼働環境や運用管理などのスムーズな移行を実現する具体的なプロセスについても,十分な検討が必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが策定に参画した情報システム基盤の整備計画の概要とそのねらいについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システム基盤の整備計画の中で,ねらいどおりの効果を得るためにあなたが特に重要と考え,工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた情報システム基盤の整備計画について,まだ不足している点,問題点は何か。また,今後一層の強化・拡充を図っていくべきことは何か。あなたの考えを簡潔に述べよ。
📗H06:1994
【AN-H06-1-PM2-Q1】情報戦略の企画について
情報は人,物,金とともに,経営の4資源の一つと考えられ,情報システムは各資源を有機的に結合する経営組織体の神経系統機能に位置づけられる。このことから,経営戦略実現の手段として情報システムを構築する事例が増えている。
この場合,経営戦略の一環として情報戦略を企画し,決定された情報戦略に基づいて情報システムを構築することが重要である。
経営戦略,情報戦略は企業ごとに様々であるが,次のような例が挙げられる。
・顧客満足度向上のために,製品の品質情報や顧客情報などのデータベースを整備して,きめ細かな顧客サービスを行う。
・売上やシェアの拡大のために,荷動きや売上データなどをリアルタイムに収集し,フレキシブルな分析ができる環境を整備して,顧客のニーズの変化に迅速に対応する。
・海外への生産拠点の移動に伴うグローバルロジスティックスを支援するために,販売・物流・生産のシステムを統合して,ビジネスのスピードを向上させる。
このように,情報戦略は経営戦略のフレームワークのもとに企画されなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが企画に参画した情報戦略の背景となる経営戦略の概要と,そのような経営戦略が設定された事業環境について,800字以内で述べよ。
■設問イ
あなたが企画に参画した情報戦略について,その概要を簡潔に述べよ。また,情報戦略の企画に当たって,あなたが特に考慮したこと,又は工夫したことは何か,具体的に述べよ。
■設問ウ
あなたは設問イで述べた情報戦略の実現における課題について,情報戦略の企画時にどのようなことを考え,事前に対策を立てたか,簡潔に述べよ。
【AN-H06-1-PM2-Q2】費用対効果の評価について
情報システムの開発計画を立案する場合,開発予定のシステムの費用対効果を十分に分析・評価しておくことは,システムアナリストにとって重要な作業である。
期待効果は,在庫削減や経費削減など直接的に金額換算できる定量的効果と,競争力の強化や顧客サービスの向上など直接的には金額換算しにくい定性的効果に分けて考えられる。特に定性的効果については,情報システムが効果に寄与する度合いや,効果の客観的な評価尺度が明確でない場合があり,システム導入による効果の評価が難しいケースが多い。
システムアナリストは,こうした定性的効果が中心である非定型業務のシステム化などについても,合理的な評価尺度を設定して導入効果を適切に判断し,システム開発計画を立案しなければならない。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが参画した情報システムの開発計画立案について,対象業務とシステム化の背景を800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムの開発計画において,費用対効果をどのように評価したか,具体的に述べよ。効果は定量的効果と定性的効果に分け,特に定性的効果については,どのような工夫をして効果を把握しやすくしたのか述べよ。
■設問ウ
あなたは,稼動後の効果把握のための体制や方法について,システム開発の計画段階でどのように配慮したか,簡潔に述べよ。
【AN-H06-1-PM2-Q3】システム開発における新技術・新製品の導入計画について
情報技術は日進月歩で進んでおり,システムアナリストとしては,常に最新の技術動向を把握しておく必要がある。システム開発計画を立案する際には,新技術・新製品のメリットを取り込んだ,最も効果的,効率的なシステムの実現方法を検討することが重要である。
しかしながら,新技術・新製品の導入には,うたわれているとおりの性能や信頼性を保証する実績が少ないこと,既存のシステムとの接続性,整合性に不安があること,保守サービスが必ずしも保証されてないことなど,様々なリスクを伴う。新技術・新製品の導入に当たっては,こうしたリスクを回避するための対策や工夫が重要となる。
このほか,新技術・新製品の導入効果を高めるためには,単に機能の目新しさだけに目を向けるのではなく,新しい技術に対する教育・訓練の必要性や,ソフトウェア資産・ハードウェア資産の継承性など幅広い検討が必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが開発計画の策定に参画したシステムにおいて,どのような新技術・新製品を導入しようとしたのか。その目的又は必要性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
システム開発計画の立案に当たり,どのような視点から新技術・新製品導入の可否を判断し,選択を行ったのか。あなたが特に重視した点について具体的に述べよ。
■設問ウ
新技術・新製品の導入を円滑に進めて効果を上げるために,導入方法,導入スケジュール,導入体制などについて留意した点を述べよ。