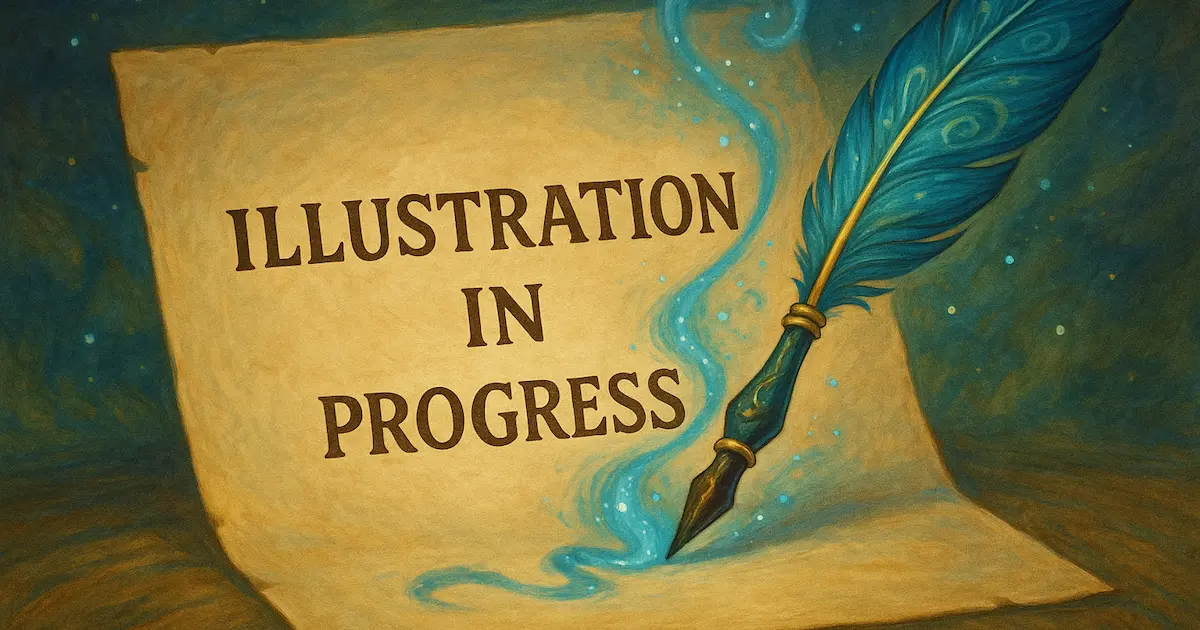📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
日用品を製造・販売するA社は、災害時にも安定供給を継続する社会的責任を負う。基幹システムや通信網の脆弱性を踏まえ、ERPサーバの冗長化やネットワークの多重化を実施。BCPの見直しと教育訓練を通じ、実効性のある体制を構築した、ITストラテジストの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(ST-H24-Q2)
出典:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験 平成24年 午後2 問2
📘問題
■タイトル
事業継続計画の策定について
■内容
東日本大震災をはじめ,国内外で発生した災害・事故では,事業継続計画の重要性を再認識させられた。また,既に事業継続計画を策定していても,災害・事故の直接・間接の影響を受けて,計画の見直しを余儀なくされた企業・組織も多い。
ITストラテジストは,全体システム化計画の策定の中で,事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態などを的確に捉え,事業部門と共同で事業継続計画を策定しなければならない。事業継続計画には,基本方針,想定リスク,事業継続対象の範囲,目標復旧期間,実行体制などの項目が盛り込まれる。事業継続計画の策定においては,例えば,次のような点に着目して検討する必要がある。
・情報システムのハードウェア,ソフトウェア,データ,ネットワーク,ファシリティなどの管理実態を把握した上で,そこに存在する問題点を明確にする。
・明確化された問題点に対応するための事前対策を整理し,初期コストと運用費用を見積もり,対策のための投資の是非について,事業部門と協議する。必要に応じて,情報システムに関する基本的な考え方,構成の変更など,抜本的な対策についても検討する。
・事業部門,情報システム部門だけでなく,人事,総務などの間接部門を含めた全社的な人的リソース・スキルを把握し,災害・事故発生時の事後対策実行体制を確立するためのアクションプランを作成する。
事業継続計画の策定では,計画の実効性を高めることも重要である。そのために,情報システムの変更などに伴う計画内容の定期的な見直し,関連外部機関との相互支援体制の準備,計画に基づく教育・訓練の実施などについても,あらかじめ検討しておく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わった事業継続計画の策定において捉えた,事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態の概要を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業についての社会的責任,事業活動の特性,事業を支える情報システムの利用実態について,どのような点に着目して事業継続計画を検討し,策定したか。策定した事業継続計画の概要とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた事業継続計画の実効性を高めるために,工夫した点は何か。更に改善する余地があると考えている項目を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
生活必需品を製造・販売するA社は、社会的責任として災害時にも安定供給を維持すべき立場にある。基幹業務を支えるERPやSCMシステムの単一構成、通信回線の単一キャリア依存といったリスクを特定し、冗長化・バックアップセンターの分散配置、マルチキャリア対応などを盛り込んだBCPを策定した。加えて、BCPとIT資産台帳との整合性確認や、業務継続訓練の実施により、計画の実効性を確保。今後は業務部門の主体的参画を促し、全社的な危機対応力の強化を図る。
📝論文
🪄タイトル 生活必需品メーカーのBCP策定
本稿は、事業継続計画の策定について述べる。
🔍第1章 事業の社会的責任・特性とシステムの利用実態
1-1 事業の社会的責任と事業活動の特性
(1) A社の事業の社会的責任
A社は、日用品・化粧品・ヘルスケア製品・化学品などを製造・販売する大手メーカーである。生活者の暮らしに密接に関わる製品を多数展開しており、特に家庭用洗剤、紙おむつ、スキンケア商品などは国内外で高いシェアを誇る。A社の事業の社会的責任は、日々の衛生・健康・快適性に関わる製品を安定供給し、生活者の生活の質を向上させることにある。自然災害や社会的混乱時においても、必要不可欠な製品を止めることなく提供し続ける責任を負っている。
(2) A社の事業活動の特性
A社の事業活動は、国内外の製造拠点・物流センター・販売チャネルが密接に連携するサプライチェーンによって成り立っている。日用品は需要変動が小さく、常に安定供給が求められるため、欠品を避ける体制が構築されている。また、ECチャネルを含む多様な販売経路が拡大しており、各チャネルごとに適切な在庫調整や生産計画をリアルタイムで制御する仕組みが必要である。
1-2 事業を支える情報システムの利用実態の概要
A社では、製造・販売・物流・マーケティング情報を一元的に管理するためのERPおよびSCMシステムを導入しており、国内外の拠点からアクセス可能な体制を整備している。これにより、需要予測、生産計画、出荷管理などが効率化されている。
しかしながら、国内外で拡張を繰り返してきた結果、一部の拠点では旧式の機器が残存し、ERPの中核サーバが単一構成で稼働していることも判明している。また、通信インフラについても、主に1社の通信キャリアに依存しているため、災害時のネットワーク断絶リスクが顕在化していた。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 事業継続計画策定上で着目した点と計画概要
2-1 事業継続計画策定上の着目点
(1) ハードウェアの管理実態の把握と着目した問題点
私はまず、ERP・SCMシステムを構成するハードウェアの実態を調査した。衛生・健康に資する製品を安定供給するという観点から、これら基幹システムの可用性は極めて重要と考えた。調査の結果、ERPのDBサーバが一部旧来のまま単一構成で運用されており、障害発生時には即座の切り替えが困難であることが判明した。さらに、ハードウェア投資の計画に一部抜けがあり、更新対象から漏れている機器が存在していた。
(2) ネットワークの管理実態の把握と着目した問題点
次に、各拠点から基幹システムへアクセスするための通信インフラの実態を確認した。全国に拠点を有するA社においては、ネットワーク障害が即座に業務停滞に直結するリスクとなる。調査の結果、国内主要拠点のネットワークが単一キャリア構成であり、当該キャリアのサービスが停止した場合、システムへの接続が不可能となることが判明した。緊急対応としてはFAXや電話での連絡が考えられるが、業務効率は著しく低下する恐れがあった。
2-2 策定した事業継続計画の概要
(1) 基本方針と想定リスク
基本方針は、生活必需品の製造・供給体制を途絶させず、必要な数量を安定的に市場に届け続けることである。この方針を実現するために、ERPの基幹サーバの冗長化を実施し、バックアップデータセンターを国内外2か所に分散配置する計画とした。さらに、通信回線についてもマルチキャリア対応とし、一部拠点では衛星通信バックアップも導入した。想定リスクとしては、大地震や感染症拡大による出社制限、通信障害、サーバ障害を中心に据えた。
(2) 事業継続対象の範囲、目標復旧時間、実行体制
対象範囲は、ERP・SCMシステムを活用した生産・物流・販売・在庫管理に関わる全業務とし、復旧時間目標は12時間以内とした。実行体制は、情報システム部門を中核に、SCM統括、国内・海外製造部門、物流部門、営業統括、CS(お客様相談室)部門を含むクロスファンクショナルチームを結成し、外部ベンダ・通信キャリアとの連携体制も確立した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 事業継続計画の実効性上の工夫点と改善する余地
3-1 事業継続計画の実効性を高めるために工夫した点
(1) 計画内容の定期的な見直し
全社的なシステム構成・設備状況の棚卸しとBCPの整合性を取るため、IT資産台帳との連携を強化し、年度ごとの内部監査でBCP整合性確認を必須項目とした。経営会議のアジェンダにBCPの進捗報告を定期設定し、事業継続対策が現場で形骸化しない仕組みを整えた。
(2) 計画に基づく教育・訓練の実施
災害発生時に備え、現場部門・工場・倉庫スタッフに向けて代替業務フローや手動処理手順に関する訓練を定期的に実施した。特に、SCMシステム停止時の生産指示・出荷指示を紙ベースで行うリカバリープロトコルを整備し、演習で実行確認を行った。
3-2 さらに改善する余地があると考えている項目
(1) 全社的な危機対応意識の醸成
情報システムのBCPは整備されたものの、業務部門・現場サイドでは、「BCPはIT部門の責任」という認識が根強く、主体的な関与が限定的であった。今後は、全社教育の中にBCP啓発モジュールを取り入れ、実業務との接点を意識させる教育体制を構築したい。また、BCP策定そのものに業務部門が参画する体制へと移行し、より実効性の高い事業継続体制へ進化させていく必要がある。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
この論文は、ITストラテジスト試験(ST-H24-問2「事業継続計画の策定について」)の設問ア~ウに明確に対応し、実務経験をベースに高い完成度で論述されている優れた論文です。以下に評価を示します。
🔍 総合評価:合格安全圏(A評価)
✅ 評価ポイント(設問ごと)
【設問ア】
事業の社会的責任・特性・情報システムの実態(第1章)
- 明確性:◎
日用品・化粧品・ヘルスケア製品といった生活必需品を供給するメーカーという事業内容は、BCP策定の必然性を論理的に裏付けている。 - 情報システムとの接続:◎
ERP・SCMの導入状況、システムの老朽化や単一キャリア依存といったリスクを具体的に提示し、次章以降の論拠を形成している。
→ 記述の粒度・構造ともに優れ、戦略的視座と現場実態の両立ができている。
【設問イ】
検討・策定上の着眼点と計画概要(第2章)
- 着眼点の列挙:◎
ハードウェアとネットワークの2観点に整理され、各所の脆弱性が明確に提示されている。 - BCPの構造:◎
基本方針、想定リスク、復旧時間目標、実行体制といった構成要素が網羅され、IPAの問題文の留意点(分散・多重性・業務部門との連携)を反映。 - ストラテジストの視座:◎
ITだけでなく、SCMや営業・CS部門まで巻き込んだ全社対応の姿勢が評価できる。
→ 論理的かつ網羅的で、読みやすく展開されており、採点者に明快な印象を与える構成。
【設問ウ】
実効性確保の工夫と改善余地(第3章)
- 改善努力の記述:◎
教育・訓練の実施や、IT資産台帳とBCPの照合など、継続的改善の取り組みが具体的で説得力がある。 - 改善余地の提示:◎
「IT部門任せの認識」というリアルな社内課題が示され、それに対する今後の展望(全社啓発・業務部門の巻き込み)が戦略的である。
→ 形骸化防止・実効性向上の議論が本質的で、ストラテジストらしい視座で全社改革への方向性が明示されている。
📝 文章構成・論述技術
- 文体は平易かつ専門的で、制限文字数の中で過不足なく要素が盛り込まれている。
- 各章のタイトルも設問対応が明確であり、論理的構造が際立つ。
- 読み手を意識した情報の順序と展開で、理解と説得力に優れる。
💡 改善提案(微修正レベル)
- 「IT資産台帳との連携」や「クロスファンクショナルチーム」といった用語が出てくるが、初出での簡単な補足があるとより親切。
- 改善余地の記述に、「IT以外のBCP(例:物流・人員移動)」にも触れると立体的になる。
✅ 総括
この論文は、「ITストラテジストがBCPを策定する際に必要な視座、構想力、全体最適の観点を体現」した模範的な記述であり、試験合格水準を十分に上回る内容です。実務にも直結する再現性のある記述で、他の受験者にとっても有益な教材になり得ます。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。