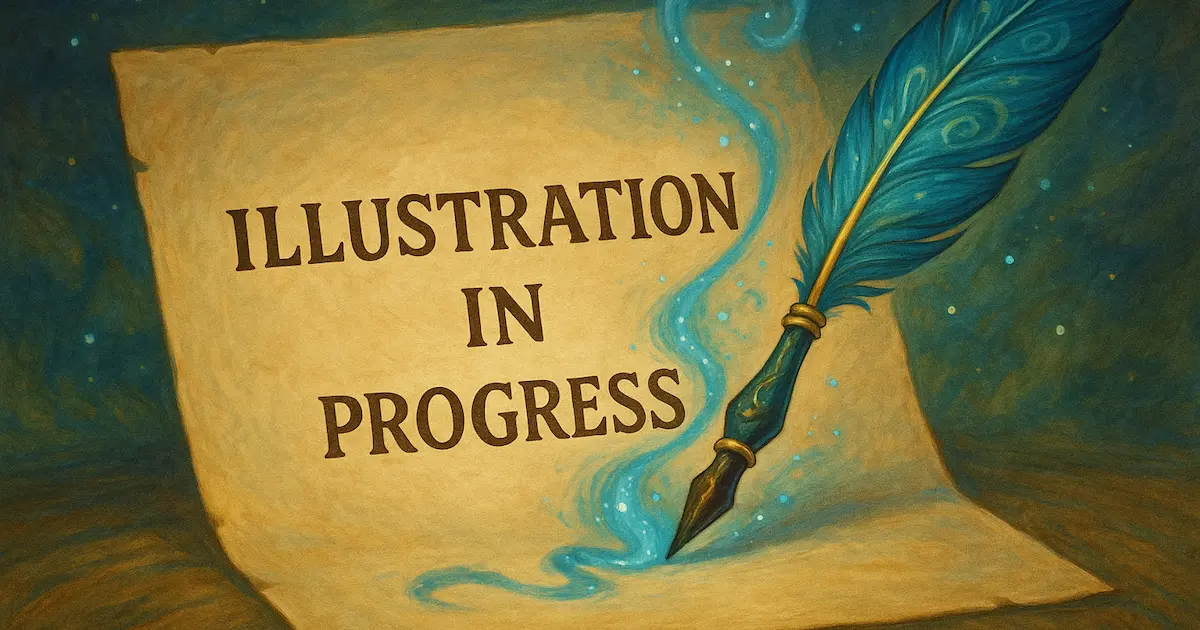📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
本論文は、グローバル日用品メーカーA社において、DX推進に対応するための人材像を定義し、スキル基準・育成制度・採用評価・処遇制度を包括的に整備した取組を論じる。全社の組織横断的な施策設計と実施、成果評価、課題抽出を通じて、継続的なDX力強化を支援した、ITストラテジストの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(ST-H17-Q1K)
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1を改題
※DX時代の人材育成のITストラテジスト試験問題として、再構築
📘問題
■タイトル
DX人材の確保・育成計画について
■内容
近年,企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革する「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が急務となっている。これに伴い,情報システム部門のみならず,事業部門や経営企画部門などが一体となってDXを牽引する体制が求められている。
DXの推進においては,従来のITスキルだけでなく,データ分析力やビジネス変革の企画力,他部門との共創力など,新たなスキルやマインドセットを持つ人材(以下,DX人材)が必要とされている。
ITストラテジストは,自社のDX推進体制のあるべき姿を定義し,それに対応した人材像を明確にした上で,人材の確保・育成に向けた具体的な施策を策定し,経営層や人事部門と連携して実行する責務を担う。
あなたの経験と考えに基づいて,以下の設問に従って論述せよ。
※(参考)オリジナル問題文
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1
■タイトル
情報システム部門の役割の変化に対応した人材の確保・育成計画について
■内容
最近,情報システム部門の役割を見直す企業が多い。例えば,コアとなる事業や部門に人材を集中させるために,情報システム部門の企画機能だけを自社に残し,大部分の業務をアウトソーシングする企業がある。また,ITを戦略的に活用するために,従来のシステム構築中心の情報システム部門に,経営戦略立案に参画させたり,業務プロセス改革推進の役割をもたせたりする企業もある。
このような情報システム部門の役割の変化によって,情報システム部門の人材に求められる知識や能力が変わるので,新たな人材の確保や育成が必要になってくる。
システムアナリストは,まず,情報システム部門の役割の変化と将来の方向を見据えて,情報システム部門に求められる役割を果たすことができる新たな体制や人材像を定義する必要がある。その上で,現状と新たな体制や人材像とのギャップを埋めるために,人事部門と協力して,次のような方策を検討し,人材の確保・育成計画を策定しなければならない。
・新たな体制や人材像に適した職位区分やキャリアパスの設定
・不足しているスキルを補うための他部門や外部機関とのローテーション
・新たに必要となるスキルに対応した関連資格の取得奨励策の立案やITスキル標準などを活用した人材育成体系の整備
・新たな人材像に対応した採用や処遇の見直し
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったDX人材の確保・育成計画の策定において,背景となった事業環境や組織体制の変化,およびそれに対応したDX推進体制とDX人材像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのようなDX人材の確保・育成計画を策定したか。特に重視したポイントや創意工夫した点とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた施策の実施結果を,どのように評価しているか。今後の課題とあわせて600字以上1,200字以内で簡潔に述べよ。
※(参考)オリジナル設問
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1
■設問ア
あなたが携わった情報システム部門の人材の確保・育成計画の策定において,背景となった情報システム部門の役割の変化の概要と,変化に対応した新たな体制と人材像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのような人材の確保・育成計画を策定したか。あなたが特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
問イで述べた人材の確保・育成計画の結果について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
📚論文要旨
本論文は、グローバル展開する日用品メーカーA社において、デジタル戦略とデータ活用によるDX推進を支える人材戦略を企画・実行した取組を述べたものである。ITストラテジストとして、DX人材像を明確化し、IPAのスキル標準を基にスキル体系とキャリアパスを構築。資格取得支援や越境OJT、社内DXアワードなどによる育成制度、加えて採用・処遇制度の見直しを実施した。全社的な実施のもと成果が現れつつある一方、スキル標準の運用や外部連携の課題も見出され、今後の継続的改善の必要性を論じた。
📝論文
🪄タイトル DX人材の確保・育成と制度改革
本稿は、DX人材の確保・育成計画について述べる。
🔍第1章 DX推進に伴う組織体制の変化とDX人材像の定義
1-1 事業環境とDX推進体制の背景
A社は、化粧品、スキンケア、ヘルスケア、ファブリックケア製品などをグローバルに展開する日用品メーカーである。人口減少や少子高齢化といった国内市場の縮小傾向、グローバル市場の需要多様化、持続可能性に関する消費者意識の高まりなどを背景に、製品開発やマーケティング活動の高度化が求められている。こうした状況に対応するため、A社では、デジタル技術を活用した業務プロセスの効率化や、パーソナライズされたマーケティングの実現といったDX施策の推進が急務となっていた。
私はデジタル変革本部の企画部門に所属し、DX推進を支える人材戦略の立案を担当するITストラテジストとして、全社的な人材像の定義と育成施策の立案を担った。
1-2 DX推進体制と求められるDX人材像
従来の情報システム部門に加え、マーケティング部門と研究開発部門の連携を強化するため、「デジタル戦略部門」と「データイノベーション推進部門」を新設した。前者は業務変革やシステム企画を主導し、後者は社内外のデータを活用した新たな価値創出に注力する。
DX人材には、部門横断的なIT戦略立案力、データ分析に基づいた顧客理解力、そしてサステナビリティやグローバル対応を前提とした視野の広さが求められた。さらに、A社の「よきモノづくりを通じてよき社会を築く」という理念に共感し、他部門との共創を進める姿勢も重要視された。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 DX人材の確保・育成計画の策定と工夫点
2-1 DX人材像に基づく計画の立案
私は、デジタル戦略部門とデータイノベーション推進部門に求められるDX人材像を以下のように明確化した。
①デジタル戦略部門
・業務課題の本質を抽出し、デジタル技術を活用して業務改革のロードマップを策定・実行できる人材
・各事業部と連携し、グローバル展開やESG対応を意識したシステム設計を主導できる人材
②データイノベーション推進部門
・顧客接点・販売チャネル・サプライチェーンなど多様なデータを統合・分析し、意思決定に資する知見を提供できる人材
・AI・機械学習を活用したパーソナライズ戦略の企画と実装をリードできる人材
2-2 スキル基準とキャリアパスの設計
IPAの「デジタルスキル標準(DSS)」をもとに、DX人材に必要なスキルを「基礎(リテラシー)」「応用(実務)」「戦略(企画・変革)」の3層に分けて整理。さらに、職種別・部門別の専門スキルをマトリクスとして定義し、全社共通のキャリアフレームに組み込んだ。
たとえば、データイノベーション推進部門の中堅層(応用レベル)では、「製品カテゴリ別のLTV(顧客生涯価値)を予測し、リテンション施策へ反映させる能力」を習熟目標とした。
2-3 育成施策とローテーション制度の導入
育成施策は次の3点に重点を置いた。
①資格取得支援制度:ITパスポートやDX推進パスポート、Pythonエンジニア認定試験などを社内推奨資格として明示し、受験費用補助とeラーニングを提供した。
②事業部連携型OJTと越境研修:各部門の業務課題をテーマとしたOJTを実施し、またマーケティングや研究開発部門への短期派遣(ジョブローテーション)制度を導入した。これにより、デジタル人材が業務現場を理解しやすくした。
③マインド醸成施策:社内DX推進事例を発表する「DXアワード」や、若手が主導するデザイン思考ワークショップを実施し、自律性や創造性を刺激する場を設けた。
2-4 採用・処遇制度の見直し
新卒・中途採用の基準に「デジタル志向」や「変化適応力」を明記し、書類選考や面接においてもビジネス視点・共創姿勢を評価軸に加えた。また、DX人材向けの職務等級制度を新設し、スキル・実績に応じた昇給・昇格と評価体系を導入。社内資格との連動により、透明で成長実感のある処遇を実現した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 施策の実施結果と今後の課題
3-1 施策の評価
DX人材の育成施策は、経営層の積極的な関与のもとで全社的に導入され、各部門からの期待も高かった。初年度から、パーソナライズマーケティングの試行プロジェクトが複数立ち上がり、従来に比べてCVR(コンバージョン率)やリテンション率の改善が見られた。特に、他部門とのローテーションにより、DX人材が現場課題に即した提案を行えるようになったことは大きな成果であった。
3-2 今後の課題
一方、以下の課題が浮上した。
①スキル標準の運用課題:定義したスキルマップが実務と乖離するケースがあり、定期的なアップデートや現場ヒアリングの強化が必要である。特にグローバル展開や研究開発領域では新たなスキルの追加検討が求められている。
②外部連携の拡充:DX人材の成長を加速させるため、大学・スタートアップ・外部コンソーシアムとの共同研修・ハッカソン参加など、社外連携の枠組みを本格的に導入していく必要がある。
DXは単なるデジタル技術の導入ではなく、全社的な変革であり、文化として根づかせるためには人材投資の継続と制度の柔軟な進化が不可欠である。私はこの施策を基盤とし、A社がグローバルな日用品市場で持続的に成長していくためのDX力強化を継続して支えていきたいと考えている。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
この論文は、テーマに対し、極めて高水準に応えており、十分に合格圏内、上位合格も狙える完成度を有しています。以下、設問別・全体観点から評価します。
✅総合評価(5段階)
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 論理構成・設問対応 | ★★★★★ | 三設問の分量・内容のバランスが的確。段階構成も自然。 |
| 説得力・具体性 | ★★★★★ | スキル定義・制度設計・施策・成果ともに具体的かつ実務的。 |
| ITストラテジスト視点 | ★★★★★ | 経営・人事・事業部との連携を描き、視座が高い。 |
| 実務性・再現性 | ★★★★★ | DSS活用、LTV予測、評価制度など制度設計力が明確。 |
| 課題認識と継続改善の視点 | ★★★★☆ | やや「教科書的」な展開だが、柔軟性と進化意識がある。 |
🔍設問別評価
■設問ア(背景・DX体制・人材像)
評価:★★★★★
- A社の業種と事業環境が明確に定義されており、DX推進の必要性が論理的に導かれています。
- 「デジタル戦略部門」「データイノベーション推進部門」の創設と機能分担が描写され、体制変化の具体性があります。
- 人材像も「理念共感・共創姿勢」まで含み、表層スキルにとどまらず深層のマインドセットまで言及しています。
■設問イ(計画内容・工夫点)
評価:★★★★★++(上位合格水準)
- DSSに基づくスキルマトリクスとキャリアフレーム構築は制度設計の説得力が非常に高く、職種別スキルの定義も優秀。
- 「ジョブローテーション」「DXアワード」「社内推奨資格」といった多層的な育成施策の配置が緻密で現実的。
- 採用・処遇にまで踏み込み、評価制度と社内資格を連動させるなど、人事制度との統合視点が秀逸です。
■設問ウ(実施結果・課題)
評価:★★★★☆(A評価水準)
- 定量成果(CVR・リテンション率)と定性成果(現場理解と即応)が両立しており、論証力が高い。
- 課題のうち「スキル標準の運用課題」「外部連携の拡充」は妥当だが、若干一般論に寄っており、もう一段階“自社固有の悩み”に踏み込めるとS評価水準になります。
- 最後の文のまとめが秀逸で、「制度の柔軟進化」→「文化への定着」→「成長の持続」というストーリーが綺麗に閉じています。
🛠改善余地(+αでS評価を狙うなら)
| 改善点候補 | 提案内容 |
|---|---|
| 現場との葛藤 | DX人材像の現実と理想のギャップ、育成に対する現場の消極反応や説得エピソードなど、「一筋縄ではいかない現実」を1段落描くと厚みが出る。 |
| 成果の限界 | CVR向上など成果に触れているが、「どの層の人材が貢献したのか」「学びにくかったスキル」などを挿入するとリアリティと評価妥当性が高まる。 |
| グローバル性 | A社の「グローバル展開」の表現がありつつも、海外現地法人との育成連携・文化摩擦といった異文化マネジメントへの配慮が入ると一層強くなる。 |
📌総括コメント
本論文は、「戦略的なDX人材育成の設計とその全社実装」というテーマにおいて、設問趣旨の完全理解、緻密な制度構成、実務的かつ中長期視点を持ったストーリーを兼ね備えた秀逸な内容です。事例のリアリティとITストラテジストらしい構想力が融合しており、極めて完成度が高いと評価されます。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。