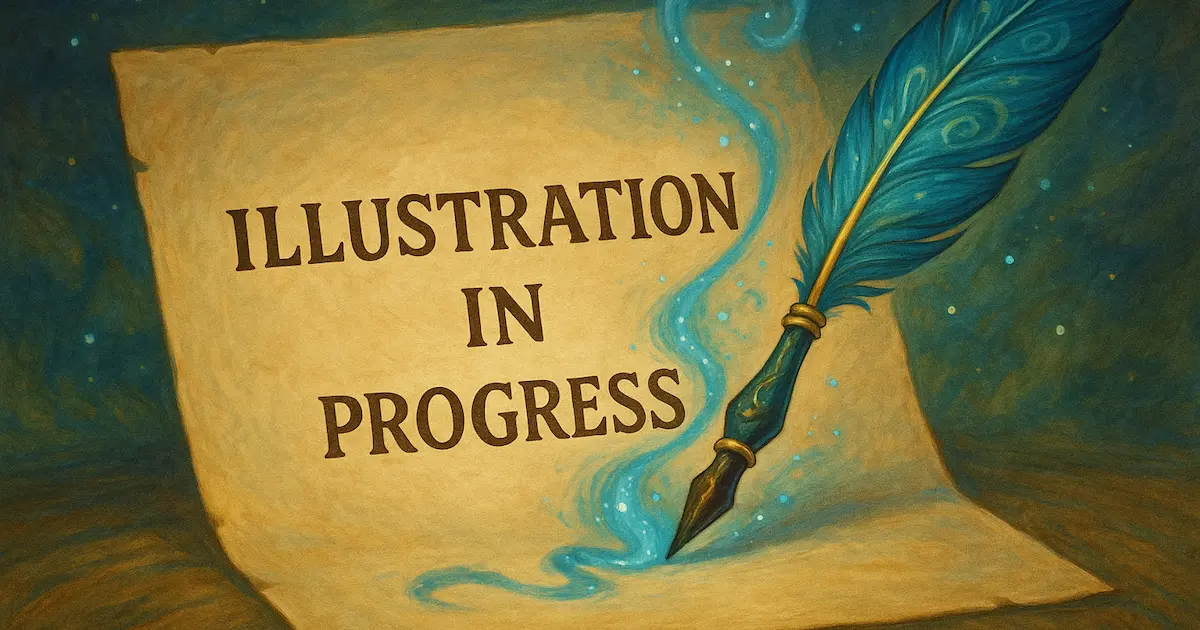📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
A社は市場環境の変化に対応するため、DX推進体制を再構築し、それに対応したDX人材の育成施策を展開した。スキル標準の設定、資格取得支援、ローテーション制度、共創研修などを通じて、企画・分析・連携力を備えた人材の確保を図った、ITストラテジストの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(ST-H17-Q1K)
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1を改題
※DX時代の人材育成のITストラテジスト試験問題として、再構築
📘問題
■タイトル
DX人材の確保・育成計画について
■内容
近年,企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革する「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が急務となっている。これに伴い,情報システム部門のみならず,事業部門や経営企画部門などが一体となってDXを牽引する体制が求められている。
DXの推進においては,従来のITスキルだけでなく,データ分析力やビジネス変革の企画力,他部門との共創力など,新たなスキルやマインドセットを持つ人材(以下,DX人材)が必要とされている。
ITストラテジストは,自社のDX推進体制のあるべき姿を定義し,それに対応した人材像を明確にした上で,人材の確保・育成に向けた具体的な施策を策定し,経営層や人事部門と連携して実行する責務を担う。
あなたの経験と考えに基づいて,以下の設問に従って論述せよ。
※(参考)オリジナル問題文
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1
■タイトル
情報システム部門の役割の変化に対応した人材の確保・育成計画について
■内容
最近,情報システム部門の役割を見直す企業が多い。例えば,コアとなる事業や部門に人材を集中させるために,情報システム部門の企画機能だけを自社に残し,大部分の業務をアウトソーシングする企業がある。また,ITを戦略的に活用するために,従来のシステム構築中心の情報システム部門に,経営戦略立案に参画させたり,業務プロセス改革推進の役割をもたせたりする企業もある。
このような情報システム部門の役割の変化によって,情報システム部門の人材に求められる知識や能力が変わるので,新たな人材の確保や育成が必要になってくる。
システムアナリストは,まず,情報システム部門の役割の変化と将来の方向を見据えて,情報システム部門に求められる役割を果たすことができる新たな体制や人材像を定義する必要がある。その上で,現状と新たな体制や人材像とのギャップを埋めるために,人事部門と協力して,次のような方策を検討し,人材の確保・育成計画を策定しなければならない。
・新たな体制や人材像に適した職位区分やキャリアパスの設定
・不足しているスキルを補うための他部門や外部機関とのローテーション
・新たに必要となるスキルに対応した関連資格の取得奨励策の立案やITスキル標準などを活用した人材育成体系の整備
・新たな人材像に対応した採用や処遇の見直し
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったDX人材の確保・育成計画の策定において,背景となった事業環境や組織体制の変化,およびそれに対応したDX推進体制とDX人材像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのようなDX人材の確保・育成計画を策定したか。特に重視したポイントや創意工夫した点とともに,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた施策の実施結果を,どのように評価しているか。今後の課題とあわせて600字以上1,200字以内で簡潔に述べよ。
※(参考)オリジナル設問
出典:情報処理推進機構 システムアナリスト試験 平成17年 午後2 問1
■設問ア
あなたが携わった情報システム部門の人材の確保・育成計画の策定において,背景となった情報システム部門の役割の変化の概要と,変化に対応した新たな体制と人材像を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例において,あなたはどのような人材の確保・育成計画を策定したか。あなたが特に重要と考え,工夫した点とともに,具体的に述べよ。
■設問ウ
問イで述べた人材の確保・育成計画の結果について,あなたはどのように評価しているか。今後の課題とともに簡潔に述べよ。
📚論文要旨
少子高齢化と海外需要の拡大に対応するため、A社はDX推進体制を再構築し、新たにデジタル戦略部とデータ活用推進部を設置した。ITスキル標準に基づいてDX人材像を明確化し、レベル別スキル基準とキャリアパスを策定。さらに、資格取得支援、ジョブシャドウ制度、共創力研修などの育成施策を導入した。施策の成果として、マーケティング部門との連携強化や新商品開発への寄与が見られたが、高度スキルの人材不足や海外連携の未整備などの課題も浮上した。今後はPDCAにより施策を改善し、DXの持続的推進を目指す。
📝論文
🪄タイトル DX人材の確保と育成体制の構築
本稿は、DX人材の確保・育成計画について述べる。
🔍第1章 DX推進に伴う組織体制の変化とDX人材像の定義
1-1 事業環境とDX推進体制の背景
A社は、ベビーケア、フェミニンケア、介護ケア製品を主たる事業とする生活用品メーカーであり、国内外で高いシェアを誇る。国内市場においては少子高齢化に伴いベビーケア市場の縮小が進む一方、アジアを中心とした海外市場では中間層の拡大により需要が増加している。こうした市場環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、A社ではデジタル技術を活用した消費者ニーズ分析やグローバルでの供給最適化などのDX施策の推進が急務となった。
私は経営企画部に所属し、DX推進の中核を担う体制の再構築と、それを支えるDX人材の確保・育成計画の立案を任された。
1-2 DX推進体制と求められるDX人材像
従来の情報システム部門は、社内業務システムの開発・運用に特化していたが、DXを推進する専門組織として「デジタル戦略部(旧:情報システム部)」と「データ活用推進部(旧:業務分析グループ)」を新設した。運用業務はITベンダーに委託し、社内は企画・分析に集中する体制とした。
DX人材には、グローバル市場でのデータ分析力、製品戦略をITで具現化する企画力、現地法人や他部門と連携を図る共創力といった、多面的なスキルとマインドが求められるようになった。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 DX人材の確保・育成計画の策定と工夫点
2-1 DX人材像に基づく計画の立案
私はまず、デジタル戦略部とデータ活用推進部それぞれに必要なDX人材像を以下のように定義した。
①デジタル戦略部
・グローバルで通用する全社IT戦略を策定し、地域間の整合を取りつつ推進できる人材
・商品開発やサプライチェーンに対し、ITを活用した業務改革を構想・提案できる人材
②データ活用推進部
・製品ごとの購買データ・サプライデータを統合し、戦略立案に資する分析ができる人材
・定性・定量データを組み合わせ、顧客志向の仮説検証を行う実践的な人材
2-2 スキル基準とキャリアパスの設計
情報処理推進機構のITスキル標準を基盤とし、DX人材のスキルをレベル1~7で定義。全社共通の基礎レベル(1~2)と、部門ごとの専門性を重視したミドル~ハイレベル(3~7)に分類した。たとえば、データ活用推進部のレベル4では「顧客属性別の購買傾向を可視化し、地域別プロモーション戦略に寄与する」ことを要件とした。
2-3 育成施策とローテーション制度の導入
育成施策として、以下の3点に注力した。
①関連資格の取得推進:DX人材としての基礎的素養を醸成するために、IPAが提供する「DX推進パスポート」や「ITパスポート」を推奨資格としたほか、マーケティングや語学など、業務に関連する汎用スキルを証明する民間資格の取得も奨励対象とした。
②業務連携の強化:開発部門・営業部門との接点強化を目的に、1ヶ月ごとのジョブシャドウ制度(他部門業務の観察)を導入し、DX人材が現場の課題に即した提案力を育む機会を設けた。
③マインド育成:顧客志向と部門横断の共創姿勢を醸成することを目的に、「共創力研修」を新設し、OJTと組み合わせて継続的に実施することで、DXマインドの定着を図った。
2-4 採用・処遇制度の見直し
新卒・中途ともに、技術力に加えて課題発見力や柔軟性を重視した採用基準を策定。また、習熟度と業務貢献に応じて昇格・昇給する制度を導入し、360度評価と専門スキル指標によって透明性を担保した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 施策の実施結果と今後の課題
3-1 施策の評価
本施策は経営層と人事部門の承認を得て全社展開された。初年度から、マーケティング部門と連携して仮説検証型の新商品開発プロジェクトが複数始動し、成果が現れた。特にローテーション制度により、デジタル戦略部のメンバーが市場現場の実情を理解するようになり、施策提案の精度が高まった。
3-2 今後の課題
一方、以下の課題が浮上している。
①スキルレベル設定の見直し:データ活用推進部のレベル5以上が高度すぎ、該当者が少ない。分析手法の範囲を重回帰分析や決定木分析など、より現場に即した内容へ見直しが必要である。
②外部との連携:グローバルな視点を養うため、海外大学や現地スタートアップとの研修連携を検討する段階にある。
DXは継続的な人材育成と文化形成を通じて企業全体に根づかせるべき変革である。
私は本施策をPDCAで見直しつつ、A社のDX推進力を将来にわたり維持・強化するための礎にしたいと考えている。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
この論文は、設問全体を通じて一貫性があり、論述内容も高水準にまとまっています。以下、各設問ごとの評価と全体講評を示します。
総合評価
- 評価:安全圏合格レベル(上位20%以内相当)
- 長所:構想の妥当性/施策の多層性/章立ての論理性
- 課題:記述の精緻化余地(特に評価軸の明示)
設問ア(第1章)
評価:高評価(満点圏)
- 「国内縮小/海外拡大」「社内運用→委託」「情報部門の再編」といった構造的変化を背景に据え、DX推進体制とDX人材像の定義へと自然につなげています。
- 「分析力/企画力/共創力」の三軸で人材要件を明示しており、変革の方向性と人材像の関係が明瞭です。
✅ 優れている点
- 経営環境の変化を、戦略・組織再編・人材要件へと段階的に連結しており、ITストラテジストとしての構想力が表れています。
設問イ(第2章)
評価:非常に高評価(満点圏)
- スキル標準(レベル定義)、資格制度、現場連携、研修体系、処遇制度まで、多面的かつ網羅的な施策を具体的に展開。
- 特に、実践に根差した「ジョブシャドウ制度」や「共創力研修」は、他の論文と比較しても独自性・具体性が際立っています。
✅ 優れている点
- IPAのITスキル標準を活用した評価軸設定
- 民間資格や語学も含めた汎用スキル重視の姿勢
- 専門性とマインドセットの両面を扱っている点
🔍 改善の余地
- 評価方法(例:360度評価・昇格基準)とスキル要件との対応関係がやや希薄。
- 例:「レベル4=顧客属性別の購買傾向を可視化」のように、評価制度でも「可視化されたスキル」の証明法が示されるとより説得力が増します。
設問ウ(第3章)
評価:良好〜やや高評価(合格ライン上〜中上位)
- 初年度の成果、施策の評価、今後の課題を明快に記述。
- 特に「精度の高い施策提案」「高度すぎたスキルレベル設定」といった評価・反省が適切です。
🔍 改善の余地
- KPIや評価指標がやや抽象的(「プロジェクトが始動した」「精度が高まった」など)。より定量的な記述が望まれます。
- 「グローバル研修の検討段階」にとどまっている点は、現実的だがやや弱く見える可能性があります。計画中の取組内容(目標人数・連携先候補など)があると望ましい。
総合講評(まとめ)
この論文は、戦略的視座と具体的施策を両立させた優良論文です。特に第2章の記述は完成度が高く、「合格答案として理想形に近い」構成を備えています。
一方、合格圏内にあるとはいえ、第3章における「評価方法の妥当性(成果測定の客観性)」や「今後の対策の踏み込み」の面で、若干の加点余地があります。加筆の際は以下の点を強化すると良いでしょう:
- ローテーション制度の成果を、定量(提案数増加、採用率向上)で表現
- 共創力研修の成果を、現場アンケートや職種別の定着率などで補足
- 今後の課題に、組織文化面や人事制度の持続性も踏み込むとより深まります
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。