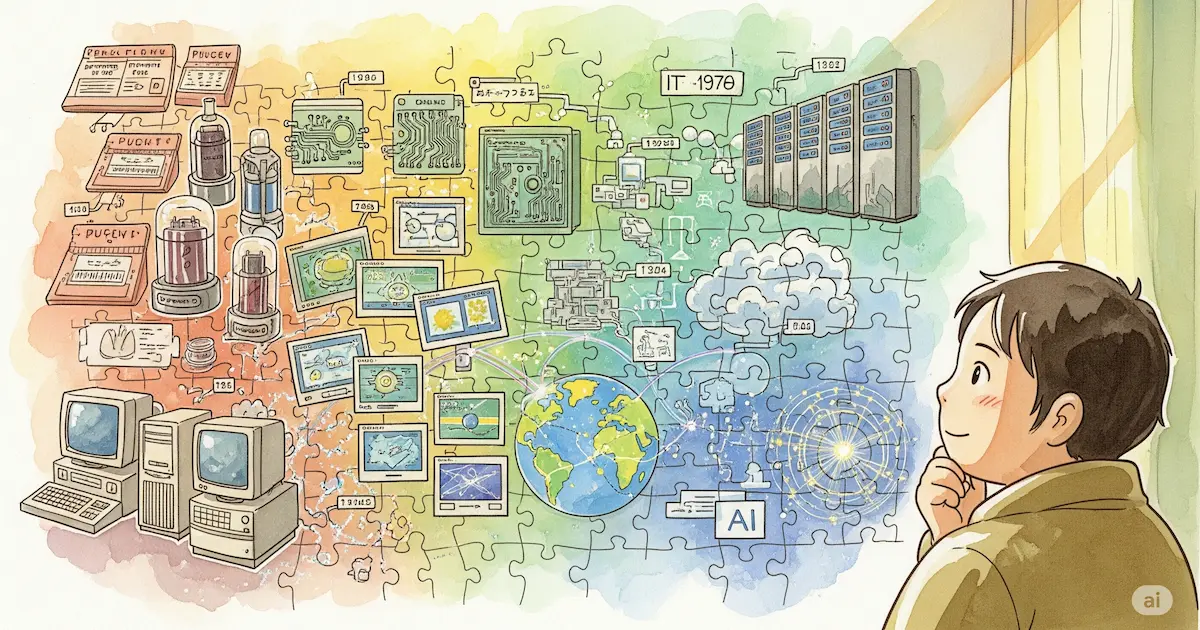🍀概要
この資料は、過去のITサービスマネージャ(旧 テクニカルエンジニア(システム管理)含む)試験問題(論述形式)をテキスト化した「ITサービスマネージャの歴史書」です。Web上では見つけにくい、貴重で有益な示唆を含む、過去の問題文を、調査してテキスト化しました。 過去の課題から、現代そして未来に求められる理想像を紐解き、あなたの知識と視点を深めます。分析や考察に役立つよう、すぐにコピペして利用できる形式となっています。
🧾問題・設問
出典:情報処理推進機構 ITサービスマネージャ試験 平成21年~令和7年(2009~2025年) 午後2(🔗取り扱いガイドライン)
出典:情報処理推進機構 テクニカルエンジニア(システム管理)試験 平成7年~令和20年(1995~2008年) 午後2
📘ダウンロード
こちらから、掲載した問題文を全て含む、MS Word、PDFファイルをダウンロードできます。
※情報処理推進機構のガイドラインをご確認の上、ご利用ください。(🔗取り扱いガイドライン)
🪄アーカイブ全文
📗R07:2025
【SM-R07-1-PM2-Q1】顧客満足を向上させるための活動について
ITサービスを提供する組織にとって,顧客満足は重要な関心事である。
顧客満足を向上させるには,顧客の期待と評価を把握して対応することが求められる。ITサービスマネージャは,事業関係管理における顧客とのコミュニケーション活動やサービスレベル管理におけるITサービス報告などの活動を通じて,顧客の期待と評価を把握する。顧客とのコミュニケーション活動では,顧客の事業環境の変化に対する理解を深め,
ITサービスの価値向上などに対する顧客の期待を把握することが必要となる。また,ITサービス報告では,状況に応じて変化するITサービスに対する顧客の評価を把握する。例えば,ITサービスに十分な価値があるとみなされなくなった場合,サービスレベル目標を達成したという報告を行っても顧客は不満足と感じることがある。
次に,把握した顧客の期待と評価の内容を分析し,顧客満足向上のための改善計画を策定する。例えば,
・顧客の事業環境の変化を背景としたITサービスの価値向上などに対する期待については,組織のサービスカタログを調査し,新サービスを迅速に提案できないかなど組織内の考えをまとめ,顧客に提案できる改善計画として取りまとめる。
・顧客に提供しているITサービスに対する評価については,満足度を数値で評価してもらい,評価の理由も確認する。顧客の期待と現状とのギャップを分析し,顧客満足向上のための改善計画を取りまとめる。また,改善計画を顧客と討議し,合意することも重要である。改善計画にはKPIを設定し,計画の達成状況を把握することも必要となる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,顧客の期待と評価を把握するためにどのような活動を行っているかについて,400字以上800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた活動から把握した顧客の期待と評価の内容をどのように分析したか。また,顧客満足向上のためにどのような改善計画を策定したか,設定したKPIを含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた改善計画の実施状況と評価,及び顧客の期待と評価を把握するための活動の改善点について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R07-1-PM2-Q2】クラウドサービスを活用したITサービスのサービスマネジメント活動について
組織が提供するITサービスの一部に,クラウドサービスプロバイダ(以下,CSPという)が提供するクラウドサービスを活用したITサービスが増加している。クラウドサービスを活用したITサービスのサービスマネジメント活動は,ITサービスマネージャの重要な業務である。
クラウドサービスの活用に当たっては,組織が提供するITサービスの目標に照らして,CSPが提供するサービスカタログのサービス内容や,提案依頼に対してCSPが提示するサービス内容を,関係部署とも連携を図り,十分に検証することが重要である。
クラウドサービスでは,使用されるリソースのモニタリングやリソースのコントロールをCSPが実施するので,オンプレミスで提供するサービスとは異なり,例えば,次のようなサービスマネジメントにおける問題に直面する。
・クラウドサービスの障害対応はCSPが行うので,CSPの作業の進捗状況が把握できず,利用者へのサービス回復時刻の見通しなどの連絡がタイムリーに行えない。
・顧客からのクラウドサービスに関連する改善要求及び苦情対応はCSPと調整することになるので,顧客へのフィードバック及び対応に時間を要する。
ITサービスマネージャは,このような問題の解決に向けて,組織の管理プロセスを見直す,CSPと十分対応を協議するなどして,対応策を決定する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,活用するクラウドサービスの概要を組織が提供するITサービスの目標に照らして,400字以上800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたクラウドサービスの活用において直面したサービスマネジメントにおける問題,解決に向けて実施した対応策,及び対応策を決定する上で工夫した点について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで実施した対応策の評価,及び改善に向けて今後取り組むべきと考えていることについて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R06:2024
【SM-R06-1-PM2-Q1】環境の変化に対応するための変更管理プロセスの改善について
ITサービスマネージャは,変更管理プロセスを定め,変更によるサービスヘの影響を評価する。近年,サービス改善のための変更要求の増加,DevOpsの採用などによって,展開を行う回数が増加するなどの環境の変化が起きている。
従来の変更管理プロセスは,ウォーターフォール型開発を前提として内部統制の強化に重点を置いたものも多く,高頻度,短期間で変更要求を承認できる規程となっていない場合がある。ITサービスマネージャは,このような環境の変化に合わせて必要な統制を確保しつつ,変更要求の承認を遅延させないために,変更管理プロセスを改善していく必要がある。例えば,次のような改善策を行う。
・変更要求の対象範囲を見直し,変更のカテゴリ“標準変更"の適用を拡大する。
・CAB(変更諮問委員会)の運営方法を見直す。
・DevOpsによる展開に合わせて,変更のカテゴリを新たに定義し,適用範囲や変更のプロセスを定める。
また,変更管理プロセスの改善策実施後に,変更要求の承認が適切に実施されているか,サービスに影響を与えていないかなど,採用した改善策の効果を評価し,変更管理プロセスの更なる改善を進めていくことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,既存の変更管理プロセスに影響を与えた環境の変化の内容について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた環境の変化によって,変更管理プロセスに生じた問題点,及び問題点を解決するために実施した変更管理プロセスの改善策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた変更管理プロセスの改善策の評価と課題について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R06-1-PM2-Q2】サービス運用におけるヒューマンエラーに起因する障害の管理について
ITサービスの障害は企業活動に大きな影響を及ぼす。サービス運用の現場で発生する障害は,運用担当者のヒューマンエラーに起因するものが多い。ヒューマンエラーに起因する障害を防ぐことは,ITサービスマネージャの重要な業務である。
ヒューマンエラーの原因には,不注意,知識不足,思い込み,慣れ,過労などがあるが,ヒューマンエラーの背景として,教育などのスキル管理,作業ルールなどのプロセス,コミュニケーションなどの組織風土に課題があることも多い。
ITサービスマネージャは,ヒューマンエラーに起因する障害が発生した場合に,
次のような技法を用いて,原因を分析して対策を行うことが大切である。
・パレート分析を用いて,重要な原因を見つけ出す。
・なぜなぜ分析を用いて,対策をとるべき根本原因を見つけ出す。
対策に当たっては,直接原因だけでなく,プロセスや職場環境など,直接原因を引き起こしている根本原因の分析も行い,障害の再発を防止する観点から検討を行うことが重要である。
また,発生したヒューマンエラーを個々に分析して対策を行うだけでなく,これまでに組織で発生したヒューマンエラーの傾向を分析して組織としての課題を抽出し,対策を行うことも大切である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,運用担当者のヒューマンエラーに起因した障害,及びヒューマンエラーの内容について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたヒューマンエラーに起因した障害の再発を防止するために実施した対策は何か。また,対策を検討するに当たって,根本原因をどのように分析したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
これまでに組織で発生したヒューマンエラーの傾向をどのように分析したか。また,組織としての課題は何であったか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R05:2023
【SM-R05-1-PM2-Q1】サービスレベル管理におけるサービスレベルの合意について
サービスレベルの維持を目的として行うサービスレベル管理において,顧客ニーズを満たすために必要なサービスレベルを定義,文書化及び合意することは,ITサービスマネージャの重要な業務である。SLAは,サービスの条件及びサービスレベル目標を記述する文書であり,顧客の視点でサービスレベル目標を定義することが望まれることから,サービス提供組織(以下,組織という)と顧客とのサービスレベルの合意に向けた取組が重要となる。
顧客のサービス要求事項は,事業環境の変化,社会環境の変化及び情報技術の進展などによって多様化・複雑化・高度化している。例えば,QRコード決済サービスへの高い耐障害性,個人情報を扱うサービスへの高いセキュリティ性などがある。
また,組織においては,AI,自動化技術などの新技術活用による品質向上・効率向上が期待される一方,設備面・体制面・費用面などの制約が考えられる。組織と顧客とのサービスレベルの合意に向けた取組に当たっては,サービス提供に関わる内部供給者及び外部供給者(以下,サプライヤという)のサービスレベル目標又は契約との整合性が必要となり,サプライヤとの協議・調整も欠かせない。
サービス開始後,サービスレベル目標を満たせない事態の発生又は兆候を認識した場合には,必要に応じてサービスの条件及びサービスレベル目標を再定義する。また,SLAの見直しに関わるサービスレベル管理の仕組みを確立することも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,サービスレベルの合意に向けて,顧客との交渉で討議の対象となったサービスレベル項目,及び討議を要することとなった背景について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたサービスレベル項目について,サービスレベルの合意に向けた取組,及びSLAの見直しに関わるサービスレベル管理の仕組みについて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたサービスレベルの合意に向けた取組を,どのように評価しているか。また,サービスレベル管理における今後の課題は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R05-1-PM2-Q2】リリース及び展開の計画について
ITサービスマネージャは,変更管理プロセスと連携しながら,リリース及び展開管理プロセスの活動を行う。
リリースを安全に展開するため,リリース及び展開の計画(以下,展開計画という)を策定する。展開計画の策定に先立って,リスクを特定し,次のような検討を行う。
・リリースがサービスに与えるリスクを分析,評価し,リスクを最小限にとどめるための回避策又は軽減策を検討する。
・リリースがサービスに影響を与えないことを,展開前に本番環境に近い環境で試験し,試験では確認できないリスクを明確にした上で,その回避策又は軽減策を検討する。
・インシデント発生リスクを軽減させるため,展開後の稼働状態の監視方法を検討する。
特定したリスクと検討した結果に基づき,リスクを回避又は軽減させるための方策をまとめ,リリースを安全に展開するための展開計画を策定する。例えば,
・展開時に発生する想定外の事態に備えて,影響の小さい機能や対象範囲から段階的に展開を行う。
・DevOpsの採用などによって,頻繁に展開を行う場合には,展開作業の自動化を行って作業時間の短縮や展開作業におけるミスの混入を防止する。
また,展開実施後は,リスクを回避又は軽減するために採用した方策及び展開計画の有効性をレビューし,今後の展開に備えることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,リリースの内容及び特定したリスクについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたリスクを回避又は軽減するために採用した方策,及び展開計画について,根拠と期待した効果を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
展開実施後のレビュー結果を踏まえ,採用した方策及び展開計画の評価と課題について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R04:2022
【SM-R04-1-PM2-Q1】災害に備えたITサービス継続計画について
災害によるITサービスの中断・停止は事業に大きな影響を与える。ITサービスマネージャは,災害発生による事業への影響を極小化するためのITサービス継続計画を,事前に策定しておく必要がある。
ITサービス継続計画には,ITサービス継続要件を実現する対策実施,教育訓練,維持改善,緊急時対応が含まれる。
ITサービス継続計画の策定に向けた具体的な手順は,次のとおりである。
① 災害によって発生する,ITサービスの継続に影響を与える事態を特定する。例えば,事態には,ハードウェア障害,通信障害,停電などがある。
② 特定した事態による事業への影響を分析して評価する。例えば,影響には,業務の長時間停止,保有データ消失による事業継続不可などがある。
③ 事業への影響を極小化するための具体的な対応策を立案する。例えば,対応策には,災害発生時のサービス代替手段の準備,重要データの遠隔地保管,復旧手順の策定,災害発生に備えた教育訓練の定期実施などがある。対応策は,事業継続計画で定めた目標(目標復旧時間,目標復旧時点,目標復旧レベル)に従って決定し,ITサービス継続計画に反映する。
また,社会環境の変化,技術動向などによって事業への影響も変わるので,ITサービスマネージャには,ITサービス継続計画を見直し,改善していく活動が望まれる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,“災害によって発生する,ITサービスの継続に影響を与えると特定した事態”,及び“分析して評価した事業への影響”について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業への影響を極小化するために策定したITサービス継続計画の目標と,計画に反映した対応策及びその対応策が妥当であると判断した理由について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対応策の評価,及び“ITサービス継続計画を見直し,改善していく活動”について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R04-1-PM2-Q2】ITサービスの運用品質を改善する取組について
ITサービスの運用チームは,サービスの運用を通じて,信頼性の高いITサービスを安定的に提供する。サービスレベルの向上を図り,顧客の期待に応えるために,ITサービスマネージャには,ITサービスの運用品質の改善目標を定めて,運用品質の改善に取り組むことが求められる。
ITサービスの運用品質の改善目標には,例えば,作業ミス件数の20%削減やサービスデスクにおける受付から回答までの時間の30分短縮といった具体的な目標値を設定し,達成期限も設ける。
次に,改善目標を達成するための方策を立案して実施する。次のような観点から方策の内容を設定する。なお,複数の方策を立案して実施することもある。
・プロセス:手順の見直し,標準化の推進など
・ツール:ツールを使った自動化など
・人:運用チームのメンバのスキル向上,役割と責任の明確化など
そして,方策の管理指標を定め,定期的に方策の実施状況を確認する。
方策の実施に当たっては,運用チームのメンバによる議論を促して取組への動機付けを行うなど,運用チームの力を結集するための工夫を行うことも大切である。
改善の取組においては,方策の管理指標の達成状況及び改善目標の目標値の達成状況を評価する。未達の場合は原因を分析し,必要に応じて,方策などを見直す。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,運用チームの構成,及びITサービスの運用品質の改善目標とその設定根拠について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた改善目標を達成するための方策について,方策の内容及び管理指標を,運用チームの実態を踏まえて工夫した点を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方策の管理指標の達成状況,改善目標の目標値の達成状況及び改善の取組全体の評価について,良かった点,悪かった点,今後の改善点を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R03:2021
【SM-R03-1-PM2-Q1】事業関係管理におけるコミュニケーションについて
顧客との関係を良好に保つための事業関係管理は,ITサービスマネージャの重要な業務である。事業関係管理では,顧客の事業及び業務内容を深く理解し,顧客の期待に沿ったサービスの提供に向けて,顧客満足の把握と改善,利害関係者間の調整などのマネジメント活動が必要となる。
事業関係管理では,目的に応じて,顧客とのコミュニケーションだけでなく,サービスの供給に関与する利害関係者とのコミュニケーションも必要である。
コミュニケーションの対象とする情報には,例えば,サービスの要求事項,サービスのパフォーマンス傾向,サービス満足度,苦情,障害対応の状況,新規サービス及びサービス変更に関わる要求事項などがある。
コミュニケーションの仕組みとしては,ミーティングでの報告,電子メールでの相談,グループウェアでの情報共有,SNS又は連絡ボードでの連絡などが考えられる。
情報の重要性,迅速性,緊急性などに配慮して,情報伝達の間隔や方法を定めるなど,サービスや組織の特徴を踏まえた効果的な取決めを行い,確実に実践していくことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,事業関係管理の概要及び事業関係管理におけるあなたの役割について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業関係管理のために特に重要と考えたコミュニケーションについて,その目的,対象とした情報,特に重要と考えた理由,及びコミュニケーションの仕組みについて,工夫した点を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたコミュニケーションについて,顧客との良好な関係を保つという観点でどのように評価しているか。また,今後の課題と対応についてどのように考えているか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R03-1-PM2-Q2】サービス可用性管理の活動について
ITサービスマネージャには,顧客とサービス可用性の目標を合意した上で,サービス可用性を損なう事象の監視,課題の抽出,改善策の実施など,サービス可用性の目標を達成するための活動を行うことが求められる。
サービス可用性の目標及び目標値については,ITサービスの特徴を踏まえて,例えば,サービス稼働率99.9%などと顧客と合意する。
サービス可用性の目標を達成するために,次のような活動を行う。
① サービス可用性を損なう事象を監視・測定する。
故障の発生などサービス可用性を損なう事象を監視して,事象の発生回数と回復時間などを測定する。また,評価指標を定めて測定結果を管理する。
② 測定結果を分析して,課題を抽出し,改善策を実施する。
例えば,インシデントによって,MTRS(平均サービス回復時間)が悪化している場合は,拡張版インシデント・ライフサイクルでの検出,診断,修理,復旧及び回復のどこで時間を要していたかを分析する。復旧段階の時間が長く,手順の不備が原因であった場合は,復旧手順を整備する。
また,サービス停止には至らないが,平均応答時間が増加している場合は,原因を分析して改善策を実施し,将来のサービス拡大などの環境変化に備える。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,サービス可用性の目標及び目標値,並びにそれらとITサービスの特徴との関係について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたサービス可用性の目標を達成するために重要と考えて行った活動について,監視対象とした事象と測定項目は何か。測定結果の評価指標は何か。また,測定結果をどのように分析したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた分析の結果から,サービス可用性の目標を達成するために対応が必要と考えた課題と改善策は何か,又は,将来の環境変化に備えて対応が必要と考えた課題と改善策は何か。いずれか一方の観点から,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗R01:2019
【SM-R01-1-PM2-Q1】環境変化に応じた変更プロセスの改善について
ITサービスマネジメントを実践する組織では,品質の確保に留意しつつ,緊急変更を含む変更管理プロセス並びにリリース及び展開管理プロセス(以下,変更プロセスという)を既に構築・管理している。
しかしながら,俊敏な対応を求める昨今の環境変化の影響によって,既存の変更プロセスでは,例えば,次のような問題点が生じることがある。
① アジャイル開発で作成されたリリースパッケージの稼働環境へのデプロイメントにおいて,変更プロセスの実施に時間が掛かる。
② 新規のサービスをサービスデスクで作業可能とする変更要求の決定に時間が掛かる。
ITサービスマネージャには,このような問題点に対し,変更プロセスの改善に向けて,例えば,次のような施策を検討することが求められる。
① アジャイル開発チームへの権限の委譲,プロセスの簡略化などによるデプロイメントの迅速化
② サービスデスクでの標準変更の拡大を迅速に行うためのプロセス見直しと利害関係者との合意
改善に向けた施策の決定に当たっては,変更要求への俊敏な対応と品質の確保の両面に配慮する必要があり,俊敏な対応を重視するあまり,品質の確保が犠牲にならないように工夫することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,既存の変更プロセスに影響を与えた環境変化の内容について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた環境変化によって影響を受けた変更プロセスの概要,変更プロセスに生じた問題点とその理由,改善に向けた施策及び施策の期待効果について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた施策の実施結果と評価について,俊敏な対応と品質の確保の観点を含め,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-R01-1-PM2-Q2】重大なインシデント発生時のコミュニケーションについて
ITサービスマネージャは,重大なインシデントが発生した場合には,あらかじめ定められた手順に従い,インシデント対応チームを編成して組織的な対応を行う。重大なインシデントの対応手順は,通常のインシデント対応手順に“何が重大なインシデントに当たるか”といった定義や必要な活動を加えて規定される。手順の中には,例えば,インシデントの発生や解決に向けた対応の経過状況を解決に関わる内部メンバだけでなく,適切な人に適切な方法で通知するなどの利害関係者とのコミュニケーションの活動が規定されている。
具体的には,次のような利害関係者とのコミュニケーションを行う。
① 顧客に対しては,適切な要員からインシデントの発生や対応結果を連絡する。
② サービスデスクに対しては,利用者からの問合せ対応に必要となる回復計画や回復時間などについての情報共有を行う。
③ 外部供給者に対しては,専門的技能及び経験を保有する要員の人選と解決に向けた活動の依頼を行い,支援を受ける。
重大なインシデントへの対応では,目標時間内での解決のために緊急な手順の実施が必要とされることもあり,インシデント対応チームのメンバ及び利害関係者とは正確かつ迅速な情報共有が重要となる。
また,ITサービスマネージャはサービスの回復後,重大なインシデントへの対応についてのレビューを行い,コミュニケーションにおける課題を明らかにすることも必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,発生した重大なインシデントの概要及び利害関係者について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた重大なインシデントへの対応で実施した手順の内容を述べよ。また,対応に当たって,利害関係者とどのようなコミュニケーションを行ったか。情報の正確性と対応の迅速性の観点を含め,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた重大なインシデントへの対応で明確になったコミュニケーションにおける課題と改善策について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H30:2018
【SM-H30-1-PM2-Q1】ITサービスマネジメントにおけるプロセスの自動化について
ITサービスマネジメントを実践する組織では,ITサービスマネジメントにおけるプロセスを効果的かつ効率よく実施するために,ツールを使ってプロセスの作業を自動化している。例えば,
・“インシデント及びサービス要求管理プロセス”において,知識ベース検索機能を備えたツールを使って,サービスデスクが利用者からの問合せに対応する。
・“サービスの報告プロセス”において,ツールを利用してデータを集計し,サービス報告書をまとめる。
さらに,自動化の範囲を次のように拡大し,プロセスに関する自動化を進め,プロセスを首尾一貫して実行する程度(以下,プロセス成熟度という)を向上させていく。
(1)自動化されずに人が行っている作業に新しい技術を適用する。
・サービスデスクが行っている利用者とのチャット対応作業の一部を,AIを活用し,人間に代わってコンピュータが対応する。
・人間がデータを入力して作成しているサービス報告書の作成作業の一部を,RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を使って自動化する。
(2)プロセス間の連携を自動化する。例えば,変更管理プロセスからの“変更の成功”通知で,構成管理プロセスにおいてCMDBを更新する運用を自動化する。
ITサービスマネージャは,自動化の範囲の拡大に当たって,次のような活動を行う。
・プロセスで使っているツールの利用状況を把握し,今後の取組内容を決める。
・効果を評価するためのKPIとその目標値を定め,実施計画を作成する。
・業務適用又は試行運用を開始し,期待する効果の達成度を評価する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,自動化対象としたプロセスの概要及び自動化の状況について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロセスに関する,自動化の範囲の拡大に当たっての活動における取組内容及び実施計画について,KPIとその目標値を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた活動によって実現したプロセスの自動化及び組織におけるプロセス成熟度向上の評価について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H30-1-PM2-Q2】ITサービスの運用チームにおける改善の取組みについて
ITサービスマネージャは,運用チームの業務記録の内容,運用しているサービスの管理指標の傾向を把握・分析し,課題を明確にした上で改善に取り組むことが求められる。
例えば,次のような改善の取組みによって,作業生産性の向上,作業品質の向上,顧客満足の向上などを実現する。
・故障対応時間の短縮が課題の場合には,故障対応のスキル不足を解消するために,実地訓練に取り組む。
・作業手順の誤りや漏れをなくすことが課題の場合には,作業手順について,有識者とのレビューを義務付ける。
・サービスデスクの応対に対する利用者からの不満を解消することが課題の場合には,コミュニケーション力を向上させるための教育を行う。
改善の取組みに当たっては,目標達成に向けて運用チームの力を結集することが大切である。そのために,ITサービスマネージャは,次のような工夫を行う。
・課題を明示することでチームメンバの議論を促して取組みへの動機付けを行う。
・達成状況を“見える化”して改善に意欲的に取り組めるようにする。
また,改善の取組み後は,設定した目標に無理はなかったか,動機付けは十分であったかなどを振り返り,改善の取組みを評価する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,運用チームの構成,及び運用チームの課題とその根拠について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた課題を達成するために,どのような改善の取組みを行ったか。課題に対して,設定した目標,運用チームの力を結集するために工夫した点を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた改善の取組みの結果はどうであったか。目標の達成状況,及び取組みの評価について,良かった点,悪かった点を含めて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H29:2017
【SM-H29-1-PM2-Q1】ITサービスの提供における顧客満足の向上を図る活動について
提供しているITサービスに対する顧客満足の向上を図る活動は,ITサービスマネージャの重要な業務である。顧客満足の向上を図るためには,顧客とのコミュニケーションによって顧客の期待・要求事項を正確に理解し,顧客との良好な関係を維持することが必要である。
顧客とのコミュニケーションの仕組みとしては,サービスの報告プロセスで実施する定例サービス報告会などが挙げられる。
サービスの報告では,次のような内容を顧客に報告し,レビューを行う。
・SLAで定義したサービス目標の達成状況,課題,及び課題への対策
・インシデント,変更など重大なイベントに関する情報
・顧客満足度測定の分析結果
コミュニケーションの仕組みを使って,サービスの価値,費用なども含めた顧客の期待と満足の状態を把握することが望ましく,顧客満足を得られていない内容については,顧客満足の向上のための活動計画を策定し,確実に実施していく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,顧客とのコミュニケーションの仕組みについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
サービスの報告でレビューしたサービス目標の達成状況,課題,及び課題への対策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べたコミュニケーションの仕組みを使って把握した顧客の期待と満足の状態,及び顧客満足の向上のために策定した活動計画と実施状況について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H29-1-PM2-Q2】継続的改善によるITサービスの品質向上について
ITサービスの品質を向上するには,サービス品質の目標を設定し,目標達成に向けた改善活動を継続的に実施することが求められる。
サービス品質の目標として具体例を挙げると,稼働率の改善,インシデント発生件数の削減,サービス要求のリードタイム短縮などがある。また,目標達成のための方策としては,内部プロセスの改善,要員の技能向上などがある。
サービス品質の目標達成に向けた改善活動の取組みは,PDCAサイクルを適用して次のように進めていく。
① 現状のサービス品質を把握した上で,サービス品質の目標及び目標値を設定する。
② 目標値達成のための方策を立案し,実施する。方策を立案する際は,方策の実施状況を把握するための管理指標を設定する。また,実施費用及び実施期間にも留意する必要がある。
③ 管理指標の達成度合いを把握し,サービス品質の目標値の達成状況を確認する。
④ ①~③の活動を振り返り,評価した上で目標達成に向けての活動を見直し,次の取組み計画を策定し,継続的改善に取り組む。
このような活動の実施に当たっては,重要業績評価指標(KPI)を定め,定期的に評価し,目標達成に向けた継続的改善活動を行うことも有効である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要及び特に重要と考えたサービス品質とその目標及び目標値について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたサービス品質の目標値を達成するために立案した方策について,管理指標と方策立案時の考慮点を含め,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
サービス品質の目標達成に向けた改善活動を振り返り,評価した結果を次の取組み計画にどのように生かし,継続的改善活動を行ったかについて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H28:2016
【SM-H28-1-PM2-Q1】ITサービスを提供する要員の育成について
ITサービスマネージャは,ITサービスを提供する要員を適切にマネジメントすることが求められる。ITサービスを提供する要員に,適切な知識と技能及びそれらを適用する能力(以下,“要員の能力”という)が不足している場合には,ITサービスマネジメントの活動に支障を来す。例えば,
・問題管理プロセスを適切に運用する能力が不足している場合,インシデント発生時の事後対応的な活動にとどまり,事前予防的な活動を実施できず,インシデントの再発防止ができない。
・キャパシティの予測技法に関する知識が不足している場合,キャパシティ計画を適切に策定できず,サービスの応答時間の目標が達成できない。
このような場合,ITサービスマネージャは,ITサービスを提供する“要員の能力”を高めるための要員育成目標を設定し,次のような活動を行う必要がある。
・ITサービスを提供するチームの役割を踏まえた上で,個々の要員の経験などを考慮し,“要員の能力”のうち重点的に高める必要がある能力を決定する。
・要員教育,訓練など,要員育成策を決定する。
具体的には,要員育成計画の作成,OJTの着実な実施,モチベーション維持のための方策の実施などを行う。また,社内の人材育成体系,外部の研修機関の活用などにも考慮する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ITサービスを提供する上で必要となる“要員の能力”について,必要となる理由を含めて800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた“要員の能力”のうち重点的に高めようとした能力及び実施した要員育成策について,工夫した点を含めて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた要員育成策の評価,及び今後改善したいと考えている内容について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H28-1-PM2-Q2】プロセスの不備への対応について
ITサービスマネジメントで規定されるプロセスの確立は,ITサービスの品質を確保する上で重要である。例えば,インシデント管理のプロセスに不備があってインシデントの対応に時間が掛かったり,問題管理のプロセスに不備があってインシデントの発生が減らなかったりする。
ITサービスマネージャは,発生したインシデントに対処した後に,インシデントの内容や対応状況を整理し,インシデントの原因である問題を識別する。プロセスの不備がある場合には,プロセス単体の観点(手順の曖昧さ,抜け漏れ,想定外の事象の発生など)だけでなく,プロセス間の連携の観点(共有する情報の不足,連携するタイミングの悪さなど)も含めて調査し,対策を検討するべきである。
また,インシデントの原因となった問題を解決した後,過去に発生したプロセスの不備に起因するインシデントの傾向分析を行うなど,事前予防的な活動を行うことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,不備があったプロセスの概要及び不備の内容について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロセスの不備をどのように調査し,どのような対策を立案したか。工夫した点を含め,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
プロセスの不備に関連して行った,事前予防的な活動について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H27:2015
【SM-H27-1-PM2-Q1】ITサービスに係る費用の最適化を目的とした改善について
ITサービスに係る費用の最適化を目的として,ITサービスマネージャは,顧客の要求事項,サービス提供者の経営環境,技術の変化などに応じ,顧客と合意したサービス目標に照らして,適切な費用改善策を立案し,実施する必要がある。
適切な費用改善策を立案し実施するためには,まず,現状のサービスを提供するために要している費用の状況を把握し,改善目標を設定する。次に,パレート図,特性要因図などを用いて,非効率な活動がないか,必要な資源の選定・活用において改善の機会がないかなどについて分析する。その上で,運用効率や生産性の向上に向けて,次のような観点から施策を検討する必要がある。
・サービス管理手順の簡素化,自動化ツールの活用など,プロセスの見直し
・他サービスとの要員配置の調整,外部要員の活用など,体制の見直し
・外部の供給者に委託しているサービスのサービス時間や費用など,契約内容の見直し
ITサービスマネージャは,関係部門とも協議し,費用対効果,実行可能性などを十分に検討した上で費用改善策を決定し,実施することが重要である。
費用改善策を実施した後は,改善目標を達成できたかどうかを監視・分析する必要がある。また,様々な環境の変化に応じて,費用の最適化に向けた継続的な取組みを推進していくことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ITサービスに係る費用の最適化を目的とした改善を行うに至った背景について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた背景を契機として実施した費用改善策と,改善策を立案し実施する上で検討した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた費用改善策を実施した後,改善目標を達成できたかどうかを監視・分析した内容と,費用の最適化に向けた継続的な取組みについて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H27-1-PM2-Q2】外部サービス利用における供給者管理について
ITサービスを提供する際に,業務の一部や全てを外部委託すること,ITサービスの基盤に外部のデータセンタやクラウドサービスを活用することなど,供給者が提供するサービス(以下,外部サービスという)を利用することが広く行われている。
外部サービスを利用する上で,ITサービスマネージャは,顧客からの要求事項に応えるために供給者に対して次のような要求事項を明らかにしなければならない。
・品質や性能,費用
・インシデント連絡や業務報告などのコミュニケーション
・機密情報の取扱いなどの情報セキュリティ
ITサービスの提供時には,ITサービスマネージャは供給者管理を徹底し,ITサービスの可用性低下,業務の遅延,情報セキュリティ事故発生などの品質低下が起こらないようにする必要がある。
このため,ITサービスマネージャは,次のような活動を行うことが重要である。
・供給者への要求事項に基づいて,例えば,故障発生などの品質項目,機密情報へのアクセスなどの情報セキュリティ項目について,範囲・間隔を定めて監視する。
・評価基準を設け,監視結果や業務報告から外部サービスについて評価する。
・供給者への要求事項に照らして不適合がある場合は,原因と再発防止策について報告を求める。
また,顧客からの要求事項などの変化に応じて供給者への要求事項を見直すだけでなく,品質項目の監視内容を見直すなど,供給者管理の改善の継続も重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要,顧客からの要求事項,及び利用した外部サービスについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた顧客からの要求事項に応えるために,供給者に求めた要求事項と,供給者管理の活動内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた供給者管理の活動の評価と,供給者管理の改善の継続について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H26:2014
【SM-H26-1-PM2-Q1】ITサービスの移行について
ITサービスの安全かつ円滑な開始に向け,顧客やIT部門の関係者と連携してITサービスの移行を確実に実施するための計画(以下,移行実施計画という)を策定することは,ITサービスマネージャの重要な業務である。
移行実施計画では,①ITサービスの受入基準に従って移行の対象となるITサービスを検証する方法と,②移行手順及び移行体制を整え稼働環境に展開する方法,などを計画する。その際に,対象となるITサービスの特徴や各種制約など移行の実施において考慮すべき点とその対応策を明確にすることが重要である。
具体的には,まず,①については,リリースの内容,運用手順,運用体制,キャパシティなどの検証において考慮すべき点を,②については,稼働環境に展開する上で,時間,環境,体制の制約など考慮すべき点を洗い出す。次に,考慮すべき点について,関係者と十分に協議し,対応策を決定する。また,対応策が確実に実施されるよう工夫することも重要である。
移行の実施後は,移行実施計画に沿って実施した結果についてレビューを行い,その結果を例えば組織のナレッジとして蓄積し,共有するなど,活用することも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
移行の対象としてあなたが携わったITサービスの概要と,移行実施計画の策定に当たって洗い出した考慮すべき点のうち,特に重要と考えたものについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた考慮すべき点について関係者と協議し,決定した対応策,決定した理由,及び対応策が確実に実施されるための工夫について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べたITサービスの移行実施後のレビュー結果とその活用について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H26-1-PM2-Q2】ITサービスの障害による業務への影響拡大の再発防止について
近年,複数のシステムが仮想化されたサーバで運用されたり,企業内外のシステムがネットワークで密接に連携したりするなど,システム環境は複雑化している。
このような複雑化した環境への理解不足や障害に対する検討不足があると,ITサービスの障害時に,例えば次のような事態を引き起こして,業務への影響が拡大することがある。
・優先して回復すべきITサービスへの対応が後回しになる。
・ネットワークで連携しているシステムへの連絡が遅れる。
・回復作業において他のITサービスに影響を与える。
このような事態が発生した場合には,障害回復後,改めて障害対応の経過を整理した上で,例えば次のような視点から業務への影響が拡大した原因を分析して,再発防止策を立案する。
・障害対応手順などはシステム環境に即していたか。
・情報収集や判断を含めた指揮命令は迅速かつ的確に行えたか。
・業務に及ぼす影響は正しく把握できていたか。
また,再発防止策を実施した後,業務への影響が拡大した事例を組織内で共有する,システム環境や業務の変化に応じて再発防止策を見直すなど,再発防止を確実にするための活動を行うことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ITサービスの障害による業務への影響が拡大した事例について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事例の再発防止策について,業務への影響が拡大した原因の分析の視点及び判明した原因を含め,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた再発防止策を実施した後,再発防止を確実にするために行った活動について,工夫した点を含め,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H25:2013
【SM-H25-1-PM2-Q1】サービスレベルが未達となる兆候への対応について
サービスレベルについて顧客と合意し,合意したサービスレベルを遵守することは,ITサービスマネージャの重要な業務である。サービスレベルを遵守していくためには,サービスレベルが未達となる兆候に対して適切な対応を図ること(以下,兆候の管理という)が重要となる。
兆候の管理に当たっては,まず,監視システムやサービスデスクなどを通じて,システム資源の使用状況や性能の状況,利用者からの問合せ状況などの情報を幅広く収集する。
次に,それらの状況の変化や傾向などを分析するとともに,過去の事例も参考にしながら,サービスレベルが未達となる兆候であると認識した場合には,原因を究明して適切な対策を講じる。
また,兆候の管理を効果的に行うためには,関連部門と連携することによって,様々な情報を多面的に分析するなどの工夫が重要である。さらに,兆候の管理を行う仕組みを継続的に改善していくことも必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,兆候の管理の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた兆候の管理において,サービスレベルが未達となる兆候及びそのように認識した理由と,サービスレベルを遵守するために実施した対策及びその結果について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた兆候の管理を効果的に行うための工夫と,仕組みの改善について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H25-1-PM2-Q2】外部委託業務の品質の確保について
ITサービスの提供においては,ITサービスの提供に必要な業務の一部を外部委託する場合がある。外部委託業務の品質は,顧客や利用者に提供するITサービスの品質に影響を与える。したがって,外部委託業務の品質について委託元と委託先で合意した上で,合意した品質を継続的に確保することが,双方のITサービスマネージャには求められる。
品質の合意に当たっては,外部委託業務の内容だけでなく,提供するITサービスの特徴,顧客とのSLAへの影響などを考慮して,委託元と委託先とで協議する必要がある。合意した品質を継続的に確保するためには,作業プロセスの確立,要員の確保,品質管理体制の整備などにおける課題を踏まえて,品質確保策を立案し,実行しなければならない。
また,品質確保策の実行において,品質に関わる問題を把握した場合には,業務遂行上の観点だけでなく管理上の観点も含めて,対策を講じる必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,外部委託業務の概要及びその外部委託業務の品質がITサービスの品質に与える影響について,あなたの立場(委託元か委託先か)を明確にした上で,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた外部委託業務において,品質の合意に当たって協議したこと及び合意した品質と,その品質を継続的に確保する上での課題及び品質確保策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた品質確保策の実行において把握した品質に関わる問題と,その問題を把握した経緯及びその問題に対して講じた対策について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H24:2012
【SM-H24-1-PM2-Q1】重大なインシデントに対するサービス回復時の対応について
業務に与える影響が極めて大きく,緊急にサービスを回復させることが求められる重大なインシデントとして,基幹業務システムの障害,全社認証基盤の停止,メールシステムの停止などがある。
このような重大なインシデントに対し,ITサービスマネージャは,事前に用意した作業手順に従ってサービスを回復させる。しかし,回復作業中にトラブルが発生し,作業手順どおりには対応できない場合がある。
このような場合には,ITサービスマネージャは,関係者と協議し,対策を立案しなければならない。対策の立案に当たっては,安全で迅速であることに留意し,次のような観点から検討を行う。
・サービスを全面的に再開する。
・サービスを部分的に再開する。
・代替サービスを提供する。
また,対策の実施に当たって,ITサービスマネージャには,進捗状況を確認したり,顧客やサービス利用者に提供する情報を一元管理したりするなど,作業を統括することが求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,重大なインシデントの概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた重大なインシデントの回復作業中に,どのようなトラブルが発生したか。また,トラブル発生時に,関係者とどのような観点から検討を行い,どのような対策を立案したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策の実施時に,作業を統括するために行ったことについて,その目的とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H24-1-PM2-Q2】ITサービスの継続性管理について
大規模災害や社会的に影響が大きい事件・事故など,ITサービスを停止させる不測の事態の発生は避けられない。このような事態に備え,ITサービスをあらかじめ決められた範囲で復旧させ,顧客のビジネスへの影響を最小限にとどめられるようにしておくこと(ITサービスの継続性管理)は,ITサービスマネージャの重要な業務である。
ITサービスマネージャは,不測の事態に備えて,ITサービス復旧に向けた対策を準備しておくだけでなく,その対策を確実に機能させるために,日頃から,例えば次のような活動を行う必要がある。
・定期的に研修,復旧訓練(トレーニング)を行う。
・システム変更などによって,復旧すべきサービスの内容に変更が生じた場合には,速やかに対応マニュアルの改訂を行う。
・顧客の組織改定や人事異動などに応じて連絡体制や実施体制を更新する。
また,顧客の事業環境や外部環境などの変化に応じて,復旧に向けた対策の大幅な見直しを行うことも必要となる。例えば次のようなものがある。
・顧客のビジネス環境の変化に伴う事業継続計画の変更に合わせた見直し
・従来想定していなかった規模・種類の災害などの発生とその復旧に向けた取組みを参考にした見直し
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,不測の事態に備えて,ITサービス復旧に向けて準備した対策の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた対策を確実に機能させるための日頃からの活動について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた対策の大幅な見直しについて,見直しの理由とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H24-1-PM2-Q3】ユーザとの接点からの気付きを改善につなげる活動について
日頃からITサービスを実際に利用する人(以下,ユーザという)との接点,例えば,サービスデスクやユーザポータル(ITサービスに関する情報の提供・交換のためのWebサイト)には,ユーザからの様々な声が集まる。このような声からITサービスの問題に気付き,これを改善につなげることは,ITサービスの提供を依頼する人(以下,顧客という)にとってもメリットが大きい。
ITサービスマネージャは,顧客と合意して次のような活動に取り組む必要がある。
(1)問題の気付き
ユーザとの接点に集まる声を調査して,ITサービスの問題に気付く。例えば,操作に関する同様の問合せが多いこと,サービスの状況に関する問合せが増えたことから,それぞれ,操作性,情報提供の問題に気付く。
(2)改善策の立案
気付いた問題について,顧客の視点から,業務へのインパクト,問題の継続性,緊急性などを評価して,改善の優先度を検討する。優先度が高い問題に対して,顧客の業務への効果やコストなどを勘案して,改善策を立案する。
(3)改善策の実施や効果の検証に向けての準備
改善策の確実な実施や効果の検証に向けて,役割分担などに留意し,顧客や開発部門などの関係者と連携して,ユーザへの改善内容の説明,効果を検証する手順の具体化などを行う。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ユーザとの接点に集まる声を調査することで気付き,改善につなげた問題について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた問題の改善の優先度について,評価項目として何を設定し,どのような検討を行ったか。また,どのような改善策を立案し,顧客の業務にどのような効果があると考えたか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた改善策の確実な実施や効果の検証に向けて,関係者と連携して行ったことについて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H23:2011
【SM-H23-1-PM2-Q1】ITサービスに関する顧客への報告について
ITサービスの提供において,顧客に対してサービスの状況を定期的に報告することは,ITサービスマネージャの重要な業務である。報告に当たっては,顧客の立場にたち,必要とされる適切な情報を分かりやすく説明することが求められる。
報告内容としては,サービスレベルの目標に対する達成状況,インシデントの発生や対策の状況などの基本的な事項にとどまらず,サービスの状況の分析によって判明したこと,今後のITサービスを考える上での参考情報など,顧客にとって有益な事項も含めることが望ましい。具体的には,ITリソースの利用率の推移によって発生が懸念されるリスクと対処方法,サービスデスクへの問合せ内容の分析によって明確になった問題点と解決策などがある。
また,ITサービスマネージャは,報告に対する顧客からの評価などに基づいて,改善を行っていく必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,顧客への基本的な報告事項について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた基本的な報告事項以外で,顧客にとって有益と判断して報告に含めた事項と,そう判断した理由は何か。また,報告内容を分かりやすく説明するために工夫したことは何か。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
あなたが行った報告について,今後改善したいと考えている点をその理由とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H23-1-PM2-Q2】キャパシティ管理について
応答時間,処理時間などのITサービスの状況や,CPU使用率,ストレージ使用量などのITリソースの状況を常時監視し,現在及び将来のキャパシティに関する様々な問題に対して迅速かつ適切に対応することは,ITサービスマネージャの重要な業務である。
例えば,監視作業を通じて,次のような問題を発見することがある。
・特定の時間帯に,オンライン処理の応答時間が悪化する。
・特定のディスクにアクセスが集中し,Webアプリケーションがタイムアウトする。
・夜間バッチの処理時間が延び,翌日のオンラインサービス開始に影響する。
このような問題の解決に向けて,リソースの増強,システムのチューニングだけでなく,サービス内容の検証,業務内容の見直し提案などの様々な角度から,複数の対応策を検討する必要がある。実施する対応策の決定に当たっては,問題の重要度や緊急度,対応策の作業難易度や作業期間,費用などを総合的に評価しなければならない。
また,問題への対応策の立案・実施に加えて,キャパシティに関する要件の把握方法の改善,リソースの増強要求のキャパシティ計画への確実な反映,リソースの監視方法の変更などのキャパシティ管理方法自体の見直しを行うことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,監視作業を通じて発見したキャパシティに関する問題及びその問題によるITサービスへの影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた問題の解決に向けて検討した対応策を列記せよ。また,実施することに決定した対応策の内容と,そう決定した理由は何か。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べた問題に関連して行ったキャパシティ管理方法自体の見直し内容について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H23-1-PM2-Q3】ITサービスの改善活動について
ITサービスの現場では,サービスに影響を及ぼす重大な障害やサービスに直接影響を及ぼさない軽微なミスが発生したり,他方では,サービスに対して顧客から高い評価を受けたりするなど,様々な事象が発生する。ITサービスマネージャには,これらの事象に対して,適切な対応を行うとともに,対応を通じて得られた成果を組織全体に展開するなどのITサービスの改善活動を実施することが求められる。
① 事前予防策や再発防止策を講じ,その成果を整理する
軽微なミスが続いた場合は,基本動作や手順に問題はないかなど,全ての作業を点検し,重大な障害とならないように事前に予防する。サービスに影響を及ぼす重大な障害が発生した場合は,リリースのプロセスに問題はなかったか,障害発生後の対処は適切であったか,などの様々な観点から原因を究明して再発を防止する。その上で,対策の内容,検討の経緯,実施の結果などを成果として整理する。
② 顧客から高い評価を受けた取組みなどを分析し,その成果を整理する
満足度調査などで顧客から高い評価を受けた取組みや,高い目標を達成した取組みについて,評価の理由や目標達成の成功要因を分析する。その上で,取組みの内容,分析の結果などを成果として整理する。
③ ①,②で得られた成果を組織全体に展開する
展開に当たっては,成果を発表する場を設けたり,組織全体への展開状況を確認したりするなどの工夫が必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ITサービスの改善活動の対象とした事象について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事象に対して実施した対応と得られた成果について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた成果の組織全体への展開について,工夫した点を中心に,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H22:2010
【SM-H22-1-PM2-Q1】ITサービスの構成品目に関する情報の管理について
ITサービスの構成品目としては,ハードウェア,ソフトウェア,データセンタなどの設備,更には顧客情報,運用体制図,運用手順書,SLAなどがある。これらの構成品目に関する情報を一元管理する構成管理データベース(CMDB)を活用することは,サービスデスクでの顧客対応,障害回復,設備の増設・変更など,ITサービスにおける様々なプロセスを効率よく的確に行う上で,極めて重要である。
しかし,必要な情報がCMDBに登録されていない,情報が更新されていない,使い勝手が悪い,などが原因で,連絡先が分からなくてサービス停止が長引く,ライセンスの有効期限切れでサービスが突然停止するなどの問題が発生することもある。
ITサービスマネージャには,例えば,次のような取組みによって,CMDBの内容,運用方法及び利便性を改善することが求められる。
・利用場面に応じて,必要となる構成品目とそれらの関係をCMDBに追加する。例えば,①サービスデスクで顧客からの問合せに答えるには,顧客,提供サービス,IT機器及びそれらの関係,②障害などに対処するには,ソフトウェアのバージョン,IT機器の型番,③電力設備の工事の準備には,設備,収容されるIT機器及びそれらの関係をCMDBに追加する。
・CMDBの運用ルールを徹底する。例えば,①PCへのCMDBの複製を禁じる,②責任者を定めて運用ルールの順守状況をチェックする。
・利用目的に応じて,ツールなどの導入を図る。例えば,①構成品目の情報を自動収集するツールを導入する②保守契約の満了やディジタル証明書の有効期限を自動通知する仕組みを導入する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,CMDBの利用において発生した問題及びその原因について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた問題に対してどのような改善を行ったか。工夫した点を中心に,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた改善の具体的な効果及びその評価と,CMDBの更なる活用に向けた課題について,600字以上1,200字以内で述べよ。
【SM-H22-1-PM2-Q2】リリース管理におけるリリースの検証及び受入れについて
新規のシステム又は改変されたシステムを,稼働環境に円滑に実装するためのリリース管理は,ITサービスマネージャの重要な業務である。リリース管理においては,リリースの内容を把握した上で,適切な実装計画を立案し,確実に実施するためのマネジメントが重要となる。
中でも,実装直前に行うリリースの検証及び受入れは,リリース管理における重要なプロセスであり,それまでに次のような準備をしておく必要がある。
・受入れテスト環境の構築
・実装手順及び不測の事態に備えた切戻し手順の作成
・人的リソースの確保
しかし,リリースの検証及び受入れのとき,次のような問題が発生することがある。
・緊急の受入れ要請があり,受入れテストに十分な時間を確保できない。
・受入れテストの結果,運用機能の改善が必要であると判明した。
・実装に当たり,当初想定した以上の作業要員が必要であると判明した。
このような場合,ITサービスマネージャは,早急な問題解決に向けて利用者,関連部門などと対応を協議し,対策を実施する必要がある。
また,再発防止に向けて,発生した問題の根本原因を究明し,適切な施策を講じなければならない。根本原因の究明に当たっては,リリースの検証及び受入れ,又はリリース管理の視点にとどまらず,ほかの管理プロセス(変更管理,構成管理など),更には稼働環境,運用基準なども含めた広範な視点から,分析を行うことが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,リリースの検証及び受入れの概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
リリースの検証及び受入れのときに発生した問題と,問題解決に向けて利用者,関連部門などと協議した対応の内容及び実施した対策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた問題の根本原因と,再発防止に向けて講じた施策について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H22-1-PM2-Q3】インシデント発生時に想定される問題への対策について
ITサービス提供中に発生する障害関連のインシデントは,ITサービスの稼働率低下,利用者の満足度低下などの問題を引き起こし,SLAの順守に影響を与える場合が多い。ITサービスマネージャは,インシデントを発生させないための予防的な対策とともに,インシデント発生時に想定される問題への対策を事前に検討しておくことが重要である。
例えば,主要な業務システムが稼働するサーバに障害が発生した場合を考える。このときに想定される問題としては,回復の手順に不慣れでITサービスの回復が遅れること,サービスデスクに問合せが殺到して,利用者とのコミュニケーションが十分にとれないこと,などがある。
このような問題への対策としては,ITサービスを速やかに回復させるために,主要な業務システムが稼働するサーバの障害時の運用訓練を定期的に行うこと,サービスデスクへの問合せを緩和させるために,“お知らせ”などを通じて利用者に障害状況,障害回避策などを伝える手順を確立すること,などが考えられる。
ITサービスマネージャは,対策を検討するに当たって,SLAの順守への影響が最小となるようにすること,費用対効果が最大となるようにすること,対策の前提となる技術やサービスの入手可能時期を明らかにすること,などに留意する必要がある。
また,実際にインシデントが発生したときの対応の過程で,事前に検討しておいた対策に不備が判明する場合がある。このような不備に対して解決策を立案し,事前に検討しておいた対策の改善を図ることも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,インシデント発生時に想定される問題の概要について,SLAの順守に与える影響を含め,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた問題への対策の内容と,対策を検討するに当たって留意した点について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策の改善について,インシデント発生時の対応の過程で判明した不備を含め,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H21:2009
【SM-H21-1-PM2-Q1】変更管理プロセスの確実な実施について
新商品の販売や制度変更への対応,提供機能の改善など,システムに対する様々な変更要求が発生する。一方,システムに対する変更にはリスクが存在し,事業に重大な影響を及ぼすこともある。このため,ITサービスマネージャは,変更要求の受付からその終了に至るまでの,変更を管理するための一連の手続(以下,変更管理プロセスという)を定め,確実に実施することが重要である。
変更管理プロセスに問題があると,例えば,次のような事象が発生する。
・変更要求の処理に時間が掛かる。
・変更の失敗が度重なる。
このような場合には,その原因となる変更管理プロセスの問題を特定し,その改善策を立案・実施することによって,再発を防止しなければならない。
また,変更管理プロセスが確実に実施されていることを,定期的に確認する必要がある。このための方策としては,例えば,次のようなことが考えられる。
・重要業績評価指標(KPI)などを用いて,実施状況をレビューする。
・内部監査などによって,遵守状況をチェックする。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,変更管理プロセスについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた変更管理プロセスで,どのような事象が発生したか。その原因となる変更管理プロセスの問題は何であったか。また,再発を防止するためにどのような改善策を立案・実施したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
変更管理プロセスが確実に実施されていることを,定期的に確認するために行っている方策について,今後の課題とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H21-1-PM2-Q2】ITサービスの改善計画の立案におけるサービスデスクの活用について
ITサービスの改善に当たっては,サービス提供者の視点だけではなくサービス利用者の視点を考慮することも重要である。ITサービスマネージャには,提供するITサービスに対して,提供者と利用者の両方の視点を考慮したITサービスの改善計画の立案に責任をもつことが求められる。
利用者の視点を考慮するためには,サービスデスクで得られた利用者からの電話や電子メールなどによるコンタクト記録を有効に活用する必要がある。具体的には,ITサービスの改善計画の立案に当たって,次のようなことを実施する。
・サービスデスクのコンタクト記録を確認し,提供しているITサービスへの要望を抽出する。次に,抽出した要望に対し,発生頻度や緊急度などの観点から利用者の満足度を評価するとともに事業への影響を考慮して,改善事項を選定する。
・選定された改善事項に対し,対策に要する費用と期間,対策による効果,対策を実施する優先度などを評価して,対策案を検討する。
また,ITサービスマネージャは,ITサービスの改善に当たって,コンタクト記録の有効活用だけにとどまらず,利用者の満足度向上のために,サービスデスクを通じて利用者と主体的にコミュニケーションを図ることも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,ITサービスの改善計画について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたITサービスの改善計画の立案に当たって,コンタクト記録の確認から改善事項の選定までをどのように行い,対策案の検討をどのように行ったか。改善事項の選定を中心に,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
ITサービスの改善に当たって,利用者の満足度向上のために,利用者とどのようなコミュニケーションを図ったか。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
【SM-H21-1-PM2-Q3】事前予防的な問題管理について
ITサービスマネージャには,提供サービスに潜在する問題の発見と対策を行う事前予防的な問題管理が求められる。そのためには,インシデント,危うく障害となるところだった“ヒヤリハット”,顧客の意見などを時系列や発生要因などによって分析し,判明した発生の傾向や頻度に対して仮説検証などによる考察を深める必要がある。
例えば,時系列分析によって,CPU使用率のしきい値超えのインシデントが増えたことが判明した場合は,なぜ増えたのかについて,次のような仮説を立てて検証する。
・トランザクションの変化はないか,特定のトランザクションが増えていないか。
・プログラムの変更はなかったか,そのプログラムがCPUを占有していないか。
検証の結果,後者の仮説が正しい場合は,CPUを占有するプログラムの変更をなぜチェックできなかったのかについて,更に仮説を立てて検証する。
また,発生要因分析によって,LANケーブル誤切断のインシデントが多いことが判明した場合は,なぜ誤切断したのかについて,次のような仮説を立てて検証する。
・作業環境に問題はないか,LANケーブルが乱雑に放置されていないか。
・マニュアルに問題はないか,記述のあいまいなところや間違いはないか。
このように,仮説と検証を繰り返すことによって考察を深め,提供サービスに潜在する問題を発見する。発見した問題に対しては,適切な対策を実施する必要がある。
なお,事前予防的な問題管理を定着させるためには,インシデントの件数が基準値を超えた場合に分析を義務付けることや,実施した分析や対策の発表の場を設けて,優れた分析や対策を行った者を表彰するなどの取組も有効である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったITサービスの概要と,分析して判明したインシデントなどの発生の傾向や頻度について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたインシデントなどの発生の傾向や頻度に対し,どのように考察を深め,潜在する問題を発見したか。また,発見した問題を解決するためにどのような対策を実施したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
事前予防的な問題管理を定着させるためにどのような取組を行ったか。今後改善すべき点とともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📗H20:2008
【SM-H20-1-PM2-Q1】SLAに基づく情報システムの運用について
ITを利用したサービスをデータセンタなどから提供する場合に,情報システムの運用を顧客や利用部門との間で合意されたSLAに基づいて行うことが多くなってきた。
SLAを遵守したサービスを提供することはシステム管理エンジニアの重要な職務であり,そのためには次のようなSLA遵守のためのプロセスを確実に実行する必要がある。
(1)サービスレベルの継続的なモニタリングとモニタリング結果の蓄積
(2)サービスレベルの傾向分析と評価
(3)サービスレベルが悪化した場合の原因究明と対策実施
(4)顧客や利用部門へのSLA遵守状況などの定期的な報告
しかし,SLA遵守のためのプロセスを実行する際には,次のような問題が発生することがある。
・モニタリングの方法によってはサービスに影響を及ぼす。
・サービスレベル悪化の原因を特定するための情報が不足している。
・対策を実施するときにサービス停止が必要となる。
このような問題に対してシステム管理エンジニアは,顧客や利用部門を含めた関係部門の協力を得ながら解決策を立案し実施していくことによって,SLA遵守に努める必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,合意されたSLAについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたSLAに対して,その遵守のためのプロセスを実行する際に発生した問題について,具体的に述べよ。また,その解決策について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた解決策について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H20-1-PM2-Q2】システム運用管理ツールの導入準備について
システム運用管理における業務効率や運用品質の向上のためには,システム運用管理ツール(以下,ツールという)を効果的に利用することが重要である。ツールを利用することで,障害の自動検知による対応の迅速化,システム構成の管理支援による作業の省力化,オペレーションの自動化による運用品質の向上,などが可能となる。
ツールを導入するに当たって,システム管理エンジニアは,運用管理業務における課題や目標を整理した上で,次のような準備作業を行う必要がある。
(1) 課題や目標を達成するために,ツールに求められる要件を整理する。
(2) ツールの機能,性能,費用,効果などを机上で評価し,候補を挙げる。
(3) 候補のツールを試用して評価し,採用するツールを決定する。
(4) ツールを活用した場合のシステム運用手順書を作成する。
(5) 本番運用への影響などを考慮し,ツールのインストール手順書を作成する。
これらの準備作業を進めていく際に,様々な問題が発生することがある。システム管理エンジニアは,これらの問題を主体的に解決していくことが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
ツールの導入対象となった運用管理業務の概要と,その運用管理業務の課題や目標,及びツールの導入におけるあなたの役割について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたツールの導入において,課題や目標を踏まえて実施した準備作業と,その際に発生した問題について,具体的に述べよ。また,その問題をどのように解決したか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたツール導入の準備作業について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H20-1-PM2-Q3】システム障害の長時間化の防止策について
システム障害が想定を超えて長時間化した場合,それによる損失は甚大なものとなることがある。このことから,システム管理エンジニアは,できる限り短い時間でシステム障害から復旧できるように,長時間化の防止策を講じる必要がある。
例えば,システム障害が長時間化した場合は,対応の経過を整理した上で,次のような視点から長時間化した原因を究明し,防止策を立案・実施する。
(1)連絡は適切な時間内に実施できたか
例えば,障害検知の遅れや,連絡不備による初動の遅れはなかったか。
(2)情報は適切に収集できたか
例えば,スキル不足や手順・体制の不備で情報が混乱することはなかったか。
(3)手順は適切であったか
例えば,並行して実施できる作業はなかったか。
(4)想定外の事態に適切に対応できたか
例えば,修理部品の到着の遅れに対し,代替策はとれなかったか。
(5)部門間の連携は適切であったか
例えば,開発部門との間で,復旧方法の確認に手間取ることはなかったか。
原因の究明や防止策の立案に当たっては,運用部門だけでなく,開発部門や利用部門などの有識者を交えたレビューも有効である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,長時間化したシステム障害の内容及び業務への影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム障害について,長時間化した原因をどのような視点から究明したか。また,長時間化した原因は何であったか。それぞれ具体的に述べよ。さらに,立案・実施した防止策について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた防止策について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H19:2007
【SM-H19-1-PM2-Q1】サービス開始に向けて開発部門と連携して実施した準備作業について
高品質で効率の良いシステム運用管理を実現するためには,情報システムのサービス開始に向けて,開発段階から入念な準備を行うことが重要である。
サービス開始に向けた準備には,運用管理部門内で独自に実施する作業に加えて,開発部門との綿密な連携が必要な作業がある。
開発部門との連携が必要な準備作業としては,例えば次のようなものがある。
(1)実現すべき運用管理機能を整理し,開発部門と共同で検討する。
(2)開発部門の設計レビューに参加し,運用管理面からの検証を行う。
(3)システムテストに参画し,運用管理機能の確認を行う。
システム管理エンジニアは,このような準備作業を実施するために,まず開発スケジュールなどの情報を入手しておく。その上で,適切な時期に開発部門と作業の分担や体制について合意する必要がある。
準備作業を実施する過程では,スケジュールや体制の制約などから様々な問題が発生することがある。これらの問題に対して,システム管理エンジニアは,開発部門と協力して対応策を立案・実施し,解決を図らなければならない。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,サービス開始に向けて開発部門と連携して実施した準備作業について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた準備作業について,どのように検討を進め,開発部門とどのような合意をしたか。また,準備作業を実施する過程でどのような問題が発生し,どのように解決したか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた準備作業について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H19-1-PM2-Q2】情報システムの管理・運用上の課題への暫定対策及び本対策について
システム管理エンジニアは,情報システムの運用状況や利用者のクレームなどから,システムの管理・運用における課題を把握する。課題としては,例えば“システムの立上げに時間がかかり,サービス開始時間が遅れる”,“ネットワークの負荷が増大し,ダウンロードに時間がかかる”,“レスポンスが悪化し,業務に影響が出ている”などがある。
これらの課題への対処には,緊急に実施する暫定対策と,その後に実施する本対策に分けざるを得ない場合がある。
このような場合,次のような観点から暫定対策と本対策を検討し,実施する。
(1)暫定対策は,運用状況の改善やクレームの解消などを早期に行うための一時的な対応であり,スピードが要求される。対策案の検討に当たっては,実施の容易さを重視するとともに,効果の限界などを明らかにしておく必要がある。
(2)本対策は,中長期的な安定運用のための抜本的な対応でなければならない。対策案の検討に当たっては,根本原因を追及した上で,実行可能性,作業期間,コスト,効果などを明らかにしておく必要がある。
また,本対策の実施方法や実施時期を明確にし,必要以上に暫定対策を継続しないようにすることも重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,暫定対策及び本対策が必要となった課題,並びに対策を分けた理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた課題への暫定対策の検討経緯・内容及び本対策の検討経緯・内容について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた暫定対策及び本対策の実施結果について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H19-1-PM2-Q3】作業ミスによる障害発生の防止について
情報システムの障害は,企業活動に多大な影響を及ぼすことがある。このことから,障害の発生を防止することは,システム管理エンジニアの重要な業務である。
障害を発生させる原因の一つとして,誤操作や確認漏れなどの作業ミスがある。作業ミスを引き起こす原因には,不注意,知識不足,思い込み,慣れなどがあるが,作業ミスの発生を防止するに当たっては,基本動作の徹底,体制の整備,作業手順やシステム上の改善など,あらゆる面での対策を検討しなければならない。その上で,これらの対策を組み合わせて実施することが重要である。
具体的な対策としては,例えば次のようなものがある。
(1)チェックリストに基づいた作業の実施
(2)複数人での作業の実施と相互確認
(3)作業手順書へのチェックポイントの追加
(4)重要な操作に対する確認メッセージ表示機能の追加
また,発生した作業ミスについて,その原因と対策の実施状況を関係者に周知徹底することも,防止策として有効である場合が多い。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,作業ミスによって発生した障害及びその作業ミスについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた作業ミスの原因と,作業ミスを防止するために実施した対策を列記せよ。また,その中で,あなたが重要と考えた対策について,その理由とともに,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H18:2006
【SM-H18-1-PM2-Q1】システム障害への対応訓練について
情報システムは,企業や官公庁などの業務遂行上のインフラとして安定稼働することが重要である。このため,システム管理エンジニアには,情報システムの障害を未然に防止するための施策に加えて,障害が発生したときに迅速かつ確実に対応して業務に及ぼす影響を極力小さくするための施策の立案と実行が求められる。このような施策の一つとして,システム障害への対応訓練がある。
訓練の計画立案に当たっては,まず,訓練の目的を確認し,目的に沿った訓練項目や評価項目・評価基準を設定する。次に,訓練の実施に向けて,関係者とともに次のような事項について検討しなければならない。
(1) 訓練に必要な情報システム資源
(2) 訓練の時期・期間
(3) 訓練の体制・手順
実行可能な訓練計画にするためには,情報システム資源,コスト,要員などの制約条件に合わせて,訓練の実施環境や訓練項目を見直すことが必要である。また,実施する時期・期間によっては,訓練の段階的な実施の検討が必要となる場合もある。
訓練実施の際に,評価項目・評価基準に照らして問題点が判明した場合,システム管理エンジニアには,関係者と協議の上,問題解決に向けた対策を立案し,着実に実行することが求められる。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,システム障害への対応訓練の目的について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた目的に沿った訓練計画の概要と,実行可能な訓練計画にするために工夫した点について,それぞれ具体的に述べよ。また,訓練実施の際に,評価項目・評価基準に照らして判明した問題点と,問題解決のための対策について述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた訓練の結果を踏まえて,今後,訓練計画を立案するときの課題について,簡潔に述べよ。
【SM-H18-1-PM2-Q2】緊急を要する変更要求に対する変更管理プロセスについて
事業環境の変化や各種制度の変更などに伴って,運用中の情報システムに対して様々な変更要求が発生する。システム管理エンジニアは,変更要求に確実に対処するとともに,変更後も情報システムを安全に安定して運用しなければならない。そのためには,変更要求の受付,影響調査,承認,実施などのステップからなる,標準の変更管理プロセスを確立しておく必要がある。
変更要求の中には緊急を要するものがあり,標準の変更管理プロセスでは対処できないことがある。このような緊急を要する変更要求を想定して,標準の変更管理プロセスを基に緊急時の変更管理プロセスも作成しておかなければならない。
緊急時の変更管理プロセスの作成に当たっては,まず,緊急を要する変更要求を具体的に想定する。次に,緊急度,影響範囲,所要時間など,変更要求の特性を分析した上で,標準の変更管理プロセスに対して,簡略化,並行化,順序の入替えなどを検討する。
さらに,緊急時の変更管理プロセスを確実に実施できるようにするためには,関連部門とともに,要員確保や資源調達の方法,連絡網の整備などを検討しておくことが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムにおける標準の変更管理プロセスの概要と,想定した緊急を要する変更要求の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた緊急を要する変更要求への対応において,標準の変更管理プロセスでは対処できないと考えた部分は何か。具体的に述べよ。それを踏まえて作成した緊急時の変更管理プロセスについて,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた緊急時の変更管理プロセスについて,どのように評価しているか。簡潔に述べよ。
【SM-H18-1-PM2-Q3】分散配置されたシステムの運用管理について
電子メールやスケジュール管理などのサービスを提供するために,インターネット技術を利用したシステムが本社と事業所に分散配置されることがある。
分散配置されたシステムの運用管理のために,本社にはシステム全体の運用管理を統括するシステム管理エンジニアが,事業所には事業所内の運用管理を行うシステム担当者が任命されるのが一般的である。システム担当者は,事業所の社員が兼務している場合が多く,システムやシステムの運用管理について知識が不足していたり,十分な時間を割けなかったりすることがある。このため,システムの障害に対して適切な措置や迅速な対応ができないなどの問題が発生することがある。
事業所でのこのような問題に対処するため,システム管理エンジニアは,次のような運用管理面の施策を立案し,システム担当者を指導・支援する必要がある。
(1) システム担当者の役割の明確化や体制の見直し
(2) 障害発生時の対応方法などを記載したマニュアルの整備
(3) システム操作やユーザ支援などのための研修や訓練の実施
施策の立案やシステム担当者の指導・支援に当たっては,運用管理の重要性をシステム担当者や事業所内の関係者に理解してもらうこと,システム担当者の技術レベルを把握しておくこと,システム担当者との信頼関係を確立しておくことなどが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった分散配置されたシステムの運用管理体制と,システム管理エンジニアとして認識した,事業所での運用管理の問題について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた問題に対し,どのような運用管理面の施策を立案し,事業所のシステム担当者を指導・支援したか。工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた指導・支援について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H17:2005
【SM-H17-1-PM2-Q1】システム障害の再発防止策について
今日では,情報システムの障害発生が,企業や官公庁の基幹業務に多大な影響を与える可能性が高くなっている。このような状況を踏まえて,障害発生時には,まず障害からの迅速な復旧を図る。その後,発生した障害の根本原因を究明し,再発防止策を検討して実施することが重要である。
システム管理エンジニアとしては,運用上の仕組み,運用手順,関係者間の情報伝達方法など,システム運用面からの再発防止策を講じる必要がある。例えば,システムを確実に運用するために,運用手順の作成時に,同様なシステム運用の経験をもつエンジニアに参加してもらいレビューを行うことや,作業結果を確実に確認するために,目視確認からツールによる自動確認に変更することなどが考えられる。
システム運用面からの再発防止策は,次の手順に従って関係者と協議し,実施が決定される。
(1) 障害発生時に特定された直接的な原因の背景にある根本原因を究明する。
(2) 根本原因を取り除くための対策案を,システム運用面から幾つか列挙する。
(3) 列挙された対策案に対し,費用対効果,体制面などから採否を決定する。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,発生したシステム障害の概要及び業務への影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた障害に対し,究明された障害発生の根本原因は何か。また,その根本原因を取り除くために検討した,システム運用面からの再発防止策は何か。さらに,それらの採否をどのように決定したか。工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた再発防止策について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H17-1-PM2-Q2】ヘルプデスクのサービスの拡大について
情報システム及びその利用者が多様化している中で,ヘルプデスクの利便性を高めて利用者の満足度の向上を図るためには,システム利用に関する問合せへの対応が中心であった従来のサービスに加えて,ヘルプデスクのサービスの拡大が必要になることがある。
拡大するサービスとしては,開発部門や運用部門などの関連部門と連携して,システム設定を変更する,システム機能の改善要望を受け付ける,機器を修理する,利用者権限を変更するなどの窓口業務を行うことが挙げられる。また,それらの対応状況やシステム運用に関する情報を,システム利用者に提供することも重要になる。
このようなサービスを実現するためには,システム管理エンジニアは,例えば次のような事項について検討し,関連部門を含めた業務効率を考慮して適切な方策を立案し,実施する必要がある。
(1)関連部門と連携した処理及び管理のプロセス
(2)ヘルプデスクと関連部門の役割分担
(3)関連部門に蓄積された,問題の解決や回避に関するノウハウの共有
(4)システム運用に関する情報の収集及び提供の仕組み
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったヘルプデスクの概要(サービス,利用者,体制など)と,関連部門と連携して拡大したサービスの概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたヘルプデスクのサービスの拡大を実現するために検討した事項を列記せよ。また,その中で,あなたが特に重要と考えた検討事項を具体的に述べ,それに対する方策について,工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方策について,どのように評価しているか。今後の改善点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H17-1-PM2-Q3】情報漏えいに関する対策について
情報システムの利用範囲が広くなるにつれて,情報システムで取り扱う情報の中に,個人情報や企業の機密情報が多く含まれるようになってきている。このような情報が社外に漏えいすると,企業の存続にもかかわる大きな問題になる可能性がある。
システム管理エンジニアには,このような機密性の高い情報に対して,システムの物理面,管理面及び技術面から漏えいを防止するための対策と,漏えいした場合の損害を最小限に食い止めるための対策の検討が求められる。
情報漏えいに関する対策を検討する際には,関係部門とともに,機密性の高い情報を特定し,その漏えいリスクを明確にする必要がある。
その上で,漏えいを防止するために,物理面からは,入退室者の厳格な本人確認や外部記憶媒体の持込み・持出し制限などを検討する。管理面からは,相互チェックの仕組みやアクセス権限の適切な更新などを検討する。また,技術面からは,アクセス範囲の限定や外部記憶媒体への情報書込み制限の仕組みなどを検討する。
漏えいした場合の損害を最小限に食い止めるには,漏えいの事実を早期に把握して,迅速に対応することが求められる。そのためには,情報システムへのアクセスログの継続的な取得及びその評価の仕組み,関係部門と連携した漏えい時の対応体制や対応プロセスなどの確立が重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,機密性の高い情報の概要及びその情報が漏えいした場合の影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報について,関係部門と協力してどのような方法で漏えいリスクを明確にしたか。その上で,漏えいを防止するための対策,及び漏えいした場合の損害を最小限に食い止めるため講じた対策について,工夫した点を中心に,具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策について,どのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H16:2004
【SM-H16-1-PM2-Q1】情報システムにおけるサービスレベルについて
近年は,企業の内外を問わず,情報システム部門の提供するサービスの品質を数値化した,いわゆるサービスレベルが運用業務の実施内容の評価指標として活用される傾向にある。
システム管理エンジニアがユーザと合意の上で設定するサービスレベルの項目としては,例えば次のようなものがあり,それぞれの基準値も合意しておく必要がある。
・オンラインサービスの提供時間
・情報処理作業依頼の受付からアウトプットの納品までの時間
・障害復旧時間
・ヘルプデスクへの問合せに対する応答時間
システム管理エンジニアは,サービスレベルの維持に責任があり,状況を監視しておくことが必要である。サービスレベルの基準値と実測値とがかい離している場合は,状況を分析の上,対策を立案し実施しなければならない。また,サービスレベルの維持状況についてユーザに説明・報告し,ユーザからの評価を確認することも重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムにかかわるサービスの概要と,重要と考えたサービスレベルの項目の設定理由と基準値について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたサービスレベルについて,その維持のためにどのような方策を講じたか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたサービスレベル維持のための方策をどのように評価しているか。今後の課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H16-1-PM2-Q2】運用業務のアウトソーシングに向けた移行計画の立案について
情報システムの運用業務の全体又は一部を外部に委託する,いわゆるアウトソーシングが広く行われている。システム管理エンジニアは,運用業務のアウトソーシングへの移行に際し,中心的役割を期待される。
運用業務のアウトソーシングへの移行では,対象業務,サービス内容,責任分担を事前に明確にした上で,移行計画の立案,移行の準備と実施,移行後のフォローを行う。アウトソーシングへ円滑に移行するためには,適切な移行計画を立案することが重要である。
移行計画の立案作業において,委託側のシステム管理エンジニアと受託側のシステム管理エンジニアは,次のような事項について協議し,合意する必要がある。
・システム運用に関する用語や考え方,運用ルール
・ユーザへの対応窓口,障害発生時の対応などの運用体制
・移行手順,移行時のサービスレベルなどを含めた移行作業の実施方法
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,アウトソーシングの目的及び対象となった運用業務の概要について,あなたの立場(委託側か受託側か)を明確にした上で,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたアウトソーシングへの移行に際し,移行計画の立案作業の中で重視した事項に関して,重視した理由及び相手側のシステム管理エンジニアと協議し,合意した内容について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた移行計画をどのように評価しているか。実施結果を踏まえ,簡潔に述べよ。
【SM-H16-1-PM2-Q3】情報システム障害の切分けについて
情報システムに障害が発生した場合は,利用者への影響を最小限に抑えるために,システムを早期に復旧しなければならない。障害発生時には,障害の検知,障害の切分け,復旧処理の実施など一連の障害対応を行うことになる。早期復旧に向けて適切な対応を行うためには,障害の切分けを的確に行うことが重要である。
障害発生時は,障害対応マニュアルに定められた切分け手順に従って障害箇所の特定を行う。しかし,障害対応マニュアルの手順では切分けができなかった場合,システム管理エンジニアは,関係者を招集し,障害状況の分析などの作業を統括して障害箇所の特定を行わなければならない。
切分けに当たっては,システムの特徴を踏まえて,次のような調査を行いながら状況を分析し障害箇所を絞り込んでいくことが必要である。
・障害事象と機器構成との関連を調べる。
・障害事象とソフトウェア構成との関連を調べる。
・障害事象を時系列に整理し事象間の関係を調べる。
・発生した障害事象と類似する過去の障害事象を調べる。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムの概要と,障害対応マニュアルに定められた切分け手順では切分けができなかった障害について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた障害の切分けについて,どのように作業を統括し,どのような方法で切分けを行ったか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた障害の切分けをどのように評価しているか。今後の改善点は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H15:2003
【SM-H15-1-PM2-Q1】情報システムの運用効率向上について
情報システムは,業務の拡大や変更によって大規模化・複雑化する傾向にある。大規模化・複雑化したシステムを運用するためには,より多くのハードウェア,ソフトウェア,施設,要員などの運用資源が必要となる。このように増大する運用資源要求に対して経済性を追及していくために,システム管理エンジニアは継続的に運用効率向上を図る必要がある。
運用効率向上のための改善プロセスは,関連部門と協力しながら,例えば次のように進められる。
① 運用資源の稼働状況を定量的に分析し,改善点を明確にする。
② 運用資源の低減又は活用の目標値を定め,施策を立案する。
③ 施策を実施する。
④ 施策及び実施結果を評価する。
運用効率向上の施策としては,運用体制の改善,運用スケジュールの見直し,システム構成の見直し,新技術の導入などがある。
施策の立案及び実施に当たっては,安全性・安定性の確保も十分考慮する必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが運用効率向上の対象とした情報システムと運用の概要,及び運用効率向上に着手した理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた情報システムにおいて,運用効率向上のためにどのようにして運用資源の稼働状況を分析したか。その結果としてどのような施策を実施したか。それぞれ工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
運用効率向上の施策及び実施結果をどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H15-1-PM2-Q2】セキュリティ侵害への対応策について
外部と接続された企業内ネットワークシステムにおいては,外部からの不正アクセスやウイルスなどによるセキュリティ侵害への対応策が不可欠となっている。このため,業務の特徴や重要性を踏まえて,システム面及び運用管理面からセキュリティ侵害への効果的な対応策を講じておく必要がある。
システム面の対応策としては,外部からの不正アクセスを防止するためのハードウェア・ソフトウェアの導入や,ウイルス感染を防止するためのソフトウェアの導入などがある。
運用管理面の対応策としては,外部からの不正アクセス状況の監視,ウイルス対策ソフトウェアの最新バージョンへの更新,セキュリティパッチの適用など,適切な予防措置を講じることが重要である。また,不正アクセスやウイルス感染などが発生した場合の連絡体制,対応手順など,異常事態発生時の対応策についても明確にしておく必要がある。
あわせて,ユーザに対して,セキュリティに対する意識を高めるための教育・指導や,運用ルール遵守の徹底なども重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったネットワークシステムの概要と,セキュリティ侵害へのシステム面での対応策の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム面の対応策に加えて,業務の特徴や重要性を踏まえ,運用管理面ではどのような対応策を実施したか。理由とともに,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対応策及び実施結果をどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H15-1-PM2-Q3】コンピュータ室の施設管理について
分散処理の進展によって,専用のコンピュータ室だけでなく,オフィスの一角にコンピュータ室を作り,情報システム機器を設置する形態も多くなってきた。また,設置機器も大型汎用機からパソコンサーバまで多様化してきている。
このような環境において,頻繁に発生する情報システム機器の新設・増設・更新の要求に的確に対応するため,システム管理エンジニアには,コンピュータ室の施設使用状況を把握し,計画的に施設管理を行うことが要求される。
コンピュータ室の施設使用状況としては,
・スペースについては,機器レイアウトや占有容積
・電源や空調については,各設備機器の能力や使用状況
・通信設備については,回線の接続系統や回線の収容能力
などを把握する必要がある。
加えて,機器の新設・増設・更新・撤去に関する情報を早期に収集し,現状の施設使用状況や設置基準に照らし合わせて,施設の収容限界を予測することや施設計画を立案することが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムにおける情報システム機器の概要と,コンピュータ室の施設の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたコンピュータ室において,機器の新設・増設・更新の要求に的確に対応するために,施設管理をどのように行っているか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたコンピュータ室の施設管理をどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H14:2002
【SM-H14-1-PM2-Q1】ヘルプデスクの運営について
昨今の情報システムにおいて,ヘルプデスクは企業内利用者へのサポート窓口や,顧客サービスにおける第一線の窓口として重要な役割を担うようになってきた。また,利用者が初心者からベテランまで広範であること,情報技術の変化が激しいこと,対象とするシステムが複雑になってきたことなどによって,ヘルプデスクにはきめ細かな対応が要求されている。
このような状況において,利用者に対して迅速かつ的確なサポートを行うためには,
・よくある質問とその回答集(FAQ)
・利用者ごとの属性
・利用者ごとの対応履歴
などを蓄積したデータベースを構築し,ヘルプデスク内で共有することが重要である。
また,情報技術や対象とするシステムについて最新の知識の習得,問合せ内容を正確に聞き出すインタビューテクニックや,ユーザのレベルに応じて的確に説明を行えるスキルの習得など,ヘルプデスク要員に適切な教育を行う必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたがかかわったヘルプデスクの概要と,あなたの役割及びヘルプデスク利用者の特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アを踏まえて,ヘルプデスクの運営における課題とその対応策について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対応策をどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H14-1-PM2-Q2】パソコンの管理について
文書の作成や交換,業務システムへの接続,電子メールの利用など,企業内ネットワークでのパソコンの活用が進むに伴い,機種,接続形態,利用するソフトウェアなどが多岐にわたるとともに,その台数も急激に増加している。
このため,パソコンの導入時や利用時における管理が的確に行われないと,データ交換ができない,セキュリティが確保できないなど,業務運営に支障を来すことになる。
システム管理エンジニアは,標準的なパソコンの使用,搭載するソフトウェア仕様などを規定した導入ガイドラインを作成しておくことが必要となる。このガイドラインに基づいて導入したパソコンに対して,ネットワークアドレス管理,ソフトウェアライセンス管理,物品管理など,パソコンに関する様々な管理の仕組みを確立し,関係部署に周知徹底することが重要となる。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが管理の対象としたパソコンの用途,接続形態,接続されているネットワーク規模などのシステムの概要と,パソコン管理の必要性について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムのパソコン管理において,どのような問題が発生し,それをどのように解決したか。管理の仕組みと工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
現在の管理の仕組みをどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H14-1-PM2-Q3】24時間連続サービスを提供するオンラインシステムの運用について
インターネット利用の拡大やシステムのグローバル化によって,24時間連続してサービスを提供するオンラインシステムが増加している。
こうしたシステムでは,従来のように夜間や休日にサービスを停止して,データバックアップ,バッチ処理,プログラムリリース,ハードウェア保守などを行うことが容易にはできないので,運用面において特別な考慮や工夫が必要とされる。
したがって,システム管理エンジニアは24時間連続サービスを提供するために,システム設計時に,システム構成や処理方式などの技術的検討を行うとともに,運用基準,運用方式,運用体制,障害対応などを十分考慮して運用設計を行うことが重要である。
また,運用時においても,運用監視,障害時の連絡,ユーザ支援などに特別な工夫が必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの構成,処理方式などの概要と,24時間連続サービスを必要とした背景について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムにおいて,24時間連続サービスを提供するために,システム設計時に運用設計上どのような工夫をしたか。また,運用時にはどのような工夫をしたか。それぞれ具体的に述べよ。
■設問ウ
現在のシステムをどのように評価しているか。また今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H13:2001
【SM-H13-1-PM2-Q1】ネットワークの変更について
営業所や支店の統廃合や拡張,業務態勢や組織の変更,新しい通信技術やハードウェアの導入などに伴い,ネットワークに対する様々な変更要求が頻繁に発生する。
一方,ネットワークは,情報システムのかなめとなってきており,ネットワークの停止が情報システム全体に大きな影響を及ぼすことも考えられる。したがって,ネットワークの変更は,確実に行うことが必要である。
このためには,ハードウェア,通信回線,ソフトウェアなどのネットワーク資源に関する物理構成,論理構成,バージョン,過去の変更履歴などの情報を適切に管理しておくとともに,ネットワークの変更においては,これらの情報を十分に活用することが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった情報システムのネットワークの概要と,ネットワークの変更を確実に行うために重点的に管理したネットワーク資源について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたネットワーク資源に関する情報の管理と,ネットワークの変更におけるその情報の活用について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
ネットワーク資源に関する情報の管理について今後改善したいことは何か。ネットワークの変更の視点から簡潔に述べよ。
【SM-H13-1-PM2-Q2】システム移行のリハーサルについて
円滑なシステム移行を行うため,本番移行前にシステム移行のリハーサル(システム移行テスト)を行うことが必要となる。
システム移行テストに当たっては,テスト計画の作成段階から,運用部門,開発部門,ユーザ部門との役割分担や体制を明確にしておかなければならない。
テスト計画の作成においては,業務処理やシステム構成などを十分理解したうえで,移行のために準備した移行用プログラムや移行手順,データの移行結果,移行処理時間などの検証対象を明確にするとともに,その評価基準を設定しておくことが重要である。
また,テスト実施後,評価基準に基づいて的確に評価を行い,発見された問題点に対しては,システムの本番移行前に確実に解決するよう対策を講じる必要がある。この際,システム機能,移行用プログラムなど開発にかかわる問題については,開発部門に改善を申し入れなければならない。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった移行対象システムと,システム移行の概要及び特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムのシステム移行テストに関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 運用部門,開発部門,ユーザ部門との役割分担及び体制
② 検証対象とその評価基準
③ テスト実施後,発見された問題点とその対策
■設問ウ
システムの本番移行結果から見て,あなたは設問イで述べたシステム移行テストをどのように評価しているか。簡潔に述べよ。
【SM-H13-1-PM2-Q3】システム管理業務の見直しについて
システムを安定的かつ効率的に運用するために,システムの資源管理,障害管理,セキュリティ管理,性能管理など多岐にわたるシステム管理業務がある。
一方,システムの運用環境は,業務機能の変更や追加,利用量の増加,新しい情報技術の採用やシステム形態の変更,機器構成の変更など,時間の経過とともに変化する。このような運用環境の変化に合わせて,システム管理業務を見直し,適切な改善を図ることが必要となる。
見直しに当たっては,サービス水準,運用コスト,運用要員数など,様々な制約条件を考慮することが重要となる。また,改善策によっては利用者への影響もあるので,改善策の周知や理解を得るための事前の調整も行うことも必要となる。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要と,システム管理業務を見直す要因となった運用環境の変化について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アを踏まえ,システム管理業務の見直しに関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 対象としたシステム管理業務
② 考慮した制約条件
③ 改善策と実施に当たって工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた改善策と工夫した点についてどのように評価しているか。簡潔に述べよ。
📗H12:2000
【SM-H12-1-PM2-Q1】障害の未然防止について
システム運用においては,多種多様な障害が発生する。これらの障害を未然に防止することは,発生した障害に対する再発防止策の実施と共に障害管理の重要な業務である。
障害の未然防止策には,予防保守,確実な操作の徹底,設備や機器の二重化などがあるが,システム運用管理エンジニアとしては,投資効果を踏まえた対策を選択する必要がある。
このために,システム構成上の特徴に応じた管理対象を定め,それらの稼働状況や障害発生傾向について把握,分析する手段と体制を確立し,分析結果に基づく未然防止策を実施しなければならない。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要とシステム構成上の特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムにおける障害の未然防止に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 未然防止のための主要な管理対象とそれを選んだ理由
② ①で選んだ主要な管理対象について,稼働状況や障害発生傾向の把握及び分析を行う手順と体制
③ ②の結果として実施した障害の未然防止策
■設問ウ
設問イで述べた障害の未然防止策の実施後,障害の発生にどのような変化が見られたか。簡潔に述べよ。
【SM-H12-1-PM2-Q2】開発環境の運用管理について
開発業務を効率的に行うために開発環境を整備し,適切に運用管理することは,システム運用管理エンジニアの重要な業務である。
特に本番環境と開発環境が同一のコンピュータ上で稼働していたり,磁気ディスク装置,印刷装置,端末,ネットワークなどを共有しているような環境では,本番業務に影響を与えないように,的確な方策を講じ,厳正に管理することが必要である。
こうした環境での運用管理業務の例としては,次のようなものがある。
(1)テスト実施後に開発環境を本番環境に復元すること
(2)本番環境と開発環境が共有する資源の使用スケジュールを調整すること
(3)本番用ライブラリと開発用ライブラリを区分けすること
また,このような運用管理業務を適切に実施するためには,開発部門との役割分担を明確にしておくことも必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった開発環境の概要,及び本番環境とのかかわりについて,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた開発環境の運用管理に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 本番環境に影響を与えると考えた問題点
② その問題点を解消するために実施した対策と工夫点
■設問ウ
設問イで述べた運用管理の対策をあなたはどのように評価しているか。また課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H12-1-PM2-Q3】開発プロジェクトへの運用部門の参画について
円滑で効率的なシステム運用を実現するためには,運用部門が開発プロジェクトに参画することが必要である。
開発プロジェクトに参画するシステム運用管理エンジニアは,運用面から見たシステム構成に関する提案や,運用管理機能の実装などを,開発プロジェクトに強く働きかけていくことが重要である。そのために,運用標準の提示,運用面からのシステム設計のレビュー,性能テスト結果の検証,システム移行方法の立案などを積極的に行う必要がある。
また,運用部門は,開発プロジェクトと密接な連携をとりながら,円滑な本番開始に向けて,事前に適切な運用準備を行う必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった開発対象システムと開発プロジェクト体制の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた開発プロジェクトにおいて,あなたが果たした役割に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① あなたがその開発プロジェクトで果たした役割と実施した内容
② ①で述べた活動をもとに,本番開始に向けて,事前に運用部門で実施した内容
■設問ウ
設問イで述べた開発プロジェクトへの参画をどのように評価しているか。また課題は何か。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H11:1999
【SM-H11-1-PM2-Q1】システム運用のアウトソーシングについて
近年,単なるオペレーション委託ではなく,運用業務を包括的に外部の専門企業に委託するアウトソーシングの事例が多くなってきている。
アウトソーシングは通常,次のような目的をもって実施されている。
・システム運用の効率化
・サービスレベルの向上
・システムの安定運用
システム運用管理エンジニアは,システムのアウトソーシングの目的を達成するために,アウトソーシングの業務内容,範囲,特性を考慮した適切な施策を講じることが重要である。
あなたのアウトソーシングを委託又は受託した経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
アウトソーシングの対象となったシステムの概要と運用体制及びあなたの立場(委託又は受託)について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムのアウトソーシングに関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 委託又は受託した業務内容と範囲
② アウトソーシングの目的
③ その目的を達成するための施策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた施策と工夫についてどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H11-1-PM2-Q2】システムの運用にかかわるコスト削減について
システムの運用において,新規投資の抑制,経費の削減など,様々な形でコストの削減が求められている。
運用部門としては,コンピュータ機器や設備,ネットワーク,運用要員,電力や消耗品など,コスト項目を洗い出し,積極的にコスト削減を行うことが重要である。
コスト削減施策の検討に当たっては,システム開発側とも協力して,システムの安定稼動に十分に配慮し,ハードウェアの適正化,消耗品の見直し,要員の削減などの適切な施策を実施することが必要である。
また,コスト削減施策によっては,利用者の理解と協力も必要となり,利用者に対する事前の調整が重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要と運用体制について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの運用にかかわるコスト削減に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 運用部門で実施できるコスト削減項目
② 利用者の理解と協力によって実施できるコスト削減項目
③ 実施したコスト削減施策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた施策と工夫についてどのように評価しているか。また,今後どのような追加施策を考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H11-1-PM2-Q3】ヘルプデスクの運営について
インターネット,イントラネット,エンドユーザコンピューティングなどの普及に伴い,システムの利用に関する相談窓口としてのヘルプデスクの重要性が増大してきている。
ヘルプデスクの運営に当たっては,回答の迅速さ,回答の的確さ,サービスの範囲などについて,利用者が満足しているかどうかを常に把握し,ユーザ満足度の維持・向上のための適切な施策を講じることが重要である。
また,経費や人員など,運営上の制約も多くあり,効率的な運営を心がけることも必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたがかかわったヘルプデスクについて,サービス内容,利用者数,運営体制などを,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたヘルプデスクに関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 重視したユーザ満足度の項目
② ユーザ満足度を維持・向上させるための施策と工夫した点
③ 効率的な運営のための施策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた施策と工夫についてどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H10:1998
【SM-H10-1-PM2-Q1】分散システムの障害対応について
ダウンサイジングの進展,イントラネットやエクストラネットの普及などによって,ワークステーションやパソコンを活用した分散システムが増えてきている。
分散システムの運用管理においては,多くの点でホスト集中型のシステムの場合とは異なった対応が必要となる。特に障害に関しては,
・マルチベンダ構成となっているので,障害の切分けに時間がかかる。
・機器や運用場所が分散しているので,障害の回復処理が複雑となる。
・分散サイトにはシステムに詳しい要員がいないので,的確な障害対応は期待できない。
などの分散システム特有の問題点がある。
したがって,障害時の業務への影響の極小化や回復時間の短縮など障害対応上の要件と,分散システム特有の問題点とを十分に把握し,運用管理面からの適切な方策を講じておくことが重要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった分散システムの概要と運用体制について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた分散システムの障害対応に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 障害時の業務への影響と障害対応上の要件
② その要件を実現するに当たって,課題となった分散システム特有の問題点
③ 前述の問題点を解決するために実施した運用管理上の方策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた方策についてどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H10-1-PM2-Q2】分散システムの構成管理について
分散システムの運用においては,
・システム構成が複雑で,構成要素が多種多様である。
・構成要素の管理対象が広域にわたり散在している。
・ユーザが構成要素を勝手に変更してしまうことがある。
などの理由で,障害発生時の対応やシステム構成の変更などが難しくなることが多い。
したがって,ハードウェアの型式,ソフトウェアのバージョン,ネットワークのアドレス情報など,構成要素についての情報を,適切に管理することが重要である。
このためには,運用管理基準の明確化,管理ツールの効果的な活用,正確な構成情報の把握などの施策が必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった分散システムの概要と構成について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた分散システムの構成管理に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 構成管理の対象として重要と考えた構成要素とその理由
② その構成要素を管理する上での問題点
③ 前述の問題点を解決するために実施した方策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた方策についてどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H10-1-PM2-Q3】システム運用におけるユーザ対応について
コンピュータシステムやネットワークが複雑化・多様化するにつれて,システム運用におけるユーザ対応業務の内容も幅広くなってきている。
ユーザ対応業務の内容としては,
・ユーザの管理(IDやパスワードの発行,電子メールアドレスの管理など)
・ユーザの支援(利用に関する問い合わせ,ユーザ教育・指導など)
・ユーザ部門との調整(バッチ処理のスケジュール調整,オンライン時間の変更調整など)
などが挙げられる。
システム運用管理エンジニアは,こうしたユーザ対応を的確かつ効率的に行うため,業務の分担,ユーザとの連絡方法,運用ルールの整備,ツールの準備などにおいて,さまざまな工夫をする必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要とユーザ対応の体制について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムのユーザ対応に関する次の事項について,具体的に述べよ。
① ユーザ対応の業務内容
② ユーザ対応を効率的に行う上での問題点
③ 前述の問題点を解決するために実施した方策と工夫した点
■設問ウ
設問イで述べた方策についてどのように評価しているか。また,今後どのような改善が必要と考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
📗H09:1997
【SM-H09-1-PM2-Q1】システムの障害対応について
コンピュータシステムの運用においては,障害が発生したときの一次対応を迅速・的確に行うことが,利用者への影響を最小限にとどめ,その後の回復処理や原因究明を円滑に行うために重要である。
このため,システム運用管理エンジニアは,システムを構成するハードウェアやソフトウェアなどの障害の検知,その障害が業務に与える影響度の把握,関係者への連絡,システムの回復や原因究明に必要となる障害情報の収集など,障害時の一次対応手順や方法を確立しておく必要がある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要と,障害が発生した場合の利用者への影響など,障害に対応するうえでの特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた特徴を踏まえ,障害の一次対応に関する次の事項について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
① 障害検知の仕組み
② システム回復や原因究明に必要な情報とその収集方法
③ ハードウェアやソフトウェアの障害など,障害に応じた関係者への連絡体制とその連絡方法
■設問ウ
障害の一次対応に関する今後の改善課題は何か。またその課題をどのように解決しようと考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
【SM-H09-1-PM2-Q2】システム運用におけるキャパシティ管理について
システムのキャパシティ管理は,システムを安定稼働させるために重要な業務である。システムリソースの不足による危機的事態を回避するためには,システム負荷状況の把握と分析,将来のシステムリソースの使用予測を行うとともに,それらの結果をシステムリソース増強計画に的確に反映させるための手順を確立しておく必要がある。
キャパシティ管理のための監視対象としては,CPU,メモリ,ディスク,チャネル,回線の使用率などがあるが,それらのシステムリソースの使用状況が複合的に関係しながらシステムの限界に達することもあり,多面的な分析を行うことが必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要と,キャパシティ管理の対象となるシステムリソースの使用上の特性について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた特性を踏まえ,キャパシティ管理に関する次の事項について,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
① キャパシティ管理の対象とするデータの選定根拠と収集手順
② システムリソースの負荷状況を把握するうえでの分析・評価の方法
③ ②の評価の結果から発見される問題点への対応手順
■設問ウ
あなたは将来のシステムリソースの使用予測を,どのように行っているか。また,その予測をシステムリソース増強計画にどのように反映させているか。簡潔に述べよ。
【SM-H09-1-PM2-Q3】運用支援システムの効果的利用について
運用支援システムは,多様化・複雑化するシステム運用業務における省力化,正確性・迅速性向上などを目的として利用される。
運用支援システムの導入に当たっては,業務システムの規模や業務量,ハードウェア,基本ソフトウェア及び運用体制など,センタや分散サイトの運用環境を考慮して,適切なソフトウェアパッケージや自動化機器の選択を行う必要がある。
しかし,これらの運用環境は変化するので,運用支援システムの継続的改善を行い,効果的利用を図ることが大切である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった業務システムの概要と,運用支援システムの導入目的及び概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた運用支援システムに関する次の事項について,具体的に述べよ。
① 導入後に生じた運用環境の変化
② 変化に起因する利用上の問題点
③ 問題点を解決するために工夫した方策とその評価
■設問ウ
あなたは,今後,予想される運用環境の変化に対して運用支援システムをどのように改善しようと考えているか。簡潔に述べよ。
📗H08:1996
【SM-H08-1-PM2-Q1】システム運用におけるコスト管理について
システム運用におけるコスト管理においては,効率的にコストをかけているか,ユーザに適切に配賦されているかを把握するとともに,配賦基準に関する情報を開示して,ユーザ部門の十分な理解を得られるようにしておくことが重要である。
このようなコスト管理を通じて,運用におけるコスト対効果を高める努力が必要となる。このためには,稼働率の低い機器の他の機器への統合及び撤去,消耗品などの単価の見直しや消費量の削減など,無駄なコストを削減するといった方策が考えられる。同時に,運用支援ソフトや自動化機器の導入,機器のリプレース,レンタルやリースなど機器の契約方法の見直しといった,短期的には投資を伴うが中長期的にはコスト対効果を高める方策についても十分検討する必要がある。また,配賦基準を調整することによってユーザ部門にコストの抑制を促すなどの方策もある。
こうした方策の検討に当たっては,サービス水準の維持を前提とすべきであるが,ユーザ部門と合意のうえで水準を落とすことが必要となる場合もある。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった運用部門の日常のコスト管理の概要とシステム運用コストの特性について,800字以内で述べよ。
■設問イ
コスト対効果を高めるためにどのような方策を実施し,どのような効果があったか。方策を検討する際に考慮した点とともに具体的に述べよ。
■設問ウ
今後発生すると考えられるコスト管理上の課題について,簡潔に述べよ。
【SM-H08-1-PM2-Q2】障害回復に備えた運用上の方策について
システムの障害は業務に多大な影響を与えるため,障害が発生した時にはシステムを迅速に復旧できるようにしておくことが重要となる。障害への迅速な対応と回復処理が正しく行われるようにするには,次のような運用上の方策が必要である。
・障害発生時の連絡ルートや責任者などの連絡体制の確立
・障害箇所の特定のための切分け手順の確立
・ハードウェア障害時の縮退,代替,切替えなどの回復手順の確立
・ソフトウェア障害時の修正,旧世代への戻しなどの回復手順の確立
・データベースのバックアップと回復手順の確立
・ソフトウェアのバージョンや更新履歴の管理方法の確立
このような方策の立案に当たっては,システム開発担当者などの協力を得て,システム全般にわたった検討を行うことが重要である。また,回復手順の訓練,データベースの保存など,日常業務における着実な実行を管理することも必要である。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要と信頼性に関する特徴について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムにおいて,障害回復を迅速に行うために重要と考えた運用上の課題は何か。それに対してどのような方策を行ったか,工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方策について,あなたはどのように評価しているか。また,今後の改善をどのように考えているか。それぞれについて簡潔に述べよ。
【SM-H08-1-PM2-Q3】システム運用要員の育成について
システム運用部門を取り巻く環境は,情報システム技術の著しい進歩によって大きく変化しており,システム運用要員に求められる知識や行うべき業務内容も変化しつつある。例えば,クライアントサーバ型システムに代表される分散システムの普及によって,様々な分散機器に対する幅広い知識や,ユーザ部門との密接な連携などが必要となってきている。
このため,従来からの知識,技術,能力だけでは円滑なシステム運用が困難であり,運用環境の変化に対応したシステム運用要員の育成が求められる。
システム運用要員の育成に当たっては,運用対象の適用業務についての知識や異常時の処置を含む運用の基本的な技術は当然のこと,新しい情報システム技術の修得,コミュニケーションや問題発見のための能力などについても十分に考慮しなければならない。
また,適切な育成カリキュラムの設定,指導体制の整備,日常業務を遂行しながらのOJTの着実な実施などが必要である。更に,企業の人材育成体系と部門独自の育成体系との効果的な組合せや,各種外部機関の活用なども考慮すべきである。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが所属したシステム運用部門の概要と特徴および最近の運用環境の変化について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた運用環境の変化に対して,システム運用要員に求められる知識,技術,能力はどのように変わってきたか。これらの修得,向上のためにどのような方策を採ったか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた方策についてどのように評価しているか。また,更なる改善のためにどのように考えているか。簡潔に述べよ。
📗H07:1995
【SM-H07-1-PM2-Q1】システムの運用におけるセキュリティ対策について
災害,システム障害,故意・過失による不正使用や改ざんなどから,人,施設,設備,ハードウェア,ソフトウェア,データ,ネットワーク,端末などを保護し,システムの安全かつ安定した稼動を保証するために,コンピュータセンタのセキュリティ対策を実施することはシステム運用上重要である。
セキュリティ対策には,システムの機能として組み込まれたパスワード,スクランブルなどの技術面での対策,コンピュータ室の入退室管理,防犯管理など管理面での対策,防犯設備,検知器,報知器など設備面での対策がある。特に管理面や設備面でのセキュリティ対策については,システム運用管理エンジニアが主体的に行うものである。
セキュリティ対策の実施に当たっては,システムの特徴や求められるセキュリティ要件,投資費用,コンピュータ室の運用のしやすさなどを考慮し,そのシステムにとって現実的な対応を行うことが望ましい。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要について,セキュリティ対策の視点から,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムに要求されている管理面や設備面でのセキュリティ要件で何が重要な点と考えたか,その理由は何か。また,それに対してどのような対策を実施したか。その対策についてどのように評価しているか。具体的に述べよ。
■設問ウ
そのシステムにおけるセキュリティ対策上の現在の課題は何か。そのためにどのような解決策を考えているか。簡潔に述べよ。
【SM-H07-1-PM2-Q2】システム運用のサービス基準について
情報システムの運用に当たっては,ユーザに提供するサービスの基準を設定し,それに基づいて業務を管理することが大切である。
サービス基準の項目には,ターンアラウンドタイム,応答時間,障害回復時間などがあり,その重要度と目標値はオンラインリアルタイム処理型,バッチ処理型といったシステムの運用形態や,システムが障害を起こしたときのユーザの業務に及ぼす影響の度合いなどによって様々である。
サービス基準を達成し,維持するためには,サービス基準の項目に対応した運用部門としての管理項目を設定し,それぞれの管理項目について,実績を把握し,目標値と比較・評価するなどの日常的な管理方法を確立しておくことが重要である。またそこから見いだされた問題に対しては,システム開発部門などとの連係も含めて,適切な措置を講じることが求められる。
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わったシステムの概要,並びにサービス基準の中で特に重点管理対象とした項目,その採用理由及び目標値について,800字以内で述べよ。
■設問イ
サービス基準を達成し,維持するために設問アで述べた重点管理項目について,あなたは日常どのような管理を実施したか。その管理を通じて実際に見いだされた問題とその原因は何か。また,どのような対策をとったか。具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対策について,あなたはどのように評価しているか。また,更なる改善のためにあなたが考えている対策は何か。それぞれについて簡潔に述べよ。
【SM-H07-1-PM2-Q3】分散システムの運用管理について
情報システムに対するニーズの多様化に伴い,エンドユーザのもとに設置されたワークステーション・パソコン・LANなどで構成されるクライアントサーバ型のシステムなど,ホスト系とは独立に処理・運用される分散システムが普及しつつある。
このような分散システムの運用には,マルチベンダから提供される多種多様なハードウェア及びソフトウェアが運用管理の対象となることや,運用の現場にシステム運用の専門家がいないことに加えて,運用支援ツールは発展途上にあるなど,分散システム固有の困難さが存在する。
したがって,従来のホスト集中型システムの運用管理手法はそのままでは分散システムには適用できない。例えば次のような課題を解決していくに当たっても,分散システムの特性を考慮する必要がある。
・ハードウェア及びソフトウェアの構成とその変更をどのように管理するか
・障害に迅速に対応でき,システムの停止時間を最小にするにはどうすべきか
・データベースのバックアップの取得など,定期的に行うべき作業の計画と実行管理をどのように行うか
・システムアドミニストレータの育成と配置など,ユーザ部門における運用体制の整備をどう進めるか
あなたの経験に基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
■設問ア
あなたが携わった分散システムについて,システムの構成と運用上の特徴を,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステムの運用上の特徴を踏まえて,あなたは分散システムの運用管理における主な課題は何であると考えたか。その課題を解決するためにどのような対策を実施したか。工夫した点を中心に具体的に述べよ。
■設問ウ
あなたの実施した対策はどのような効果があったと評価するか。また,残された課題は何か。簡潔に述べよ。