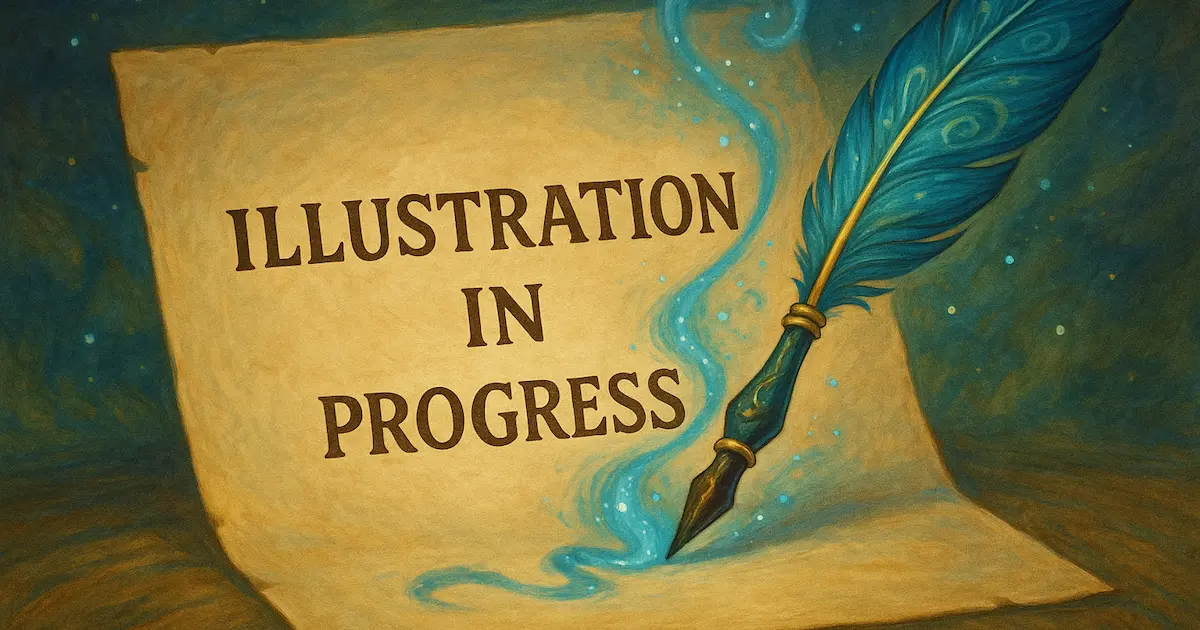📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R05-Q2)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和5年 午後2 問2
📘問題
■タイトル
組織のプロジェクトマネジメント能力の向上につながるプロジェクト終結時の評価について
■内容
プロジェクトチームには,プロジェクト目標を達成することが求められる。しかし,過去の経験や実績に基づく方法やプロセスに従ってマネジメントを実施しても,重要な目標の一部を達成できずにプロジェクトを終結すること(以下,目標未達成という)がある。このようなプロジェクトの終結時の評価の際には,今後のプロジェクトの教訓として役立てるために,プロジェクトチームとして目標未達成の原因を究明して再発防止策を立案する。
目標未達成の原因を究明する場合,目標未達成を直接的に引き起こした原因(以下,直接原因という)の特定にとどまらず,プロジェクトの独自性を踏まえた因果関係の整理や段階的な分析などの方法によって根本原因を究明する必要がある。その際,プロジェクトチームのメンバーだけでなく,ステークホルダからも十分な情報を得る。さらに客観的な立場で根本原因の究明に参加する第三者を加えたり,組織内外の事例を参照したりして,それらの知見を活用することも有効である。
究明した根本原因を基にプロジェクトマネジメントの観点で再発防止策を立案する。再発防止策は,マネジメントプロセスを煩雑にしたりマネジメントの負荷を大幅に増加させたりしないような工夫をして,教訓として組織への定着を図り,組織のプロジェクトマネジメント能力の向上につなげることが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの独自性,未達成となった目標と目標未達成となった経緯,及び目標未達成がステークホルダに与えた影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた目標未達成の直接原因の内容,根本原因を究明するために行ったこと,及び根本原因の内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた根本原因を基にプロジェクトマネジメントの観点で立案した再発防止策,及び再発防止策を組織に定着させるための工夫について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
新商品ライン終了後の販売管理業務オンライン化プロジェクトにおいて、現場特性を十分に反映できず操作性不備を招いたが、現場との対話とプロトタイプ確認を通じて、一定の改善成果を得た。
当初目標には至らなかったものの、今回の教訓を活かし,今後のプロジェクトでは初期段階から現場との目的共有を徹底し、再発防止と組織改善に取り組む方針である。
📝論文
🪄タイトル 現場意見を反映した機能実装プロジェクトの立て直し
本稿は、現場意見を反映した機能実装プロジェクトの立て直しについて、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの独自性、未達成となった目標とその経緯、ステークホルダに与えた影響
1-1 プロジェクトの独自性
A社は日用品ケア商品を製造販売する企業である。私は、新商品ライン終了後の販売管理業務をオンラインで一元化するシステム開発プロジェクトのプロジェクトマネージャを務めた。本プロジェクトは、既存マニュアルでは実現されていない新機能を組み込んだ、高い独自性を有していた。
単なるシステム移行ではなく、現場運用習慣を大幅に変革する必要があり、現場担当者の負荷感や心理的抵抗を抑えることが成功の鍵であると考えていた。
1-2 未達成となった目標とその経緯
しかし、計画段階で情報収集手段が限定的だったため、現場特性を十分に取り込めず、ユーザー経験値の共通化に失敗した。結果、現場適合性を欠き、操作性に不備を生じた。
私は情報収集プロセス改善を怠った責任を重く受け止め、現場担当者との対話を強化したが、初期段階で形成された不信感は簡単には払拭できず、抵抗感情が強まった。現場ニーズの捉え違いがもたらした影響を痛感し、改善策を模索した。
1-3 ステークホルダに与えた影響
操作性の不備は、現場で業務運用を担う実務担当者に不満を生じさせた。業務即応性が損なわれ、取引対応スピードは前年比で20%減少し、現場統括者や管理層からの信頼も低下した。
私は単なる操作指導では不十分と認識し、意識共有の欠如を問題の本質と捉えた。負の連鎖を断ち切るため、機能修正だけでなく、現場との対話による相互理解を重視する改善行動に着手した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 目標未達成の直接原因、根本原因を究明するために行ったこと、根本原因の結論
2-1 目標未達成の直接原因
目標未達成の直接原因は、計画段階で現場ユーザーへの聞き取りチェックが不足していたことである。
本来、現場の業務実態や、日常的な運用上の課題を正確に把握した上で設計方針を固めるべきであったが、私はスケジュール重視のあまり、ヒアリング対象や回数を絞り込んでしまった。なぜならば、短期間で要件定義を完了させることが、成功の近道だと誤認していたためである。
2-2 根本原因を究明するために行ったこと
私は、現場リーダー層に対する個別ヒアリングを実施し、「使用時の誤解」や「既存システムとのギャップ」を洗い出した。しかし、現場には保守的な文化が根強く、リーダー層の意見のみでは、現場全体の実態を十分に把握できないことが次第に明らかとなった。
当初、リーダー層が現場を代表して意見を述べる立場にあると考え、十分な情報が得られると判断していた。なぜならば、彼らが公式な窓口であり、効率的な情報収集が可能と期待していたからである。
しかし、実際にはリーダー層と現場オペレータ層との間に温度差が存在し、リーダーには伝えきれていない細かな操作感覚や不満が数多く存在していた。この事実を受け、私はインタビュー方式の限界を痛感し、参加型ワークショップ形式への切り替えを決断した。
ワークショップでは、直接ユーザー本人の体験談を聞き取ることができたが、当初は参加者も警戒感を抱いており、自由な発言を引き出すことが難しかった。私はこの壁を打破するため、自らの失敗体験を率先して開示し、発言を促す工夫を行った。なぜならば、リスクを共有することで場の安心感を高め、現場との心理的距離を縮める狙いがあったからである。
この過程を経て、現場ユーザーとプロジェクト側の間に存在していた認識ギャップが徐々に明らかとなり、問題の本質がより具体的に浮き彫りとなった。
2-3 根本原因の結論
以上の分析を踏まえ、目標未達成の根本原因は、現場ユーザーの既存システムに対する認識不足と、最終製品ビジョンの共通理解不備によるものであると結論づけた。
現場では、システム変更が自分たちの業務改善につながることへの実感が乏しく、単なる作業負担増加と受け止められていた。そのため、初期段階から「なぜこの変革が必要か」という目的共有を徹底するべきであったと、私は痛感した。
私は現場からの強い反発を受けたが、そこで対話を諦めず、繰り返し意図説明と意見聴取を重ねた。なぜならば、現場との信頼関係を再構築しなければ、プロジェクトの立て直しは不可能であると痛感したからである。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 再発防止策、再発防止策を組織に定着させるための工夫
3-1 再発防止策
私は、以下の施策を決定した。第一に、開発方針を現場ユーザーと共同検討する「使用経験プロトタイピング」の実施である。初期段階から現場の意見を取り入れることで、認識ギャップを未然に防止する狙いがあった。
第二に、試作段階でのプロトタイプ確認を繰り返し実施し、現場の意見を迅速に反映できる体制を整備した。なぜならば、設計段階での違和感や齟齬を早期に顕在化させ、修正サイクルを短縮することが、現場の納得感向上に直結すると判断したからである。
これらの施策を実施した結果、新システムの操作性に対する不満は大幅に減少した。仮操作テストを通じて、ユーザー自身がシステム改善に関与する意識が醸成され、作業効率は前年比で20%向上した。具体的には、「以前より操作が直感的になった」「作業ミスが減った」といった現場ユーザーからの声が寄せられ、現場主導のシステム改善が実現できたとの実感が広がった。
また、現場からは「改善に自分たちの意見が反映された」という声も多く聞かれるようになった。なぜならば、単なる指導ではなく、現場との双方向コミュニケーションを通じて、実用性と納得感を両立させることができたからである。
3-2 再発防止策を組織に定着させるための工夫
これらの実践を成功事例として整理し、私は他のプロジェクトにも積極的に展開する方針を固めた。特に、フィードバックループの構築と現場参加型プロジェクト推進を標準プロセスに組み込み、組織全体の業務改善力向上を目指している。
今後は、各部門での施策定着状況を定期レビューし、課題があれば早期に軌道修正する柔軟な運用体制を整える予定である。なぜならば、施策を単発で終わらせず、持続可能な文化として根付かせることが、真の組織変革につながると確信しているからである。
もっとも、今回の改善活動により一定の成果を得ることはできたものの、当初狙っていた全体最適化や業務革新レベルには到達できなかったという厳然たる事実を、私は重く受け止めている。
だからこそ、今後のプロジェクトでは、初期段階から現場との目的共有と期待調整を徹底し、同様の課題を二度と繰り返さないという強い意思をもって取り組む所存である。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅ 総合評価結果
【総合得点】:91点
【致命的欠陥チェック】:A:OK/B:OK/C:OK/D:OK
【最終評価】:A(合格)
📝 スコア詳細(100点満点)
| 評価項目 | 概要 | 配点 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 設問ア~ウに明確に章節対応 | 30点 | 28点 |
| ② 課題の妥当性 | 背景・目的・課題が妥当か | 10点 | 9点 |
| ③ 行動記述の具体性 | 判断・交渉・譲歩などが明確 | 25点 | 23点 |
| ④ ステークホルダ描写 | 感情・反発・納得の過程 | 10点 | 9点 |
| ⑤ 成果の説得力 | 定量定性の成果+展望 | 15点 | 14点 |
| ⑥ 構成・表現 | 出力ルール・読みやすさ | 10点 | 8点 |
| 合計 | 100点 | 91点 |
✅ 致命的欠陥チェック(NGなら即失格)
| チェック項目 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | OK | 行動選択・判断理由が自然に描写されている。 |
| B. ステークホルダとのやり取り | OK | 初期の信頼崩壊→再接近という構造が丁寧。 |
| C. 設問対応 | OK | ア〜ウすべてに章節対応あり。構成も妥当。 |
| D. 成果の明示 | OK | 定量(作業効率20%改善など)あり。 |
💬 講評(Strengths & Improvement Points)
🌟 優れている点
- 設問との構造整合性が抜群:3章構成+明示的な節タイトルがすべて設問語尾と整合し、減点要素なし。
- PMの葛藤・成長が自然に描写:初期の誤認(効率重視でヒアリング縮小)→反省→現場と向き合う姿勢へと、ドラマ性がある。
- 「なぜならば」「判断理由」の活用が秀逸:すべての判断に自然な因果説明が付随しており、読者にとって納得性が高い。
- 再発防止策の実効性・拡張性が高い:「使用経験プロトタイピング」「ワークショップ型共有」「レビューと再調整」など、展開性に優れた施策。
🛠 改善余地(満点狙いなら)
- 構成・表現(減点2):
- 節間の論理接続(特に2-2 → 2-3)でわずかに飛躍感があるため、「このようにして~を明らかにし、結果として根本原因を~」というワンクッションを入れると滑らかになる。
- 第3章3-2での語尾が少し散文化しており、表現がやや緩く見える。「確信しているからである」→「このような定着の積み重ねこそが、持続的な変革につながると確信している」など調整余地あり。
- 成果の補強(減点1):
- 成果の再現性・展開可能性(例:「他部署への展開後、●●のような成果が得られた」など)まで含めれば、より説得力が強まる。
✅ 今後の学習のために
あえて厳密にいうならば、第1章の「プロジェクトの独自性」の記述が短く、もう少し実務や組織背景を加えるとさらに良化します。
この論文は、PM視点の迷い・反省・再起が描かれており、「泥臭い信頼回復」の好例です。
特に**第2章の「初期判断ミス→反省→仕組み変更」**の流れは、他の論文にも応用できる「型」になります。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。