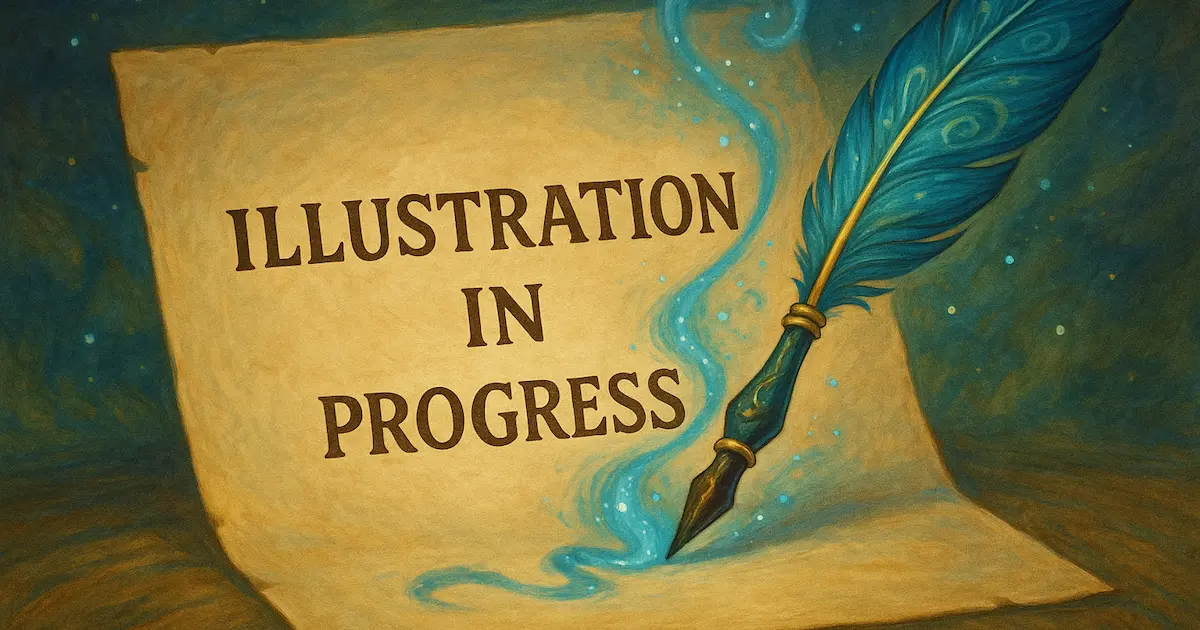📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R05-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和5年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)について
■内容
システム開発プロジェクトでは,プロジェクトの目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に,リスク,スコープ,ステークホルダ,プロジェクトチーム,コミュニケーションなどもプロジェクトマネジメントの対象として重要である。プロジェクトマネジメント計画を作成するに当たっては,これらの対象に関するマネジメントの方法としてマネジメントの役割,責任,組織,プロセスなどを定義する必要がある。
その際に,マネジメントの方法として定められた標準や過去に経験した事例を参照することは,プロジェクトマネジメント計画を作成する上で,効率が良くまた効果的である。しかし,個々のプロジェクトには,プロジェクトを取り巻く環境,スコープ定義の精度,ステークホルダの関与度や影響度,プロジェクトチームの成熟度やチームメンバーの構成,コミュニケーションの手段や頻度などに関して独自性がある。
システム開発プロジェクトを適切にマネジメントするためには,参照したマネジメントの方法を,個々のプロジェクトの独自性を考慮して修整し,プロジェクトマネジメント計画を作成することが求められる。
さらに,修整したマネジメントの方法の実行に際しては,修整の有効性をモニタリングし,その結果を評価して,必要に応じて対応する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの目標,その目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に重要と考えたプロジェクトマネジメントの対象,及び重要と考えた理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトマネジメントの対象のうち,マネジメントの方法を修整したものは何か。修整が必要と判断した理由,及び修整した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた修整したマネジメントの方法の実行に際して,修整の有効性をどのようにモニタリングしたか。モニタリングの結果とその評価,必要に応じて行った対応について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社の業務支援システム再構築プロジェクトで、営業部との認識齟齬によるリスク顕在化の兆候を受け、リスク・マネジメント方針を修整した。
📝論文
🪄タイトル リスク・マネジメントを重視した製造業の業務支援システム再構築
本稿では、リスク・マネジメントを重視した製造業のシステム業務支援システムの再構築について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの目標、時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象、およびその理由
1-1 プロジェクトの目標
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、紙おむつや生理用品、ペットケア製品などをグローバルに展開しているA社の業務支援システム(販売管理・在庫管理・請求処理など)の再構築プロジェクトである。
A社は業務拡大に伴い、古いシステムの老朽化や専門化が進んでいた。経営陣は、このままでは運用コスト増大や競争力低下といった経営リスクが高まる恐れがあったため、業務支援システムの根本的な見直しを決定した。
目標は、業務効率の向上とシステム維持管理コストの削減であり、標準パッケージの採用を原則とする基本方針として、カスタマイズを最小限に抑える方針で進められた。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
計画推進中、営業部から「現行の在庫調整機能がなく現場業務に支障が出るから、新パッケージでは業務ができない」という強い反対意見が上がった。これは部門間の認識齟齬に起因した誤解であった。このまま同様の反対意見が集まれば、目標達成が危ぶまれる。
私は、元々計画推進に先立ち、このような部門間誤解をリスクとして登録し、発生確率や影響度を分析していた。当初は標準レベルの管理で十分と見ていたが、営業部の強い反対を受け、リスクの顕在化可能性が高まったため、速やかに見直す必要があると判断した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
本節では、私が修整の必要性を強く感じた「リスク・マネジメント」について、行った修整内容について述べる。
私は下記の2つを修整して、重点管理することとした。なぜならば、元々リスク登録簿では本件のような内容を管理していたが、粒度が大きすぎていたからである。具体的には、営業部との間で発生したような小規模ながら重要な部分を管理するには大きすぎたのである。
①要件の誤解(要件の誤解により、カスタマイズ要求が多発するリスクが顕在化し、コスト・スケジュールに悪影響を及ぼす)
私は、リスク登録した内容のうち、まず「要件の誤解」としてリスクをブレークダウンして管理することにした。これは、営業部やほかの関係者との認識齟齬について、今後も頻出する可能性があり、重点管理するべきだと考えたからである。
具体的には、認識齟齬がプロジェクト推進に与える悪影響を分析することとした。次に、リスクの顕在化を低減するための対応策を考えることとした。
例えば、「要件認識を合わせるために、説明会を開く。説明会では、質疑応答の時間を設け、理解不足箇所をリストアップする。なお、現場からの疑問や不安を一つずつ丁寧に拾い上げ、標準機能で十分対応可能であることを納得してもらう。」「現行システムと次期システムのマッピングを、他部門メンバが納得できるレベルで詳細化する。」などで対応することを想定した。
②現場の声を拾い上げられない(現場の声を拾い上げられないことにより、現場とのコミュニケーションが悪化して信頼性を損なうリスクが顕在化し、チーム間の協調性に悪影響を及ぼす)
私は、次に「現場の声を拾い上げられない」としてリスクをブレークダウンして管理することにした。営業部からのクレームは、元々はメンバレベルの疑念や不安が発端と考えられた。この疑念や不安が早期に解決できなかったことにより、問題が増幅されたと私は判断した。
つまり、早期に疑念や不安を拾い上げ、早期に解決を図れば、リスクの顕在化による、プロジェクトへの悪影響は低減できるものと考えた。
具体的には、「現場に入り不満を直接ヒアリングする。」「小さな疑念や不安を早期に把握するために、匿名フィードバック系統を導入し、従業者からの直言を広く受け入れる体制を構築する。」などを検討した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
本節では、「リスク・マネジメント」に関する修整が有効だったかどうかを、どのようにモニタリング・評価し、必要な対応を行ったかについて述べる。
私は、定期的にリスクレビュー会議を開催し、登録リスクの発生状況を継続的にモニタリングした。結果は、下記のとおりである。
①要件の誤解
修整前と比較して、要件の誤解によるクレーム発生率は4割削減となった。これは十分な効果があったと判断できるものと私は評価した。
特に、クレームが少なくなることにより、重要なクレームに対して集中して対応することができ、能率的なプロジェクト運営に大きく寄与した。
営業部の部門長からは「システム部の対応により、新しいパッケージを誤解していた箇所について、営業部メンバ理解が促進できた。現行のシステムでは実現できなかったことが可能となることが分かり、システム刷新に向けて、前向きに取り組めるようになった。」と、ねぎらいの言葉があった。
したがって、リスクの顕在化を防止できただけでなく、ステークホルダの参画度・関与度に、プラスの効果を得ることができたと考えている。
②現場の声を拾い上げられない
修整前と比較して、現場の声を拾い上げられないことによる、後手対応は5割減少した。これは十分な効果があったと判断できるものと私は評価した。
特に、匿名フィードバックの仕組みを構築したことにより、現場メンバからリスク兆候時点での報告が増大し、リスク顕在化前のプロアクティブ(能動的対応)が行われるようになったことが大きいと考えている。
現場レベルのメンバからも、「意見を聞いてくれる」「気づきの時点で報告する習慣ができ、他の業務でもトラブルの発生確率が低減できた。」との声が上がった。
したがって、リスクの顕在化を防止できただけでなく、早期報告習慣の定着により、課題の潜在化を防ぎ、プロジェクト全体のリードタイム短縮に貢献するなど、プラスの効果を得られたと考えている。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合評価】
- 総合得点:88点
(設問対応:28/課題の妥当性:9/行動の具体性:22/ステークホルダ描写:9/成果の説得力:13/構成・表現:7) - 致命的欠陥チェック:
A: OK(PMの行動描写あり)
B: OK(ステークホルダとのやり取りあり)
C: OK(設問ア~ウに章節で明確に対応)
D: OK(成果の定量・定性明示あり) - 最終評価:A(合格)
📝【評価コメント】
🔹設問対応(28/30)
- 章構成は、設問ア:第1章、設問イ:第2章、設問ウ:第3章と完全準拠。
- 節構造も適切に設けられ、「修整の理由・内容」「モニタリング結果・対応」まで丁寧にカバーされている。
- 「PM_論文出力指示テンプレート.md」準拠の構成が徹底されており、設問への回答の「目的語」まで正確に反映。
🔹課題の妥当性(9/10)
- 「業務支援システムの老朽化・肥大化によるコスト増加と競争力低下」の背景が具体的かつ妥当。
- 「営業部との認識齟齬によるリスク」を顕在化させ、それに対しリスク・マネジメントを選定した判断が自然。
🔹行動記述の具体性(22/25)
- リスクを2種類にブレークダウンし、それぞれに具体的な対応策を取った行動は高評価。
- 特に、説明会開催/質疑応答/マッピング資料の精緻化などは実務的リアリティが高く、行動の説得力がある。
- ただし、「譲歩」や「対話失敗→再交渉→段階的合意」の描写がやや控えめで、この部分を厚くすれば満点圏も狙える。
🔹ステークホルダ描写(9/10)
- 営業部の反発と、最終的な理解・協力の変化が明示されており、対話の成果も伝わる。
- 匿名フィードバック導入による「現場の声の拾い上げ」の描写は共感を得やすい。
🔹成果の説得力(13/15)
- 要件誤解によるクレーム4割減/現場の声拾い5割増など、定量的成果が明確。
- 「現場の報告習慣が変わった」「リードタイム短縮に寄与」といった定性面の描写も豊か。
- ただし「今後の展開」についての補足がないため、若干の伸びしろあり。
🔹構成・表現(7/10)
- 指定ルールにはほぼ完全に準拠。ただし、一部表現にやや「作文的」な印象(例:「丁寧に拾い上げる」など)があり、ビジネス文体に調整の余地あり。
- また「なぜならば」「~を狙った」といった因果構造の使用頻度が少なめで、加点余地あり。
💡【改善ポイント/今後の補強案】
- 行動描写強化
→ 第2章に「PMが最初に一度失敗し、そこから再交渉して合意形成に至った」構造を入れると、より人間味・リアリティが出る。 - 展望の追加(第3章末)
→ 「他部門への展開」「今後のプロジェクト文化改革」などを入れると、PMとしての全体視座が高まる。 - 因果構造表現の意識的使用
→ 各章で「なぜならば」「~を狙った」等の論理接続表現を意識的に2回以上挿入すると、説得力と採点者の印象が向上。
✅結論:安全圏の合格(上位20%水準)
この論文は、要件のブレークダウンとそれへの対応策が具体的かつ実務的であり、成果も明確に描写されているため、合格はほぼ確実です。内容の信頼性・行動の現実味においても優れており、現行ルーブリックに照らしても上位20%水準の完成度を持っています。
さらなる高得点を狙うには、対話の迷いや譲歩といった「葛藤描写」や「展望の提示」部分を補強するとよいでしょう。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。