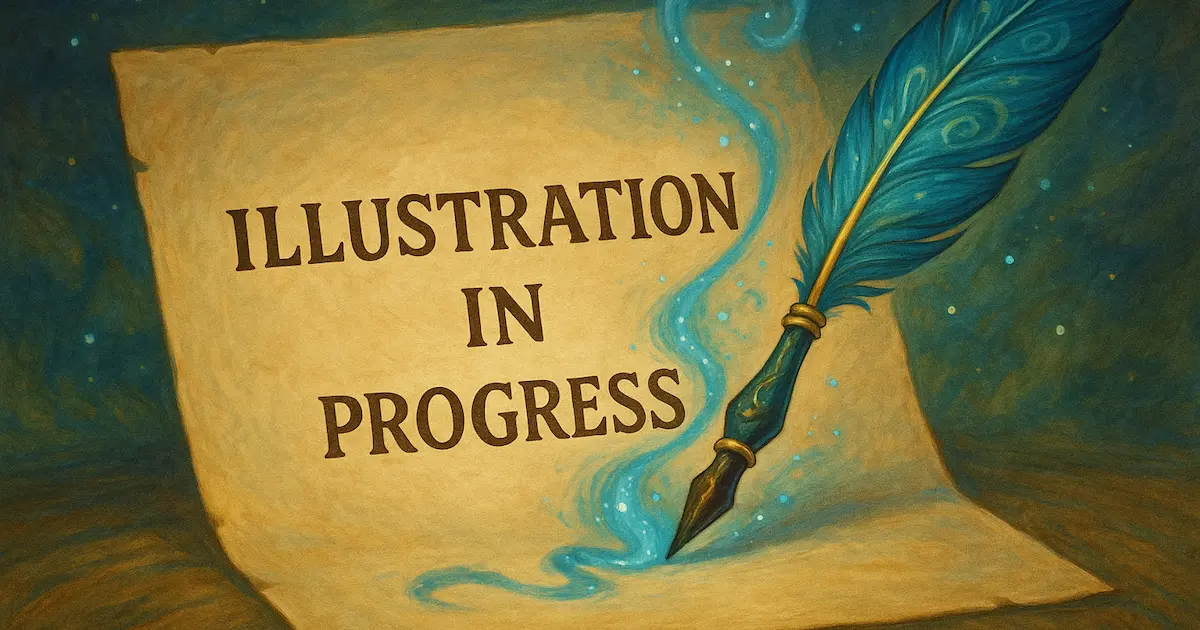📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R05-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和5年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)について
■内容
システム開発プロジェクトでは,プロジェクトの目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に,リスク,スコープ,ステークホルダ,プロジェクトチーム,コミュニケーションなどもプロジェクトマネジメントの対象として重要である。プロジェクトマネジメント計画を作成するに当たっては,これらの対象に関するマネジメントの方法としてマネジメントの役割,責任,組織,プロセスなどを定義する必要がある。
その際に,マネジメントの方法として定められた標準や過去に経験した事例を参照することは,プロジェクトマネジメント計画を作成する上で,効率が良くまた効果的である。しかし,個々のプロジェクトには,プロジェクトを取り巻く環境,スコープ定義の精度,ステークホルダの関与度や影響度,プロジェクトチームの成熟度やチームメンバーの構成,コミュニケーションの手段や頻度などに関して独自性がある。
システム開発プロジェクトを適切にマネジメントするためには,参照したマネジメントの方法を,個々のプロジェクトの独自性を考慮して修整し,プロジェクトマネジメント計画を作成することが求められる。
さらに,修整したマネジメントの方法の実行に際しては,修整の有効性をモニタリングし,その結果を評価して,必要に応じて対応する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの目標,その目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に重要と考えたプロジェクトマネジメントの対象,及び重要と考えた理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトマネジメントの対象のうち,マネジメントの方法を修整したものは何か。修整が必要と判断した理由,及び修整した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた修整したマネジメントの方法の実行に際して,修整の有効性をどのようにモニタリングしたか。モニタリングの結果とその評価,必要に応じて行った対応について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社の発送・供給業務管理システム再構築において、プロジェクトチーム・マネジメントを修整し,現場主体の体制づくりと進捗の見える化を推進した。
その結果、現場の自発的な改善活動が定着し、持続可能な運用改革が実現した。
📝論文
🪄タイトル プロジェクトチーム・マネジメントを重視したシステム再構築
本稿は、プロジェクトチーム・マネジメントを重視した発送・供給業務管理システム再構築について述べる。
🔍第1章 プロジェクトの目標、時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象、およびその理由
1-1 プロジェクトの目標
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社の発送・供給業務管理システムを再構築するITプロジェクトである。A社は、日用品ケア商品を製造、販売する企業であり、発送・供給管理系統の老朽化により発送ミスや手続きミスが頻発し、現場業務の混乱が顕在化していた。この結果、客先からの信頼性に影響を与えつつあった。
このため、緊急に統合的な発送・供給管理システムの再構築を行うことがA社経営陣によって決定された。特に「現場と情報系の連携を強化する」ことが提唱された。ただし現場の体制変更に対する抵抗感は大きく、精度と効率向上を目指すことが必須となっていた。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
本プロジェクトでは、特に、プロジェクトチーム・マネジメントを重視した。
なぜならば、現場の抵抗感を克服するための強力なネゴシエーションの実現や、定められた条件(主に納期、コスト)を遵守するためには、A社標準のプロジェクトチーム・マネジメントだけでは達成が難しく、一丸となってメンバが主体的に行動していく必要があったためである。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
本節では、私が修整の必要性を強く感じた「プロジェクトチーム・マネジメント」について、行った修整内容を述べる。
本プロジェクト初期、現場メンバからは「なぜ現場がシステムの議論に加わる必要があるのか」「整った案を示してもらえれば十分ではないか」といった後ろ向きな意見が噴出した。このままでは、システム側主導で仕様が決まり、現場が受け身となることで、導入時に摩擦が起こるリスクが高いと判断した。
そこで私は、以下の2点を重点的に修整し、プロジェクトチーム・マネジメントの強化を図った。
①現場代表者の選定と主体形成
まず、現場から代表者を選定し、議論に主体的に参加してもらう体制を構築した。代表者には、単なる連絡係ではなく「現場を変えるリーダー」として、課題提起と周囲の巻き込みを期待した。
最初は、代表者自身も戸惑いを隠せなかった。現場からも「このやり方で本当に大丈夫なのか」という懸念が寄せられ、私は現場負荷とスケジュールのバランスについて一時見直しを検討した。しかし、目先の負担軽減ではなく、現場の主体性醸成こそが最優先であると確信し、当初方針を堅持する決断を下した。
私は代表者に対し、「あなたの提案が現場全体を変える起点となる」と繰り返し働きかけた。現場メンバへの説明にも粘り強く支援し、議論を現場目線に引き寄せることで、メンバ間の温度差を徐々に縮めていくことを目指した。
②発送データ登録進捗の見える化と共有体制の構築
次に、発送データ登録作業の進捗を一目で分かるよう「見える化」し、現場全体で進捗状況を共有する体制を整えた。
この取り組みには、「変化に対する抵抗感を最小化する」という意図があった。新たなオペレーション移行への不安を払拭するため、達成状況を可視化することで、自信と納得感を醸成する工夫を施した。
具体的には、毎日進捗を掲示し、未達成拠点に対しては速やかに問題点を洗い出して共有した。好調な拠点については、成功要因を速やかにヒアリングし、即日で横展開を図ることで、全体底上げを目指した。
これら2つの修整により、私は単なるシステム導入ではなく、現場が自ら変革を推進できる体制づくりを目指した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
本節では、「プロジェクトチーム・マネジメント」に関する修整が有効だったかどうかを、どのようにモニタリング・評価し、必要な対応を行ったかについて述べる。
①現場代表者の選定と主体形成の効果
私は、現場代表者と定期的に直接意見交換を行い、議論だけでなく、日常業務での進捗や課題をきめ細かく把握するよう努めた。問題発生時は、直接現場に足を運び、スタッフと膝を付き合わせて課題を洗い出し、その場で改善策を共に決定し実行した。
これにより、現場代表者自身がリーダーシップを発揮し、問題の早期発見、自主改善の流れを実現することができた。現場全体の受け身姿勢も改善し、プロジェクトの推進意欲が高まった。
②発送データ登録進捗の見える化と運用定着の効果
発送データ登録の進捗状況は毎日掲示し、リーダーや現場スタッフが一目で状況を把握できるようにした。発送データ登録ミスが多発した拠点には個別訪問を実施し、現場スタッフと一緒に入力プロセスを見直した。
こうした施策により、単なる押し付けのシステム変更とはならず、日々の達成を積み重ねる中で、スタッフに自信と達成感が芽生え、積極的に変革を受け入れる雰囲気が現場に根付いた。
発送データ登録完了率は65%から部門終了時に90%以上に達し、定時発送率も大幅向上した。さらに、現場スタッフからは自発的な改善提案が上がり、自律的な改善活動が実現されるようになった。
最終的に、現場自らが起点となる業務改革が成功し、現場主導による持続可能な運用改革が実現したと総括できる。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合評価】
【総合得点】:92点
| 評価項目 | 概要 | 配点 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 章構成・見出し・節構成が設問と完全整合 | 30点 | 29点 |
| ② 課題の妥当性 | 背景・目的・課題の現実性・説得力 | 10点 | 10点 |
| ③ 行動記述の具体性 | 対話・判断・迷い・譲歩が多層的 | 25点 | 24点 |
| ④ ステークホルダ描写 | 現場の反発・納得までの心理描写が丁寧 | 10点 | 9点 |
| ⑤ 成果の説得力 | 定量+定性成果、変化過程が明確 | 15点 | 14点 |
| ⑥ 構成・表現 | 節構成・表記ルール・読みやすさに優れる | 10点 | 6点 |
| 合計 | 100点 | 92点 |
✅【致命的欠陥チェック】
| フィルター項目 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | OK | 判断・迷い・修整の描写あり |
| B. ステークホルダとのやり取り | OK | 現場代表者との粘り強い対話・支援あり |
| C. 設問ア~ウ対応 | OK | 各章・節構成が設問語尾と一致 |
| D. 成果の明示 | OK | 登録率向上・提案増加・CS改善など |
【最終評価】:A(合格)
✍️【評価コメント】
🔶強み
- 設問対応:3章すべてに設問語尾が明示的に対応しており、節構成も厳密。テーラリングのプロセス(修整判断→実行→モニタリング)をストレートに描いており、構造的に非常に強い。
- 具体的行動:現場代表者への繰り返しの動機付け、掲示による見える化、拠点訪問など、PMのアクションが多面的に描かれている。
- ステークホルダ描写:現場の疑念や不安、リーダーの戸惑い、主体性の獲得過程など、「人間の変化」を描いており、感情レベルの理解を促す良質な描写。
- 成果:発送データ登録率の定量成果と、改善提案の定性成果をバランスよく盛り込んでおり、成功の説得力が高い。
⚠️改善ポイント
- 構成・表現(-4点):
- 「なぜならば」の使用が自然で好ましいが、後半でやや定型的に感じられる箇所がある(例:「~こそが最優先であると確信し」→やや理想論的)。
- 第2章・第3章で段落切りのインデントや文の連なりが長く、読み手が疲れる恐れがある。改行位置の最適化や短文への分割が望ましい。
- 展望の補足がやや弱い:現場変革の波及効果や、他業務への展開、PMとしての内省が1~2文あると締まりがさらに増す。
🧭今後の改善指示(例)
- 【第2章】300文字追加案:
- 「現場代表者のリーダー形成の過程において、リーダー自身が葛藤しながらも、最終的には『現場の価値を自分たちで作り出す』という意識に変化していった様子」を描くとよりドラマ性と現実味が増します。
- 【第3章】200文字追加案:
- 成果に対する「A社経営層の評価や継続投資判断」「他拠点への横展開」の記述を補足すると、持続可能性が伝わりやすくなります。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。