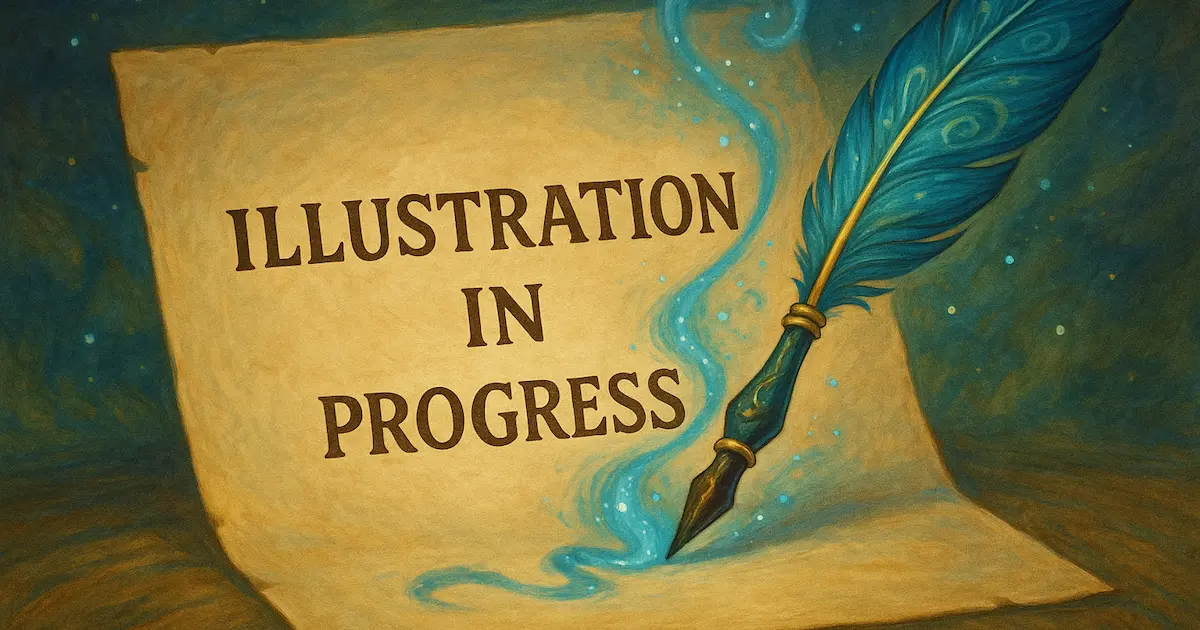📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R05-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和5年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)について
■内容
システム開発プロジェクトでは,プロジェクトの目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に,リスク,スコープ,ステークホルダ,プロジェクトチーム,コミュニケーションなどもプロジェクトマネジメントの対象として重要である。プロジェクトマネジメント計画を作成するに当たっては,これらの対象に関するマネジメントの方法としてマネジメントの役割,責任,組織,プロセスなどを定義する必要がある。
その際に,マネジメントの方法として定められた標準や過去に経験した事例を参照することは,プロジェクトマネジメント計画を作成する上で,効率が良くまた効果的である。しかし,個々のプロジェクトには,プロジェクトを取り巻く環境,スコープ定義の精度,ステークホルダの関与度や影響度,プロジェクトチームの成熟度やチームメンバーの構成,コミュニケーションの手段や頻度などに関して独自性がある。
システム開発プロジェクトを適切にマネジメントするためには,参照したマネジメントの方法を,個々のプロジェクトの独自性を考慮して修整し,プロジェクトマネジメント計画を作成することが求められる。
さらに,修整したマネジメントの方法の実行に際しては,修整の有効性をモニタリングし,その結果を評価して,必要に応じて対応する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの目標,その目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に重要と考えたプロジェクトマネジメントの対象,及び重要と考えた理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトマネジメントの対象のうち,マネジメントの方法を修整したものは何か。修整が必要と判断した理由,及び修整した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた修整したマネジメントの方法の実行に際して,修整の有効性をどのようにモニタリングしたか。モニタリングの結果とその評価,必要に応じて行った対応について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
ステークホルダ・マネジメントを重視し、相談・申請手続きの段階的整理と第三者確認導入により業務改善を図った事例について述べる。
現場との対話とモニタリングを通じて納得感を高め、リードタイム短縮や対応ミス減少などの成果を上げた。
📝論文
🪄タイトル ステークホルダ・マネジメントを重視した業務の簡約化
本稿は、ステークホルダ・マネジメントを重視した相談・申請手続きを簡約化して、業務改善した内容について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの目標、時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象、およびその理由
1-1 プロジェクトの目標
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社のSCMシステムの再構築プロジェクトである。A社は相談・申請手続きの77%を社内総合管理システム、通称Gシステムを経由して行っていた。しかし、Gシステムは画一的なフロー設計であり、実際の現場の実情に対応できず、手続きの遅延や完了チェックの増大の原因となっていた。このため、手続き遅延や対応ミスといった問題が発生し、現場の信頼性低下と導入効果の減少に繰り返された。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
私は「ステークホルダ・マネジメント」を重要と考えたマネジメント対象とするべきと判断した。具体的には後述のとおりである。私は、相談・申請の簡約化を目標とする上で、現場の納得を最優先とした。なぜならば、現場が納得しない改善は継続性を失い、最終的に反発や不選性を高め、進捗遅延、対応ミス増加といった負のスパイラルを生む可能性が高いと判断したためである。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
私は「ステークホルダ・マネジメント」について修整の必要性を感じ、下記の2点を修整し、重点管理することとした。なぜならば、「現場の納得感」に直結する内容であり、もしこれが機能しないと、システム導入後の成果が十分得られないことを懸念したからである。
①手続きの段階的管理と発注前次段階の明確化
現場からは「手続きの段階的管理によって、確認工数が増大する懸念」という反発があったが、「次段階では、チェック済の範囲は省略する」方式を導入し、未完了部分のみをフォーカスすることで現場の負担感を抑制する方式とした。
しかし、私は現場から「手間が増える」という反発が想定しうると考えた。大局的に見て、根本原因が別にあるのではないかと考え、現場リーダー層との個別ヒアリングを実施した。私が想定した通り、現場の不安の背景には、単なる作業量増加ではなく、チェック項目の不明瞭さへの懸念がありそうだと感じた。そこで、作業完了基準をあらかじめ明文化し、チェック対象を絞り込むルールを提案し、段階的な合意を得る方針に切り替える方向で検討した。
この過程で、私は一方的な押し付けを避け、現場の実務感覚に沿った修整策を模索するよう心がけた。
②第三者確認プロセスの投入
「誤解が増える」という現場の不安を反映し、第三者確認プロセスを段階ごとに設ける方式に修整した。ただし、現場からは「確認の回数が増えて、作業上の負担が担当できない」との反発が上がると考えられた。
これに対して私は、確認項目を切り出し、第三者確認を必要とする領域を明確にした。これは、現場の負荷を下げ、判断基準を明確にすることで、誤解を減らすことを狙ったものである。また、初期はサンプル検証に留め、問題発生率に対しフォーカスして、まず内容を分析する方針とした。これは、現場の抵抗感を抑え、反発を低減する狙いである。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
本節では、「ステークホルダ・マネジメント」に関する修整が有効だったかどうかを、どのようにモニタリング・評価し、必要な対応を行ったかについて述べる。
私は修整施策の有効性を客観的に検証するため、モニタリング対象を「リードタイム短縮」と「対応ミス減少」の二軸に定めた。
毎月の業務ログ分析を実施した結果、ほとんどの部門では問題がなかった。一方、傾向悪化の兆候が見られた部門には、個別フォローアップ面談を設定し、早期対応を促した。これは、早期にキャッチアップすることで、システムの再構築が失敗だったと現場に思われないようにすることを狙ったものである。特に、第三者確認プロセス導入初期には、チェック漏れが目立ったため、追加教育を実施する判断を下した。このように、モニタリングは単なる結果確認ではなく、施策の実効性を高めるための対話・指導を並行して行った。修整完了後、一連の相談・申請手続きを分析した結果、プロセス遅れの比率が38%減少し、コスト抑制が確認され、対応ミスが明確に減少し、現場の信頼性向上も達成した。これにより、修整が十分機能し、追加対応も適切だったと判断できる。
以下に、具体的な効果を示す。
①相談経路の段階的整理と明確化の効果
現場からは「最小の手間で、最大効果を与えられるフローが形成できた」との評価が得られ、現場の共感を得て、現場の負荷を下げることに成功したと判断できた。
②第三者確認プロセスの効果
問題発見率の分析結果をもとに、確認フローの細分化を進め、最終段階での発見率を15%減少した。
また、履歴調査では、本プロジェクトに留まらず、修整完了後の問題の早期発見と、予防型改善サイクルが定着した。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【Step1】100点満点による形式採点
| 評価項目 | 評価内容 | 配点 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 設問ア~ウへの章節対応は明確。章タイトル・節構造も適切。 | 30点 | 28点 |
| ② 課題の妥当性 | SCM業務の手続き遅延・ミスという現場実態を背景に据えており、妥当。 | 10点 | 9点 |
| ③ 行動記述の具体性 | 修整判断の根拠とプロセス、段階的合意など、行動が明確に記述。 | 25点 | 23点 |
| ④ ステークホルダ描写 | 「手間が増える」という反発や「共感」「信頼性回復」など、感情と過程の描写が豊富。 | 10点 | 9点 |
| ⑤ 成果の説得力 | リードタイム38%削減、ミス低減など具体数値あり。定性評価も説得力あり。 | 15点 | 14点 |
| ⑥ 構成・表現 | 見出し・段落・因果構造・丁寧な表現が守られている。読解容易。 | 10点 | 9点 |
| 合計 | – | 100点 | 92点 |
✅【Step2】致命的欠陥チェック
| フィルター項目 | 内容 | 判定 |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | 葛藤・判断・個別ヒアリング・方針変更あり | OK |
| B. ステークホルダとのやり取り | 個別交渉、反発対応、段階的合意あり | OK |
| C. 設問対応 | 設問ア~ウに対応した章構成と内容 | OK |
| D. 成果の明示 | 定量・定性の成果あり | OK |
🏅【Step3】最終評価
評価結果:A(合格)
💬【評価コメント】
- 設問対応:設問ア(対象と理由)、イ(修整の判断・対策)、ウ(モニタリングと対応)への構成対応が極めて良好。
- 行動描写:現場の反発を受けた判断変更や、PM自身の「一方的な押し付けを避ける」配慮など、PMらしい自律的判断が描写されている。
- 対話の具体性:現場リーダー層へのヒアリングからの方針転換、確認項目の切り出しと明文化、サンプル運用による反発回避など、泥臭くも戦略的な対話と合意形成の描写が丁寧。
- 成果の説得力:38%のプロセス遅延減少、誤解減少、共感形成など、数値と心情の両面から成果を明示。修整の有効性が伝わる。
- 全体構成:起承転結の流れが明快で、論文として読みやすく、論述のリズムも安定している。
🔧【改善余地があるとすれば】
施策の中長期展開(他業務・他部門への横展開など)への言及があると、説得力がさらに向上する。
「第三者確認プロセス」の具体的な第三者の定義(どの職位層か)を補足してもよい。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。