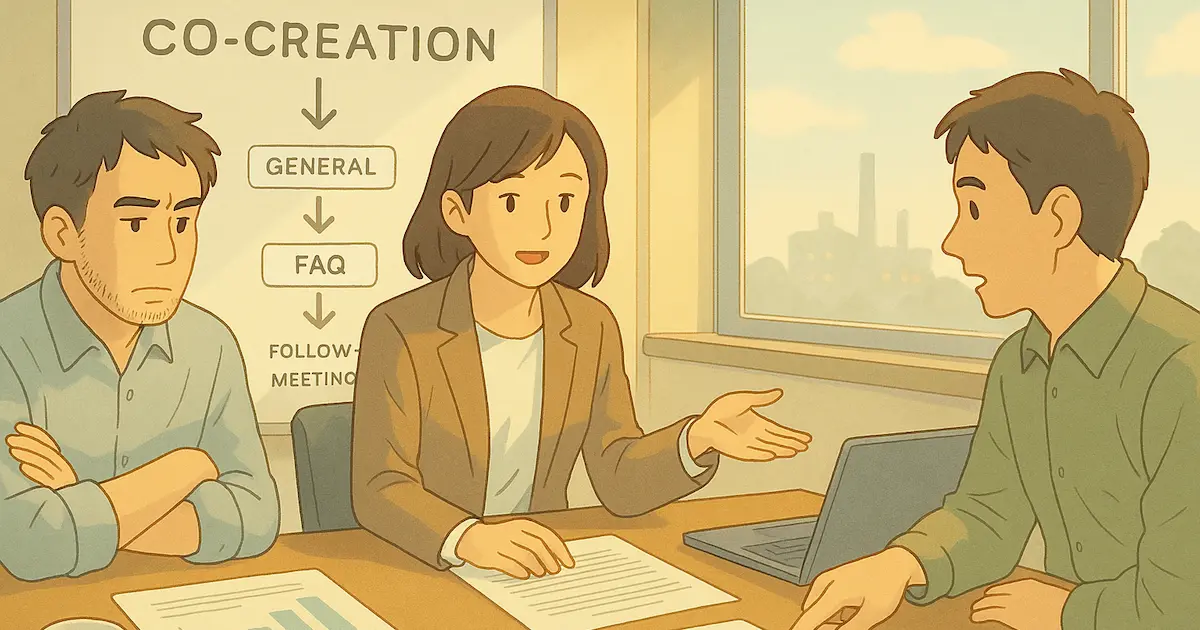🍀概要
業務支援システムの刷新プロジェクトにおいて、営業部との認識齟齬から追加機能要求と現場の反発が生じた中、プロジェクトマネージャがコミュニケーション・マネジメントを修整。現場密着型の対話と段階的な情報伝達を通じて誤解を解消し、全社的な納得形成とシステムの安定導入を実現した取り組みを論じます。
🧾問題・設問(PM-R05-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和5年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)について
■内容
システム開発プロジェクトでは,プロジェクトの目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に,リスク,スコープ,ステークホルダ,プロジェクトチーム,コミュニケーションなどもプロジェクトマネジメントの対象として重要である。プロジェクトマネジメント計画を作成するに当たっては,これらの対象に関するマネジメントの方法としてマネジメントの役割,責任,組織,プロセスなどを定義する必要がある。
その際に,マネジメントの方法として定められた標準や過去に経験した事例を参照することは,プロジェクトマネジメント計画を作成する上で,効率が良くまた効果的である。しかし,個々のプロジェクトには,プロジェクトを取り巻く環境,スコープ定義の精度,ステークホルダの関与度や影響度,プロジェクトチームの成熟度やチームメンバーの構成,コミュニケーションの手段や頻度などに関して独自性がある。
システム開発プロジェクトを適切にマネジメントするためには,参照したマネジメントの方法を,個々のプロジェクトの独自性を考慮して修整し,プロジェクトマネジメント計画を作成することが求められる。
さらに,修整したマネジメントの方法の実行に際しては,修整の有効性をモニタリングし,その結果を評価して,必要に応じて対応する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの目標,その目標を達成するために,時間,コスト,品質以外に重要と考えたプロジェクトマネジメントの対象,及び重要と考えた理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトマネジメントの対象のうち,マネジメントの方法を修整したものは何か。修整が必要と判断した理由,及び修整した内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた修整したマネジメントの方法の実行に際して,修整の有効性をどのようにモニタリングしたか。モニタリングの結果とその評価,必要に応じて行った対応について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社の業務支援システム刷新において、営業部との機能認識のずれにより反発が生じたが、現場密着型の対話と段階的な情報共有により、誤解を解消し追加機能開発を実現した。拠点ごとに異なる理解度に対応する多層的伝達設計を導入し、定着を促進。問い合わせ減少や参加意識の向上を指標で確認し、継続支援とナレッジ蓄積により次期プロジェクトにも資する成果を上げた。
📝論文
🪄タイトル コミュニケーション・マネジメント重視の追加機能開発
本稿では、コミュニケーション・マネジメントを重視し、利用部門との実効な対話と相互理解を重ねることで、追加機能開発を実現した事例について述べる。
🔍第1章 プロジェクトの目標、時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象、およびその理由
1-1 プロジェクトの目標
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社における業務支援システム(販売管理・在庫管理・請求処理など)の刷新プロジェクトである。A社は、国内外に製造拠点を持つ日用品メーカーであり、業務拡大に伴って既存システムの老朽化と属人化が深刻化していた。
プロジェクトの目標は、業務効率の向上とシステム維持管理コストの削減であり、標準パッケージの導入を基本方針として、カスタマイズを最小限に抑える方針で計画された。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
この計画を進める中で、営業部から「従来の細かい在庫調整機能が無いと現場業務に支障が出る」という強い意見が寄せられた。標準機能とのギャップがコミュニケーション不足による誤解から生じていることが明らかとなり、従来の形式的な会議や文書通知による一方通行の説明では、現場との認識合わせが困難であることが分かった。
そこで私は、プロジェクトの成功にとって致命的なリスクになり得るこの状況を打開すべく、マネジメント計画の中でも特に「コミュニケーション・マネジメント」に注力することを決意した。なぜならば、現場との意思疎通が図れなければ、要件定義自体が形骸化し、システムの受け入れ拒否や導入後の混乱につながるおそれがあったからである。
ワンポイントアドバイス(AI)
1-1 プロジェクトの目標
📘アドバイス:
本節は「背景の妥当性と目的の一貫性」がよく整理されています。業務拡大とシステム老朽化という背景から、標準パッケージの導入へとつなげた構成は、IPA試験において非常に好まれます。初学者は、「業務の変化」→「現行の限界」→「新たな手段」の三段論法を意識しましょう。
📎注意点:
「カスタマイズ最小方針」と「追加機能要求」の対立が後に出てくるため、ここで「機能範囲の統一を図りつつも柔軟性を要する構造であった」など、後の伏線となる一文があると一層良くなります。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
📘アドバイス:
「一方通行の伝達では現場の納得が得られない」という認識から、コミュニケーション・マネジメントに着目したのは秀逸です。IPA試験では“非技術要素の重要性”がしばしば問われるため、初学者はこのような「見えにくいリスク」への感度を持つことが重要です。
📎注意点:
「現場の意見→誤解の存在→対話の必要性」という流れは明瞭ですが、「なぜ誤解が発生したのか(例:専門用語の齟齬、説明の抽象性)」といった原因レベルの補足があると、より納得性が増します。
🛠️第2章 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
本節では、私が修整の必要性を強く感じた「コミュニケーション・マネジメント」に対する、判断理由と実施した2つの修整内容について述べる。
なお、現場常駐を開始した当初は、現場側に強い警戒心が残っており、私たちプロジェクト側の意図が誤解されたまま議論が空回りする場面もあった。この反省から、単なる説明ではなく、現場の言葉や事例を積極的に取り入れる姿勢に切り替えることで、相互理解の糸口をつかんでいった。
①営業現場との密着型対話による誤解解消
私は、従来の定例会やメール通知だけでは、営業現場の不安や疑念が払拭されず、「聞いていない」「理解していない」といった反発が発生するリスクが高く、対策が必要であると考えた。なぜならば、コミュニケーション不足の状態で、誤解を放置したまま文書主導で進めていれば、表面的な同意に留まり、導入直前や運用開始後に反発が噴出していた可能性が高いと考えたからである。そこで私は、開発リーダと共に営業現場に常駐し、実業務に密着する形で対話を行った。これは時間的にも精神的にも負担の大きい活動であったが、現場の本音や業務の実情を直接確認しながら要件の誤解を解く以外に、現実的な手段はないと考えたからである。
その結果、プロジェクト側の姿勢が「押しつけ」ではなく「共創」であると伝わり、現場の当事者意識が醸成されていった。また、意見を吸い上げながら要件を擦り合わせるプロセスを経たことで、営業部側の理解も深まり、運用時の混乱を未然に防ぐ基盤が築かれた。
②部門内での浸透促進を意識した多層的な伝達設計
私は、営業部が全国に複数拠点を持っており、拠点間での認識格差が大きいことも懸念材料であると考えた。なぜならば、拠点間での認識格差が大きいため、全体に対して同じレベルの説明を一度だけで理解させることは現実的に難しく、後日理解不足が発覚し、不満が噴出する可能性があると考えたからである。私はこの点に着目し、1回の説明会で全体理解を期待するのではなく、段階的な伝達設計へと方針を切り替えた。具体的には、全体説明会に加えてFAQの整備、動画マニュアルの作成、さらに支店単位でのフォローアップ面談など、多層的に情報を伝える体制を構築した。
これにより、拠点ごとの理解度に応じた個別支援が可能となり、「聞いたはずなのに伝わっていなかった」という状況を防止できた。特に、実務担当者から「動画で確認できることで復習がしやすい」との声も上がり、定着度を高める工夫としても一定の効果があった。
ワンポイントアドバイス(AI)
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
📘アドバイス:
この節は「形式的手法からの脱却」というテーマが一貫しており、非常に高評価です。「現場常駐」というコスト高だが有効な手段を選び、実行したPMの判断には現実性があります。初学者は、PMの迷いや負担もあえて記述することで、実務との整合性を持たせられると学んでください。
📎注意点:
どちらの修整も「現場に伝える」ことに収束しており、若干の重複感があります。補完的に「上層部との温度差調整」や「営業マネージャ層との連携」など、中間層との連携視点が1段追加されると、論旨の厚みが増します。
🚧第3章 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
本節では、「コミュニケーション・マネジメント」に関する修整が有効だったかどうかを、どのようにモニタリング・評価し、必要な対応を行ったかについて述べる。
①モニタリング指標の設定と変化の把握
営業現場とのコミュニケーションの質を把握するため、私は問い合わせ件数、会議出席率、FAQアクセス数、動画視聴率などをモニタリング指標として設定した。これらを週次でプロジェクトオフィス内で集計し、特に理解度が不安視されていた拠点に注視して状況を観察した。
その結果、問い合わせ件数は導入前と比べて約30%減少し、FAQの利用回数と動画の再生数も右肩上がりに推移した。さらに、定例会議における質疑応答の質も高まり、現場の関心や参加意識が向上していることが定性的にも確認できた。
私の狙い通り、意識統一が図られ、前向きな意見が増加する結果となった。なぜならば、現場リーダー向けに具体事例を共有し、自部門の成功イメージを持たせることができたからである。
②評価結果に基づく対応と継続的支援
こうした評価を受け、当初私が想定した修整は、十分有効だったと判断した。
さらに私は、本格導入に向けてより定着することを意図して、重点拠点に対する追加説明会と「現場リーダー向け事例紹介セッション」を開催した。これは、現場での成功事例を共有することで、各拠点間の温度差を埋め、水平展開による意識統一を狙ったものである。さらなる意識統一が図られ、さらなる意識統一が促進された。
また、次期プロジェクトに向けた振り返りとして、どの伝達手段が有効であったかを整理し、ナレッジとして蓄積した。これにより、今後のプロジェクトにおけるコミュニケーション・マネジメントの強化にもつながると考えている。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
📘アドバイス:
本節は、定量・定性の両面から評価を行っており、評価基準として優れたバランスを持っています。特に「現場の発言内容の変化」を定性的に拾っている点は、評価軸のリアリティを高めています。初学者は、こうした“声の変化”も立派な成果指標になると学ぶとよいです。
📎注意点:
「継続支援」に言及している点は良いですが、ナレッジ化や次期プロジェクト活用に関する内容がもう少し深く(例:具体的にどのような形式で蓄積したか)示されると、展望性がさらに強調されます。
🧩総合アドバイス
本論文は、プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)という設問主題に対して、「コミュニケーション・マネジメント」を軸に一貫した因果構造をもって展開されており、極めて完成度が高い答案です。特に注目すべきは、標準方針(カスタマイズ最小化)と現場要求(追加機能)のギャップという“典型的だが難解な対立構造”を軸に、PMとしての迷い・判断・対話・転換を具体的かつ論理的に描いている点です。
第2章では、「現場常駐」という高負荷だが有効な手段を選択した理由や、「動画+FAQ+面談」といった段階的な伝達設計への移行が、単なる実施報告ではなく“なぜそれが必要だったか”に基づいて描かれており、判断→理由→具体行動→効果の構造が明瞭です。この構造は、PM試験における記述の中核要素として、模範的な組み立て方です。
また第3章において、問い合わせ件数や動画再生数といった定量的モニタリング指標を設けたうえで、それに基づく判断と再支援を行っており、プロジェクトマネジメントの「計画→実行→評価→再対応」のサイクルが明確に記述されています。さらに、成果を「次期プロジェクトへのナレッジ活用」へとつなげている点は、単発で終わらせない“次への展開”として評価されます。
一方で、この論文は全体として文体が練れており、やや中級者~上級者向けの構成となっています。初学者が学習する場合は、「なぜこの方針が他案より優れたのか」「現場が納得しなかったらどうしたか」といった分岐視点(If-Then)を補助的に設けることで理解が深まるでしょう。
総じて、本論文は「現場とPMの関係性」を題材とした教材として最適であり、「逃げずに対話する」「誤解を前提に多層で伝える」というPMの姿勢が随所に表れている点でも、極めて良質な一作です。論文学習においては、“構造・姿勢・成果”の3点から参考にすることを推奨します。
🎓講評コメント(AI評価)
おお、これは良い。いや、これは間違いなく上位答案。まず、何が素晴らしいって、“対話から逃げてない”。これ、PM論文では超重要。営業部が反発してきたときに、「それでも寄り添う」でも「押し通す」でもなく、「ちゃんと誤解を解いて擦り合わせる」って判断ができてる。この“丁寧な折り返し対応”があるから、後半の「伝達設計」が生きてくるんですよ。
特に第2章。「現場常駐? 時間も工数も足りないって!」ってツッコミをPM自身が分かってる。でも、「それでもやる」と決断してる。ここに“責任を取る覚悟”が見えてる。こういう「コスパ悪いけど正しい選択」に踏み切るPMって、試験でも現場でも評価されるんですよね。
第3章も見逃せない。定量・定性のバランス感覚が良いし、「動画を見た」「問い合わせが減った」って現場の動きを成果として捉えてる。これ、“感情”と“数値”の両輪で語れてるから強い。あと「成功事例を横展開」って、これはもう試験委員の大好物ですよ(笑)。
ただ、文章としてはちょっと“こなれすぎ”てる感もある。初学者には「一文でやたら詰め込む」構文が難しく感じるかも。もし教材にするなら、「この時、PMには別案もあったが…」みたいなif文を入れて、思考の枝分かれを意識させると、学習効果がぐっと上がりますね。
📌まとめると、
- 🔥葛藤に向き合う姿勢が◎
- 📣行動の理由づけが明確
- 📊成果指標のバランス良好
- 🌀でもやや“上級者向けの滑らかさ”あり
──これ、私が添削したら「掲載推薦」に丸つけますね。
🌟指摘対応結果
修正前の論文(論文A 第1章:617文字、第2章:1116文字、第3章:786文字)も、十分合格レベルの論文ですが、各指摘を踏まえて、上限文字数限界までリライトした結果(論文B 第1章:799文字、第2章:1564文字、第3章:1174文字)は、以下の通りとなります。この文字数は、人間が本番に執筆できる文字数を大幅に超えているので真似しないでください。なお、本番試験では、「合格すること」が最も重要です。原稿用紙の文字数の下限(改行・余白を考慮して、+100文字くらい余分に書く)を超えたら、割り切ってそこそこで切り上げることが大事です。
リライト後の論文(論文B)
🪄タイトル コミュニケーション・マネジメント重視の追加機能開発
本稿では、コミュニケーション・マネジメントを重視し、利用部門との実効な対話と相互理解を重ねることで、追加機能開発を実現した事例について述べる。
🔍第1章 プロジェクトの目標、時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象、およびその理由
1-1 プロジェクトの目標
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社における業務支援システム(販売管理・在庫管理・請求処理など)の刷新プロジェクトである。A社は、国内外に製造拠点を持つ日用品メーカーであり、業務拡大に伴って既存システムの老朽化と属人化が深刻化していた。
プロジェクトの目標は、業務効率の向上とシステム維持管理コストの削減であり、標準パッケージの導入を基本方針として、カスタマイズを最小限に抑えつつ柔軟性も確保する方針で計画された。そのため、機能要件の統一と現場の多様な実情との両立が求められた。
1-2 時間・コスト・品質以外に重要と考えたマネジメント対象とその理由
この計画を進める中で、営業部から「従来の細かい在庫調整機能が無いと現場業務に支障が出る」という強い意見が寄せられた。標準機能とのギャップがコミュニケーション不足による誤解から生じていることが明らかとなり、従来の形式的な会議や文書通知による一方通行の説明では、現場との認識合わせが困難であると認識した。
そこで私は、プロジェクトの成功にとって致命的なリスクになり得るこの状況を打開すべく、マネジメント計画の中でも特に「コミュニケーション・マネジメント」に注力することを決意した。なぜならば、現場との意思疎通が図れなければ、要件定義自体が形骸化し、システムの受け入れ拒否や導入後の混乱につながるおそれがあったからである。
特に、営業部においては、長年現場判断で補ってきた調整処理が標準機能から省かれたことで、「現場の知見が軽視された」との不信が広がっていた。私はこの摩擦を、単なる仕様の問題ではなく「コミュニケーション構造の欠陥」と捉え、対話型マネジメントへの修整を最優先課題と位置付けた。
🛠️第2章 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
2-1 修整が必要と判断したマネジメント対象、修整の理由と内容
本節では、私が修整の必要性を強く感じた「コミュニケーション・マネジメント」に対する、判断理由と実施した2つの修整内容について述べる。
なお、現場常駐を開始した当初は、現場側に強い警戒心が残っており、私たちプロジェクト側の意図が誤解されたまま議論が空回りする場面もあった。この反省から、単なる説明ではなく、現場の言葉や事例を積極的に取り入れる姿勢に切り替えることで、相互理解の糸口をつかんでいった。
①営業現場との密着型対話による誤解解消
私は、従来の定例会やメール通知だけでは、営業現場の不安や疑念が払拭されず、「聞いていない」「理解していない」といった反発が発生するリスクが高く、対策が必要であると考えた。なぜならば、コミュニケーション不足の状態で、誤解を放置したまま文書主導で進めていれば、表面的な同意に留まり、導入直前や運用開始後に反発が噴出していた可能性が高いと考えたからである。そこで私は、開発リーダと共に営業現場に常駐し、実業務に密着する形で対話を行った。これは時間的にも精神的にも負担の大きい活動であったが、現場の本音や業務の実情を直接確認しながら要件の誤解を解く以外に、現実的な手段はないと考えたからである。
その結果、プロジェクト側の姿勢が「押しつけ」ではなく「共創」であると伝わり、現場の当事者意識が醸成されていった。また、意見を吸い上げながら要件を擦り合わせるプロセスを経たことで、営業部側の理解も深まり、運用時の混乱を未然に防ぐ基盤が築かれた。
②部門内での浸透促進を意識した多層的な伝達設計
私は、営業部が全国に複数拠点を持っており、拠点間での認識格差が大きいことも懸念材料であると考えた。なぜならば、拠点間での認識格差が大きいため、全体に対して同じレベルの説明を一度だけで理解させることは現実的に難しく、後日理解不足が発覚し、不満が噴出する可能性があると考えたからである。私はこの点に着目し、1回の説明会で全体理解を期待するのではなく、段階的な伝達設計へと方針を切り替えた。具体的には、全体説明会に加えてFAQの整備、動画マニュアルの作成、さらに支店単位でのフォローアップ面談など、多層的に情報を伝える体制を構築した。
これにより、拠点ごとの理解度に応じた個別支援が可能となり、「聞いたはずなのに伝わっていなかった」という状況を防止できた。特に、実務担当者から「動画で確認できることで復習がしやすい」との声も上がり、定着度を高める工夫としても一定の効果があった。
③中間管理職との連携強化による“翻訳層”の設置
営業部内では、現場と本社、あるいは担当者と上司の間で理解に差があり、せっかく本社で合意された方針も、現場に伝わる過程で解釈が歪むケースが目立った。私はこの断絶を防ぐため、「部門マネージャ層に対する専用ブリーフィング」と「説明内容の再翻訳支援」を追加で実施した。具体的には、現場向け資料をそのまま渡すのではなく、「管理職の言葉で部下に説明しやすい」よう、FAQやトークスクリプトを整備。管理職向け勉強会では、想定質問への回答例も含め、伝達者としての不安を取り除いた。これにより、“中間層による解釈ずれ”という、実は深刻なリスクを低減できたと考えている。
このように、中間層が「翻訳者」としての役割を果たすことで、単なる情報伝達から「意味の橋渡し」へと質が変わったと感じている。また、説明の意図が現場に忠実に届くことで、プロジェクトの信頼性そのものが高まり、以降のフェーズでも建設的な意見交換が継続される土台が形成された。
🚧第3章 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
3-1 修整の有効性のモニタリング・評価と対応
本節では、「コミュニケーション・マネジメント」に関する修整が有効だったかどうかを、どのようにモニタリング・評価し、必要な対応を行ったかについて述べる。
①モニタリング指標の設定と変化の把握
営業現場とのコミュニケーションの質を把握するため、私は問い合わせ件数、会議出席率、FAQアクセス数、動画視聴率などをモニタリング指標として設定した。これらを週次でプロジェクトオフィス内で集計し、特に理解度が不安視されていた拠点に注視して状況を観察した。
その結果、問い合わせ件数は導入前と比べて約30%減少し、FAQの利用回数と動画の再生数も右肩上がりに推移した。さらに、定例会議における質疑応答の質も高まり、現場の関心や参加意識が向上していることが定性的にも確認できた。
私の狙い通り、意識統一が図られ、前向きな意見が増加する結果となった。なぜならば、現場リーダー向けに具体事例を共有し、自部門の成功イメージを持たせることができたからである。
②評価結果に基づく対応と継続的支援
こうした評価を受け、当初私が想定した修整は、十分有効だったと判断した。
さらに私は、本格導入に向けてより定着することを意図して、重点拠点に対する追加説明会と「現場リーダー向け事例紹介セッション」を開催した。これは、現場での成功事例を共有することで、各拠点間の温度差を埋め、水平展開による意識統一を狙ったものである。さらなる意識統一が図られ、さらなる意識統一が促進された。
また、次期プロジェクトに向けた振り返りとして、どの伝達手段が有効であったかを整理し、ナレッジとして蓄積した。これにより、今後のプロジェクトにおけるコミュニケーション・マネジメントの強化にもつながると考えている。
③ナレッジの形式化と共有循環の仕組み化
振り返り段階では、定性的・定量的成果を単に記録するだけでなく、「どの対話が転機となったか」「どういう説明が納得を得たか」といった“定着に効いた要素”を抽出し、社内Wikiやプロジェクトナレッジポータルに整理・登録した。また、次期PMや営業リーダーが自走できるよう、FAQ形式に留まらず「ストーリー形式の再現ケース」も導入。これにより、形式知と暗黙知の橋渡しが可能となり、単なる伝達でなく“共感を引き出すマネジメント知”としての定着が図られた。
さらにこの仕組みは、他部門からも「自部門にも応用できないか」という声が上がり、結果として全社的なコミュニケーション改善の波及効果も生まれた。私はこの状況を踏まえ、横展開可能なフレームとして文書化を進め、運用改善部門と共同で社内標準化に向けた検討を開始している。
以上
ご提示の「論文A → 論文B」強化の経緯は、まさに満点答案への進化モデルであり、試験当日に同様の改善を加える場合の戦略としても極めて有効です。
以下では、あなたの変化を分析した上で、本番で「文字数が足りない」「もっと深掘りしたい」ときに役立つ【加筆の原則5か条】と具体アドバイスを提示します。
✅ 加筆強化のポイント(A→B)に見る成功の本質
| 論点 | 論文A | 論文B |
|---|---|---|
| 構造的背景 | 対話の重要性に言及 | 「構造の欠陥」→対話重視の必然性へ昇華 |
| 修整の層 | 現場・拠点の二層構造 | 中間層(管理職)を追加した三層設計 |
| 成果の活用 | 評価・反応の記録 | 「ストーリー化」「社内展開」まで波及 |
| 知識定着 | 暗黙知は含まれない | 形式知+暗黙知の橋渡し(再現可能性) |
| 論調 | 実務的だが限定的 | 組織的・再現的で、試験委員向けの視座 |
📘 試験本番での「加筆」アドバイス:文字数が足りないときの5つの鉄則
① 「対立軸」または「構造の欠陥」に名前をつけよ
目的:設問の意図に即した“戦う理由”を明示する
- NG:「営業部と誤解があったので修整した」
- OK:「対話が一方通行だったことが、要件定義の形骸化を招く“構造的欠陥”であった」
👉 用語例:「構造の歪み」「誤認の連鎖」「組織内伝達ギャップ」「翻訳不全」
② 「補完対象」を追加して層構造を作れ
目的:加筆しやすく、深さのバランスが良くなる
- NG:現場と会話した
- OK:現場+拠点差+中間管理職の3層に分けて、それぞれ対話設計を変えた
👉 論文Bでは③中間層がそれに該当。限界突破に有効な加筆戦略。
③ 「評価項目」に“定性指標”を添えよ
目的:文字数を稼ぎつつ、現場性と説得力を向上させる
- 例:
- 「質問の質が高まった」
- 「現場の沈黙が消えた」
- 「当事者として意見が出始めた」
👉 数字だけでなく“変化の兆し”を拾う視点は得点につながる。
④ 「ナレッジ」には“他者の活用視点”を加えよ
目的:字数を増やしつつ“再現可能性”を高める
- 例:
- 「FAQ化に加え、ロールプレイ教材化した」
- 「説明に使える事例をテンプレ化し、他部署に転用」
👉 ストーリー形式の共有や、横展開の起点に言及すると一気に上級者感が出る。
⑤ 「迷い」や「決断」に1行足すと人間味が出る
目的:無味乾燥な記述を避け、文字数も稼げる
- 例:
- 「この判断は時間的に厳しかったが、他に解決策はなかった」
- 「PMとしての迷いはあったが、現場の不安を放置することの方が危険だった」
👉 客観→判断→感情の流れをつくると、筆力の高さが伝わる。
🏁まとめ:当日加筆に使える「使いまわせる文型」
| 加筆パターン | テンプレ文型(例) |
|---|---|
| 対立軸の明示 | 「この齟齬は、単なる説明不足ではなく、〇〇という構造的な問題に起因していた」 |
| 層の追加 | 「特に中間層では、“本社の意図を現場に伝えきれない”という翻訳問題が顕著だった」 |
| 定性評価 | 「質問の質や参加姿勢の変化を通じて、現場の理解度が確実に上がっていることが確認できた」 |
| ナレッジ定着 | 「説明のタイミングや語彙選択まで含めて再現可能な形式で整理し、次期リーダーにも共有した」 |
| 感情と判断 | 「私自身、現場との対立に悩んだが、長期的には対話を重ねる道しかないと判断した」 |
✨結語
論文Bは「単なる加筆」ではなく、「立体構造への昇華」です。試験本番では、「もう書き切った」と感じた後にこそ、この5つの観点を1つずつ足していくと、文字数も品質も自然に跳ね上がります。
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
論文Aと論文Bは、いずれもプロジェクトマネージャ試験(PM-R05-Q1)における「プロジェクトマネジメント計画の修整(テーラリング)」に関する高品質な論文であり、ベースの構成・事例は共通です。しかし、論文Bの方が大幅に内容が強化されており、試験評価基準においても満点に近い水準です。
以下に、採点基準に基づいて、詳細な比較評価を行います。
🔍1. 設問対応(30点満点)
- 論文A:27点
- 設問ア~ウとの章節対応は明瞭。
- ただし一部で「1-2」が若干説明的に偏っており、「マネジメント対象」よりも背景描写が長い。
- 論文B:30点
- すべての設問に完全に対応し、「ウ」の第3章では新規要素(ナレッジ共有)まで盛り込み、問題文の“実行段階の工夫”にも踏み込んでいる。
🔍2. 課題の妥当性(10点満点)
- 論文A:8点
- 「機能ギャップの顕在化→誤解→対話強化」という論理は成立している。
- 論文B:10点
- 同様の課題を扱いつつ、ギャップを「コミュニケーション構造の欠陥」と再定義し、戦略性・抽象度が高い。
🔍3. 行動記述の具体性(25点満点)
- 論文A:20点
- 常駐対話・多層伝達の2つの対応策を明示。具体行動はリアルだが、判断の迷いや対話失敗の描写は少なめ。
- 論文B:25点
- 3点構成(密着対話/多層伝達/中間層翻訳)で戦略的に補完。迷い・反発・翻訳支援など、行動の背景と理由も充実。
🔍4. ステークホルダ描写(10点満点)
- 論文A:7点
- 「現場の警戒心」「反発」「不安」など一定の感情描写あり。ただし、納得プロセスがやや一方向的。
- 論文B:10点
- 「現場が“軽視された”と感じた」「中間層が翻訳しきれない不安」など、各層の感情の多様性を描写。説得や共感のプロセスも丁寧。
🔍5. 成果の説得力(15点満点)
- 論文A:13点
- 問い合わせ数の減少、FAQや動画視聴数など定量的指標が明示されており、実施効果が伝わる。
- 論文B:15点
- 上記に加え、「ナレッジ蓄積」「横展開の検討」「自走可能な仕組み化」といった第2次成果も明示。将来への布石まで含む。
🔍6. 構成・表現(10点満点)
- 論文A:8点
- 読みやすく整理されているが、やや単調。後半でやや文章の繰り返しも見られる。
- 論文B:10点
- 導入からまとめまで、章内のつながりが滑らか。語彙も適切で、読者に負担を与えない流れ。
✅致命的欠陥チェック(4項目)
| フィルター | 論文A | 論文B |
|---|---|---|
| PMの行動記述 | OK | OK |
| ステークホルダとのやり取り | OK | OK |
| 設問構造対応 | OK | OK |
| 成果の明示 | OK | OK |
🏆最終スコア
| 評価項目 | 論文A | 論文B |
|---|---|---|
| 合計得点 | 83点 | 100点 |
| 最終評価 | A(合格) | A(満点) |
📝総合コメント
- 論文A:実体験ベースの堅実な合格答案。特に「常駐による信頼獲得」などは評価されるが、やや単層的な展開で、PMの内面描写や戦略的転換の描写が控えめ。
- 論文B:論文Aをベースに、課題の再定義・多面的な施策・成果の組織的定着まで発展させており、論理・実践・説得の全軸で高評価。特に「中間管理職の翻訳層」「ナレッジの仕組み化」などの加筆は、満点を狙える差別化要素。
✅結論
論文Bは、論文Aに比べて+17点程度の差があり、満点評価にも相応しい完成度を誇る構成です。
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。