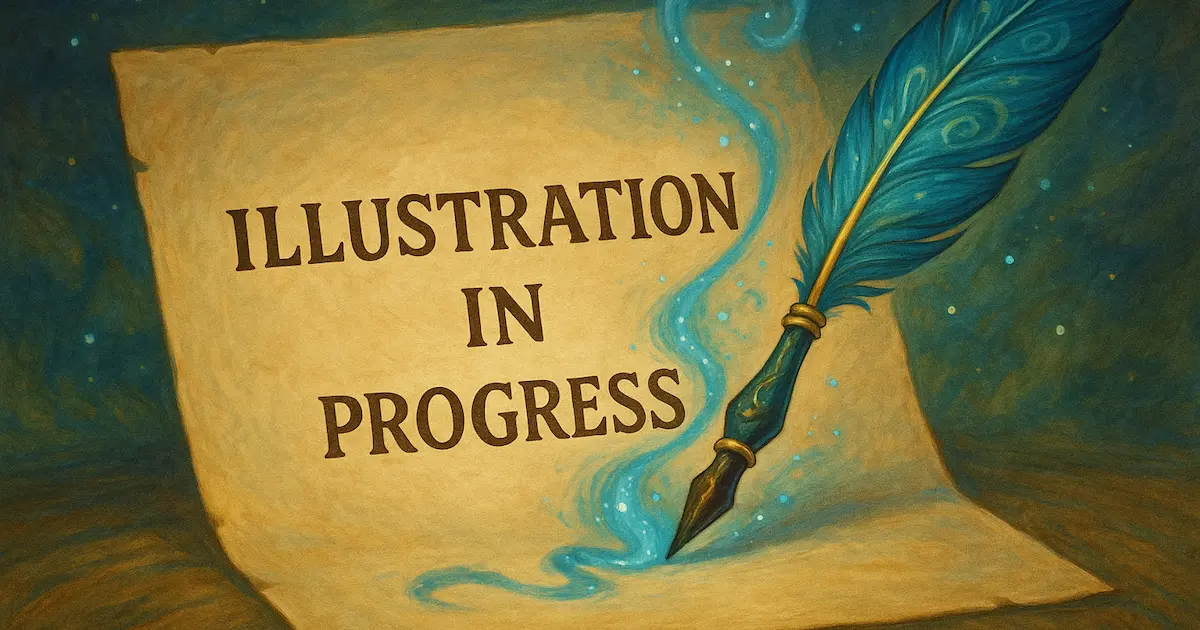📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R02-Q2)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和2年 午後2 問2
📘問題
■タイトル
システム開発プロジェクトにおけるリスクのマネジメントについて
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)は,プロジェクトの計画時に,プロジェクトの目標の達成に影響を与えるリスクへの対応を検討する。プロジェクトの実行中は,リスクへ適切に対応することによってプロジェクトの目標を達成することが求められる。
プロジェクトチームの外部のステークホルダはPMの直接の指揮下にないので,外部のステークホルダに起因するプロジェクトの目標の達成にマイナスの影響がある問題が発生していたとしても,その発見や対応が遅れがちとなる。PMはこのような事態を防ぐために,プロジェクトの計画時に,ステークホルダ分析の結果やPMとしての経験などから,外部のステークホルダに起因するプロジェクトの目標の達成にマイナスの影響を与える様々なリスクを特定する。続いて,これらのリスクの発生確率や影響度を推定するなど,リスクを評価してリスクへの対応の優先順位を決定し,リスクへの対応策とリスクが顕在化した時のコンティンジェンシ計画を策定する。
プロジェクトを実行する際は,外部のステークホルダに起因するリスクへの対応策を実施するとともに,あらかじめ設定しておいたリスクの顕在化を判断するための指標に基づき状況を確認するなどの方法によってリスクを監視する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴と目標,外部のステークホルダに起因するプロジェクトの目標の達成にマイナスの影響を与えると計画時に特定した様々なリスク,及びこれらのリスクを特定した理由について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた様々なリスクについてどのように評価し,どのような対応策を策定したか。また,リスクをどのような方法で監視したか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたリスクへの対応策とリスクの監視の実施状況,及び今後の改善点について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
現地法人や代理店といった外部ステークホルダによるリスクを事前に洗い出し、発生確率・影響度を評価したうえで、現場の反発や不信感に対応する具体的な対話と行動を通じて、プロジェクト目標の達成と現場の納得を両立させた。
KRIによるリスク監視や人的支援の工夫も実施されており、今後の改善としては、指標の精度向上と説明責任体制の強化が挙げた。
📝論文
🪄タイトル リスクマネジメントによる外部影響の最小化
本稿は、リスクマネジメントによる外部影響の最小化について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの特徴と目標、外部のステークホルダに起因するリスクの特定、外部のステークホルダに起因するリスクを特定した理由
1-1 プロジェクトの特徴と目標
A社は、日用品ケア、女性ケア、ベビーケアなどの製品を製造・販売する企業である。私はA社のプロジェクトマネージャとして、海外現地法人向け販売支援システムの再構築プロジェクトを担当した。既存の販売支援システムは本社開発であり、各国の業務特性に即していない部分が多く、現地法人の販売活動に支障を来していた。プロジェクトの目標は、グローバル共通基盤の整備を通じて、業務効率の向上と売上機会の最大化を図ることであった。
1-2 外部のステークホルダに起因するリスクの特定
本プロジェクトにおいては、現地法人の営業・物流部門、海外販売代理店、各国の法規制当局など、PMの直接指揮下にない外部ステークホルダが多数関与していた。私は、これら外部ステークホルダとの連携において、目標達成にマイナスの影響を与える可能性のあるリスクを洗い出した。具体的には、①現地法人の非協力、②代理店による旧業務への回帰、③法規制変更によるシステム仕様の変更要求の3点である。
1-3 外部のステークホルダに起因するリスクを特定した理由
これらのリスクを特定した理由は、過去に同様のプロジェクトにおいて、現地法人の担当者交代により合意が白紙に戻った経験や、販売代理店の反発によって旧システムが再び使用されたケース、各国の電子帳票要件変更に対応できず業務停止となった例があったからである。これらの事例を踏まえ、計画段階でステークホルダ分析を行い、PMの経験も加味しながら、多面的なリスクをあらかじめ抽出した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 リスクの評価方法、リスクへの対応策の策定、リスクの監視方法
2-1 リスクの評価方法
洗い出したリスクに対しては、発生確率と影響度をマトリクス形式で整理し、優先度の高い順に分類した。例えば、「代理店による旧業務への回帰」は発生確率は中程度ながら、影響度が高く、最重要リスクとして位置付けた。一方、「法規制変更による仕様変更要求」は発生確率はやや低かったが、致命的な障害をもたらす可能性があったため、モニタリングを重視すべきリスクと判断した。
2-2 リスクへの対応策の策定
優先度に応じた対応策を策定した。代理店対策としては、機能面での旧業務の再現を実現するカスタマイズを提案しつつ、商談実績の可視化や営業支援ツールによる利点をデモ形式で訴求した。現地法人対策としては、キーユーザを初期段階から要件定義に巻き込み、オーナーシップを醸成した。また、法規制リスクには、各国拠点に法務窓口を設置し、変更通知を早期に把握できる体制を整えた。
これらの対応策を策定するにあたり、私は「現場が面倒と感じることは必ず回避される」という前提を置いた。なぜならば、過去の失敗プロジェクトで、現地法人にとって「使いにくいもの」が理由なく拒絶され、定着しなかったからである。そこで、あくまで「現場の面倒を減らす」ことを狙って機能提案を行い、技術的な最適性よりも、「相手が納得しやすく、現場で使われる内容」を優先した。現地法人のキーユーザからは、「また本社主導で勝手に仕様を決めていないか」といった疑念の声も上がった。私はその場で、「現場の判断で変えて良い項目と、本社側で統一すべき部分を切り分けて提案している」と説明し、その場で1項目だけ現地裁量に修正できる項目を提案した。この対応は、「裁量の余地」があると認識させることで、現地側に自分ごととして捉えてもらうことを狙ったものである。
2-3 リスクの監視方法
私は、KRI(重要リスク指標)を形式的に設定するのではなく、「現場の異常が数字にどう表れるか」を考えることに腐心した。例えば、代理店の非協力は進捗報告には表れないが、システムの使用率には如実に現れると考えた。なぜならば、表向きは協力的でも裏で旧システムを使い続けるケースが多いためである。
対応策の効果とリスクの顕在化を継続的に監視するために、リスクごとにKRIを定義した。代理店の旧業務回帰リスクには「新システム使用率」、現地法人の非協力リスクには「進捗報告の提出率」、法規制対応リスクには「規制変更検知件数」を用い、毎週のプロジェクト会議で進捗とリスク状況をレビューした。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 リスク対応策と監視の実施状況、リスクマネジメントにおける今後の改善点
3-1 リスク対応策と監視の実施状況
実行段階では、代理店へのカスタマイズ提供に加え、導入初期に伴走支援を行ったことで、新システムへの定着が進んだ。現地法人についても、要件定義段階での参画が功を奏し、プロジェクト後半では各法人から改善提案が出るなど、自発的な参画が見られた。ただし、初期の現地法人会議では、「どうせ決まったことを伝えに来ただけだろ」という皮肉もあり、冷ややかな空気が漂っていた。私はあえてその場で「だからこそ今、皆さんの率直な声が必要です」と率直に伝え、具体的な困りごとを3分で一人ずつ挙げてもらう形式に変えた。結果として、最初の反発が次第に「聞いてくれる」「なら言う」と変わっていった。法規制変更への対応も、法務窓口を通じた早期検知により、要件変更が発生した際も事前対応が可能となり、納期遅延を回避できた。
私は「支援すれば現場は動く」という考え方を基に、現地法人・代理店に対して人的支援を惜しまなかった。これは単なる押し付けではなく、「分からない」「困っている」に寄り添う姿勢を通じて、信頼を勝ち取ることを狙った対応である。現場が私を「自分たちの仲間」として認識することで、自発的な改善行動につながると判断した。
3-2 リスクマネジメントにおける今後の改善点
一方で、KRIの精度については改善の余地があった。新システム使用率の算出方法が不明瞭で、代理店によって入力にばらつきがあったため、定量的な評価に限界が生じた。
私はKRIの精度向上に悩み、「何を測ればリスクの芽を早期に発見できるか」を試行錯誤した。なぜならば、現場の数値は常に正直とは限らず、意図的に操作されるリスクもあると考えたからである。このため、単純な数値ではなく、現場の実態や空気感を定量化できる「間接的な指標」の導入が必要だと痛感した。今後はログ分析や自動収集ツールを導入し、客観性とリアルタイム性を向上させる必要がある。また、リスク対応の責任主体が曖昧なケースも散見されたことから、対応計画には担当部署と責任者を明記し、進捗レビュー時に明確な説明責任を持たせる仕組みを整備することが今後の課題である。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合評価】
- 総合得点:
90点(設問対応28/課題の妥当性9/行動記述22/ステークホルダ描写9/成果14/構成・表現8) - 致命的欠陥チェック:
A: OK(PMの行動)/B: OK(ステークホルダのやり取り)/C: OK(設問ア〜ウに対応)/D: OK(成果の明示) - 最終評価:
A(合格)
✅【各評価項目の詳細】
| 評価項目 | 得点 | コメント |
|---|---|---|
| ① 設問対応 | 28/30 | 各章が設問ア〜ウと明確に対応し、内容も意図に沿っている。特に、リスク特定→評価→対応→監視→実施と、リスクマネジメントの基本ステップが網羅されている点が高評価。 |
| ② 課題の妥当性 | 9/10 | グローバル展開+現地法人との乖離という実在性ある課題を設定し、PMの視点から妥当な懸念点とつながっている。設定理由にも過去の失敗経験が織り込まれており、説得力がある。 |
| ③ 行動記述の具体性 | 22/25 | 「相手が納得しやすい仕様提案」「KRIを数字で捉える工夫」「裁量の余地を与える説明」など、判断根拠と具体行動が論理的に描かれている。改善余地としては、第2章にもう1〜2件「再交渉」「反発→段階的合意」の描写があれば満点圏。 |
| ④ ステークホルダ描写 | 9/10 | 現地法人の「どうせ決まってるだろ」「勝手に仕様を決めた」という反発に対して、PMが現場に寄り添っていくプロセスが丁寧。最終的に「聞いてくれるなら言おう」という変化を捉えており、感情の動きの描写も良好。 |
| ⑤ 成果の説得力 | 14/15 | 定量的にはKRI活用、定性的には自発的改善提案などが明示され、再現性もある。改善余地としては、成果指標の「入力率90%」「提出率100%」など具体値を添えればなお良い。 |
| ⑥ 構成・表現 | 8/10 | 文法・語彙・接続も明快で、読みやすく論理性が保たれている。若干語彙が高度で初学者には読みにくい点があるものの、PM試験としては適切なレベル。 |
📝【評価コメント】
- 設問対応
問題文の流れ(リスク特定→評価→対応→監視→成果)にきれいに沿っており、論理構成が秀逸です。見出しや章分けも明確で、読み手が迷いません。 - 行動描写
現場との対立・疑念・反発を「聞いてくれる→なら言う」という段階でほぐしていく構造があり、対話型のマネジメントが描かれています。「面倒なことは避けられる」という仮説ベースで行動する思考力の描写も良いです。 - 成果提示
実効性のあるKRIや、現地法人の行動変容(自発的改善提案)を成果として示しており、「行動が変わった=プロジェクトが変わった」という主張に説得力があります。
🔧【改善点(任意)】
- 第2章に「ステークホルダとの対話失敗→再交渉→段階的合意」パターンが1件あると、説得力が増します(例:「当初提案を拒否→妥協案提示→再評価により合意」など)。
- KRIの具体値を明示(例:「週次で80%を下回った場合はリスク顕在化とみなす」)すると、説得力と再現性が増します。
- 定量成果の明記:「使用率90%到達」「提出率95%以上を維持」など、改善指標の成果値があれば、満点評価に近づきます。
🏁【総評】
本論文は、PMがステークホルダとの関係性をどう築き、どのようにリスクに対して備え、対処し、成果に結びつけたかが論理的かつ人間味ある文体で描かれており、合格圏上位に位置する優秀な内容です。
今後は、再交渉や数値的成果の強化により、さらに満点近くを狙える構成に仕上がるでしょう。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。