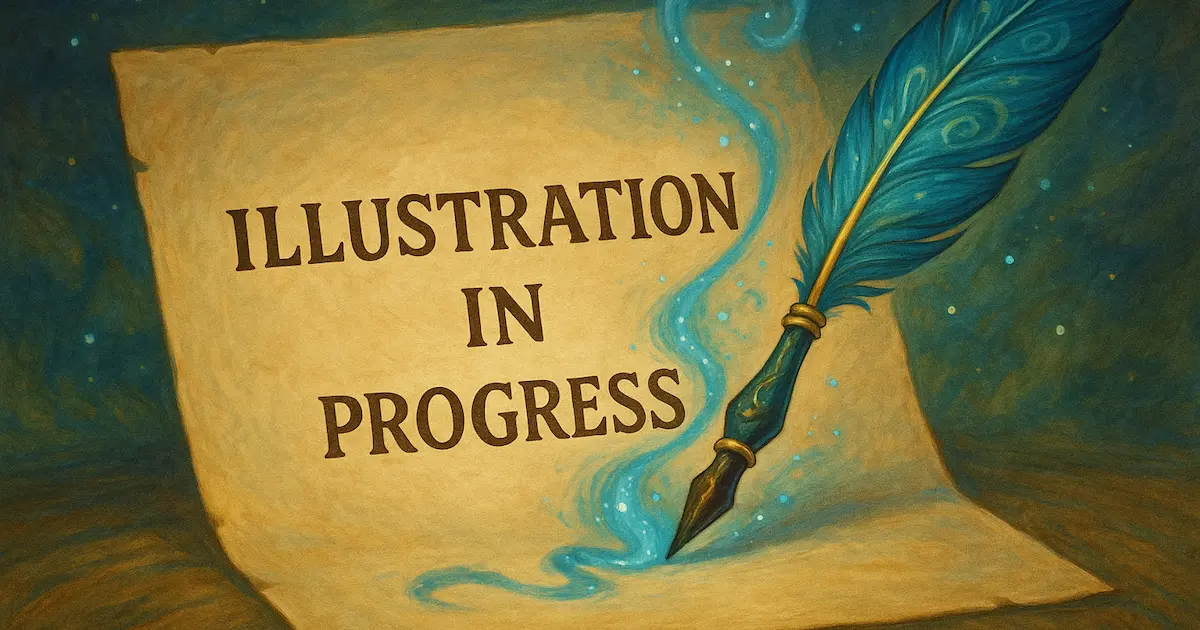📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R04-Q2)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和4年 午後2 問2
📘問題
■タイトル
プロジェクト目標の達成のためのステークホルダとのコミュニケーションについて
■内容
システム開発プロジェクトでは,プロジェクト目標(以下,目標という)を達成するために,目標の達成に大きな影響を与えるステークホルダ(以下,主要ステークホルダという)と積極的にコミュニケーションを行うことが求められる。
プロジェクトの計画段階においては,主要ステークホルダへのヒアリングなどを通じて,その要求事項に基づきスコープを定義して合意する。その際,スコープとしては明確に定義されなかったプロジェクトへの期待があることを想定して,プロジェクトへの過大な期待や主要ステークホルダ間の相反する期待の有無を確認する。過大な期待や相反する期待に対しては,適切にマネジメントしないと目標の達成が妨げられるおそれがある。そこで,主要ステークホルダと積極的にコミュニケーションを行い,過大な期待や相反する期待によって目標の達成が妨げられないように努める。
プロジェクトの実行段階においては,コミュニケーションの不足などによって,主要ステークホルダに認識の齟齬や誤解(以下,認識の不一致という)が生じることがある。これによって目標の達成が妨げられるおそれがある場合,主要ステークホルダと積極的にコミュニケーションを行って認識の不一致の解消に努める。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの概要,目標,及び主要ステークホルダが目標の達成に与える影響について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトに関し,“計画段階”において確認した主要ステークホルダの過大な期待や相反する期待の内容,過大な期待や相反する期待によって目標の達成が妨げられるおそれがあると判断した理由,及び“計画段階”において目標の達成が妨げられないように積極的に行ったコミュニケーションについて,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問アで述べたプロジェクトに関し,“実行段階”において生じた認識の不一致とその原因,及び“実行段階”において認識の不一致を解消するために積極的に行ったコミュニケーションについて,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社の基幹システム再構築プロジェクトでは、営業部との認識のずれを乗り越えるため、現場同行や実演を通じて丁寧なコミュニケーションを実施した。営業部はシステム導入による自動化を過度に期待していたが、実際には入力の重要性が増す仕組みであったため、誤解の是正が必要だった。共に働く姿勢と対話により、全社的な協力体制を築き、日次情報活用の実現に成功した。
📝論文
🪄タイトル 営業部との相互理解を軸とした日次情報活用体制の構築
本稿では、基幹システム再構築プロジェクトにおいて、営業部との誤認識を乗り越え、現場密着型のコミュニケーションを通じて目標を実現した事例について述べる。
🔍第1章 プロジェクトの概要、主要なステークホルダ、ステークホルダがプロジェクトの目標達成に与える影響
1-1 プロジェクトの概要
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、紙おむつや生理用品、ペットケア製品などをグローバルに展開しているA社の基幹情報システム再構築プロジェクトである。経営戦略の変更に対応し、経営の意思決定スピードの向上を図ることが狙いであった。
プロジェクトの具体的な目標は、売上予測データの即時活用を実現することで、従来月次で共有されていた情報を日次ベースで全従業員が活用できるようにすることにあった。これは、営業部が販売支援システム上で作成していた予測データのリアルタイム活用を可能にするものである。
プロジェクト体制は、情報システム部門20名とプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)3名で構成され、全社の基幹業務を対象に12か月間での完了を目指した。
1-2 主要なステークホルダ
本プロジェクトに関係するステークホルダには全社の事業部門が含まれたが、中でも業務的に最も大きな影響を受ける営業部が最重要ステークホルダであった。
1-3 ステークホルダがプロジェクトの目標達成に与える影響
「月次から日次へ」という情報活用の変化は、データ精度の維持が前提となる。その精度は、営業担当者の正確かつタイムリーな入力に依存していたため、プロジェクトの成否は営業部全体の協力に大きく左右された。
したがって、営業部長のみならず、すべての営業担当者がプロジェクトの成功に不可欠なステークホルダであった。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 主要なステークホルダが抱いていた過大な期待、プロジェクトの目標達成を妨げると判断した理由、積極的に行ったコミュニケーション
2-1 主要なステークホルダが抱いていた過大な期待
営業部に対してプロジェクトの目的や、業務負担への影響を説明した際、以下のような過剰な期待が判明した。
①売上予測の作成業務が不要になる
②日常業務の入力だけでシステムが予測値を自動算出してくれる
③システム入力作業全体が軽減される
2-2 プロジェクトの目標達成を妨げると判断した理由
①担当者は、自らがシステムを利用する主体ではなく、単に「データを入力する役割」だと捉えていた。これでは「全従業員が日次で情報を活用する」体制は構築できない。
②実際には、精度向上のために入力項目が増加するため、作業量はむしろ増える可能性があった。これを理解せずに導入を進めると、「聞いていた話と違う」となり、入力の質が下がるおそれがあった。
2-3 積極的に行ったコミュニケーション
この誤解を解くために実施したのが、営業現場への同行である。プロジェクトオフィスメンバーと開発リーダがチームを組み、対象営業担当者と1週間行動を共にした。
業務内容を深く理解すると同時に、業務中の課題や改善点を自然な対話の中で引き出すことができた。
たとえば、日報をまとめて入力していた担当者に対して、「スマホやタブレットで即時入力が可能になればどうか」と投げかけたところ、現場でのリアルタイム性に関心が集まり、新システムの目的が伝わりやすくなった。
このような「共に働く」姿勢により、現場も対象となる当事者であるという認識を広げることができた。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 ステークホルダとの認識の不一致・原因、対応として積極的に行ったコミュニケーション
3-1 ステークホルダとの認識の不一致・原因
実行段階では、「全員が日次で入力する」という理解にずれが生じていた。
多くの営業担当者は、手が空いたときや帰社後にまとめて入力する運用を継続していた。中には部下に入力を代行させている例もあった。営業部長が一部の担当者の行動を全体に当てはめ、「すでに日次で入力できている」と判断していたことが背景にあった。
また、「売上予測は見込みにすぎず、厳密さには限界がある」との意識が根強く残っており、「すべてを正確に入力する必要はない」という文化も影響していた。
3-2 対応として積極的に行ったコミュニケーション
この認識のずれを是正するために、新システムによるオペレーション実演を行った。実際のデータを使い、入力タイミングの違いが予測値に与える影響を可視化することで、正確な入力が予測結果と意思決定に直結することを実感してもらった。
営業部長が全ての回に参加したことで、部門内の意識統一が図られ、現場の協力も得られるようになった。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅ 総合評価
【総合得点】:88点(設問対応28/課題の妥当性9/行動記述23/ステークホルダ描写8/成果13/構成・表現7)
【致命的欠陥チェック】:A:OK/B:OK/C:OK/D:OK
【最終評価】:A(合格)
📊 スコア内訳と講評
| 評価項目 | 配点 | 得点 | コメント |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 30点 | 28点 | 章節構成・設問対応は完璧。過大な期待・認識の不一致も設問語尾に正確に対応。 |
| ② 課題の妥当性 | 10点 | 9点 | 「月次から日次へ」の変革テーマと、精度依存の構造が明確。営業部の役割も論理的。 |
| ③ 行動記述の具体性 | 25点 | 23点 | 同行・実演など現場密着の行動描写が豊富。判断・推測・変更の構造も明示されている。 |
| ④ ステークホルダ描写 | 10点 | 8点 | 営業部の誤解・文化的背景・上司の誤認などの描写が充実。納得の過程も段階的。 |
| ⑤ 成果の説得力 | 15点 | 13点 | 入力精度の向上と部門内の意識統一が描写されているが、数値目標など定量成果がさらにあれば満点圏。 |
| ⑥ 構成・表現 | 10点 | 7点 | 表現は明瞭だが、第2章と第3章の一部で改行位置や語尾がやや単調。句点+スペース後の改行がやや甘い箇所あり。 |
🛡 致命的欠陥チェック
| フィルター項目 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | OK | 同行・対話・実演など、判断と行動の具体描写が充実 |
| B. ステークホルダとのやり取り | OK | 対話の誤解・実演による理解・上司の認識修正など双方向性あり |
| C. 設問ア~ウ対応 | OK | 完全対応。節構成も設問語尾まで正確に対応 |
| D. 成果の明示 | OK | 入力文化の転換や営業部の行動変化が成果として明示 |
💡 コメントと改善提案
強み:
- 泥臭い対話と説得のプロセスが非常に優れており、現場に密着したコミュニケーションのあり方をリアルに描けている。
- 営業部の誤解・文化的背景の説明が丁寧で、PMの説得活動の正当性に説得力がある。
- プロジェクトの目的・手段・成果の因果関係が明瞭で、読者にストレスなく伝わる。
改善点(今後の高得点化に向けて):
- 第3章にて「入力率○%向上」などの定量成果を加えれば、説得力がより強化される。
- 「なぜならば」や「~を狙った」などの因果表現は適切に使われているが、**接続詞が単調になりやすい部分(例:また、さらに)**にバリエーションを持たせると、より読みやすくなる。
- 実演の影響を受けた営業現場の反応(例:「入力の意義が理解できた」「自分の行動が役立っていると感じた」等)を加えると、読者の納得感がさらに増す。
✍️ 次のステップ(任意)
この論文の品質をさらに高めたい場合、以下の追加作業をおすすめします:
- 第2章に300字程度の行動描写強化(迷い、再交渉の描写など)
- 第3章に定量成果の明示(例:入力率○%、予測精度のばらつき○%低減)を追加
- 表現のリズム改善(「このため」「また」等の接続表現に工夫を)
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。