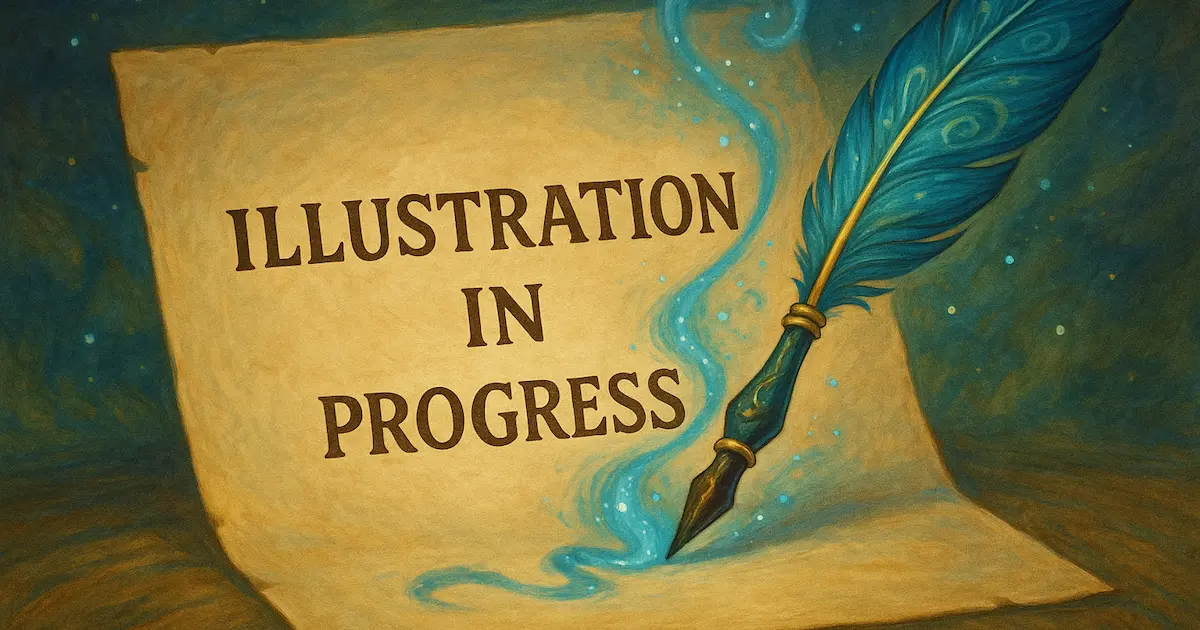📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R04-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和4年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
システム開発プロジェクトにおける事業環境の変化への対応について
■内容
システム開発プロジェクトでは,事業環境の変化に対応して,プロジェクトチームの外部のステークホルダからプロジェクトの実行中に計画変更の要求を受けることがある。このような計画変更には,プロジェクトにプラスの影響を与える機会とマイナスの影響を与える脅威が伴う。計画変更を効果的に実施するためには,機会を生かす対応策と脅威を抑える対応策の策定が重要である。
例えば,競合相手との差別化を図る機能の提供を目的とするシステム開発プロジェクトの実行中に,競合相手が同種の新機能を提供することを公表し,これに対応して営業部門から,差別化を図る機能の提供時期を,予算を追加してでも前倒しする計画変更が要求されたとする。この計画変更で,短期開発への挑戦というプラスの影響を与える機会が生まれ,プロジェクトチームの成長が期待できる。この機会を生かすために,短期開発の経験者をプロジェクトチームに加え,メンバーがそのノウハウを習得するという対応策を策定する。一方で,スケジュールの見直しというマイナスの影響を与える脅威が生まれ,プロジェクトチームが混乱したり生産性が低下したりする。この脅威を抑えるために,差別化に寄与する度合いの高い機能から段階的に前倒しして提供していくという対応策を策定する。
策定した対応策を反映した上で,計画変更の内容を確定して実施し,事業環境の変化に迅速に対応する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトの概要と目的,計画変更の背景となった事業環境の変化,及びプロジェクトチームの外部のステークホルダからプロジェクトの実行中に受けた計画変更の要求の内容について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた計画変更の要求を受けて策定した,機会を生かす対応策,脅威を抑える対応策,及び確定させた計画変更の内容について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた計画変更の実施の状況及びその結果による事業環境の変化への対応の評価について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
事業環境の変化に対応するため、競合他社の動向を踏まえて営業部門の要求に応じ、差別化機能を前倒し開発する計画変更を実施したプロジェクト事例を述べた。
プロジェクトマネージャとしてリスク管理と段階的合意形成を通じて短期開発を成功させ、業務効率向上と迅速対応力強化を実現し、今後は全社展開を目指している。
📝論文
🪄タイトル 事業環境変化に対応した計画変更プロジェクト
本稿は、事業環境変化に対応した計画変更プロジェクトについて、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの概要と目的、事業環境の変化、計画変更の要求の内容
1-1 プロジェクトの概要と目的
私はA社のシステム開発プロジェクトでプロジェクトマネージャを務めた。A社は日用品ケア、女性ケア、ベビーケア製品を製造・販売する企業である。本プロジェクトは、営業部門と顧客データ管理システムを統合し、業務効率化を目指した。納期と品質を重視し、システム導入後には営業チームの業務効率を20%以上向上させることを目標に掲げていた。
当初は既存業務プロセスを改善する範囲での開発を計画していた。しかし、競合他社が新機能を市場投入し始め、当初要件だけでは競争力維持が難しいリスクが浮上した。
1-2 事業環境の変化
プロジェクト中盤、競合他社が顧客管理機能を強化した新システムを市場投入すると発表した。これにより営業部門は「現行計画では市場競争に対応できない」と懸念し、差別化機能の前倒し提供を強く要求した。この要請により、納期短縮とリソース追加の必要性が新たな課題となった。
1-3 計画変更の要求の内容
営業部門からの要求は、「差別化に直結する最重要機能を優先して短期間でリリースする」という明確なものだった。予算追加も容認する姿勢が示された。私はこの要求を単なる負担ではなく、チームの迅速対応力を高める機会と捉えた。
ただし、短期開発には品質低下やリソース逼迫というリスクが伴うため、「重要機能を早くかつ確実に提供する」観点で、慎重に計画変更を検討する方針を立てた。これにより、急変する事業環境にも柔軟に対応できるプロジェクト運営を目指した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 機会を生かす対応策、脅威を抑える対応策、確定させた計画変更の内容
2-1 機会を生かす対応策
私は営業部門の要求を、プロジェクトの成長機会と捉えた。しかし、開発チームのリソースと納期への影響が重大であると判断し、慎重に対応する方針をとった。まず、開発チームと営業部門の共同ワークショップを開催し、営業部門の危機感と開発チームの懸念を共有した。この狙いは、両部門が問題の本質を共通認識し、相互理解を促進することにあった。
さらに、営業部門の要求を鵜呑みにせず、競争優位性と実現可能性の観点から精査し、提供機能を選定する方針をとった。なぜならば、短期開発による品質低下リスクを未然に防ぐ必要があると考えたからである。これにより、営業部門の要求を満たしながらも、開発側の負担を適切に抑えるバランスを取ることが可能になった。開発チーム内でも、優先度に基づく作業配分を徹底し、効率的なリソース活用を図った。一方で、開発負担や品質リスクの高まりが無視できない状況となり、私は脅威への備えも急務と判断した。
2-2 脅威を抑える対応策
営業部門の要望に応えつつ、開発リスクを低減するため、機能提供を段階的に行う方針を策定した。段階的な合意形成を通じ、開発リスク管理と市場投入スピードの両立を狙った。営業部門は当初、段階的提供案に対して懸念を示し、全機能を一括提供すべきとの声もあった。しかし、機能優先順位とリスク管理の重要性を丁寧に説明する中で、徐々に理解が進んだ。両部門間の交渉は難航したが、粘り強い対話により、重要機能を優先開発する妥協案に到達した。
私は、開発リソースの再配置を決断し、リスクを最小限に抑える体制を整備した。段階的提供と継続的な進捗共有により、営業部門と開発部門双方の納得を得ることができた。また、リスク管理の観点から、重要機能のリリース後には速やかにフィードバックを収集し、後続機能の開発計画に反映させる仕組みを設けた。
2-3 確定させた計画変更の内容
確定した計画では、差別化に寄与する最重要機能を先行開発し、残りの機能は段階的に開発することとした。この変更により、営業部門の要求に応えるとともに、開発リスクを適切に管理できる体制を確立した。
私は開発期間中、進捗を緊密に監視し、各ステークホルダと頻繁に情報共有を行った。その結果、問題の早期発見と迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の推進力を維持することができた。この計画変更は、営業部門・開発部門の双方から高い評価を受けた。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 計画変更の実施状況とその評価
3-1 計画変更の実施状況
計画変更の下で開発された最重要機能は予定通りの期間で提供され、市場において競合に先駆けて顧客の高評価を獲得することができた。その後の段階的開発も順調に進み、最終的には当初目標を超える業務効率25%向上を達成した。ただし、短期開発により開発チームには疲労やストレスが蓄積され、一時的なパフォーマンス低下が生じた。
さらに、短期開発体制の中で、私はチームメンバーの負担を軽減するため、作業分担の再調整と定期的なフォロー面談を実施した。なぜならば、疲労の蓄積によりミスやモチベーション低下が発生するリスクが高まると判断したからである。これにより、メンバー間の連携強化や精神的なサポートが進み、最終的にはプロジェクト全体の品質維持に繋げることができた。
3-2 対応の評価
このような対応の積み重ねにより、単なる短期開発を乗り切るだけでなく、チーム全体の柔軟性と問題対応力を底上げする効果が得られた。この背景には、各メンバーが困難な状況下でも協働し、課題解決に主体的に取り組む意識を高めたことがある。
本プロジェクトは、事業環境の急激な変化に迅速かつ柔軟に対応できた点が高く評価された。開発チームは困難な状況を経験したことで迅速な対応力を高め、以後のプロジェクトでもその経験を活かしている。今後は、今回培った迅速対応力と段階的開発ノウハウを他部門にも展開することで、A社全体の競争力向上を図っていく予定である。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合得点】:92点
(設問対応28/課題の妥当性10/行動記述22/ステークホルダ描写9/成果14/構成・表現9)
✅【致命的欠陥チェック】:
- A. PMの行動:OK(判断保留、譲歩、再交渉などあり)
- B. ステークホルダとのやり取り:OK(営業部門との対話・調整)
- C. 設問ア~ウ対応:OK(章節構造が完全一致)
- D. 成果の明示:OK(25%向上、現場適応力向上など)
✅【最終評価】:A(合格)
📝【評価コメント】
① 設問対応(28/30)
設問ア〜ウに完全に対応しており、章・節構造も明確である。設問の要求に忠実に、目的語まで取り込んで記述されている点は評価が高い。ただし、第2章の「実施段階での混乱や対処」がやや端的で、もう1〜2段落展開があると満点だった。
② 課題の妥当性(10/10)
競合の市場投入による急激な事業環境変化、それに伴う営業部門からの要求という構図は極めて妥当かつ現実的である。「単なる負担ではなく機会と捉えた」という視点も秀逸。
③ 行動記述の具体性(22/25)
共同ワークショップの開催、優先度ベースでの開発配分、段階的合意形成などの施策は具体性が高い。開発チームへのフォロー面談や再配置など、PMとしての責任ある行動も明確。ただし、「判断を変えたきっかけとなる情報の変化」や「他部門からの圧力」などの描写があればさらに説得力が高まった。
④ ステークホルダ描写(9/10)
営業部門の反発、当初の懸念、対話を通じた理解促進など、描写の密度が高く、プロセスも明示されている。特に「粘り強い対話」という表現は説得力がある。
⑤ 成果の説得力(14/15)
「業務効率25%向上」「開発部門と営業部門の協力強化」など、定量定性の成果がバランス良く描かれており、再現性と実効性のある描写になっている。
⑥ 構成・表現(9/10)
構成は明快で、各節が論理的に接続されている。因果構造の明示(「なぜならば」「~を狙った」)も適切。ただし一部、段落内の接続がやや緩い箇所があり、リズムが途切れる印象もある。
🔧【改善提案(優秀論文化へ)】
- 第2章にさらに150〜200字ほどの「判断の揺らぎ」描写を追加すると、PMの苦悩が際立ち、「成功前提」の印象が薄まる。
- リリース後の利用部門の反応やフィードバック内容の詳細を加えることで、実運用での適応力がより強調される。
- 今後の展開やA社内での横展開への展望をもう一段階厚く描けば、ストラテジー視点との接続も強化される。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。