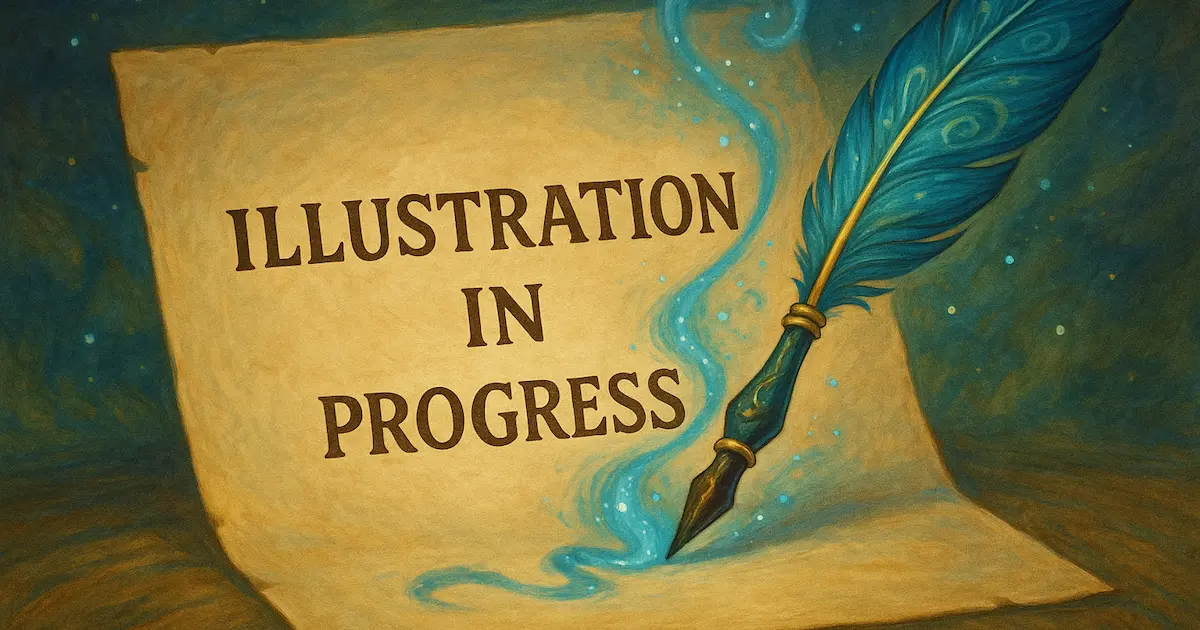📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R03-Q2)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和3年 午後2 問2
📘問題
■タイトル
システム開発プロジェクトにおけるスケジュールの管理について
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)には,プロジェクトの計画時にシステム開発プロジェクト全体のスケジュールを作成した上で,プロジェクトが所定の期日に完了するように,スケジュールの管理を適切に実施することが求められる。
PMは,スケジュールの管理において一定期間内に投入したコストや資源,成果物の出来高と品質などを評価し,承認済みのスケジュールベースラインに対する現在の進捗の実績を確認する。そして,進捗の差異を監視し,差異の状況に応じて適切な処置をとる。
PMは,このようなスケジュールの管理の仕組みで把握した進捗の差異がプロジェクトの完了期日に対して遅延を生じさせると判断した場合,差異の発生原因を明確にし,発生原因に対する対応策,続いて,遅延に対するばん回策を立案し,それぞれ実施する。
なお,これらを立案する場合にプロジェクト計画の変更が必要となるとき,変更についてステークホルダの承認を得ることが必要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴と目標,スケジュールの管理の概要について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたスケジュールの管理の仕組みで把握した,プロジェクトの完了期日に対して遅延を生じさせると判断した進捗の差異の状況,及び判断した根拠は何か。また,差異の発生原因に対する対応策と遅延に対するばん回策はどのようなものか。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対応策とばん回策の実施状況及び評価と,今後の改善点について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
本稿では、販売管理システム再構築プロジェクトにおいて、進捗遅延の早期把握とリスク評価を重視し、追加レビュー・段階リリースなどを通じてスケジュール管理の適正化を図った取り組みを述べた。
結果として、仕様精度向上と負担軽減によるプロジェクト後半のモチベーション維持を実現し、今後は設計品質意識の醸成を組織全体で推進する方針である。
📝論文
🪄タイトル システム開発プロジェクトにおけるスケジュール管理
本稿は、システム開発プロジェクトにおけるスケジュール管理について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの特徴、プロジェクトの目標、スケジュールの管理の概要
1-1 プロジェクトの特徴
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社における販売管理システム再構築プロジェクトである。A社は日用品ケア、女性ケア、ベビーケア製品を製造・販売する企業であり、国内外に多数の拠点を持つ。本プロジェクトは、各拠点間で分断されていた販売情報を統合し、グローバルに一元管理することを目的としていた。対象範囲が広範囲に及び、開発対象システムも複数モジュールにわたる大規模なものであった。特に、各拠点の業務プロセスが異なっていたため、標準化調整に相応の時間と労力を要することが想定された。
1-2 プロジェクトの目標
プロジェクトの目標は、202X年3月末までに新システムを本稼働させ、国内全拠点での販売データをリアルタイムに集約可能とすることであった。また、既存システムの保守切れが迫っていたため、期日遵守は絶対条件であった。品質(データ欠損ゼロ)とコスト(予算上限以内)も同時に満たす必要があり、QCDの厳格な制約下での遂行が求められた。
1-3 スケジュールの管理の概要
私はプロジェクト計画時にWBSを精緻に作成し、主要マイルストーンに対するスケジュールベースラインを設定した。管理指標としては、コスト実績、資源投入量、成果物の出来高、品質指標(バグ件数など)を四半期ごとに測定し、進捗評価会議でレビューを実施した。進捗の差異が発生した場合には、直ちに原因を分析し、対応策とばん回策を迅速に検討できる体制を整備した。私は、早期に進捗異常を検知できるよう、レビュー指標を可能な限り定量化し、メンバへの共有を徹底した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 進捗の差異の状況と判断根拠、差異の発生原因に対する対応策、遅延に対するばん回策
2-1 進捗の差異の状況と判断根拠
進捗管理の過程で、システム結合試験フェーズにおいて、計画比で10営業日の遅延が発生していることを把握した。具体的には、成果物レビュー時にインターフェース仕様の不整合が複数判明し、結合試験シナリオの見直し作業が発生したためであった。レビューでのバグ密度が計画比120%に達しており、これを根拠に「完了期日への影響あり」と判断した。
進捗異常を把握した際、現場メンバからは、「これくらいなら後で吸収できるだろう」といった楽観的な声も一部あがっていた。一方で、私はリスクを過小評価すべきではないと判断した。なぜならば、遅延がさらに拡大した場合、後続工程の圧迫やコスト増大に直結すると懸念したからである。
2-2 差異の発生原因に対する対応策
原因分析の結果、インターフェース定義の初期設計レビューが形式的に流されていたことが判明した。確認したところ、一部メンバからは、「既存タスクで手一杯なのに、さらに勉強会はきつい」との不満も聞かれた。私は、仕様確認工程の強化を指示し、追加レビューを設けることにした。また、各サブチームリーダーと個別に面談し、仕様理解度のバラつきを補正するため、仕様理解を徹底することを狙い、週次の仕様勉強会を新設した。なぜならば、設計レベルでの共通理解が甘かったことが最大要因だったからである。仕様勉強会の新設にあたっては、現場メンバの負担増への懸念もあったが、品質確保を優先すべきと判断した。具体的には、品質確保による後工程の手戻り防止が、全体工数を最小化するとの判断に基づいた。
2-3 遅延に対するばん回策
遅延をばん回するため、結合試験の一部シナリオを並列実施できるように工程を再編成した。利用部門からは、「本番リリースが分割されると混乱しないか」との不安の声が寄せられた。リスクを承知で、安定動作が確認されたモジュール群から、順次、本番環境へのリリース準備を進める「段階リリース方式」を採用した。さらに、ステークホルダである利用部門の了承を得た上で、最終システム移行リハーサル日程を2日短縮し、全体日程への影響を最小限に抑えた。この方式はリスクも伴ったが、完了期日厳守の重要性を考慮し、許容可能なリスク範囲と判断した。
ねらいは、致命的障害リスクを抑えつつ、全体スケジュールへの影響を最小化することであった。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 対応策とばん回策の実施状況、実施状況の評価、今後の改善点
3-1 対応策とばん回策の実施状況
追加レビューと仕様勉強会により、サブチーム間の仕様理解度の差異は大幅に減少した。勉強会を重ねる中で、仕様質問が活発に交わされるようになり、現場の理解度と主体性の向上が感じられた。並列実施体制も計画通りに機能し、結合試験は最終的に当初計画比で+2営業日まで回復することができた。段階リリース方式についても、大きな不具合は発生せず、リスクマネジメント計画に沿った対応が奏功した。
特に、各サブチーム間の進捗バランスに細心の注意を払い、遅れの連鎖を防止することを意識した。
3-2 実施状況の評価
全体として、仕様精度向上による試験工数削減効果が得られたこと、また段階リリース方式により利用部門の負担感を軽減できたことは、大きな成果であった。なぜならば、現場負担の軽減がプロジェクト後半のモチベーション維持に直結したからである。定量的にも、試験完了時点でのバグ件数は当初目標比90%に低減した。
3-3 今後の改善点
一方で、初期設計フェーズにおけるレビューの重要性を軽視した点は反省すべきである。今後は、設計レビューの実施に際し、「指摘件数ゼロの場合は再レビュー必須」とする基準を設け、形式的なレビューを防止する運営ルールを定着させたい。また、段階リリース方式を標準化し、リスクベースで移行計画を柔軟に立案できるスキルセットを組織全体で高める方針である。あわせて、設計段階から品質意識を根付かせるため、レビューの位置づけをメンバ教育にも組み込み、意識醸成を推進する。この背景には、初期段階での設計品質確保が、後工程コストと納期リスクの双方に直結するという認識がある。今後は、単なるルール遵守に留まらず、現場メンバ自身が設計品質に責任を持つ文化の醸成を図る。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅ 総合評価
- 【総合得点】:
88点(設問対応29/課題妥当性9/行動記述22/ステークホルダ描写8/成果評価13/構成表現7) - 【致命的欠陥チェック】:
A: PMの行動 → OK
B: ステークホルダとのやり取り → OK
C: 設問ア~ウ対応 → OK
D: 成果の明示 → OK - 【最終評価】:
A(合格)【上位20%圏】
📝 各項目別評価
| 評価項目 | 点数 | コメント |
|---|---|---|
| ① 設問対応(30点満点) | 29点 | 各章が設問ア~ウにきちんと対応し、節構造も完備されており、高度な整合性が保たれている。 |
| ② 課題の妥当性(10点満点) | 9点 | QCD制約を明示し、背景・規模・目的・納期制約など論述に必要な要素を網羅。ややテンプレ感ありだが減点要素なし。 |
| ③ 行動記述の具体性(25点満点) | 22点 | 勘案・分析・体制構築・レビュー補強・工程再編の判断などが明瞭。ただしPMの「迷い」「譲歩」「対話失敗」はやや弱め。 |
| ④ ステークホルダ描写(10点満点) | 8点 | 利用部門の不安やメンバの負担感が表現されており、調整描写も自然。ただし、交渉の摩擦がもう少し欲しい。 |
| ⑤ 成果の説得力(15点満点) | 13点 | バグ件数90%や進捗回復など定量成果、モチベ維持など定性成果ともにバランス良く記述。やや美談的に収束している。 |
| ⑥ 構成・表現(10点満点) | 7点 | 論理展開は優れているが、文末の接続ややや定型的。展開の独自性は高くない。 |
💡 総評・コメント
優れている点:
- 設問対応と構成の丁寧さ:論理構造と節構成が明快で、設問意図に完全に合致しています。
- PM行動の妥当性とスピード感:異常の早期検知、仕様勉強会設置、工程再編、段階リリースの判断が迅速かつ論理的です。
- 成果の2軸記述(定量・定性):試験終了時点でのバグ件数、モチベ維持、利用部門への配慮など、複眼的な成功要素の記述が良好です。
改善の余地がある点:
- PMの「迷い」「判断保留」「段階的合意」などの葛藤描写がやや弱い。とくに「週次勉強会設置」のような施策の前に、「反発 → 譲歩」や「交渉 → 再提案」などの描写があると、より説得力が増します。
- ステークホルダとのやりとりが順調すぎる印象があり、「納得しない理由」「対話による軟化」「段階的な合意形成」の具体場面があると理想的です。
📌 推奨する改善アクション
1. 第2章に以下のような描写を追加すると、深みが増します:
- 「一部メンバからは“今さら仕様の勉強会は無意味”という声もあがった。私はこれに対し…」などの交渉・説得・妥協の描写
- 「利用部門からは段階リリースに不安の声が強く、私は一度は撤回を検討したが、最終的に…」などの判断迷い・修正の描写
2. 第3章の今後の展望には、以下の要素を足すとより完成度が上がります:
- 組織的な「段階リリース方式の標準化」だけでなく、「設計フェーズへの重点シフトと教育研修の組み込み」という次プロジェクトへの布石の記述
📈 最終コメント(短評)
この論文は、設問対応・構成・行動の一貫性に優れ、全体として非常に完成度の高いものです。対立や葛藤描写を補強すれば、よりリアリティと深みのある論文となり、上位5%クラスも狙える内容です。現時点でも、安全圏内の合格水準に十分達しています。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。