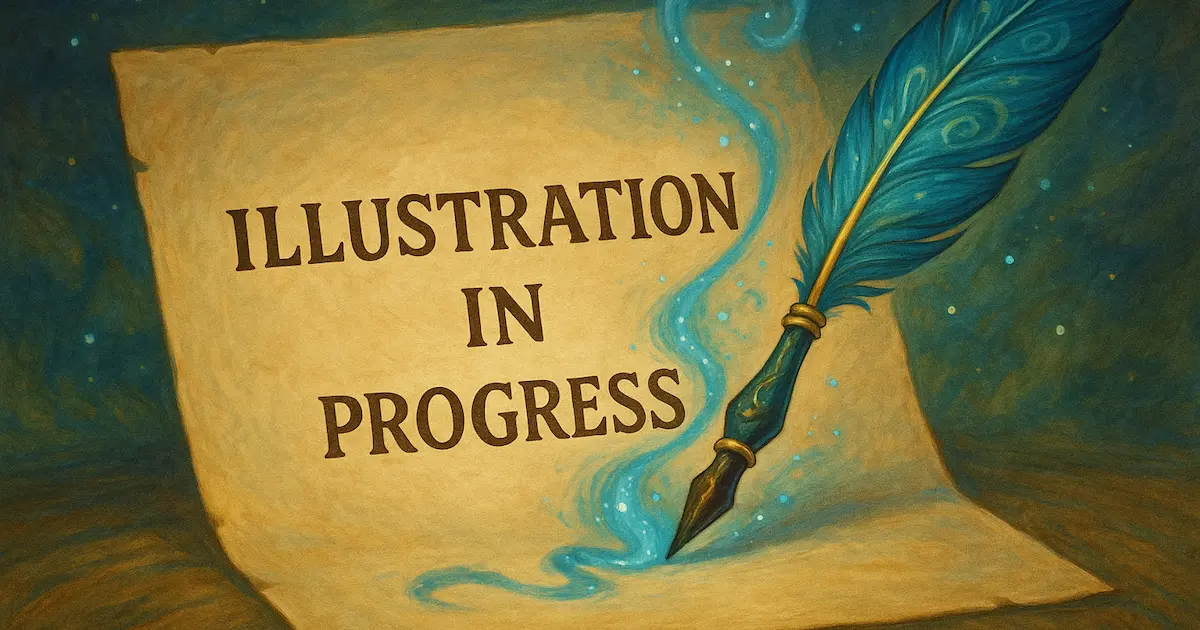📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R03-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和3年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
システム開発プロジェクトにおけるプロジェクトチーム内の対立の解消について
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)は,プロジェクトの目標の達成に向け継続的にプロジェクトチームをマネジメントし,プロジェクトを円滑に推進しなければならない。
プロジェクトの実行中には,作業の進め方をめぐって様々な意見や認識の相違がプロジェクトチーム内に生じることがある。チームで作業するからにはこれらの相違が発生することは避けられないが,これらの相違がなくならない状態が続くと,プロジェクトの円滑な推進にマイナスの影響を与えるような事態(以下,対立という)に発展することがある。
PMは,プロジェクトチームの意識を統一するための行動の基本原則を定め,メンバに周知し,遵守させる。プロジェクトの実行中に,プロジェクトチームの状況から対立の兆候を察知した場合,対立に発展しないように行動の基本原則に従うように促し,プロジェクトチーム内の関係を改善する。
しかし,行動の基本原則に従っていても意見や認識の相違が対立に発展してしまうことがある。その場合は,原因を分析して対立を解消するとともに,行動の基本原則を改善し,遵守を徹底させることによって,継続的にプロジェクトチームをマネジメントする必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴,あなたが定めた行動の基本原則とプロジェクトチームの状況から察知した対立の兆候について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトの実行中に作業の進め方をめぐって発生した対立と,あなたが実施した対立の解消策及び行動の基本原則の改善策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況及び評価と,今後の改善点について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社の基幹情報システム統合プロジェクトにおいて発生したチーム間対立を、行動原則の再定義と段階的な対話施策により解消し、信頼向上と合意形成を実現した過程を述べたものである。さらに、将来の対立防止に向け、専門性理解と共通認識を促進するワークショップ施策を計画し、プロジェクト運営の一層の円滑化を目指している。
📝論文
🪄タイトル プロジェクトチーム内対立の解消と行動原則の改善
本稿は、プロジェクトチーム内対立の解消と行動原則の改善について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの特徴、行動の基本原則、察知した対立の兆候
1-1 プロジェクトの特徴
A社は、日用品ケア、女性ケア、ベビーケア商品を製造・販売する企業である。私はA社の基幹情報システム再構築プロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャを務めた。
本プロジェクトは、分散管理されていた7部署のシステムを統合し、現行体系の機能を90%以上保持することが要求された。また、納期遵守の制約もあり、業務運用への影響最小化と、効率的な統合作業が求められる状況であった。さらに、7部署それぞれでシステム環境や運用プロセスが異なる状況にあり、統合に向けた調整難易度も高いと私は見込んだ。
1-2 定めた行動の基本原則
異なる部署の利害や業務慣行が交錯する中で、私は「専門性を尊重し、互いを尊重し合う」ことを基本原則と定めた。これは、統合作業を成功させるためには、分業基盤を互いに支え合う意識が不可欠であると判断したからである。基本原則は、プロジェクトキックオフ時に全チームメンバーへ明示的に周知した。
1-3 察知した対立の兆候
プロジェクト実行中、活動計画設計チームとテスト実行チームの間で、作業進行に対する評価基準や言語体系の違いが目立つようになった。小さな認識違いが積み重なり、責任所在の曖昧化や、タスク遂行への不満が広がる兆候が見られた。
私はこの段階で、早期介入による是正を試みるか、もう少し状況観察を続けるかで判断に迷った。最終的に、対立の深刻化を防ぐため、行動原則の再周知とリーダークラスへの注意喚起を実施することを決意した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 作業の進め方をめぐって発生した対立、実施した対立の解消策、行動の基本原則の改善策
2-1 作業の進め方をめぐって発生した対立
テスト実行チームからは、実情を重視して変更に対応すべきとの要望が出され、計画設計チームとの合意を得られなかった。これにより、互いの専門性を持ち出し、相互責任を押し付け合う傾向が強まった。
私は、両チームの主張が平行線をたどる中で、このままでは作業遅延と士気低下が避けられないと判断した。特に、遅延によるコスト増加とチームのモチベーション低下が、プロジェクト全体の品質確保に影響を及ぼすことを強く懸念した。そこで、対話機会を設けるとともに、まず各部署間の前提認識の違いを明確にする必要があると考えた。具体的には、各部署間で異なる業務プロセスやシステム環境が存在し、それらの違いを認識し、尊重しつつ連携を図る必要があった。
2-2 実施した対立の解消策
私は、行動の基本原則の内容を「相互の主張を聞き合う」へ編成し、計画・実行の論点を継続的に見える化するため、新たに「複合チェックミーティング」を設けた。なぜならば、過去の類似プロジェクトにおける失敗事例を教訓とし、対立の早期可視化が成果向上に直結すると判断したからである。これは、相手の感情を尊重し、かつ実用性を両立させることを意図したものである。
複合チェックミーティングの導入にあたって、私は一度強い懸念を抱いた。なぜならば、相互の主張が対立したまま場を持つことは、かえって感情的対立を助長する恐れがあったからである。そこで、最初のミーティングでは、議題を「事実確認」に絞り、評価・意見交換は第2回以降に限定する方式を採った。具体的には、初回ミーティングでは各チームが直面した事象と選択肢だけを列挙し、相互非難を避けることを狙った。この段階的な合意形成により、次第に「相手の事情を理解しようとする空気」が醸成され、対話の質が改善していった。
2-3 行動の基本原則の改善策
行動原則を、「専門性の対立より、相互の歩み寄りを優先する」と再定義し、プロジェクト内スクラムで協議の経緯を実名で記録するようルールを変更した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況、実施状況の評価、今後の改善点
3-1 対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況
複合チェックミーティングの実施により、計画設計チームとテスト実行チーム間で、作業進め方に対する合意が8割以上の段階で得られた。当初は基本方針すら共有できない状態だったことを踏まえると、この8割合意は、プロジェクト推進上極めて大きな前進だったと評価できる。一方で、残る2割については意見不一致が残り、今後の更なる調整努力が必要であることも認識した。今後は、定期レビューや追加ヒアリングを通じて、残る不一致点の明確化と解消に継続的に取り組む計画である。
3-2 実施状況の評価
チームメンバーからは、「誰も無視されず、意見が生かされた」との声が上がり、プロジェクト運営に対する信頼も向上した。
3-3 今後の改善点
今後は、専門性に対する理解を深める企画を採り、違いを認め合い、歩調を合わせるワークショップを実践することで、より高い完成度を目指す。
ワークショップにおいては、各専門分野の基本的な背景知識と業務プロセスの概要を互いに教え合う時間を設ける方針であり、特に、前提認識の差異を早期に埋めることを狙う。なぜならば、異なる前提認識が対立を生みやすいことを痛感したためである。具体的には、2時間枠のうち1時間を知識共有に充て、残り1時間で共通理解に基づく課題抽出を行うことを計画している。
さらに、単なる意見交換にとどまらず、相互に期待値や課題意識を言語化する訓練も併せて実施し、より高い実効性を目指す。これにより、相互理解の深化と問題解決能力の向上を図るものであり、結果として、将来的なプロジェクトの円滑化に寄与する。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合評価】:A(合格)
🧮【スコア評価(100点満点)】
| 評価項目 | 概要 | 配点 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 各設問ア~ウに明確な章節対応があるか | 30点 | 28点 |
| ② 課題の妥当性 | プロジェクトの特徴と対立の背景・兆候の妥当性 | 10点 | 9点 |
| ③ 行動記述の具体性 | 判断・迷い・行動が明示されているか | 25点 | 23点 |
| ④ ステークホルダ描写 | 感情・反発・納得の過程が描写されているか | 10点 | 8点 |
| ⑤ 成果の説得力 | 定量・定性の成果が具体的か | 15点 | 13点 |
| ⑥ 構成・表現 | 章構造・節構造・文体の一貫性と可読性 | 10点 | 9点 |
| 合計 | 100点 | 90点 |
✅【致命的欠陥チェック】
| フィルター項目 | 内容 | 判定 |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | 判断や葛藤の描写があるか | OK |
| B. ステークホルダとのやり取り | 双方向性の描写があるか | OK |
| C. 設問ア~ウ対応 | 章節構成が設問に対応しているか | OK |
| D. 成果の明示 | 成果(定量・定性)があるか | OK |
✍️【評価コメント】
- 設問対応(28/30)
各章で設問ア〜ウに忠実な構成がとられており、対応も明確。設問語尾まで意識されており優れている。 - 課題の妥当性(9/10)
7部署統合という高難度の背景と利害対立の構造が明確で、論述の土台として妥当性が高い。 - 行動記述の具体性(23/25)
「迷い」「決断」「再周知」「ミーティング設計」など、PMの判断・対応がよく描かれている。特に「最初のミーティングでは評価・意見交換を避ける」戦術は秀逸。 - ステークホルダ描写(8/10)
各チームの感情や主張がきちんと描かれており、相互理解が進んでいく過程も自然。さらに「不満が広がる兆候」や「信頼向上の声」なども含め、心理的描写の説得力が高い。 - 成果の説得力(13/15)
8割の合意という定量的成果に加え、今後の明確な改善策、現場の評価の声が描かれており説得的。ただし、定量面に「作業遅延削減○%」等があるとより強力。 - 構成・表現(9/10)
章・節構成が適切であり、表現も論理的・流暢。句読点の扱いや接続語も自然で、読みやすさの面で安定感がある。
🧩【改善提案(満点を目指すために)】
- 第2章の文字数強化・行動描写の厚み
現状でも具体的であるが、「行動の裏にあるPMの悩み・恐れ」をもう一段掘り下げられるとさらに説得力が増す。たとえば「感情的対立を助長するのではという懸念に対し、どのような選択肢とリスクを天秤にかけたか」など。 - 成果の定量化
「8割合意」に加え、「テスト工程の再作業削減率」「レビュー回数」「合意形成までの日数短縮」など、客観的指標が1つでもあるとさらに評価が上がる。 - 今後の改善策の汎用性強化
ワークショップ施策は素晴らしいが、他プロジェクトにも展開可能な「形式知化」や「ナレッジベース化」などに言及すると、より上位合格者の記述に近づく。
✅ 総評
この論文は、プロジェクトマネージャとしての判断・行動・調整を具体的に描きながら、対立の解消過程を丁寧に説明しています。要所に「迷い」や「懸念」、「ステークホルダの感情」が組み込まれており、読み応えも十分です。文体も洗練されており、実務経験と熟慮を感じさせる構成です。
今後、満点を目指すなら「定量化のさらなる強化」と「知識・仕組みへの昇華(再現性)」が鍵となるでしょう。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、最終的な監修責任は、人間(サイト管理者)にあります。公開前に内容を厳しく吟味し、十分納得できたもののみを掲載していますので、安心して学習にご活用ください。