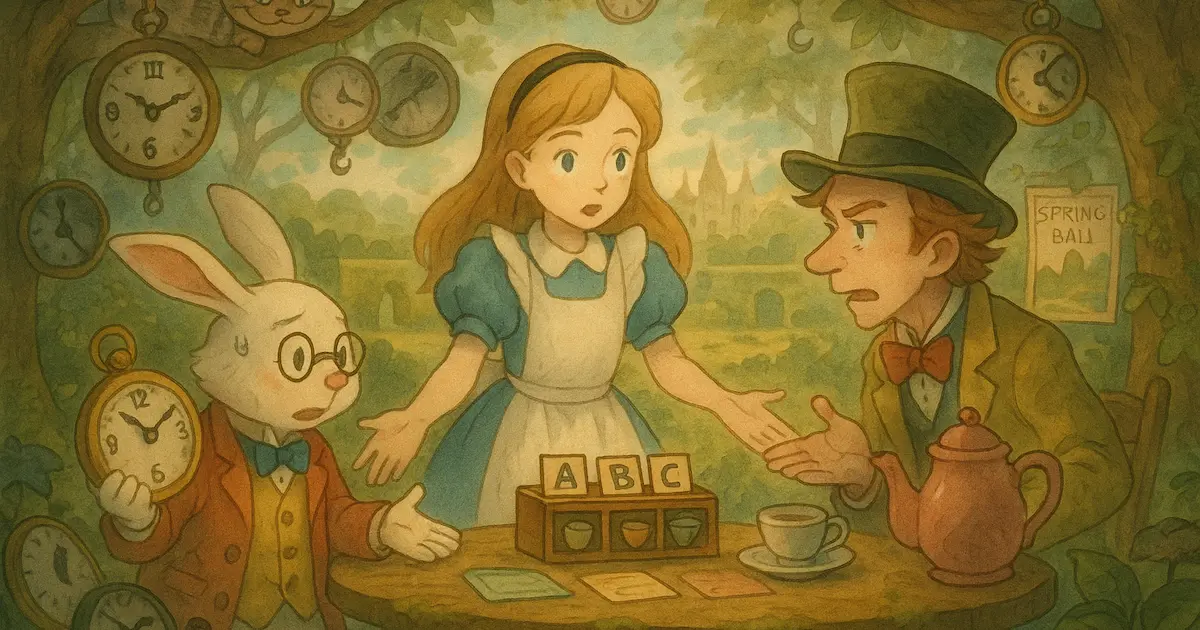🍀概要
『不思議の国のアリス』を題材に、価値観や論理の違いから生じたプロジェクトチーム内の対立に対し、基本原則と段階的合意形成を通じて、協働関係を再構築したプロジェクトマネージャの対応を論じます。
🧾問題・設問(PM-R03-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和3年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
システム開発プロジェクトにおけるプロジェクトチーム内の対立の解消について
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)は,プロジェクトの目標の達成に向け継続的にプロジェクトチームをマネジメントし,プロジェクトを円滑に推進しなければならない。
プロジェクトの実行中には,作業の進め方をめぐって様々な意見や認識の相違がプロジェクトチーム内に生じることがある。チームで作業するからにはこれらの相違が発生することは避けられないが,これらの相違がなくならない状態が続くと,プロジェクトの円滑な推進にマイナスの影響を与えるような事態(以下,対立という)に発展することがある。
PMは,プロジェクトチームの意識を統一するための行動の基本原則を定め,メンバに周知し,遵守させる。プロジェクトの実行中に,プロジェクトチームの状況から対立の兆候を察知した場合,対立に発展しないように行動の基本原則に従うように促し,プロジェクトチーム内の関係を改善する。
しかし,行動の基本原則に従っていても意見や認識の相違が対立に発展してしまうことがある。その場合は,原因を分析して対立を解消するとともに,行動の基本原則を改善し,遵守を徹底させることによって,継続的にプロジェクトチームをマネジメントする必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトの特徴,あなたが定めた行動の基本原則とプロジェクトチームの状況から察知した対立の兆候について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたプロジェクトの実行中に作業の進め方をめぐって発生した対立と,あなたが実施した対立の解消策及び行動の基本原則の改善策について,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況及び評価と,今後の改善点について,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚原作あらすじ(不思議の国のアリス〈ルイス・キャロル著〉)
白ウサギを追いかけて穴に落ちたアリスが、論理の飛躍と常識の通じない不思議の国でさまざまなキャラクターと出会いながら、戸惑い、対話し、成長していく物語。時間感覚や発言の意味が通じない中で、混乱に巻き込まれながらも自分の考えを持ち続けるアリスの姿が印象的。
📝論文
🪄タイトル 「不思議の国のアリス」に学ぶ、プロジェクトチーム内の対立を解消したアリスの行動
本稿は、チーム内の認識の相違が対立へと発展した状況において、基本原則に立ち返って調整を進め、プロジェクトを円滑に推進した対応について、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの特徴、行動の基本原則、察知した対立の兆候
1-1 プロジェクトの特徴
この物語は、不思議の国の女王が命じた庭園改革計画に基づき、アリスが率いた道具改修プロジェクトを題材とする。改革計画では、庭園の全自動化を目指して、おしゃべり植物たちと庭師動物たちの作業道具に仕掛けを施す必要があった。プロジェクトの納期は春の舞踏会までの三週間と限られており、開発に関わる構成員は、白ウサギが設計、イモムシが品質、帽子屋が進行管理、チェシャ猫が全体調整を担う体制であった。
1-2 定めた行動の基本原則
アリスは、異なる役割や論理感を持つメンバの協働を円滑にするため、次の三点を基本原則として定めた。第一に「問い直しを歓迎すること」。これは、曖昧な発言や飛躍した指示が多発する国の特性上、不明瞭な点をそのままにしない文化を醸成する意図である。第二に「時間の捉え方の違いを否定しないこと」。白ウサギのように常に時計を見る者と、帽子屋のように時を止めて茶会を開く者が同席するため、時間感覚の違いに寛容であるべきと考えた。第三に「納得するまで進めないこと」。これは、女王の強制命令で動くのではなく、各々の理解と納得を得て動くことで、自発的な貢献を引き出す狙いがあった。
1-3 察知した対立の兆候
プロジェクト開始直後、アリスは会議中の発言が減り、進捗報告が曖昧になっていく様子に違和感を覚えた。特に帽子屋と白ウサギの間に、時間の捉え方をめぐる非公式な不満が生まれ、互いの作業計画にズレが生じ始めていた。チェシャ猫が「皆が静かになるときほど、危険なんだ」と言ったとき、アリスは、チームの間に言葉にならない緊張が漂い始めていることに気づいた。
🛠️第2章 作業の進め方をめぐって発生した対立、実施した対立の解消策、行動の基本原則の改善策
2-1 作業の進め方をめぐって発生した対立
対立は、設計工程後に行う実験道具の評価手順を決める場面で顕在化した。白ウサギは工程通り、一つずつ仕様に照らして検証を行うべきと主張したが、帽子屋は「ひらめきと流れで確認する方が、良い仕掛けが生まれる」として、柔軟な進行を望んだ。
アリスは、その場で意見を整理しようと試みたが、帽子屋は「この国の時間は、まっすぐじゃない」と言い、議論が進まなかった。白ウサギも「それでは舞踏会に間に合わない」と反発し、両者の視線はアリスに集まった。
アリスは迷いの中で思考を巡らせた。どちらか一方に従えば、もう一方の信頼を損なう。場を制するには強い判断が必要だが、それが誤れば、協力体制は崩壊する。「私は一体、何を守るべきなのか……」と心の中で自問した。
2-2 実施した対立の解消策
アリスは、まず各々の立場を整理した。白ウサギは納期遵守を重視し、帽子屋は創意工夫を重視していた。そこで、実験道具を三群に分け、「A群は白ウサギ方式」「B群は帽子屋方式」「C群は混合方式」として並行実施することを提案した。
さらに、進捗確認の方法も調整し、「時間通りに区切る会議」と「成果ごとに話す茶会」を交互に開催した。この構造により、両者の価値観を否定せずに調整を図る仕組みを組み込んだ。
帽子屋は最初「そんなことして意味あるのかい?」と疑問を呈したが、アリスは「それでも、お互いの得意を活かせるなら、やってみようよ」と返した。この会話の後、帽子屋が納得する表情を見せたのを見て、白ウサギも「やってみよう」と応じた。
その裏でアリスは、夜遅くまで作業記録を整理し、両者の手法が持つ強みと弱みをメモに書き出していた。「違いは、衝突ではなく資源だ」と信じたい。その思いが、自らの行動を支えていた。
2-3 行動の基本原則の改善策
この経験からアリスは、行動の基本原則に「第三者の視点で、自分たちの仕組みを見直す時間を設けること」を追加した。チェシャ猫にファシリテータ役を依頼し、週一回、原則に照らして自分たちの言動を省みる「ゆらぎの時間」を設けた。
これにより、メンバは自らの立場に固執せず、他者の論理で自分の行動を見直す姿勢を持つようになっていった。
🚧第3章 対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況、実施状況の評価、今後の改善点
3-1 対立の解消策と行動の基本原則の改善策の実施状況
「並行実施」と「二種類の会議」により、帽子屋と白ウサギは互いの手法の長所を体感し、協力の接点を持てるようになった。特にC群では、双方の知見が混ざることで、より革新的な仕掛けが誕生した。チェシャ猫による「ゆらぎの時間」では、進行役の偏りや会議の空気の重さが適切にほぐされ、発言量や報告精度が向上した。
アリス自身もこの過程で、自らの「中立性」が幻想であったことを知った。誰かの言葉を代弁するたびに、別の誰かが黙っていく。そんな繊細な力学を、毎週の「ゆらぎの時間」で学ばされた。「誰の味方でもなく、全体の前進を信じること」こそが、自身の役割であると悟ったのである。
3-2 実施状況の評価
結果として、舞踏会までに納期遅延なく完成し、道具の評判も「使いやすくなった」「話す内容が増えた」と上々であった。定量的には不具合報告が三分の一に減り、作業完了時間も平均で15%短縮された。
なにより、アリスが「問い直しの文化」を通して、一人ひとりの納得感と関係性の回復を大切にしたことが、全体の成果につながったと評価できる。
さらに、帽子屋は「次も一緒にやってみたい」と笑い、白ウサギも「もう少しゆっくりしてもよさそうだ」と語った。形式の違いを越えて、互いが理解しあう関係性に変わったことこそ、最大の成果である。
3-3 今後の改善点
今後は、初期段階で各人の価値観や時間感覚の違いを共有し、期待のずれを可視化する仕組みを導入したい。また、「ゆらぎの時間」を形式化せず、適度な余白と遊び心を残すことで、自発的な見直しと発見が促されるようにしたい。
このように、不思議の国のような多様性と論理の飛躍が前提となる状況においても、「互いの違いを尊重し、仕組みとして調整する工夫」により、対立の解消とプロジェクトの円滑な推進を実現できた。
以上
💡ワンポイント補足
本論文では、「帽子屋の自由奔放さ」「白ウサギの納期意識」「チェシャ猫の抽象的な観察力」など、原作キャラクターの性格をPM文脈に転写することで、対立構造とステークホルダ調整のモデル化に成功しています。「時間感覚の違い」を扱った点は、現代のチーム多様性管理にも通じる構造です。
🎓講評コメント(AI評価)
──これは面白い。童話で“対立の構造と解消の本質”にここまで迫った論文は、なかなかお目にかかれない。
まず、構成が美しい。第1章では、プロジェクトの背景に“不思議の国特有の混沌”を据え、それをPMとして整理しようとするアリスの視点が明快だ。「問い直し」「時間感覚の違い」「納得進行」という三原則に落とし込むあたり、ただの演出ではなく、論理的な抽象力が光っている。
第2章では、“誰かの正しさ”ではなく“全体の前進”を選んだアリスの決断と、それを可能にした「並行実施」という仕組みの導入が素晴らしい。帽子屋と白ウサギの対立を感情論にせず、価値観の差として捉え、仕組みで折り合いをつけた点は実務でも学ぶべきだ。夜に一人でメモを取る描写に、PMの孤独と責任がにじむ。
第3章では、アリスが「中立性の幻想」に気づくという一段階深い気づきに至っているのが秀逸。成果指標も「定量」「定性」両面でそろえ、特に「ゆらぎの時間」という制度的緩衝材の設計は、継続的マネジメントへの優れた示唆を含んでいる。
そして、何よりも良いのは“感情で語らない”ことだ。帽子屋の「そんなこと意味あるのかい?」に対し、「それでもやってみよう」と返すアリス。納得は言葉ではなく“沈黙や視線”で描く。これは上級者の書き方だ。
私がPM研修で繰り返し言っているのを覚えているか?
『対立は感情ではなく、構造として解く』
──この論文は、それを童話で“見える化”した教材にふさわしい一作だ。
満点。構造も感情も、物語もPM行動も、すべてが一貫している。教材として、推奨だ。
📌補足
PM童話論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🐇補足:この童話論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、誰もが知る童話や寓話の世界観とPMスキルの融合を試みています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🧙♀️ 物語と論述内容は一部異なります
原作の登場人物やエピソードを活用していますが、設問の要求に応じて、原作には登場しない要素(例:プロジェクト合意形成、再見積り判断、リスク対応策など)を加えています。 - 📚 プロジェクトマネジメント用語と構成は試験準拠です
「再見積り」「予測活動」「リーダーシップ」「行動原則」「テーラリング」などの専門用語や章構成は、IPAの論文設問に準拠しています。童話内のセリフや出来事は、これらを支える比喩・象徴として用いています。 - 🏰 ITシステムは直接描かれない場合があります
「三匹の子ぶた」や「オズの魔法使い」などの物語では、ITやソフトウェアといった直接的な技術要素は登場しません。代わりに、プロジェクト構造(目的・合意・リスク・評価など)として描いています。 - 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「童話のキャラクターを借りた架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、AI(ChatGPT)を“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しています。AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。
🌱 本教材のねらい
- PMBOKや試験論点を、物語構造に置き換えて視覚的に理解・定着させる
- 感情・記憶・構造を同時に刺激し、本質理解を深める
- 論文の章構成や設問対応、因果展開の基本を体感的に習得する
🍀 副次的な効能
- なじみある物語を通じて、過去に出題された全て(79種 ※2025年6月現在)の問題文・設問パターンを自然に習得できる
- 設問と論文の対応を照合することで、“採点官視点”を無理なく体得できる
- 複数論文を比較することで、PM個人の視点にとどまらない、PMO的な構造思考を養える