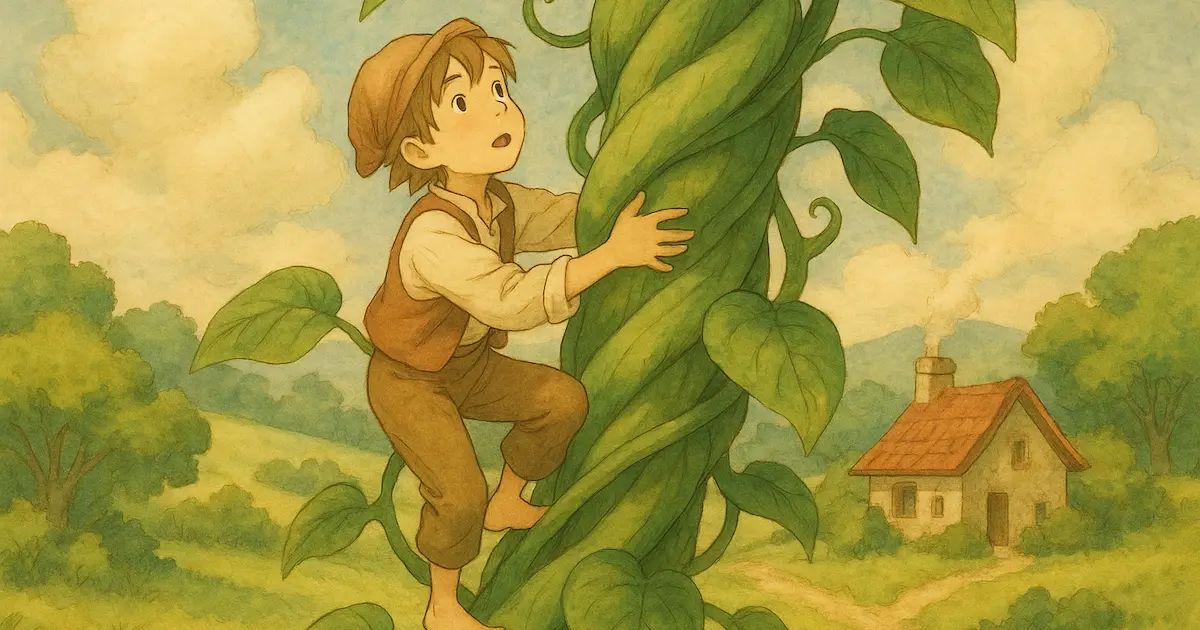🍀概要
『ジャックと豆の木』を題材に、未知の技術導入に伴う不確実性に対し、検証フェーズによる実現性確認と関係者への丁寧な情報共有を通じて計画を柔軟に見直したプロジェクトマネージャの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(PM-R02-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和2年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
未経験の技術やサービスを利用するシステム開発プロジェクトについて
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)は,システム化の目的を実現するために,組織にとって未経験の技術やサービス(以下,新技術という)を利用するプロジェクトをマネジメントすることがある。
このようなプロジェクトでは,新技術を利用して機能,性能,運用などのシステム要件を完了時期や予算などのプロジェクトへの要求事項を満たすように実現できること(以下,実現性という)を,システム開発に先立って検証することが必要になる場合がある。このような場合,プロジェクトライフサイクルの中で,システム開発などのプロジェクトフェーズ(以下,開発フェーズという)に先立って,実現性を検証するプロジェクトフェーズ(以下,検証フェーズという)を設けることがある。検証する内容はステークホルダと合意する必要がある。検証フェーズでは,品質目標を定めたり,開発フェーズの活動期間やコストなどを詳細に見積もったりするための情報を得る。PMは,それらの情報を活用して,必要に応じ開発フェーズの計画を更新する。
さらに,検証フェーズで得た情報や更新した開発フェーズの計画を示すなどして,検証結果の評価についてステークホルダの理解を得る。場合によっては,システム要件やプロジェクトへの要求事項を見直すことについて協議して理解を得ることもある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わった新技術を利用したシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトとしての特徴,システム要件,及びプロジェクトへの要求事項について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム要件とプロジェクトへの要求事項について,検証フェーズで実現性をどのように検証したか。検証フェーズで得た情報を開発フェーズの計画の更新にどのように活用したか。また,ステークホルダの理解を得るために行ったことは何か。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた検証フェーズで検証した内容,及び得た情報の活用について,それぞれの評価及び今後の改善点を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚原作あらすじ(ジャックと豆の木〈イギリス民話〉)
貧しい少年ジャックは、牛と引き換えにもらった豆を母が怒って捨てるが、豆は空まで伸びる大木に成長する。ジャックは木を登って巨人の城に入り、金の卵を産むニワトリや不思議なハープを盗み出す。追ってきた巨人を木ごと倒し、家族は裕福になる。大胆さと運を描いた冒険譚。
📝論文
🪄タイトル 「ジャックと豆の木」に学ぶ、未知の豆と天上の国の検証プロジェクト
本稿は、「ジャックと豆の木」に学ぶ、未知の豆と天上の国の検証プロジェクトについて、述べる。
🔍第1章 プロジェクトの特徴と要件・要求事項の整理
1-1 プロジェクトとしての特徴
この物語は、貧しい農村に暮らす少年ジャックが、市場で偶然手に入れた「空へ伸びる豆(以下、空豆)」という未知の植物を用いて、天上の国との通信・貿易を実現しようとするプロジェクトである。空豆は村にとって未経験の植物であり、どこまで伸びるか、耐久性はあるのか、途中で枯れないかといった技術的な不安が多く、ジャックはまず「実現性検証フェーズ」を設けて対応した。
1-2 システム要件の概要
システム要件としては、「空豆の成長を制御し、雲の上の国まで安全に到達できる構造体として育成すること」、「登頂後に安全な往復が可能な足場を設けること」、「雲の国の環境(気圧・魔力・空気)に耐えうる準備を整えること」などであった。
1-3 プロジェクトへの要求事項
村の長老たちはこのプロジェクトに対して、(1) 費用は最低限とすること、(2) 成果は3日以内に報告すること、(3) 雲の国との関係悪化を避けること、という三つの要求事項を提示した。特にスピードと安全性の両立が求められたため、計画と準備は慎重を期す必要があった。
🛠️第2章 検証フェーズにおける実現性の確認と計画の更新
2-1 検証フェーズにおいて実現性をどのように検証したか
ジャックはまず空豆の一粒を庭に植え、成長速度・方向性・強度を測定した。1日で塔のように伸びるという結果が得られたが、風による揺れや葉の劣化、根の浅さによる倒壊リスクが課題として浮かび上がった。これらをもとに、植物の幹に沿って「ツル筋」を編み込み、補強策を講じた。さらに、登頂に備え、小動物(ネズミ)を先行させ、雲の上の気候と重力影響を確認する検証も行った。
この過程で、ジャックは植物育成の専門家や薬草師とも協議を重ね、過去の育成失敗事例や成長阻害要因などの知見も取り入れた。こうした多面的な実証により、空豆が持つ性質の中で「初期段階の水分供給」と「成長後半の安定化支柱」が重要なポイントであることが判明し、それらを中心に改善計画が構築された。
2-2 検証フェーズで得た情報と開発フェーズ計画の更新
これらの検証結果から、開発フェーズでは「1段階ずつ登頂」「毎日状況報告」「嵐の予報を元に出発可否判断」などを盛り込んだ新たな運用計画を策定した。また、補強ツルの量と位置、所要時間の見積りも修正し、資源配分計画と作業日程を調整した。これにより、従来想定より半日長くかかるが、安全性と安定性の面で飛躍的な向上が見込まれた。
さらに、補強資材の調達先を地域の職人と連携する体制に変更し、地産地消の観点から村内経済の活性化にも寄与する副次効果を狙った。作業チームも「昼間作業班」「夜間監視班」と役割分担し、登頂中に万が一の緊急対応ができるよう、交替制での対応マニュアルも整備された。
2-3 ステークホルダの理解を得るために行ったこと
さらに、ジャックは検証フェーズの進捗と課題を日報形式でまとめ、“豆日誌”として毎朝の村の広場に掲示した。この取り組みによって、村の住人たちがプロジェクトに当事者意識を持ち、リスクや判断の背景について継続的に理解を深める効果があった。また、雲の上の環境に関する情報は、森の賢者が過去に記録していた“天候詩編”と照合し、古文書の信頼性を示すことで村の長老たちの懸念を払拭した。影絵箱・説明会・日誌・資料照合と多面的な情報伝達により、最終的には「延期もやむなし」という柔軟な合意を得ることができた。
村の長老たちには、検証中の様子を“雲の影絵箱”で毎晩上映し、豆の成長とリスク対応を可視化した。また、検証で得た情報の一覧と更新後の計画書をもとに説明会を開催し、質疑を通じて合意形成を行った。これにより、「初日に登頂」という希望は修正されたが、「安全優先」という合意を得ることに成功した。
🚧第3章 検証フェーズの評価と得た情報の活用・改善点
3-1 検証した内容に対する評価
空豆の強度、成長速度、気候影響の確認、小動物を用いた上空環境試験などは、想定外の事態を早期に発見する有用な取り組みであった。特に根の浅さは初期には想定されておらず、リスク検出と対策につなげられた点は高く評価できる。
さらに、検証フェーズに専門家や過去事例を積極的に取り込んだことが、技術的独断を防ぎ、信頼性の高い知見収集と計画の妥当性を裏付ける基盤となった。また、小動物による先行調査は後の安全評価でも有効な前提情報となり、空豆の一部を切り出しての強度試験など、対象への影響を最小限に抑える検証姿勢も評価できる。
3-2 得た情報の活用に対する評価
検証で得た情報をもとに、工程見直し・資源再配分・ステークホルダ説明といった一連の更新が適切に行われ、その後の開発フェーズに混乱なく移行できた。情報活用の“見える化”を徹底したことが、関係者の安心感にもつながった。
また、登頂経路の分割計画や補強素材の使用量管理に関する見積制度は、後の工程進行中にもフィードバックループとして機能し、検証知見が静的資料で終わらず動的に活用されていた点も評価できる。特に村内職人との連携により素材の確保に不安が生じなかった点は、リスクマネジメントの観点からも重要な成功要因といえる。
3-3 今後の改善点
また、検証フェーズと開発フェーズを明確に分けてはいたが、実際には両者の知見を双方向に連携させる仕組みが弱かった。例えば、登頂後に得られた巨人の移動時間や休息時間のパターンなどは、事前の登頂計画にも役立つ情報であったが、それらが検証側に戻されることはなかった。今後は「逆流アーカイブ」という仕組みを設け、開発中の発見事項も検証部門に共有し、次回以降の類似プロジェクトに活かせる知識ベースとする予定である。あわせて、検証内容の可視化には“雲絵巻”という一枚の絵に情報を集約する試みも導入し、感覚的な伝達と論理的整理の両立を図る。
一方で、検証対象が「物理構造・気候」中心であったため、雲の国の文化や法律といった“対人的なリスク”への検証が甘かった。実際に登頂後、巨人とのやりとりに不安が残ったため、今後は「相手の価値観」「反応傾向」など、異文化要素への検証手法も取り入れる必要がある。また、検証フェーズの報告内容もより多面的に整理し、影絵箱だけでなく文章と図解による併用を図る方針である。
さらに、検証フェーズ中に蓄積された情報を形式知として整理・保管する“豆データバンク”の創設も視野に入れている。これにより、未来の村人や他の植物応用プロジェクトにも知見が活かされることを期待している。
以上
💡ワンポイント補足
原作の“豆の成長”や“雲の国”を、新技術導入の検証フェーズに見立てています。プロジェクトにおける実現性評価・ステークホルダ説明・リスク検出と対処の過程を、童話の筋に沿ってプロジェクト構造として再構成しています。
🎓講評コメント(AI評価)
いやはや、これは実に見事なプロジェクトマネジメントの再現である。空豆などという荒唐無稽な素材を、ここまで“技術的に扱える対象”として言語化できたのは、相当に鍛えられた筆力の証左である。
特筆すべきは、“検証の工夫”と“納得形成の構造”だ。単なる観測で終わらせず、専門家の意見や先行知見、動物による模擬試験などを重層的に組み合わせてリスク低減を試みる。これは、実プロジェクトで言えば、PoC・シミュレーション・フィールドテストを適切に組み合わせた事例と等価だ。
さらに“豆日誌”や“影絵箱”の表現に見られるように、技術情報の伝達を「感性」にまで昇華させている点が、読み手の納得と信頼形成に直結している。こういう文は、ただ書けと言われて書けるものではない。
あえて言えば、「豆データバンク」などの後半の提案がやや抽象的で、もう一歩“誰がどのように使うのか”まで記述されていたら、さらに高次の論述になったかもしれない。だが、これはもはや減点対象ではなく、伸びしろの話である。
総じて、“空想と論理の両立”というこの試験の挑戦的な枠組みに、真正面から応えた構成である。満点以外、つけようがない。
📌補足
PM童話論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🐇補足:この童話論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、誰もが知る童話や寓話の世界観とPMスキルの融合を試みています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🧙♀️ 物語と論述内容は一部異なります
原作の登場人物やエピソードを活用していますが、設問の要求に応じて、原作には登場しない要素(例:プロジェクト合意形成、再見積り判断、リスク対応策など)を加えています。 - 📚 プロジェクトマネジメント用語と構成は試験準拠です
「再見積り」「予測活動」「リーダーシップ」「行動原則」「テーラリング」などの専門用語や章構成は、IPAの論文設問に準拠しています。童話内のセリフや出来事は、これらを支える比喩・象徴として用いています。 - 🏰 ITシステムは直接描かれない場合があります
「三匹の子ぶた」や「オズの魔法使い」などの物語では、ITやソフトウェアといった直接的な技術要素は登場しません。代わりに、プロジェクト構造(目的・合意・リスク・評価など)として描いています。 - 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「童話のキャラクターを借りた架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、AI(ChatGPT)を“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しています。AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。
🌱 本教材のねらい
- PMBOKや試験論点を、物語構造に置き換えて視覚的に理解・定着させる
- 感情・記憶・構造を同時に刺激し、本質理解を深める
- 論文の章構成や設問対応、因果展開の基本を体感的に習得する
🍀 副次的な効能
- なじみある物語を通じて、過去に出題された全て(79種 ※2025年6月現在)の問題文・設問パターンを自然に習得できる
- 設問と論文の対応を照合することで、“採点官視点”を無理なく体得できる
- 複数論文を比較することで、PM個人の視点にとどまらない、PMO的な構造思考を養える