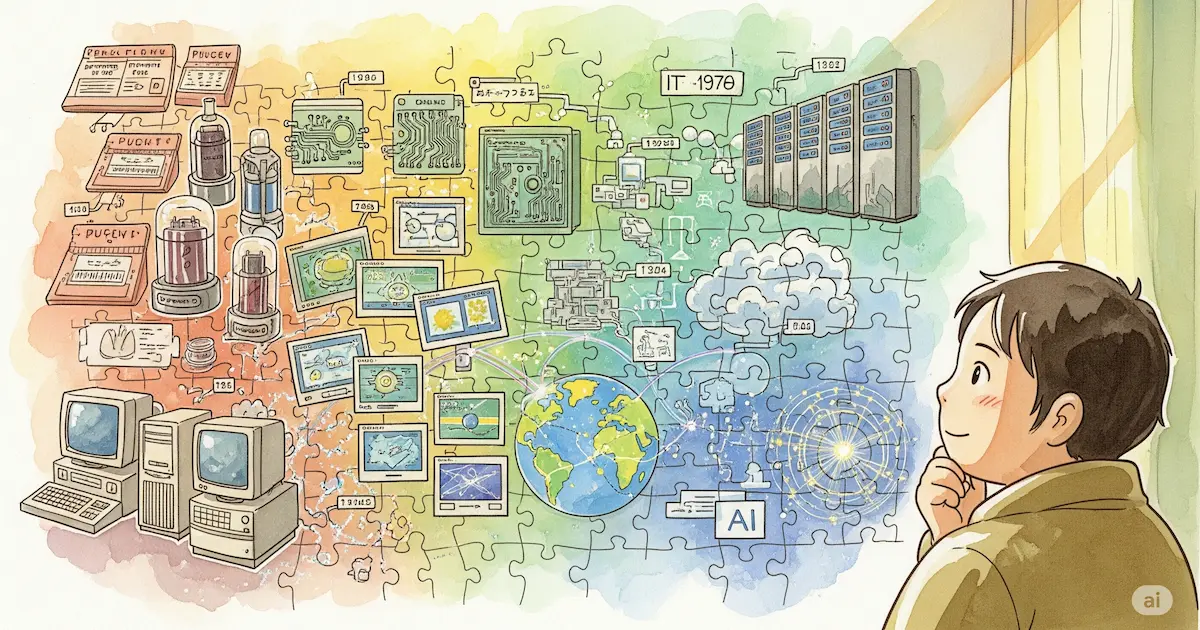🍀概要
この資料は、過去のエンベデッドシステムスペシャリスト試験問題(論述形式)をテキスト化した「エンベデッドシステムスペシャリストの歴史書」です。Web上では見つけにくい、貴重で有益な示唆を含む、過去の問題文を、調査してテキスト化しました。 過去の課題から、現代そして未来に求められる理想像を紐解き、あなたの知識と視点を深めます。分析や考察に役立つよう、すぐにコピペして利用できる形式となっています。
🧾問題・設問
出典:情報処理推進機構 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 令和5年~令和6年 午後2 (🔗取り扱いガイドライン)
出典:情報処理推進機構 エンベデッドシステムスペシャリスト試験(午後Ⅱ試験) サンプル問題(🔗取り扱いガイドライン)
📘ダウンロード
こちらから、掲載した問題文を全て含む、MS Word、PDFファイルをダウンロードできます。
※情報処理推進機構のガイドラインをご確認の上、ご利用ください。(🔗取り扱いガイドライン)
🪄アーカイブ全文
📗R06:2024
【ES-R06-1-PM2-Q1】組込みシステム製品の企画における生産形態の多様性について
昨今の組込みシステム製品は,異業種からの市場への参入もあり,生産形態が多様化している。生産形態には,自社による内製,企画を提示し設計・製造を委託するODM(Original Design Manufacturing),自社製品を相手先ブランドで提供するOEM(Original Equipment Manufacturing),ODMとOEMとの中間形態,EMS(Electronics Manufacturing Services)メーカーに製品の製造委託を行う形態などがある。
多様な生産形態の例を次に示す。
・大手家具メーカーにおける全自動洗濯機の企画では,ODMの取引先として,洗濯機の生産に実績のある家電メーカーに設計・製造から出荷まで委託した。メリットは,家電製品開発のノウハウがなくても市場への参入が可能な点にあった。
・センサー装置メーカーの既存製品である見守りセンサー装置は,業界トップの介護用機器メーカーへの各種自動介護ロボットに採用され,OEM先として,その介護用機器メーカーのブランドで提供された。メリットは,委託元の多岐にわたる製品に採用されたので,大幅な需要が見込まれる点にあった。
・電子通信機器メーカーでは,企画から開発工程までは自社で実施しているが,製品を構成している一部の半製品について,EMSメーカーに部品調達,製造を委託した。メリットは,自社の製造ラインが不要で,製品を調達できる点にあった。
それぞれの生産形態に応じ,内製する立場。委託する側(以下。委託側という)の立場。委託される側(以下,受託側という)の立場がある。例えば,委託側の立場では,事業戦略として経営陣・事業責任者などと協議し,自社の特徴及び採算性,多品種少量生産などへの対応を鑑みて,生産形態に対する委託取引先の選定をすることが考えられる。一方,受託側の立場では,同じく経営陣・事業責任者と協議し,自社の製品を提供した場合の採算性,将来性などを鑑みて,受託の諾否について検討する。
さらに,生産形態によっては,事業継続危機対策,技術の流出などのリスク,品質の担保などの様々な課題もあり,その解決策も検討することが重要である。
内製,委託側,受託側のいずれの立場においても採算性,将来性,メリット,リスクなどを分析し,総合的な視点から取引先の選定も含めて,生産形態について意思決定することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って解答せよ。
なお,解答欄には,文章に加えて,図・表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステム製品の用途及び技術的特徴を踏まえた概要, その製品の生産形態において内製・委託側・受託側のいずれの立場であったかを,2ページ (800字相当) 以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた生産形態とした理由,生産形態のメリットの内容,生產形態を遂行する上でのリスクなどの課題とその解決策について,自社・取引先の特徴を踏まえて,2ページ (800字相当)以上,かつ,4ページ (1,600 字相当) 以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた生産形態とした理由の妥当性,分析したメリットの評価,リスクなどの課題に対する解決策の評価,生産形態に対する今後の展望について, 1.5 ページ (600字相当)以上,かつ,3ページ (1,200 字相当)以内で具体的に答えよ。
【ES-R06-1-PM2-Q2】組込みシステム製品の設計における実現性の検証・試作などの事前検証について
組込みシステム製品の機能の高度化,構成の複雑化に伴い,新技術などを導入する際に製品開発に先立ち,実現性の検証又は試作などの事前検証を行うことがある。
例えば,既存の組込みシステム製品に新規のハードウェア・ソフトウェアを導入する場合,どのような要素をどのように組み合わせるか,各要素にどのような機能を割り当てるか,アーキテクチャを吟味することで,そのアーキテクチャで機能要件・非機能要件を満たせるか,製品開発に先立って実現性を検証することができる。さらに,試作によってユーザビリティなどを検討することで,その構成と機能の割当ての妥当性,製品としての市場性・有用性を検証することもできる。
これらの事前検証では,上記の効果が確認できるまで検証を繰り返すことがあり,結果によっては製品化を断念することもある。
事前検証において,実現性の検証及び試作のいずれも,検証を効率良く柔軟に実施するための多様な手法がある。検証手法の例を次に示す。
・机上で,ハードウェア・ソフトウェアの仕様を基に静的な検証を実施
・PC上でのモデルやAIを用いたシミュレーションの実行などによって,仮想的に動的な検証を実施
・FPGA又は評価ボードといった汎用のハードウェアを利用し,動的な検証を実施
・従来製品の一部変更によって動的な検証を実施
・製品に近いプロトタイプを作成し,動的な検証を実施
事前検証においては,検証の対象及び検証の目的に基づき,適切なアーキテクチャの選定,及び適切なハードウェア・ソフトウェアの検証手法の選択が求められる。また,製品としての有用性の判断に企画部門・営業部門などの他部門との連携が必要となることも考えられる。
組込みシステム製品の設計における実現性の検証・試作などの事前検証においては,検証の対象及び検証の目的を明確に定義し,各担当部門の協力を得て検証手法の構築・評価基準の設定を行い,効率良く事前検証を実施できる手法を選択する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア〜ウに従って解答せよ。
なお,解答欄には,文章に加えて,図・表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステム製品の用途及び技術的特徴を踏まえた概要, 事前検証の対象及びその目的を,2ページ (800字相当) 以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた事前検証において,選択した手法及びその手法の適用方法, その手法を選択した理由,加えて,どのように他部門と連携したかを,2ページ (800字相当)以上,かつ,4ページ (1,600字相当) 以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた内容において,選択した手法の妥当性及び検証方法の妥当性の評価,検証で得られた結果及び製品化に向けての課題について,1.5 ページ (600字相当)以上,かつ,3ページ (1,200字相当) 以内で具体的に答えよ。
📗R05:2023
【ES-R05-1-PM2-Q1】組込みシステムの製品企画段階における脅威分析について
昨今,組込みシステムの市場は,デジタルトランスフォーメーション(DX)推進,IoTの普及などによって,既存市場とともに新市場も拡大している。さらには異業種からの新規参入も増加している。その一方で,半導体電子部品不足などが納期・供給に影響を及ぼしている問題も見受けられる。
そのような状況下で新市場への参入,又は新製品を投入する際には,自社の保有技術などによる強みの分析だけではなく,外部環境によって影響される脅威を分析して,その結果を基に対策案を検討し,自社の優位性を確保することが重要である。
脅威分析の一つに,製品投入後を想定した脅威を分析するファイブフォース分析というフレームワークがある。そのフレームワークを用いて,分析した結果を基に,関連部門と連携しながら協議し,対策案を検討する。
組込みシステムにおけるファイブフォース分析で示される脅威の例を次に示す。
・既存業者間の競争:競合他社との製品の価格競争,及び競合他社との半導体電さら子部品などの供給不足による調達での競争に晒される脅威
・業界への新規参入者:海外メーカーを含め,新規参入者の資本力・ブランドカなどによって優位性を奪われる脅威
・代替品の存在:業界が異なる別製品で代用できてしまうことによって市場を奪われる脅威
・買い手(顧客)の交渉力:顧客からの値引き要請などによる利益減少の脅威
・売り手(サプライヤー)の交渉力:半導体電子部品不足,輸入品を独占的に販売する仕入先からの価格の値上げ,供給遅延などの脅威
これらの脅威に対応するためには,例えば既存業者間の競争では,競合他社との差別化が図れるか,又は複数の調達ルートが確保可能かなどの検討が重要になる。売り手(サプライヤー)の交渉力に関しては,ハードウェア開発部門,調達・購買部門などと連携して協議し,部品変更の容易性を含めた対策案などの検討が考えられる。
製品を企画する際には,自社の優位性を確保するために,ファイブフォース分析のフレームワークなどを活用して複数の脅威を分析し,その結果を基にそれぞれの対策案を関連部門と連携しながら協議し,検討する必要がある。その検討結果から対策を講ずる際の課題を抽出し,事前に解決策案を策定しておくことも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って解答せよ。
なお,解答欄には,文章に加えて,図表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わった製品の概要,企画に至った経緯,ファイブフォース分析のフレームワークなどを用いて分析したうちの三つの脅威について,2ページ(800字相当)以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた脅威において,そのうち特に重要と考えた二つの脅威についてどのようにフレームワークなどを活用し分析したか,それぞれの脅威に対し関連部門と連携してどのような対策案を検討したか,その対策を講ずる際の課題はどのように解決したか,2ページ(800字相当)以上,かつ,4ページ(1,600字相当)以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた内容について,脅威の分析結果の評価,脅威に対する対策案の評価,課題解決の評価を,1.5ページ(600字相当)以上,かつ,3ページ(1,200字相当)以内で具体的に答えよ。
【ES-R05-1-PM2-Q2】組込みシステムにおけるマルチコアの利用について
組込みシステムでは,機能の複雑化・高度化,及び処理の増加に伴い,マルチコアプロセッサを用いることが増えている。例えば,一つのプロセッサ内に,CPUコアを複数内蔵したもの,CPUコアに加えDSPGPUを内蔵したものなどが利用されている。
マルチコアプロセッサの活用に当たり,各コアにどのような処理を割り当てるかの検討が必要となる。高速化のための並列化の検討においては,タスクとデータのどちらに着目するかという観点がある。タスクの並列化では,例えば,異なるセンサーそれぞれのデータの処理を異なるタスクに分割し,それぞれのタスクを各コアに割り当て,同時並列に実行させる方法がある。データの並列化では,例えば,カメラデータの色調補正など,大量のデータを依存関係のない小単位に分割し,分割したそれぞれのデータに対して同じ処理を各コアで同時並列に実行させる方法がある。いずれの場合においても,扱うデータの依存性,処理の順序性に着目し,対象の組込みシステムに応じた処理・データの分割とコアへの割当てを行う。
分割した処理の各コアへの割当てには,同じCPUコアを複数もつマルチコアプロセッサの場合,OSの機能を用いて自動的に割り当てる方法があるほか,処理を明示的に分離する方法もある。例えば,安全性・セキュリティへの対応,応答性,又はライセンスの制限への対応においては,特定の処理を実行するコードを特定のCPUコアに明示的に割り当て,ほかからのアクセスを制限する。
マルチコアプロセッサでは,複数のコアがメモリを共有することなどによって,コア間の通信を高速に行うことができる利点があるものの,メモリなどの資源の競合の問題が発生し得る。また,あるコアで実行しているプログラムに不具合があった場合に,ほかのコアの処理にまで影響を及ぼす可能性もある。特に,機器の制御を行う組込みシステムでは,安全性の観点から,これらの問題が発生しないよう,また,発生しても極力影響を限定するような処置を取ることが求められる。
組込みシステムでのマルチコアの利用においては,組込みシステムが実現する機能・性能に鑑み,適切なマルチコアプロセッサを選択し,各コアに処理をどのように割り当てるか,コア間・タスク間の通信をどのように制御するか,安全性・セキュリティにも考慮して設計することが求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って解答せよ。
なお,解答欄には,文章に加えて,図表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わったマルチコアプロセッサを用いた組込みシステムについて,組込みシステムの用途,構成要素,マルチコアプロセッサを利用するに至った経緯・目的,及び目標を2ページ(800字相当)以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた組込みシステムにおいて,マルチコアプロセッサを利用する上での組込みシステムの制約,各コアに対してどのような理由でそれぞれにどの処理を割り当てたか,コア間の通信において考慮した事項,安全性・セキュリティなどの考慮,解決すべき課題とその解決方法について2ページ(800字相当)以上,かつ,4ページ(1,600字相当)以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた内容において,目標の達成度,解決方法の評価,今後の課題について,1.5ページ(600字相当)以上,かつ,3ページ(1,200字相当)以内で具体的に答えよ。
【ES-R05-1-PM2-Q3】組込みシステム開発時の基本要素の選定・設計・評価について
組込みシステムの要求定義は,対象となる製品によって多種多様である。それらの要求定義に対応するために,要求を分析して的確な機能要件・非機能要件を定義し,それらの要件に適合する基本要素(以下,基盤という)を選定する必要がある。選定の対象として組込みシステムの基盤には,CPU,OS,ネットワークなどがある。さらに,可用性・信頼性の要件の場合には,組込みシステムの二重化などのシステム構成も含まれる。
組込みシステムの開発時には,まず,採用する基盤の検討を実施する。次に要件と基盤との整合性を吟味し,その結果から基盤を補完する。例えば,省電力対応に特化したCPUでは,I/O処理を,割込み処理・ポーリング処理などのハードウェアとソフトウェア間でトレードオフしながらコストにも鑑みて,全体の設計を検討する。
要件及びその要件に対応するための基盤の選定の例を次に示す。
例1:コンパクトな筐体で,かつ,バッテリーでの稼働が必須の要件の場合稼働時間はバッテリー容量にも依存するので,低消費電力の組込みシステムの設計に留意する必要がある。さらに,CPUの性能に留意して実行モード・休止モードの比率などで消費電力に鑑みてバッテリーなどを選定する必要がある。
例2:車載端末に地図情報などを蓄えて,操作の要求に対して瞬時にデータを抽出でき,電源の瞬停などへの対応が要求される要件の場合GUIをサポートしているOS,及び電源断回復機能が具備された組込みシステム用データベースなどを選定する必要がある。
例3:医療機器,防災などで可用性・信頼性が要求される要件の場合デュプレックスシステム構成で構築するケースがある。その際,両システム間における適切なインタフェースなどを選定する必要がある。
例4:産業機械用の制御システムで,中長期的な供給が求められる要件の場合中長期的に入手可能で,かつ,IPコアを含めた汎用的なCPUの選定,及び汎用的なインタフェースのユニットなどを選定する必要がある。
組込みシステムの開発時には,与えられた要求を分析し,定義した機能要件・非機能要件それぞれに適合する基盤を選定することが重要である。加えてコストに鑑み,ハードウェア開発部門とソフトウェア開発部門でトレードオフを協議しながら設計することも重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って解答せよ。
なお,解答欄には,文章に加えて,図表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わった組込みシステムの概要,開発に至った経緯,要件に対して選定した基盤,及び選定で最も重要であると考えた内容について2ページ(800字相当)以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた基盤の選定において,最も重要であると考えた根拠,要件定義の内容及び吟味した整合性の内容,コストなどの影響を含めてハードウェアとソフトウェアで分担した内容,要件を満足するために抽出した課題,及びその解決策について,2ページ(800字相当)以上,かつ,4ページ(1,600字相当)以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた内容について,ハードウェアとソフトウェアで分担した結果の評価,課題抽出の評価,課題解決の妥当性の評価を,1.5ページ(600字相当)以上,かつ,3ページ(1,200字相当)以内で具体的に答えよ。
📗SAMPLE:2023
【ES-X00-1-PM2-Q1】組込みシステムにおけるデータストリーミングの処理について
組込みシステムのデータ処理において,連続的に一定のインターバルを維持して,順序を保ちつつ,データを取得,供給するデータストリーミングを扱う技術(以下,データストリーミング技術という)を用いることがある。このデータストリーミング技術の利用例としては,音声・動画再生処理が挙げられる。データストリーミング技術を広く考えると,ほかにも制御装置・IoTシステムにおけるセンサーデータの入力,データ処理,機器へのデータ出力に同様の技術を利用する場合もある。
音声・動画再生処理での応用例として,ハードディスク音楽再生装置では音楽が途切れることがないように,データをハードディスクからは間欠的に高速に読み出し,出力側には一定の速度で出力している。また,ネットワーク動画再生装置においては,通信速度が低下した場合には画質を落として,音声を優先し,転送するデータの量を低減して再生が途切れないようにしている。
制御装置の例として,レーダー及びカメラのデータを併用して車両の操縦を制御する組込みシステムがある。この場合,途切れなくデータを処理することに加え,両方のデータの同期をとる必要があり,どちらを基準に同期をとるかの吟味も必要となる。さらに,安全性上,連続的にデータを処理することが求められる場合,何らかの不具合によるデータ途絶への対応も考えなければならない。加えて,利用者の操作などによって,データストリーミング処理中にイベントが割り込んでくる場合も考慮して,適切な処理優先順位を設定することも重要である。
また,データの順序性に関して,例えば,パケット分割されたデータのパケット到着の順序性が保証されない方式のネットワークを利用するような場合は,データを正しい順序に並べ直す方策が必要となる。この場合,データの連続的な取得・供給のための速度の調整,又は同期のために,バッファを用いて調整する方法がある。このとき,並べ替え用のメモリのサイズ,バッファのサイズ,及び処理の実現方法については,データの入力周期,出力周期,転送速度,及びレイテンシーの許容範囲など,組込みシステムの用途・特徴を把握して設計・開発を行う必要がある。
データストリーミング技術を利用した組込みシステムの設計・開発においては,データの入力側・出力側及び組込みシステム全体の特徴を把握し,必要に応じて安全性を考慮して,連続的にデータを処理することが求められる。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~設問ウに従って解答せよ。なお,解答欄には,文章に加えて,図表を記載してもよい。
■設問ア
あなたが携わったデータストリーミング技術を利用した組込みシステムについて,システムの用途,構成要素,データストリーミング技術を利用する目的,及び開発の目標を,2ページ(800字相当)以内で答えよ。
■設問イ
設問アで答えた組込みシステムに用いたデータストリーミング技術において,入力側・出力側それぞれの特徴,及びシステムの制約を含む解決すべき課題とその解決方法,並びにその解決方法を採用した理由について,2ページ(800字相当)以上,かつ,4ページ(1,600字相当)以内で具体的に答えよ。
■設問ウ
設問イで答えた解決方法について,目標の達成度,解決方法の評価,及び今後の課題を,1.5ページ(600字相当)以上,かつ,3ページ(1,200字相当)以内で具体的に答えよ。