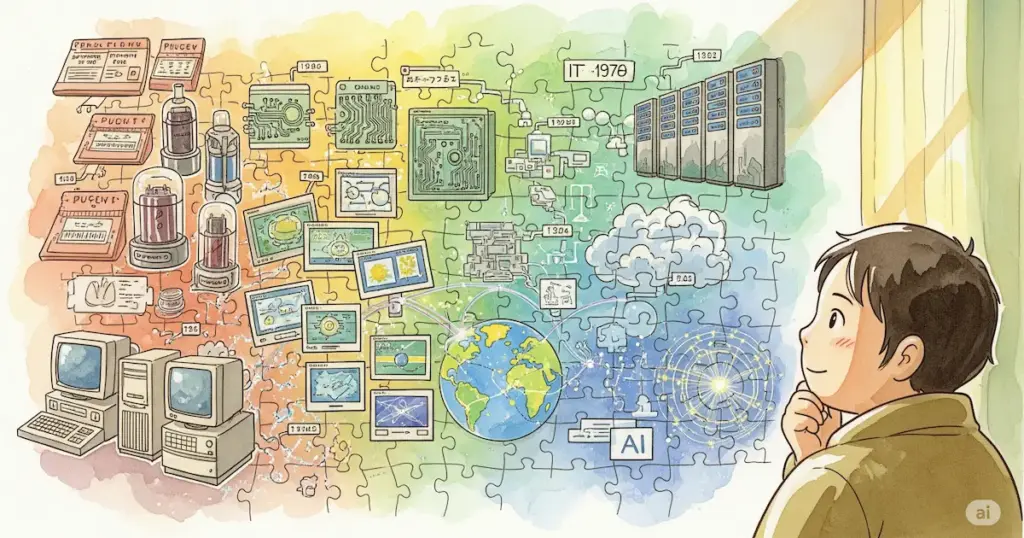🍀概要
ITサービスマネージャ試験問題の論述問題をベースに、ITサービスマネージャに求められる能力がどのように変化したかを分析しました。その結果をAI(Gemini)を活用してまとめたレポートを示します。
🌏Gemini
Geminiを利用して、分析した指示文、結果について掲載します。
指示文
ITサービスマネージャに求められている内容の変遷について、概ね3年程度ごとに区切って考察してください。
下記がITサービスマネージャ試験の全論述問題であり、各年度ごとに重視しされてきた内容です。
この内容は正しい前提で、問題文から推察される内容を中心に、社会的な要請の変化を考慮してください。
なお、レポートのタイトルは以下としてください。
ITサービスマネージャに求められる能力の変遷:情報処理技術者試験論述問題から読み解くトレンドと社会的要請
調査結果
ITサービスマネージャに求められる能力の変遷:情報処理技術者試験論述問題から読み解くトレンドと社会的要請
本レポートでは、情報処理技術者試験「ITサービスマネージャ試験」の過去の論述問題から、ITサービスマネージャに求められる能力が時代とともにどのように変遷してきたかを分析し、その背景にある社会的要請の変化を考察します。各時期の出題テーマを概ね3年ごとに区切って整理することで、ITサービスマネジメントのトレンドと、それに伴う役割の変化を明らかにします。
1995年~2005年頃:情報システムの「安定稼働」と「基礎管理」の時代
この時期は、企業における情報システムの導入が本格化し、ITが業務効率化の基盤として位置づけられ始めた黎明期にあたります。ITサービスマネージャという専門職が明確に確立される以前であり、情報システム部門の管理者がその役割を担うことが多かったと考えられます。
主要なテーマ
- システムの安定稼働と障害対応: システムが業務に与える影響が大きくなり、障害の未然防止や発生時の迅速な復旧が最重要課題でした。障害の一次対応手順の確立、原因究明と再発防止策の策定、システム障害対応訓練などが頻出しました。
- 基礎的な運用管理: ヘルプデスクの運営、パソコンやネットワークなどの分散システム管理、コンピュータ室の施設管理といった、ITインフラを物理的・技術的に安定させるための基礎的な管理業務が重視されました。
- コスト管理: IT投資が拡大する中で、システム運用のコスト削減や、コスト対効果の最大化が求められました。
社会的要請の変化
企業活動におけるITの依存度が増すにつれて、システム停止が事業に与える影響が顕在化し始めました。同時に、コンピュータウイルスや不正アクセスといったセキュリティ脅威も認識され始め、IT部門には、安定稼働とセキュリティ確保という「守り」の役割が強く求められていました。
2006年~2014年頃:「ITサービスマネジメント」の確立と「ITIL」の浸透
この時期は、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)などのITサービスマネジメントの国際的なベストプラクティスが日本企業にも浸透し、ITサービスを体系的に管理する考え方が本格的に導入され始めた時代です。ITは単なるシステムではなく、「サービス」として提供されるものだという認識が深まりました。
主要なテーマ
- サービスレベル管理(SLM): 顧客とのSLA(Service Level Agreement)に基づいたサービス提供が強調され、SLAの合意、サービスレベルのモニタリング、傾向分析、定期的な報告が重要視されました。未達成となる兆候への対応も含まれます。
- ITILプロセスの実践: インシデント管理、問題管理、変更管理、リリース管理、可用性管理、キャパシティ管理といった、ITILに準拠した各プロセスの確実な実施と改善が求められました。特に、重大インシデント発生時のコミュニケーションや、運用部門の開発プロジェクトへの参画といった連携の重要性も問われました。
- 外部委託業務の品質確保と移行: 運用業務のアウトソーシングが普及し、外部サービス利用における供給者管理や、アウトソーシング・システム移行時の円滑な計画立案と実行がテーマとなりました。
社会的要請の変化
ITが事業活動に不可欠な要素となったことで、その管理にはより体系的かつ専門的な知識が求められるようになりました。また、IT投資の費用対効果だけでなく、顧客満足度や事業貢献といったビジネス価値との関連性が意識され始めました。コンプライアンスや内部統制の強化も、ITサービス管理の厳格化を後押ししました。
2015年~2017年頃:ITサービスマネジメントの「深化」と「基礎固め」の継続
この時期は、ITサービスマネジメントの基本的な考え方が浸透した上で、それをさらに効率的かつ効果的に運用するための「深化」が求められるようになりました。特に、人やプロセスの側面に焦点が当てられています。
主要なテーマ
- ITサービス提供要員の育成: ITサービスの品質を確保するためには、運用担当者のスキル向上や、適切な人材育成計画の策定が重要であることが強調されました。
- プロセスの不備への対応と継続的改善: 確立されたプロセスであっても、その運用における不備を特定し、改善していく継続的な活動が求められました。PDCAサイクルを回し、サービス品質目標を達成するための改善活動が頻繁に問われました。
- 顧客満足の向上活動: 顧客とのコミュニケーションを継続し、サービスの報告を通じて顧客の期待と満足度を把握し、サービス価値向上に向けた活動計画を策定・実施することが重視されました。
社会的要請の変化
ITがビジネスの基盤として定着する中で、安定運用だけでなく、継続的な品質向上と顧客満足度の維持が企業競争力の源泉として認識されるようになりました。ITサービスマネージャには、組織内の人材育成やプロセス改善を通じて、サービス提供能力そのものを高めることが期待されました。
2018年~2021年頃:「俊敏性」と「自動化」への対応が始まった時代
デジタル化の進展と市場変化の加速に伴い、ITサービスはより迅速に、より柔軟に変化に対応することが求められるようになりました。この時期から、アジャイル開発やDevOpsといった新しい開発・運用手法、そして自動化技術への言及が増えてきます。
主要なテーマ
- プロセスの自動化: ITサービスマネジメントプロセスにおいて、AIやRPAなどの新技術を活用した作業の自動化、特にサービスデスクの対応やサービス報告の自動化がテーマとなりました。これにより、プロセス成熟度の向上や作業効率の改善が期待されました。
- 環境変化に対応する変更管理: DevOpsの採用などによる展開回数の増加に対応するため、従来のウォーターフォール型開発を前提とした変更管理プロセスを見直し、高頻度・短期間での変更承認を可能にする柔軟な変更管理プロセスの改善が求められました。俊敏な対応と品質確保の両立が論点です。
- 重大なインシデント発生時のコミュニケーション: 複雑化するシステム環境において、重大インシデント発生時に、関係者間の正確かつ迅速な情報共有がより重要視されるようになりました。
社会的要請の変化
DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せ、企業はビジネス環境の変化に迅速に適応することを求められるようになりました。これにより、IT部門にも開発と運用のサイクルの高速化(DevOps)や、定型業務の自動化による効率化が強く期待されるようになりました。ITサービスマネージャは、これら新しい技術や手法を取り入れ、組織のアジリティ(俊敏性)を高める役割を担い始めました。
2022年~2025年頃:「ビジネス価値創出」と「リスクマネジメント高度化」の時代
この最新の時期では、ITサービスが企業のビジネスそのものに深く統合され、ITサービスマネージャがより戦略的な視点を持つことが強く求められています。単なる運用管理を超え、ビジネスの成長とレジリエンス(回復力)に貢献する役割へと進化しています。
主要なテーマ
- ITサービス継続計画(BCP): 大規模災害や予期せぬ事態(パンデミックなど)によるITサービスの中断が事業に与える影響を最小化するためのITサービス継続計画の策定と継続的な見直しが極めて重要視されています。
- 顧客価値創出と高度なサービスレベル管理: 顧客の事業環境の変化を深く理解し、ITサービスの価値向上に対する期待を把握した上で、具体的な改善計画を策定する能力が求められています。また、クラウドサービスを活用したITサービスが増加し、CSPとの連携やサービスマネジメント上の課題解決が新たなテーマとなっています。
- 運用品質改善とヒューマンエラー対策: 運用チームの運用品質改善目標の設定、方策の立案と実施、そしてヒューマンエラーに起因する障害の根本原因分析と再発防止策がより詳細に問われています。これは、自動化が進む中でも、人の介在によるリスクを最小化する重要性を示唆しています。
社会的要請の変化
ITサービスは、もはや単なる「インフラ」ではなく、企業の競争優位性を確立する「戦略的資産」となりました。企業は、ITを通じて新たなビジネス価値を創出し、同時に予期せぬリスクに対する強靭性(レジリエンス)を持つことを強く求められています。ITサービスマネージャは、ビジネス視点に立ち、顧客との共創を通じてIT戦略を推進し、組織全体のDXを加速させる中心的な役割を担うようになりました。
まとめ
情報処理技術者試験ITサービスマネージャの論述問題は、ITサービスマネジメントを取り巻く環境の変化と、それに対応してITサービスマネージャに求められる能力がどのように進化してきたかを如実に示しています。
当初はシステムの安定稼働と基礎管理に重点が置かれていましたが、ITILの普及とともに体系的なサービスマネジメントが求められるようになりました。さらに近年では、俊敏性、自動化、そしてビジネス価値創出と高度なリスクマネジメントといった、より戦略的でビジネス志向の強い能力がITサービスマネージャに期待されるようになっています。これは、ITが企業のバックオフィスからビジネスの中核へと役割を変え、その管理もより複雑かつ高度なものになっていることを反映しています。ITサービスマネージャは、技術的な知識に加え、ビジネス理解、コミュニケーション能力、そして変化への適応力が不可欠な、まさしくビジネスとITを繋ぐ要としての役割を確立しています。
🔍インタラクティブ・アプリケーション
Geminiの調査結果を基に、インタラクティブ・レポート機能を利用して出力した例を示します。
ITサービスマネージャ能力の変遷
情報処理技術者試験から読み解く30年の軌跡
1995-2005年: 守護者 の時代
システムの「安定稼働」と「基礎管理」
ITが業務効率化の基盤として導入され始めた黎明期。ITサービスマネージャの役割は、障害を未然に防ぎ、迅速に復旧させる「守り」が中心でした。システムの安定こそが最大の使命でした。
2006-2014年: 設計者 の時代
「ITIL」の浸透と「プロセス」の確立
ITILが普及し、ITを「サービス」として体系的に管理する考え方が定着。SLAに基づいた品質管理や、プロセス遵守が重要視され、ITサービスマネージャは運用の「設計者」となりました。
2015-2017年: 育成者 の時代
マネジメントの「深化」と「人材」への注目
ITサービスマネジメントの考え方が浸透した上で、それをさらに深化させる時期。プロセスの継続的改善(PDCA)に加え、運用を担う「人」のスキルアップや育成が重要なテーマとなりました。
2018-2021年: 触媒 の時代
「俊敏性」と「自動化」への挑戦
DXの波が押し寄せ、ビジネスの速度が加速。アジャイル開発やDevOpsに対応するための俊敏な変更管理や、AI・RPAを活用したプロセスの自動化が求められ、変化を促進する「触媒」としての役割を担いました。
2022-2025年: 戦略家 の時代
「ビジネス価値創出」と「リスク管理の高度化」
ITがビジネスの中核となり、その役割は運用管理から事業貢献へと進化。BCP策定など高度なリスク管理を行いつつ、顧客の事業価値を創出する「戦略家」としての視点が不可欠となっています。