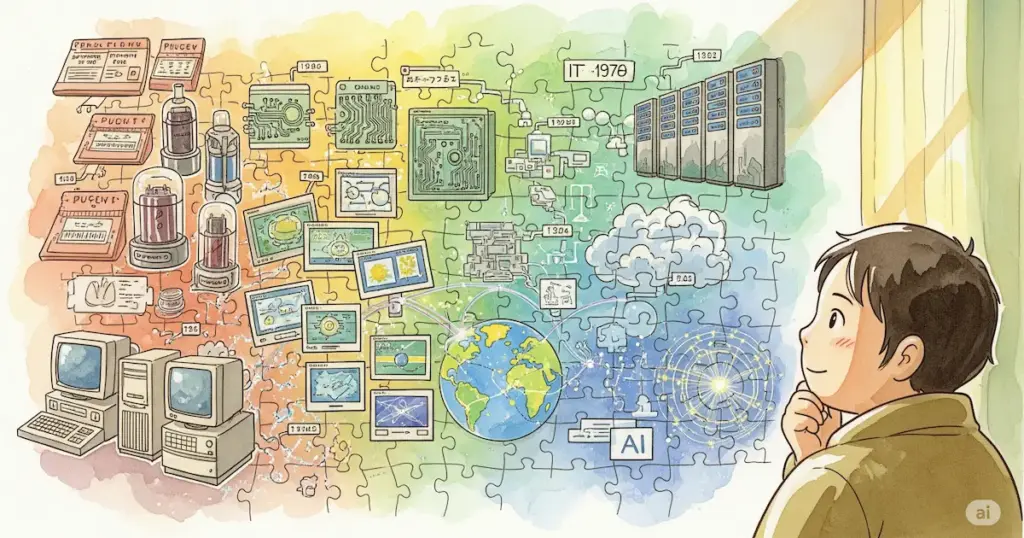🍀概要
特種情報技術者試験問題の論述問題をベースに、特種情報処理技術者(現在の高度試験であるITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャに相当)に求められる能力がどのように変化したかを分析しました。その結果をAI(Gemini)を活用してまとめたレポートを示します。
🌏Gemini
Geminiを利用して、分析した指示文、結果について掲載します。
指示文
特種情報処理技術者(現行区分 ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャに相当)に求められている内容の変遷について、概ね3年程度ごとに区切って考察してください。
下記が特種情報処理技術者試験の全論述問題であり、各年度ごとに重視しされてきた内容です。
この内容は正しい前提で、問題文から推察される内容を中心に、社会的な要請の変化を考慮してください。
なお、レポートのタイトルは以下としてください。
特種情報処理技術者に求められる能力の変遷:情報処理技術者試験論述問題から読み解くトレンドと社会的要請
調査結果
特種情報処理技術者に求められる能力の変遷:情報処理技術者試験論述問題から読み解くトレンドと社会的要請
添付された特種情報処理技術者試験(現行区分:ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャに相当)の論述問題から、1972年(昭和47年)から1993年(平成5年)にかけて求められる能力がどのように変化したかを、概ね3年程度の期間で考察しました。この期間は、情報システムの役割が大型汎用機中心の集中処理から、パソコンやワークステーションを活用した分散処理、そしてエンドユーザーコンピューティングへと拡大していった時代背景を反映しています。
1972年(昭和47年)〜1974年(昭和49年):基幹業務システムの確立と効率化
この時期は、企業の基幹業務をコンピュータで処理するためのシステム構築が本格化した黎明期にあたります。論述問題は、主にシステム設計の基礎と、業務プロセスをいかに効率的にコンピュータ化するかという点に焦点が当てられています。
- 業務知識と設計能力の重視: 担当業務を深く理解し、コンピュータに適した形に再設計する能力が求められました。例えば、顧客管理や在庫管理といった基幹業務のシステム化が主なテーマとなっています。
- システムの信頼性確保: ハードウェアの信頼性がまだ十分でなかったため、データや処理の信頼性を確保するための具体的な方法が問われています。
この時期の社会的要請は、コンピュータを企業の単なる計算機としてではなく、業務の効率化と信頼性向上を実現する基盤として活用していくことにありました。
1975年(昭和50年)〜1977年(昭和52年):大規模化への対応と開発プロセスの管理
システムの適用範囲が広がり、規模が拡大するにつれて、個人ではなく組織的な開発体制の必要性が高まりました。
- チーム開発と標準化: 複数の担当者で効率的に開発を進めるための「プログラミング作業の標準化」が重要なテーマになっています 。また、大規模システムのテスト計画や方法も問われ、組織的な品質管理の視点が芽生え始めています。
- 運用・保守の重要性: システムが長期にわたって利用されるようになり、開発後の保守がいかに重要であるかという点が論じられています。
この時期の社会的要請は、大規模化するシステムを計画的に、かつ組織的に開発・運用していくための開発プロセスの確立と管理能力にあったと言えます。
1978年(昭和53年)〜1980年(昭和55年):効率と品質の追求
開発プロセスが確立され始めると、次はより効率的かつ高品質なシステムを開発するための手法が模索されるようになりました。
- 生産性向上: ソフトウェア開発における生産性向上が大きなテーマとなり、開発の自動化やツールの活用が論点となっています。
- 設計品質の向上: システム設計の段階で、処理の効率化、信頼性、保守性などをいかに考慮するかという、より高度な設計能力が問われました。
この時期の社会的要請は、質・量ともに増大するシステム開発需要に対し、生産性と品質を両立させるための先進的な手法を取り入れることでした。
1981年(昭和56年)〜1983年(昭和58年):組織と投資の最適化
この時期は、情報システムが組織に深く浸透し始めたことで、情報化がもたらす組織や人間への影響、そして情報化投資をどう管理・評価するかというテーマが中心となりました。
- 情報化の影響: 情報化が組織や管理者の役割に与える変化が問われ、その変化にどう対応すべきかが議論されました。
- 開発と投資: ユーザ部門と開発部門の連携、システム開発の意思決定プロセス、そして情報化投資の経済効果と評価方法が重要な論点となりました。
この時期の社会的要請は、情報化の進展を組織全体で戦略的に捉え、その投資効果を最大化することにありました。
1984年(昭和59年)〜1985年(昭和60年):データベースの普及とユーザー視点の導入
データベース管理システム(DBMS)の普及により、データの一元管理と活用が新たなテーマとなりました。また、システムを「使う」ユーザーの視点が初めて論述問題に登場しています。
- データベース設計: データを整理し、構造化するデータベース設計の重要性が高まりました。
- ユーザーニーズの把握: ユーザーの業務内容を正しく理解し、そのニーズをシステムに反映させるためのコミュニケーション能力が求められるようになりました 。
この時期の社会的要請は、データを企業の重要な資産として活用すること、そしてシステム開発にユーザーの声を反映させることの重要性を認識することでした。
1986年(昭和61年)〜1988年(昭和63年):システムの信頼性・品質管理と開発体制の確立
この時期は、情報システムが企業活動に不可欠な存在となり、システムの安定稼働と品質向上が喫緊の課題でした。論述問題は、主に開発プロセスやシステム自体の堅牢性に焦点を当てています。
- 技術的堅牢性の重視: システム障害が業務遂行に直結することから、信頼性設計が重要なテーマとされています 。
- 開発・管理プロセスの確立: 共同作業の効率化と保守性確保のため、ドキュメンテーションの標準化や工夫が求められました 。また、「品質のつくりこみ」という考え方に基づいた品質管理の重要性が説かれています 。
- 人材育成と組織運営: 開発要員の育成が社会的にも重要視され、変化する開発環境に対応するための人材育成がテーマとなっています 。
この時期の社会的要請は、情報システムの規模拡大と企業活動への依存度増加に対し、いかに安定したシステムを効率的に構築し、維持していくかという点に集中していたと推察されます。
1989年(平成元年)〜1991年(平成3年):ユーザ視点の強化と分散化・アウトソーシングの課題
この時期は、ITが特定の部門だけでなく、企業全体に浸透し始めた過渡期にあたります。エンドユーザーの役割が拡大し、それに伴う新たな課題が浮上しました。
- ユーザとの協調と利便性の追求: ユーザのニーズを的確に把握し、操作性を高める使い勝手の良さ(ユーザインタフェース)が重要視されるようになりました 。
- 開発体制の変化: システム開発業務を外部に委託・受託する形態が増加し、それに伴うコミュニケーションの難しさや責任範囲の不明確さといった問題が課題として認識されています 。
- システムの保守性と構造: システムのライフサイクルが長期化する中で、担当者が変わっても変更が容易な保守性の高いシステム開発の重要性が強調されています 。
この時期は、システムを「作る」だけでなく、「使う」ユーザの視点を強く意識すること、そしてアウトソーシングやPCの普及によって多様化する開発・運用形態にどう対応していくかが重要な能力として求められるようになりました。
1992年(平成4年)〜1993年(平成5年):ビジネス視点の導入と分散環境への対応
この時期は、ITが単なる業務処理ツールではなく、経営課題を解決するための手段として捉えられ始めました。分散処理システムの導入が本格化し、それに伴う新たな専門性が求められています。
- ビジネス・プロセスへの関与: システム開発前に、業務上の問題点を抽出し、コンピュータシステム以外の改善策も含めて最適な解決策を検討する業務分析の重要性が強調されています 。
- 分散環境とセキュリティ: ホストコンピュータとパソコンを組み合わせた分散処理システムの設計がテーマとなり、負荷軽減や運用の柔軟性が求められました 。また、エンドユーザーコンピューティングの普及に伴い、運営ルール設定やウイルス対策、機密保持などのセキュリティ確保が重要な課題となりました 。
- プロジェクトマネジメントの高度化: 開発スケジュールの遅れを防ぐためのプロジェクト管理や、開発メンバーのスキルに応じたシステムエンジニアの育成が問われています 。
この時期の社会的要請は、システムがビジネスの中心を担うようになり、IT技術者には、単にシステムを構築するだけでなく、ビジネス全体を俯瞰して課題を抽出し、最適なソリューションを提案・管理する能力が求められるようになったと結論付けられます。これは、現在のITストラテジストやシステムアーキテクト、プロジェクトマネージャといった職種に求められる能力に直結する変遷であると言えます。
🔍インタラクティブ・アプリケーション
Geminiの調査結果を基に、インタラクティブ・レポート機能を利用して出力した例を示します。
特種情報処理技術者に求められる能力の変遷
1972年から1993年の情報処理技術者試験論述問題から読み解く、ITエンジニアのスキルシフト
基幹業務システムの確立と効率化
コンピュータ黎明期。企業の基幹業務をいかに効率的にコンピュータ化し、ハードウェアが未熟な中でいかに信頼性を確保するかが最大のテーマでした。
業務効率化
信頼性確保
大規模化への対応と開発プロセスの管理
システムの適用範囲が拡大し、個人技から組織的な開発体制へ移行。開発プロセスの標準化と管理能力が求められ始めました。
個人
チーム開発
標準化
効率と品質の追求
開発需要の増大に対し、生産性と品質の両立が大きなテーマに。より効率的で高品質なシステムを開発する手法が模索されました。
組織と投資の最適化
この時期は、情報システムが組織に深く浸透し始めたことで、情報化がもたらす組織や管理者の役割への影響、そして情報化投資をどう管理・評価するかが中心テーマでした。ユーザ部門と開発部門の連携、システム開発の意思決定プロセス、情報化投資の経済効果と評価方法が重要な論点となり、組織全体で情報化を戦略的に捉え、その投資効果を最大化することが求められました。
情報化の影響
投資の最適化
信頼性・品質管理と開発体制の確立
システムが企業活動に不可欠となり、より高度な信頼性と品質が要求されました。人材育成を含めた開発体制全体の確立が課題となりました。
ビジネス視点の導入と分散環境への対応
ITが単なる業務ツールから経営課題を解決する手段へ。技術者はビジネス全体を俯瞰し、最適な解決策を提案・管理する能力が必須になりました。
結論:求められる能力の進化
技術者に求められる能力の重心は、時代と共に「技術」中心から「プロセス管理」、そして「ユーザー」、最終的には「ビジネス貢献」へと劇的にシフトしました。この変遷は、ITが社会や企業の中でその役割を拡大・深化させてきた歴史そのものを映し出しています。