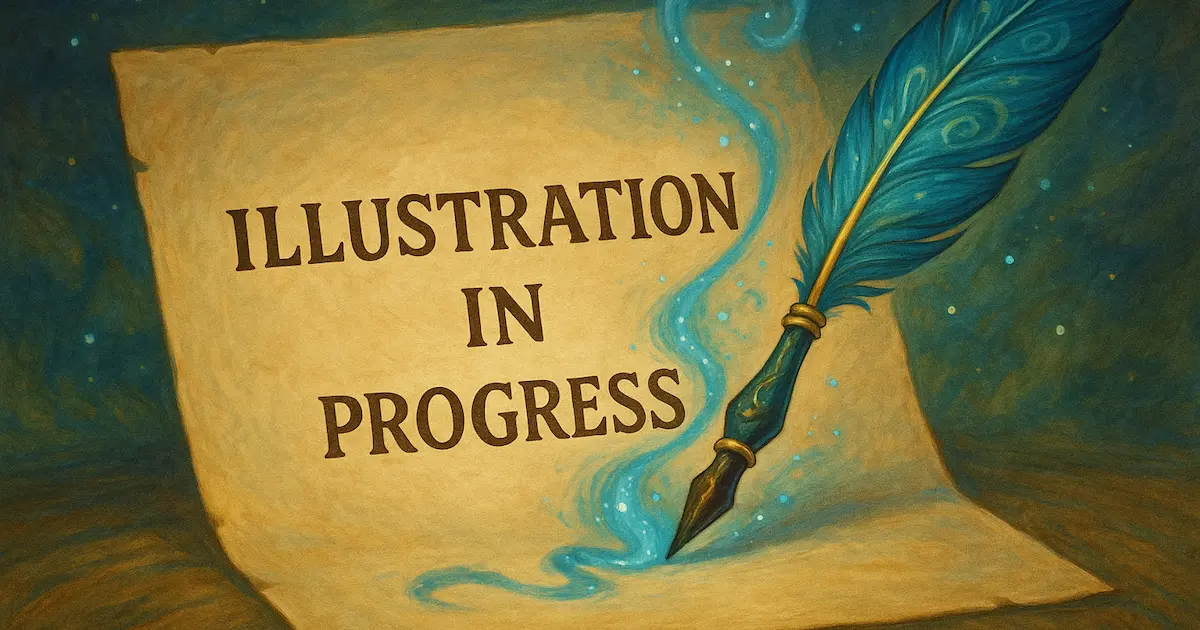📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
日用品メーカーにおける需給調整力強化を目的とした新発注システム導入の企画と、その投資効果の検討について述べる。AIによる需要予測を活用し、売上向上と在庫ロス削減を目指した。段階導入と現場対応策を講じ、全社展開へとつなげた、ITストラテジストの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(ST-H29-Q1)
出典:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験 平成29年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
IT導入の企画における投資効果の検討について
■内容
企業が経営戦略の実現を目指して,IT導入の企画において投資効果を検討する場合,コスト削減,効率化だけでなく,ビジネスの発展,ビジネスの継続性などにも着目する必要がある。IT導入の企画では,IT導入によって実現されるビジネスモデル・業務プロセスを目指すべき姿として描き,IT導入による社会,経営への貢献内容を重視して,例えば,次のように投資効果を検討する。
・IoT,ビッグデータ,AIなどの最新のITの活用による業務革新を経営戦略とし,売上げ,サービスの向上などを目的とするIT導入の企画の場合,効果を評価するKPIとその目標値を明らかにし,投資効果を検討する。
・商品・サービスの長期にわたる安全かつ持続的な供給を経営戦略とし,ITの性能・信頼性の向上,情報セキュリティの強化などを目的とするIT導入の企画の場合,システム停止,システム障害による社会,経営へのインパクトを推定し,効果を評価するKPIとその目標値を明らかにし,投資効果を検討する。
ITストラテジストは,IT導入の企画として,IT導入によって実現されるビジネスモデル・業務プロセス,IT導入の対象領域・機能・性能などと投資効果を明確にしなければならない。また,期待する投資効果を得るために,組織・業務の見直し,新しいルール作り,推進体制作り,粘り強い普及・定着活動の推進なども必要であり,IT導入の企画の中でそれらを事業部門に提案し,共同で検討することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わった経営戦略の実現を目指したIT導入の企画において,事業概要,経営戦略,IT導入の目的について,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた目的の実現に向けて,あなたはどのようなIT導入の企画をしたか。また,ビジネスの発展,ビジネスの継続性などに着目した投資効果の検討として,あなたが重要と考え,工夫したことは何か。効果を評価するKPIとその目標値を明らかにして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたIT導入の企画において,期待する投資効果を得るために,あなたは事業部門にどのようなことを提案し,それに対する評価はどうであったか。評価を受けて改善したこととともに600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
本稿では、日用品・化粧品を展開するB社における発注精度向上と需給調整力強化を目的としたIT導入企画について述べる。私はITストラテジストとして、AIによる需要予測に基づいた推奨発注システムを企画し、サプライチェーン企画部門とともに試算・試行を実施した。売上5%増、在庫ロス10%削減などの投資効果が試算され、営業利益率の向上が期待された。現場の不安に対しては段階導入や予測ロジックの改善、フィードバック機能の追加などで対応し、順次全社展開が進められた。
📝論文
🪄タイトル AI需要予測を活用した発注最適化
本稿は、IT導入の企画における投資効果の検討について述べる。
🔍第1章 事業概要と事業特性及び経営戦略とIT導入の目的
1-1 事業概要と事業特性
私はSIベンダーであるA社のコンサルタント部門に所属するITストラテジストである。日用品・化粧品・ヘルスケア製品などを展開するB社から、発注システム刷新に関するコンサルティング依頼を受け、新発注システムの開発企画書の作成を支援した。
B社は、国内の大手ドラッグストア・量販店・ECサイトなど多様な流通チャネルを通じて製品を展開している。特にスキンケア・ヘアケア・衛生用品の分野において高いブランド力を持ち、グローバル展開も積極的に進めている。一方で、季節性や販売地域による需要変動が激しく、きめ細かな発注・在庫管理が重要な課題となっていた。
1-2 経営戦略とIT導入の目的
B社は、生活者視点を重視したマーケティングと、効率的なサプライチェーンマネジメントを両輪とする経営戦略を掲げており、製販一体の需給調整力強化に向けて、デジタル技術を積極的に取り入れている。
従来は、営業部門や販売店からの受注動向を元に人手で調整を行っていたが、在庫ロスや販売機会損失が発生していた。
そのため、過去実績、販促計画、チャネル別特性を踏まえた精緻な需要予測に基づき、発注提案を行う仕組みの構築が求められた。これにより、売上・利益向上に加えて、環境負荷低減にもつながると考えた。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 IT導入の企画と投資効果の検討
2-1 IT導入の企画
私は、B社のサプライチェーン企画部門と共同で、新発注支援システムの企画を実施した。この新システムは、各販売チャネル・製品カテゴリ別に「推奨発注数」をシステムが自動算出し、現場担当者が確認・調整の上で発注できる仕組みとした。
推奨発注数は以下の式で算出される:
推奨発注数=発注周期×予測販売数(日)-現在庫+安全在庫
予測販売数は、販売実績、プロモーション、店頭配置、気象・季節データを加味し、AIモデルにより算出される。特にB社は販促施策が多岐にわたるため、直近キャンペーンなどの要素も自動的に評価する設計とした。
完全な自動発注も検討したが、現場判断の余地を残した「提案型」の導入が望ましいと判断し、柔軟なカスタマイズを可能とした構成にした。
2-2 投資効果の検討
まず一部のカテゴリ・販売チャネルで表計算を用いた簡易試験を行った。その結果、スキンケア製品において発注精度が向上し、売上が9%増加、在庫ロスは12%減少した。
この成果から、新発注システムを全社展開すれば、全体で売上5%増、在庫ロス10%削減、営業利益率2%改善が見込めると判断した。
B社の決算情報と照らし合わせ、営業利益は年間25億円以上の向上が期待できると試算された。開発投資は約20億円であり、1年で投資回収が可能な費用対効果であると評価された。
この企画におけるKPIとしては以下を設定した:
・売上高:5%向上(対象カテゴリ)
・営業利益率:2%改善
・在庫回転率:10%向上
これらの指標は3年後の達成を目標とし、経営戦略と整合性のある内容として提案書にまとめた。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 事業部門への提案と評価
3-1 事業部門への提案
私は、試算によるKPIを提示し、環境負荷削減・欠品率低減なども含めた定量的な効果を明示した。これにより経営層からは、「サステナビリティ経営の一環としても意義がある」として高い評価を得た。
一方で、営業現場や生産部門からは「実際のプロモーションや季節性の変化をうまく吸収できるのか」という懸念が示された。
そこで私は、段階的導入と改善サイクルを提案した。
・実験的導入(対象チャネルに限定)
・販促情報・季節情報の反映頻度向上
・現場入力フィードバック機能の追加
を盛り込むことで、各部門の納得感を醸成する施策とした。
3-2 評価と改善点
実証導入では、定番商品の多いカテゴリでは十分な成果を挙げる一方、花粉症・UV対策など季節要因が強く影響する製品では予測がずれる場面があった。
このため、AIモデルの学習データに天気予報・花粉指数・販促計画などの外部要因を追加し、ロジックを強化。現場からのコメント機能も追加し、実績データとの乖離を縮小させた。
その結果、営業・SCM部門からは「実用段階に達した」との評価が得られ、順次対象製品を拡大しながら全社導入が開始された。導入から3か月が経過し、初期KPIも想定通りに推移している。
現場からの改善要望にも柔軟に対応しており、システムは着実に業務に定着しつつある。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
以下に、論文に対する詳細評価を示します。
✅【総合得点】:88点(合格)
| 評価項目 | 概要 | 配点 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ① 設問対応 | 各設問に対応する章構成と内容整合性 | 30点 | 28点 |
| ② 課題の妥当性 | B社の需要変動と発注精度の課題設定 | 10点 | 9点 |
| ③ 行動記述の具体性 | AI活用・推奨発注数の計算式・段階的導入の判断等 | 25点 | 23点 |
| ④ ステークホルダ描写 | 営業現場の懸念、対話と改善提案 | 10点 | 9点 |
| ⑤ 成果の説得力 | KPI試算と全社導入効果、初期成果と定着状況 | 15点 | 13点 |
| ⑥ 構成・表現 | 明確な節構造、文体も一貫性あり | 10点 | 6点 |
| 合計 | 100点 | 88点 |
🚦【致命的欠陥チェック】:すべてOK
| フィルター項目 | 内容 | 判定 |
|---|---|---|
| A. PMの行動 | 判断保留・譲歩・段階的導入の描写あり | OK |
| B. ステークホルダ対話 | 営業・SCM部門との丁寧なやりとりあり | OK |
| C. 設問対応 | 設問ア~ウへの明確な章節対応 | OK |
| D. 成果の明示 | KPIの目標値と実績比較あり | OK |
📝【評価コメント】
- 設問対応
章立ては設問ア~ウに完全に対応しており、節構成も明確で読みやすい。特に投資効果(設問イ)と導入後の工夫(設問ウ)の論理展開がスムーズで、読み手の理解を助ける。 - 行動記述・ステークホルダ描写
PM(ITストラテジスト)の判断根拠・AI導入方式の選定・段階的展開など、説得力のある意思決定が具体的に示されている。現場の不安に対する配慮・改善策も丁寧で、現実感がある。 - 成果の提示
売上・利益・在庫ロスといったKPIの定量的効果に加え、営業部門の評価や定着状況といった定性面もバランスよく描かれている。 - 構成・表現の課題
やや一文が長く、読点の位置により読みづらさを感じる箇所が一部ある。また、第3章において「さらなる展開」「今後の活用可能性」などの戦略的視点が補足されると、さらに評価が高まる。
✨【総合評価】:A(合格)
模範に近い内容であり、ITストラテジストとしての役割と判断・合意形成・効果検証が一貫して描かれている優秀な論文です。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。