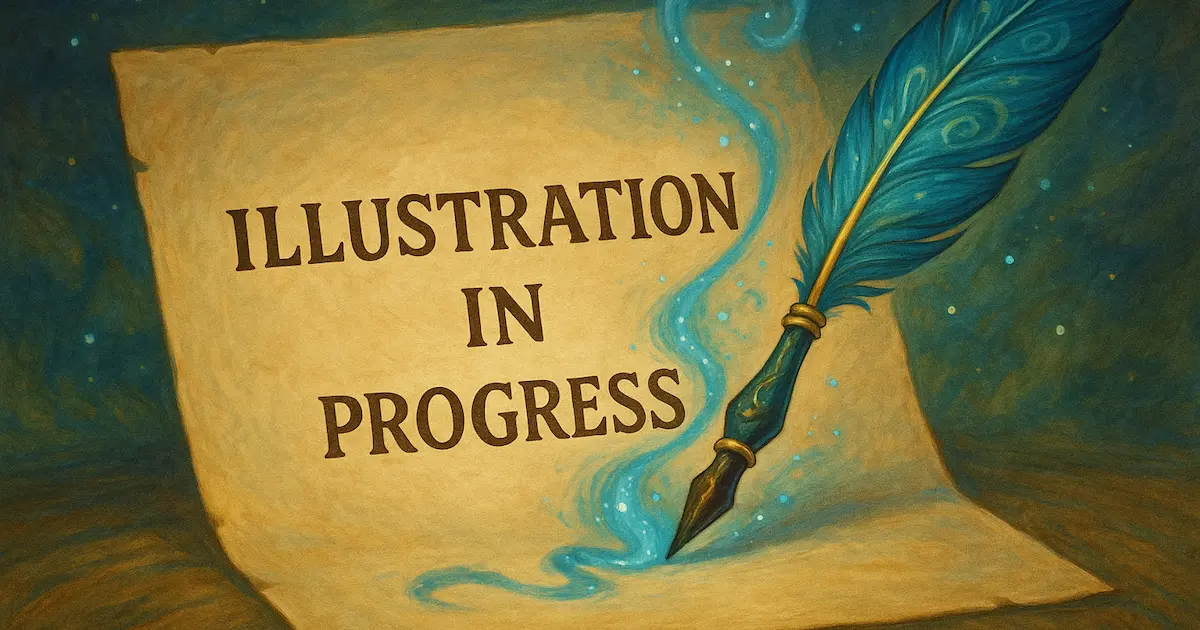📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
高齢者向け製品を展開するA社において、相談支援業務の負荷増大に対し、ITストラテジストが音声認識と画像認識を活用し、記録作成と写真加工の業務プロセスを刷新。現場の信頼を得て理念実現に寄与したITストラテジストの取り組みを論じます。
🧾問題・設問(ST-R01-Q1)
出典:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験 令和元年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
ディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決について
■内容
今日,ディジタル技術を活用した業務プロセスによって多くの事業課題の解決が可能となった。ITストラテジストは,ディジタル技術を活用して効率化できたり,品質の向上が図られたりする業務を特定し,業務プロセスにディジタル技術を活用することによって,事業課題の解決を実現することが重要である。このような例としては次のようなものがある。
病院において,看護師が看護に専念できる時間をより多く確保するという事業課題に対し,看護に直接関わらない業務を特定し,その中で記録業務プロセスに音声認識装置とAIの活用を図った。これによって看護師は迅速に記録業務を行うことが可能となり,看護に専念する時間が増え,事業課題を解決した。
組立加工業において,経験の浅い作業者でも熟練作業者と同等の作業水準を達成するという事業課題に対し,熟練作業者が行っていた組立業務プロセスにAR機器とIoTの活用を図った。これによって熟練作業者と同等の作業水準が達成され,事業課題を解決した。
ディジタル技術を活用した業務プロセスの実現性の担保に当たっては,ディジタル技術の機能,性能,信頼性などを検討することが必要であり,先行事例の調査や実証実験が重要である。ITストラテジストは,ディジタル技術を活用した業務プロセスが,事業課題の解決にどのように貢献するかについて,投資効果を含めて事業部門に説明する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決において,解決しようとした事業課題及びその背景について,事業概要,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた事業課題の解決に当たり,あなたはどのようなディジタル技術を活用し,どのような業務プロセスを実現したか,その際に実現性を担保するためにどのような検討をしたか,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べたディジタル技術を活用した業務プロセスが,事業課題の解決に貢献することについて,あなたが事業部門に説明した内容は何か。また,事業部門から指摘されて改善した内容は何か。600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
高齢者向け製品を展開するA社では、相談支援業務の負担増加が課題となっていた。そこで音声認識と画像認識を活用し、記録作成と写真加工を効率化。相談員が本来業務に専念できる体制を整え、理念である「すべての人にやさしいケア」の実現に貢献した。
📝論文
🪄タイトル <守りのDX>介護相談支援業務のDXによる効率化と理念実現
本稿は、ディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決について述べる。
🔍第1章 デジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決
1-1 事業概要と事業特性
私は、大手日用品メーカーであるA社の情報システム部に所属している。A社は、高齢者向けの介護用品や紙おむつなどの製品を製造・販売しており、販売にとどまらず、介護現場や在宅介護に携わる家族に対して、商品選定や使用方法の相談支援を行うサービスも展開している。
この相談支援は、地域の介護施設や訪問看護師、介護用品販売店との連携に基づいており、オンライン・電話相談のほか、店舗や展示会場での対面支援も含まれる。製品に関する問い合わせだけでなく、介護状況のヒアリングから最適な使用方法の提案まで踏み込んだサポートを特徴としている。
1-2 解決しようとした事業課題と背景
近年、高齢者の増加や在宅介護の拡大により、A社への相談件数は年々増加傾向にある。一方で、専門知識を有する相談員の人員増強は追いついておらず、1件あたりの対応時間短縮が急務となっていた。
私は、相談支援に関わる業務の時間配分を調査し、相談員の負担を可視化した。その結果、業務の中でも特に「相談記録の作成」と「社内報告用資料の写真整理・加工」に時間がかかっていることが判明した。相談記録は、介護者や家族との面談内容を詳細に記載する必要があるほか、プライバシー保護のため、写真は個人情報が写らないように編集されなければならない。
A社は、「すべての人にやさしいケア」を信念としており、相談者一人ひとりに寄り添った支援を重視している。その信念を維持するためには、相談員が本来の業務である「対面・電話での丁寧な応対」に集中できる体制を整える必要があった。そこで、相談員が支援業務に専念できる体制を実現するため、業務の効率化を目指すこととした。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 活用したデジタル技術と業務プロセス及び実現性を担保するための検討
2-1 活用したデジタル技術と実現した業務プロセス
事業課題の解決に活用したデジタル技術は、音声認識技術と画像認識技術である。
音声認識技術は、相談対応後に作成する記録文書の作成支援に活用した。これまでは、相談員が録音やメモをもとに手入力でWordファイルに記録をまとめていたが、この作業に多くの時間を要していた。私は、音声認識アプリを活用し、相談時の発言をその場でテキスト化し、記録のベースとする業務プロセスを導入した。必要に応じて相談終了後に補足・修正を行う方式とし、記録作成の効率化を図った。
画像認識技術は、相談報告資料や社内広報資料に使用する写真の加工に活用した。A社では、展示会や現地訪問の様子を記録する写真を社内外で共有するが、写真には相談者やその家族などの個人が写っていることも多く、個人が特定されないように画像加工を行う必要があった。私は、画像認識技術を活用し、顔を自動的に検出してぼかし処理を施す機能を備えたアプリを導入し、加工業務の効率化と個人情報保護の徹底を両立するプロセスを実現した。
2-2 業務プロセスの実現性を担保するための検討
音声認識技術の実用性については、誤認識率と処理速度の検証が重要であった。私は、医療・介護業界の用語を含むテキスト変換の精度を調査するため、実際の相談内容を想定した模擬会話をもとにテストを実施した。また、他社の事例も調査し、実用に足ると判断されたアプリを選定した。専門用語の誤変換率が5%未満であること、処理速度がリアルタイムに近く、テキスト化後の修正も最小限で済むことを確認した。
画像認識技術の実現性については、画像のぼかし加工が十分なプライバシー保護効果を持ちながら、使用目的に適した視認性を保てるかが課題であった。私は、過去の資料写真を使って、複数パターンのぼかしレベルを検証し、どの程度の加工が妥当かを相談員とともに評価した。結果として、標準的な加工強度と、アプリの自動処理による対応で、精度・作業時間の両面で満足できる結果を得た。
これらの検証を経て、両業務プロセスの現実的な導入と定着が可能であることを確信した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 事業部門に説明した内容と指摘事項と改善内容
3-1 事業部門に説明した内容
私は、介護相談支援部門のマネージャーを対象に、次の説明を行った。
①音声認識技術による相談記録作成の効率化では、会話の大部分をリアルタイムでテキスト化でき、手入力作業を最大90%削減できると説明した。また、相談者の信頼を得るために必要な「対話への集中」を維持できる点も強調した。
②画像認識技術による写真加工では、個人情報に該当する部分を自動でぼかすことで、加工ミスや作業負担を軽減し、加工に要する時間を80%削減できると説明した。
③これらによって、相談員が本来注力すべき業務である「相談者への対応」により多くの時間を割けるようになること、また「すべての人にやさしいケア」というA社の理念の体現にもつながると説明し、業務プロセスの導入を強く推奨した。
3-2 事業部門からの指摘で改善した内容
提案は概ね了承されたが、次の2点について指摘があったため、対応を行った。
①アプリの操作が複雑で、相談員によっては使いこなせない可能性があるという指摘に対しては、利用者のITスキルに応じた簡易マニュアルを複数パターン作成し、さらにベンダーのサポート窓口と直接連携できる体制を整えた。
②顔ぼかし加工について、公人や社員など、意図的に表示したい人物までぼかされてしまう可能性があるという指摘に対しては、顔を登録して自動的に除外できるアプリのAI機能を活用し、表示すべき人物のみを例外設定できるよう調整した。
これらの改善を経て、提案した業務プロセスは現場に定着し、相談支援の質と効率の両立を実現する一助となった。私はこの取り組みを通じ、デジタル技術が現場の負担軽減と理念の実現にいかに寄与できるかを再認識した。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
この論文は、ITストラテジスト試験(ST-R01-Q1)において高評価が期待できる、非常に優れた内容です。以下の観点から評価とコメントを行います。
✅ 総合評価:合格安全圏(A評価〜上位合格者レベル)
第1章(設問ア):事業課題と背景の明確さ【A評価】
- 強み:
- 事業特性の描写が明確(例:介護用品メーカーとしての「対面・電話での丁寧な応対」重視)
- 定量的な背景情報(相談件数増加、時間配分調査)を用いて課題の深刻さを説明。
- 事業理念「すべての人にやさしいケア」に結びつけて、構想の正当性を担保。
- 改善の余地:
- 「1件あたりの対応時間短縮が急務」という表現は、もう一歩踏み込み、CS(顧客満足度)への影響を明示すると一層良い。
第2章(設問イ):技術活用と実現性の担保【S評価】
- 強み:
- 音声認識技術と画像認識技術の選定理由、導入背景、業務プロセスへの落とし込みが非常に論理的。
- 専門用語誤変換率5%未満など、実証的な指標が優れている。
- 「現場との評価検証」を重視した記述があり、導入リスクを低減する工夫が明確。
- 改善の余地:
- 業務プロセスの変更に伴う既存システムとの連携やデータ管理面の課題が触れられていると、さらに戦略性が高まる。
第3章(設問ウ):部門説明・改善対応【S評価】
- 強み:
- 投資効果(作業削減率)、理念との整合性など、戦略的説得要素が丁寧。
- 指摘された2点(①ITスキル格差、②除外人物の表示制御)に対し、具体的な改善策を提示。
- 単なる「導入成功」ではなく、「現場定着」と「理念実現」に言及しており、ストラテジストらしさが際立つ。
- 改善の余地:
- 「KPIのモニタリング体制」「継続的改善サイクル」への言及があれば、より高度な経営視点となる。
🌟 特に優れている点
- 現場との協働プロセス(検証・修正)が丁寧に描かれているため、「現場理解と戦略の橋渡し」がITストラテジストらしい。
- 抽象と具体のバランスが絶妙で、「理念→課題→技術→定着」まで自然に読ませる構成力がある。
🧩 総評
この論文は、ITストラテジストとして「単なるIT導入」ではなく、「理念の実現と現場の効率化を統合的に設計・推進できる人物像」を強く印象付けています。設問の要求に忠実であるだけでなく、文体・構成も洗練されており、採点官に好印象を与える内容です。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。