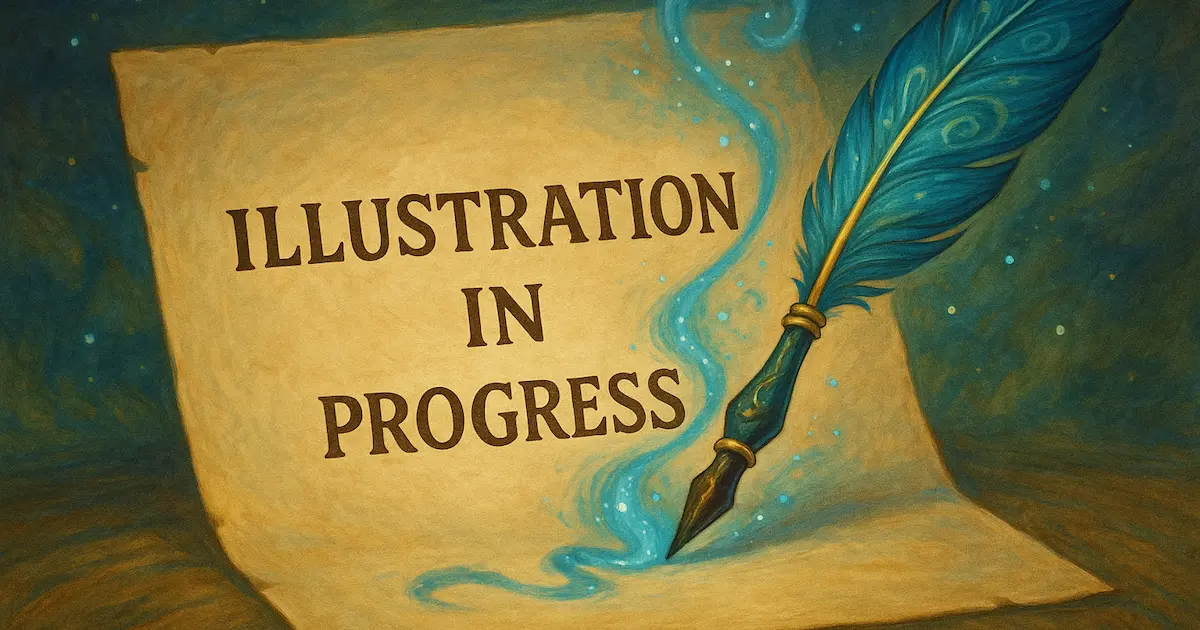📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(ST-R04-Q1)
出典:情報処理推進機構 ITストラテジスト試験 令和4年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について
■内容
近年,顧客が商品やサービスに興味をもってから,購入や利用までの一連の体験を通じて得る満足度を向上させることが,企業が差別化を図るために重要になっている。そのため,ITを活用して,顧客との接点を増やしたり,関係性を高めたりすることで,顧客に新たな価値を感じてもらえる新商品や新サービスを提供することがある。
ある保険会社では,顧客の声を収集,分析したところ,多くの商品で年齢ごとに保険料が一律であることに不満が多かった。また,契約と保険金の支払以外で顧客との接点が少なかった。そのため,健康に気を使えば保険料を割り引く,健康増進型の保険商品を企画した。具体的には,スマートデバイスで契約期間中の顧客との接点を増やし,顧客の同意のもと健康診断や歩行などの健康データを収集する。そして収集した健康データを活用して,翌年以降の保険料を割り引く仕組みを提供した。さらに,健康的な食事などへのアドバイスや,スポーツジムの利用の割引を提供した。それによって,顧客に新たな価値を感じてもらえる新商品を実現した。
ITストラテジストは,ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画を行う際,次のような事項を検討することが重要である。
・どのような顧客に対して,接点を増やしたり,関係性を高めたりするか。
・顧客との接点で,どのような新たな価値を提供するか。
・新商品や新サービスを実現するためにどのようなデータを扱うか。
その上で,顧客満足度を向上させる新商品や新サービスについて,顧客満足度を測る指標や投資効果とともに,経営層に提案する必要がある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わったITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画において,事業概要,顧客満足度を向上させることが必要となった背景を,事業特性とともに800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べた顧客満足度を向上させるために,ITを活用してどのような新商品や新サービスを企画したか。顧客との接点や関係性,新たな価値,扱うデータを明確にして,800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について,経営層に何を提案し,どのように評価されたか。経営層の評価を受けて改善したこととともに,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
本論文は、A社が育児用品の利用者に対し、スマホアプリを通じた育児支援コミュニティや専門家相談機能を提供し、顧客との接点強化と精神的支援による満足度向上を実現した事例を述べる。ITの活用により、商品提供から体験・支援型の価値提供への転換を図った。
📝論文
🪄タイトル 【攻めのDX】ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について
本稿は、ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について述べる。
🔍第1章 新サービスの企画における事業概要など
1-1 事業概要
A社は、ベビー用紙おむつや介護用品、フェミニンケア用品などを主力製品とする大手日用品メーカーである。少子高齢化が進む中でも、国内外で高いブランド力を維持しており、特に育児用品と介護用品分野では継続的な製品開発とサービスの強化に力を入れている。近年では、商品の提供にとどまらず、育児や介護を支える生活支援全体を視野に入れたデジタルサービスの展開を進めており、スマートフォンアプリケーション(以下、スマホアプリ)を活用した新たな顧客接点の創出に取り組んでいる。
1-2 事業特性及び顧客満足度を向上させることが必要となった背景
A社の主要市場である育児用品や介護用品の領域では、競合他社との差別化が難しく、商品の機能や価格だけでは顧客ロイヤルティの向上に限界がある。一方、育児や介護の現場では、保護者や介助者が孤立しやすく、精神的・肉体的な負担が大きいという課題がある。
このような背景のもと、A社では商品提供に加えて、育児や介護の“困りごと”を軽減し、安心感を提供するサービスの重要性が増していた。また、スマホアプリを通じたサービスの展開により、利用者との接点を強化し、継続的なブランド価値の訴求を実現できる可能性が高いと判断した。
そこで私は、A社の情報システム部のITストラテジストとして、新たに発売予定のベビー用紙おむつに連動する形で、次に述べる新サービスの企画を立案し、経営層に提案した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 企画した新サービス
2-1 顧客との接点や関係性
従来のスマホアプリは、育児記録(排泄、睡眠、授乳)を記録する個人利用を主な対象としていた。今回の新サービスでは、アプリ利用者間の情報共有や悩み相談ができる「育児コミュニティ」機能を搭載し、顧客との接点を個人からコミュニティへと拡大した。
また、専門家(助産師、保育士等)によるオンライン相談機能も提供し、育児に関する悩みを直接解決できる環境を整えることで、A社と顧客との関係性をより深めることを狙った。
2-2 新たな価値
利用者は、子どもの成長記録をコミュニティ内で共有したり、他の利用者と共感を得ることができる。また、アプリからの通知で「月齢に応じた育児アドバイス」や「おすすめ商品の提案」を受けられるようにした。
さらに、悩みを投稿したユーザーが、他のユーザーから共感・応援コメントをもらうことで、精神的な孤立感を和らげ、安心・信頼というA社独自の価値を体感してもらえるよう工夫した。
2-3 扱うデータと企画した新サービス
扱うデータは、ユーザーが記録した育児データ(排泄・授乳・睡眠時間など)、利用履歴、相談内容、コミュニティへの投稿内容などである。
企画した新サービスの主な機能は以下の通りである:
① 無料の育児アドバイス機能
育児ログをAIで分析し、月齢に応じた無料の育児アドバイスを提供する。
② 有料の専門家相談サービス
助産師や保育士とのチャット・ビデオ相談を有料で提供し、顧客の安心感を高める。
③ 育児コミュニティ機能
共通の悩みや経験をもつ利用者同士のつながりを促進し、育児ストレスの軽減に寄与する。
④ 育児ポイント機能
アプリ利用や投稿、相談への参加に応じてポイントを付与し、A社公式オンラインショップでベビーケア商品と交換できる仕組みを導入した。
これらの機能により、顧客に対して「支援」「共感」「利便性」の新たな価値を提供できると判断した。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 経営層への提案、評価及び改善
3-1 経営層への提案
経営層には以下の3点を中心に提案した:
① 経営戦略との整合性
本サービスは「製品中心の価値提供から体験・支援中心の価値提供」への転換を体現するものであり、中長期の顧客ロイヤルティ向上策として経営戦略と整合することを強調した。
② 顧客満足度指標としてのNPS導入
顧客満足度の可視化には、ネットプロモータスコア(NPS)を用いることを提案した。アプリ利用時やコミュニティ参加時に、顧客に簡単なアンケート形式で回答してもらうことで、継続的なモニタリングを実現する。
③ 投資効果の提示
本サービス単体での利益は中長期に発現するが、関連商品の継続購入、ブランド認知向上による売上拡大といった波及効果が大きいことを示し、IRRを活用した投資評価とあわせて経営判断を後押しした。
3-2 経営層の評価と改善したこと
提案に対して経営層からは、「IRRによる評価だけでは、将来のブランド価値向上や顧客ロイヤルティの定性的効果が正しく反映されない」との指摘を受けた。
そこで私は、次の改善を行った:
・「孤育て」「介護離職」など社会課題の解決にも貢献できるという定性的効果を明示し、CSR・ESG文脈での価値創出を強調
・商品軸での売上だけでなく、アプリ経由のサービス利用により得られる継続接点の重要性を強調
・顧客の定着率(チャーン率)の改善指標も盛り込み、短期収益だけでは評価しきれない経営上のメリットを定量・定性の両面で可視化
その結果、経営層からは「単なる製品付加価値ではなく、A社の次世代型マーケティングの先行モデルとなる」という高い評価を得ることができた。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅ 総合評価:安全圏の合格(A評価)
🔍【設問ア】事業概要・背景の記述(第1章)
📌 評価ポイント:
- **「誰に・なぜCS向上が必要か」**が明確。
- 事業特性(少子高齢化・商品差別化困難・心理的負担)とCS向上の必要性(精神的支援・接点強化)との因果関係が丁寧。
- ITストラテジストとしての立場(情報システム部に所属)も冒頭で明示されており、役割の適格性が伝わる。
💬 コメント:
- 「アプリを通じた継続的なブランド価値訴求」という文言は、背景としてのIT戦略とブランド構築の連動性を自然に伝えており秀逸。
- 導入文や接続も読みやすく、流れのよい序章構成。
🛠【設問イ】新商品・新サービスの企画内容(第2章)
📌 評価ポイント:
- 「顧客との接点の拡大」「関係性の深化」「新たな価値」「扱うデータ」がすべて明確な小見出し+具体例付きで記述されている。
- 専門家相談やコミュニティ機能、AIによるアドバイスなど、多面的な価値提供が記述されており、単なる機能紹介にとどまらず、顧客視点での利点が強調されている。
- データ活用に関しても、個人の育児ログからコミュニティ投稿、相談内容までの網羅性があり、プライバシーやAI活用の前提も感じさせる。
💬 コメント:
- 「支援」「共感」「利便性」という価値の整理が、企画の本質を一言でまとめており、読者の理解促進にも貢献。
- 企画の“面白み”だけでなく、“ITストラテジストの俯瞰的視点”も伝わる良章。
🧠【設問ウ】経営層への提案と評価・改善(第3章)
📌 評価ポイント:
- 「戦略との整合性」「CS指標の定義」「投資効果」という3点提案が、設問の要求を過不足なく網羅。
- 定性的評価への批判と改善、CSR・ESG文脈での効果の追加など、**ストラテジストとしての“経営目線への橋渡し”**ができている。
- 提案に対するフィードバックを受けての改善も自然で、現実感がある(机上の空論になっていない)。
💬 コメント:
- 「IRRと定性的価値の両立」や「チャーン率指標の提示」など、ITストラテジストとしての視座の高さが明確。
- 最終的に「次世代マーケティングの先行モデル」と評価される流れも、構想力の示し方として模範的。
📈 評価まとめ(採点目安)
| 評価項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 論文構成(設問との整合) | ◎(満点相当) | 明確に3章構成。見出しも整理されている。 |
| 問題設定の妥当性 | ◎(満点相当) | 社会課題とCSの関連を的確に捉えている。 |
| 解決策の具体性・整合性 | ◎(満点相当) | 顧客接点〜データ活用〜効果検証まで網羅。 |
| ITストラテジストらしい視点 | ◎(満点相当) | 経営層への提案・CSR視点・投資指標の設定。 |
| 表現力・説得力 | ◯〜◎ | 説得力が高く、冗長さも少ない。 |
🏁 総評
この論文は、「ITを活用したCS向上施策」を実務的かつ戦略的な視点で描き切った優秀な模範論文です。特に、「顧客の感情的な孤立」に対し、「コミュニティ機能+専門家相談」という両輪でアプローチしており、単なるシステム論を超えた価値提供を構築できています。
合格はもちろん、安全圏かつ教材掲載にも適する内容です。修正すべき重大な瑕疵は見当たりません。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
ST企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「ITストラテジスト試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。