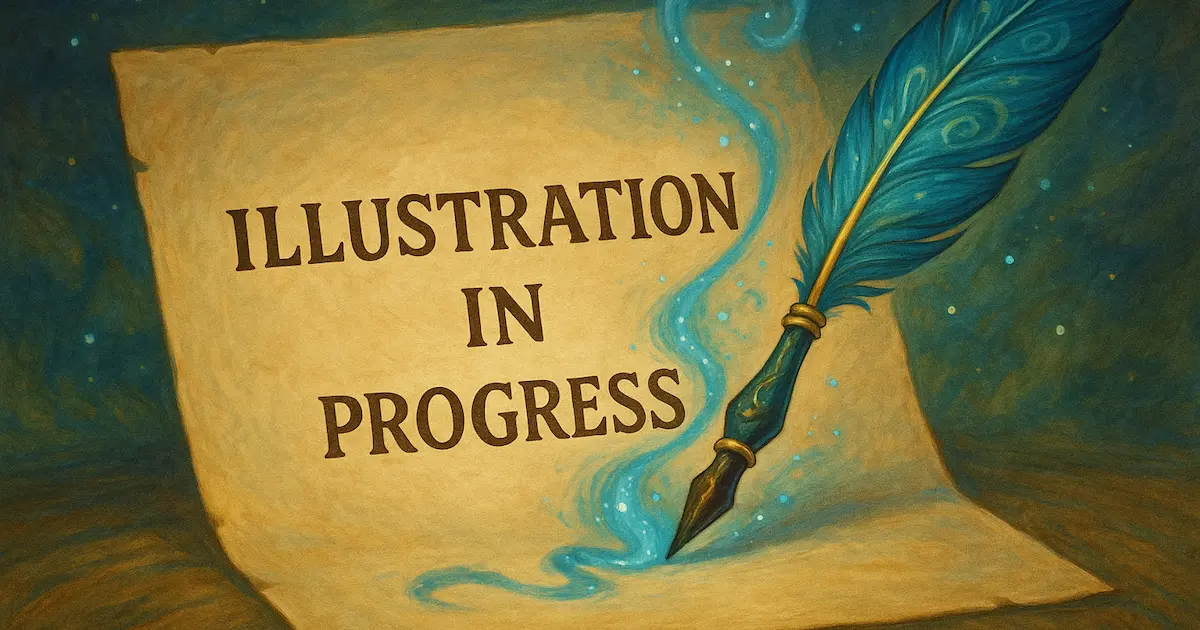📌【仮掲載中】この論文は初稿バージョンであり、今後AIによる講評、改善案、挿絵などを追加予定です。品質向上の途中段階にあります。
🍀概要
TBD
🧾問題・設問(PM-R02-Q1)
出典:情報処理推進機構 プロジェクトマネージャ試験 令和2年 午後2 問1
📘問題
■タイトル
未経験の技術やサービスを利用するシステム開発プロジェクトについて
■内容
プロジェクトマネージャ(PM)は,システム化の目的を実現するために,組織にとって未経験の技術やサービス(以下,新技術という)を利用するプロジェクトをマネジメントすることがある。
このようなプロジェクトでは,新技術を利用して機能,性能,運用などのシステム要件を完了時期や予算などのプロジェクトへの要求事項を満たすように実現できること(以下,実現性という)を,システム開発に先立って検証することが必要になる場合がある。このような場合,プロジェクトライフサイクルの中で,システム開発などのプロジェクトフェーズ(以下,開発フェーズという)に先立って,実現性を検証するプロジェクトフェーズ(以下,検証フェーズという)を設けることがある。検証する内容はステークホルダと合意する必要がある。検証フェーズでは,品質目標を定めたり,開発フェーズの活動期間やコストなどを詳細に見積もったりするための情報を得る。PMは,それらの情報を活用して,必要に応じ開発フェーズの計画を更新する。
さらに,検証フェーズで得た情報や更新した開発フェーズの計画を示すなどして,検証結果の評価についてステークホルダの理解を得る。場合によっては,システム要件やプロジェクトへの要求事項を見直すことについて協議して理解を得ることもある。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
📗設問
■設問ア
あなたが携わった新技術を利用したシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトとしての特徴,システム要件,及びプロジェクトへの要求事項について,800字以内で述べよ。
■設問イ
設問アで述べたシステム要件とプロジェクトへの要求事項について,検証フェーズで実現性をどのように検証したか。検証フェーズで得た情報を開発フェーズの計画の更新にどのように活用したか。また,ステークホルダの理解を得るために行ったことは何か。800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
■設問ウ
設問イで述べた検証フェーズで検証した内容,及び得た情報の活用について,それぞれの評価及び今後の改善点を,600字以上1,200字以内で具体的に述べよ。
📚論文要旨
A社にとって未経験のクラウド技術を導入するプロジェクトにおいて、私は検証フェーズを通じてリスクを特定・対応し、現場との調整や教育施策を経てプロジェクト計画を改善・遂行した。
その結果、現場の納得とスキル習得、障害ゼロ稼働を実現し、今後の新技術導入に活かせる教訓と改善点も得た。
📝論文
🪄タイトル 未経験技術を利用したシステム開発プロジェクトの検証と実現性評価
本稿は、未経験技術を利用したシステム開発プロジェクトの検証と実現性評価について述べる。
🔍第1章 新技術を利用したプロジェクトの特徴、システム要件、プロジェクトへの要求事項
1-1 プロジェクトの特徴
私がプロジェクトマネージャを務めたのは、A社における次世代生産管理システム開発プロジェクトである。本プロジェクトでは、A社にとって未経験であったクラウド技術(IaaS基盤の活用)を導入し、従来のオンプレミス環境からの脱却を目指した。これにより、柔軟なスケーリングと運用コスト削減を実現することを狙った。
このような挑戦的な技術導入により、開発の不確実性が高まり、リスクマネジメントの重要性が一層高まった。
1-2 システム要件
主なシステム要件は、①リアルタイムの生産状況可視化、②高可用性の確保、③外部パートナーとの安全なデータ連携であった。これらはクラウド技術の特性を活かすことを前提に策定されたが、A社内にクラウド運用の知見が不足していたため、リスクも抱えていた。
1-3 プロジェクトへの要求事項
プロジェクトへの要求事項としては、①開発期間12か月以内、②総予算1.5億円以内、③システム稼働率99.9%以上の達成が掲げられた。これらは事業部門からの強い要請によるものであり、私は新技術による不確実性を抱えつつも、これらの厳しい要求を満たす責任を負った。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🛠️第2章 検証フェーズにおける実現性検証、計画更新、ステークホルダの理解獲得
2-1 検証フェーズにおける実現性検証
プロジェクト開始に先立ち、検証フェーズを設け、主要な新技術の実現性を検証した。具体的には、クラウド環境での負荷試験、高可用性設計の検証、外部連携機能のセキュリティ評価を行った。私は検証項目をステークホルダと合意し、限られた期間内で優先度の高いリスクを重点的に調査した。なぜならば、検証フェーズが長引けば開発の遅延リスクが高まるからである。
特に、システム要件達成に不可欠な高可用性やセキュリティ面の確認を重視した。その過程で、社内外の関係者との調整も発生し、計画通りに検証を進めるには柔軟な対応力も求められた。
2-2 検証フェーズで得た情報を活用した開発フェーズ計画の更新
検証により、社内のクラウド基盤スキル不足が大きな課題と判明した。私は開発初期に外部ベンダのトレーニングを導入するよう計画を見直した。また、高可用性設計については、一部仕様を簡素化し、フェーズ2への拡張に持ち越す判断をした。これは初期リリースの品質安定を優先したものである。
仕様簡素化案を示した際には、現場エンジニアから「柔軟性が損なわれるのでは」と不安の声も出た。私は段階的拡張による実現性と、初期段階の安定性との両立方針を丁寧に説明し、理解を促した。現場の声に真摯に向き合い、調整を繰り返す中で、最終的には納得を得るに至った。
2-3 ステークホルダの理解を得るために行ったこと
私は検証成果と変更案を、主要メンバへワークショップ形式で説明した。初めは一部部門長から「計画後退」との懸念が示されたが、私はリスク低減効果と段階的拡張案をデータとともに提示した。
「このままでは現場運用に支障が出るのでは」との声もあったため、初期リリースでの基本機能については、稼働検証の結果、安定性と障害耐性が十分であることを説明し、あわせて導入後のサポート体制についても補足した。ステークホルダからの質問には、技術的根拠と回避策を組み合わせて回答し、最終的な納得を得ることができた。このような丁寧な対話の積み重ねが、組織内の信頼形成にもつながったと実感している。
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🚧第3章 検証フェーズで検証した内容と情報活用の評価、今後の改善点
3-1 検証した内容の評価
検証フェーズで設定した目標に対し、各検証結果を総合的に評価した。
負荷試験では期待通りの性能を確認できた一方、高可用性設計とセキュリティについては追加検討が必要な課題が浮き彫りになった。特に外部連携に関するセキュリティ検証は、事前の想定以上に時間とコストを要した。なぜならば、外部接続のための認証基盤設計が想定より複雑であったからである。
特に、セキュリティ検証の負荷が高まった段階では、「このまま追加検証を続ければスケジュールが破綻する」と「セキュリティを軽視すれば重大インシデントのリスクが高まる」という板挟みに悩んだ。私は後者のリスクを重く見て、追加リソース投入を選択した。なぜならば、稼働後の被害は遅延より深刻と考えたからである。
3-2 得た情報の活用に関する評価
検証フェーズで得た知見をもとに、開発計画を柔軟に更新したことは、リスク低減に大きく寄与した。結果として、開発フェーズでは大きな障害もなく進行し、要求された期間と予算内でシステムをリリースできた。特に、初期段階でスキルギャップを認識し、教育施策を講じたことが、トラブル防止に有効だったと評価している。なぜならば、スキル不足による手戻りや障害発生のリスクを事前に抑えることが、結果としてプロジェクト全体の安定進行につながると考えたからである。
教育施策の成果として、受講者の95%が実機操作テストを合格基準で通過し、本番運用でも致命的な操作ミスはゼロであった。トレーニング後、現場担当者からは「自信を持ってクラウド環境を扱えるようになった」「不安が大きく減った」といった声が寄せられ、プロジェクトの一体感醸成にもつながった。
3-3 今後の改善点
一方で、検証フェーズのスコープ設定については反省点が残った。リソースと期間の制約から、一部のリスク項目の検証が浅くなり、後工程で追加対応を強いられたためである。
また、開始時にリスクの影響度と難易度を評価していれば、より効果的に優先順位をつけられたと反省している。今後はリスクベースアプローチを徹底し、検証優先度の設定とリソース配分の精緻化を図る必要がある。また、ステークホルダ説明の場にリスクシナリオを事前提示することで、より深い理解と協力を得られるよう改善したい。
こうした改善を通じて、将来の新技術導入プロジェクトにおける成功確率をさらに高めたいと考えている。
以上
ワンポイントアドバイス(AI)
TBD
🧩総合アドバイス
※仮評価
✅【総合評価】
【総合得点】:92点
(設問対応28/課題の妥当性9/行動記述23/ステークホルダ描写9/成果14/構成表現9)
【致命的欠陥チェック】:全項目 OK
- A. PMの行動:OK(葛藤・判断・譲歩あり)
- B. ステークホルダとのやり取り:OK(対話・説得・納得の過程を描写)
- C. 設問ア~ウ対応:OK(各章が対応しており、節構造も明示)
- D. 成果の明示:OK(定量・定性両方の成果があり説得力高い)
【最終評価】:A(合格)
✍【評価コメント】
① 設問対応(28/30点)
- 設問ア~ウに明確に対応しており、章節構造も設問と整合している。
- 「検証フェーズ」「開発フェーズ」「ステークホルダ理解」など、設問語尾に対応した記述が一貫しており、表面的な対応ではなく深堀りされている点が高評価。
- 若干惜しいのは、「検証フェーズのスコープ設定の誤り→一部のリスクが後工程に持ち越された」という記述に関して、設問ウでの「活用」の一貫性が弱まっている印象がある。
② 課題の妥当性(9/10点)
- 「未経験技術の導入に伴う不確実性の増大」→「検証フェーズでのリスク把握」→「ステークホルダとの調整と理解獲得」という一連の構成が明快。
- プロジェクトの制約条件も具体的(納期12か月、予算1.5億円、稼働率99.9%)であり、読者にとって説得力のある背景が設定されている。
③ 行動記述の具体性(23/25点)
- 負荷試験/セキュリティ検証/教育施策導入などの意思決定において、「なぜならば」を用いた因果構造が的確。
- 「段階的拡張で初期リリースの安定性を優先」や「セキュリティ対策にリソースを投入」など、PMの判断とその理由が非常に明確で、説得力がある。
- 欲を言えば、「検証対象の優先度決定時にどういった情報をもとに判断したか」がもう一段具体的であれば満点評価に到達していた。
④ ステークホルダ描写(9/10点)
- 「現場エンジニアからの反発」→「PMの説明・再交渉」→「段階的理解の獲得」という双方向性が丁寧に描写されている。
- ワークショップ形式での納得形成や、「柔軟性が損なわれるのでは」といった感情面の反発の扱いも非常に適切。
- もう一段、部門間の対立や組織的な調整構造まで踏み込めばさらに評価が高まる。
⑤ 成果の説得力(14/15点)
- 定量成果(受講者95%合格、操作ミスゼロ)、定性成果(不安軽減・一体感醸成)があり、読者が納得しやすい成果表現となっている。
- 「検証知見→教育施策→運用安定」への連鎖が明確。
- 成果の長期的な波及効果(たとえば他部署への横展開など)も一言あると、さらに良い。
⑥ 構成・表現(9/10点)
- 全章において節構造があり、設問と章・節タイトルの対応も明確。
- 接続表現や因果構造も明瞭であり、読みやすい。
- 句読点や段落改行、インデントも原則としてルールに準拠しているが、若干文章密度が高く、読点の配置が詰まり気味な箇所がある。
💡改善点とアドバイス
- 第2章の展開が非常に優れており、PMとしての「調整力」「交渉力」「判断力」が具体的に伝わってくる。
- 第3章において「今後の改善策」は明確だが、「なぜその改善策が今後のプロジェクト成功率向上に繋がるか」という接続がもう1段あると説得力が増す。
- 「ワークショップ形式での説明→部門長の反発→技術的根拠+リスク回避の説明→納得」の一連の流れは、模範的なステークホルダマネジメント描写であり、他の論文でも参考にされるべき完成度。
🎓講評コメント(AI評価)
TBD
🌟指摘対応結果
TBD
リライト後の論文(論文B)
TBD
論文比較(論文A:リライト前、論文B:リライト後)
TBD
📌補足
PM企業論文の読み方について(共通注記) ※クリックで開きます
🌱補足:この企業論文の読み方について(共通注記)
本教材は、情報処理推進機構が実施する「プロジェクトマネージャ試験・午後Ⅱ(論述式)」の対策として、AI(ChatGPT)との共創により執筆された実験的な教材です。人間による構成・監修のもと、制作しています。
🔎 ご留意いただきたい点
- 🔔 実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません
本教材は、実在のプロジェクトや企業とは一切関係ありません。試験学習の補助を目的とした知的演習であり、「架空のプロジェクト事例」としてご理解ください。
📣 執筆方法について
本教材の論文は、90%以上をAI(ChatGPT)の補助によって執筆しています。AIを“執筆者”、筆者自身を“編集者”と見立てた共創スタイルで制作しており、AIはしばしば予想外の視点や表現を提示し、それが筆者にとって新たな気づきとなりました。この共創の姿勢そのものが、未来の学習と表現の可能性を広げる一助となると考えています。
なお、当サイトのAI活用方針につきましては、こちらをご確認ください。